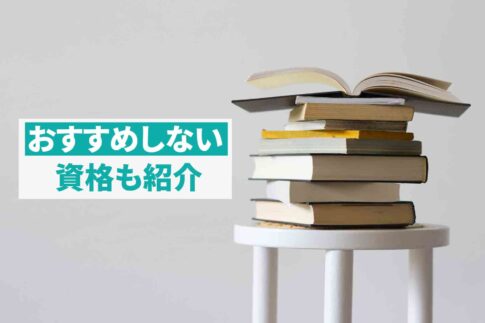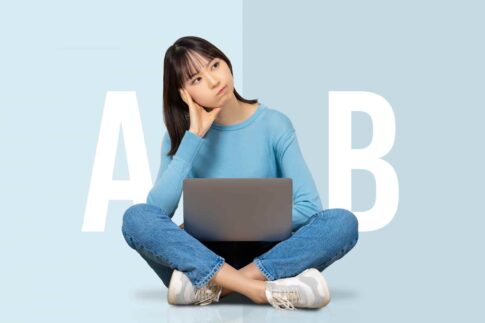大学中退をしても公務員になることは可能なのか。そう疑問に思う人も多いのではないでしょうか。
この記事では、大学中退を検討している人へ向けて、大学中退した場合でも公務員になれる方法を紹介します。
また、早く就職して安定した給与を得たい人には、民間企業の就職も一つの選択としてあるでしょう。それぞれのメリットを解説するので、民間企業と公務員どちらに就職するのか検討していきましょう。
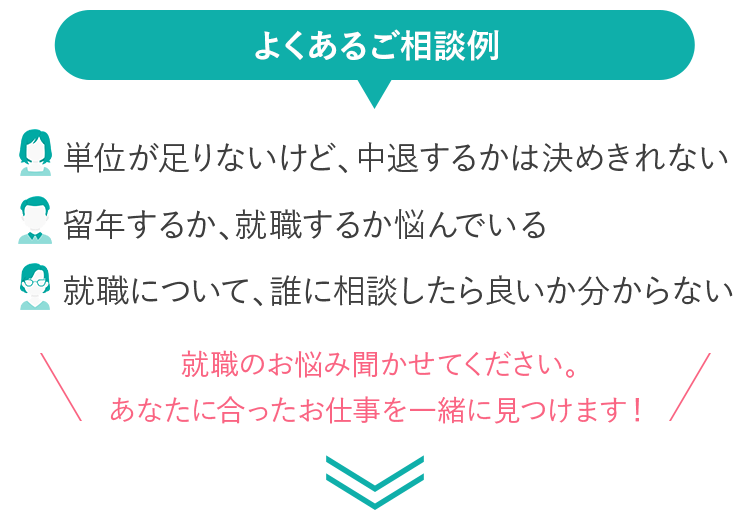

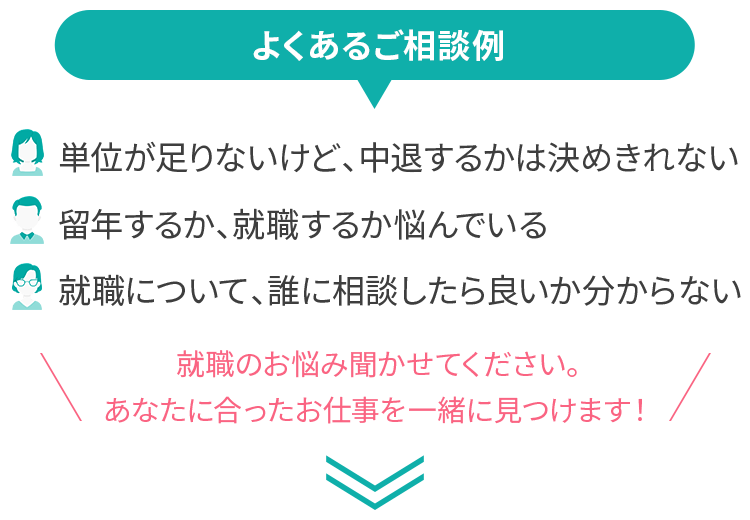
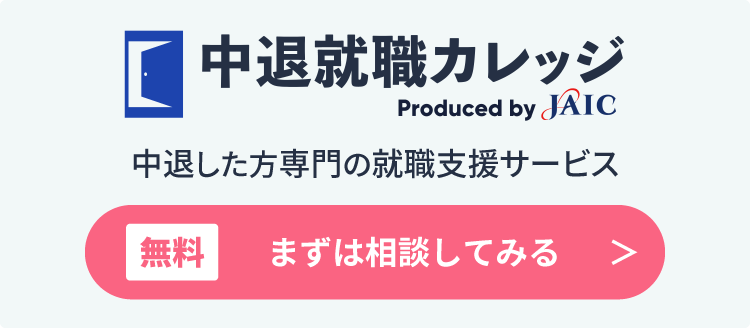
この記事の目次
大学中退で公務員になることは可能?
大学中退で公務員になることは可能です。なぜなら、公務員試験の受験資格は最終学歴ではなく「高卒程度」「大卒程度」などの区分で決まるからです。
以下の表は、令和3年度の国家公務員採用者数を示しており、高卒の採用者も一定数いることがわかります。
| 学歴 | 採用者数 |
|---|---|
| 大卒 | 6,073人 |
| 高卒 | 3,744人 |
参考:人事院「令和4年度 年次報告書」)
ただし、公務員試験では年齢制限が設けられているため、すべての公務員試験を受けられるわけではありません。
また、総務省の調査によると、各都道府県における地方公務員の部長職は大卒が9割でした。以下の表は、都道府県の公務員の部長級職員数を学歴別にまとめたものです。
| 学歴 | 職員数(部(局)長及び相当職) |
|---|---|
| 大卒 | 3,812人 |
| 短大卒 | 65人 |
| 高卒 | 366人 |
| 中卒 | 1人 |
参考:総務省「令和5年 地方公務員給与実態調査結果」
地方公務員の部長職は大卒が圧倒的に多いため、大学中退者(高卒枠)だと管理職への昇進は厳しいと言えるでしょう。
国家公務員になるのは約28%|国家公務員の学歴別職員数
大卒で国家公務員になっているのは約14万人、高卒が約7万人です。つまり、大学を中退してから国家公務員になれる割合は、全体の約28%とわかりました。
以下の表は、令和5年の国家公務員の学歴別職員数を具体的に示しています。
| 学歴 | 職員数(国家公務員) |
|---|---|
| 大学卒 | 14万4,531人 |
| 短大卒 | 3万6,649人 |
| 高卒 | 7万1,427人 |
| 中卒 | 183人 |
参考:人事院「令和5年国家公務員給与等実態調査報告書」
高卒の国家公務員の割合は大卒より少ないですが、職種によっては大きな差がないものもあります。例えば、国家公務員の中でも税務職では大卒が25,550人、高卒が22,716人と、ほぼ同じ規模の採用数です。
大学を中退して国家公務員を目指す場合、試験合格だけでなく将来のキャリアも考えることが大切です。
職種によって高卒者が多い分野もあれば、大卒が有利な職種もあります。
学歴や採用状況を踏まえ、自分に合った職種を慎重に選びましょう。
地方公務員になるのは約17%|地方公務員の学歴別職員数
地方公務員は大卒が約140万人、高卒が約32万人でした。つまり、大学を中退してから地方公務員になれる割合は全体の約17%で、国家公務員の数よりも少ないとわかりました。
以下の表は、地方公務員の学歴別職員数をまとめたものです。
| 学歴 | 職員数(地方公務員) |
|---|---|
| 大学卒 | 140万6,911人 |
| 短大卒 | 11万2,748人 |
| 高卒 | 32万2,788人 |
| 中学卒 | 1万4,798人 |
参考:総務省「令和5年 地方公務員給与の実態 概要」
地方公務員の職員数は大卒者が圧倒的に多く、140万6,911人と全体の大部分を占めています。次いで高卒者が32万2,788人と一定数は採用されていますが、大卒者の半数以下の人数です。
差が大きく開いている理由は、高卒者が教員採用試験を受けられないことが関係しています。実際に大卒者の小・中学校教育職は53万6,029人ですが、高卒者は160人しかいません。
なお、技能労務職(清掃作業員や給食調理員など)では、高卒と中卒がその大半を占めています。そのため、大学を中退して学歴が高卒となった場合でも、技能労務職であれば比較的採用のチャンスがあるでしょう。
大学中退で公務員を受験する際の年齢制限
大学を中退しても公務員試験を受けることは可能ですが、すべての試験に挑戦できるわけではありません。
ここでは、大学中退者が公務員試験を受験する際の年齢制限について詳しく解説します。年齢が上限を超えていないか事前に確認しておきましょう。
国家公務員を受験する場合の年齢制限
国家公務員試験は、大きく分けて総合職と一般職の2種類です。
一般職は「教養以外の区分」と「教養区分」に分かれ、受験資格は、年齢や学歴によって異なります。
総合職は以下の受験資格が必要で、大学中退者でも21〜30歳なら受験可能です。
| 対象者(2025年度採用) | 受験資格 |
|---|---|
| 1995年4月2日~2004年4月1日生まれ | 21歳~30歳 |
| 2004年4月2日以降生まれ | ・大学(短大を除く)を卒業、または2026年3月卒業見込みの者 ・人事院が大学卒業と同等の資格があると認めた者 |
参考:人事院「国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)」
対して、一般職の受験資格は以下のとおりで、20歳~30歳なら学歴不問で受験できます。
| 受験資格 | 試験内容 | 受験資格(2025年2月時点) |
|---|---|---|
| 教養以外の区分 | 専門試験あり | ・21歳~30歳 ・20歳以下:大学・短大 ・高専卒業または卒業見込みが必要 |
| 教養区分 | 教養試験のみ | ・20歳~30歳 ・19歳以下:大学・短大 ・高専卒業または卒業見込みが必要 |
参考:人事院「国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)」
一般職は、専門試験がない「教養区分」なら、比較的受験しやすいでしょう。
また、一般職の社会人試験なら年齢の幅が広いため、選択肢として考えるのもおすすめです。(参考:人事院「国家公務員採用一般職試験(社会人試験(係員級))」
地方公務員を受験する場合の年齢制限
地方公務員を受験する場合の年齢制限は、自治体や種別によって異なります。
以下の表は、東京都と大阪府の応募条件の一例です。
◆東京都(2025年2月時点)
| 試験名 | 年齢要件 | 必要な資格・免許 |
|---|---|---|
| 1類A採用試験 | 24歳~31歳 | 特になし |
| 1類B採用試験(新方式) | 22歳~29歳 | 特になし |
| キャリア活用採用選考 | 60歳まで | 学歴区分に応じた職務経験 |
参考:東京都職員採用「試験・選考情報」
東京都の公務員採用条件には試験区分ごとの年齢制限が明確に設定されており、大学中退者でも挑戦できる試験が多いです。
◆大阪府(2025年2月時点)
| 試験名 | 年齢要件 | 必要な資格・免許 |
|---|---|---|
| 行政(大学卒程度) | 22歳~25歳 | 特になし |
| 行政(高校卒程度) | 18歳~21歳 | 特になし |
| 行政(社会人等) | 26歳~49歳 | 特になし |
参考:大阪府「採用試験」
大阪府の公務員試験では学歴要件がない試験区分が多いため、大学中退者でも受験可能です。
また、公務員試験の年齢制限は近年引き上げられている傾向があり、社会人経験者や多様な経歴を持つ人にも受験の機会が広がっています。
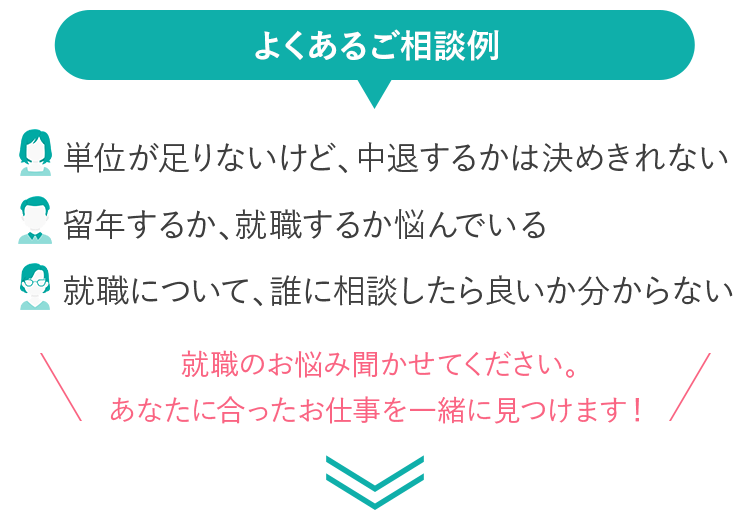

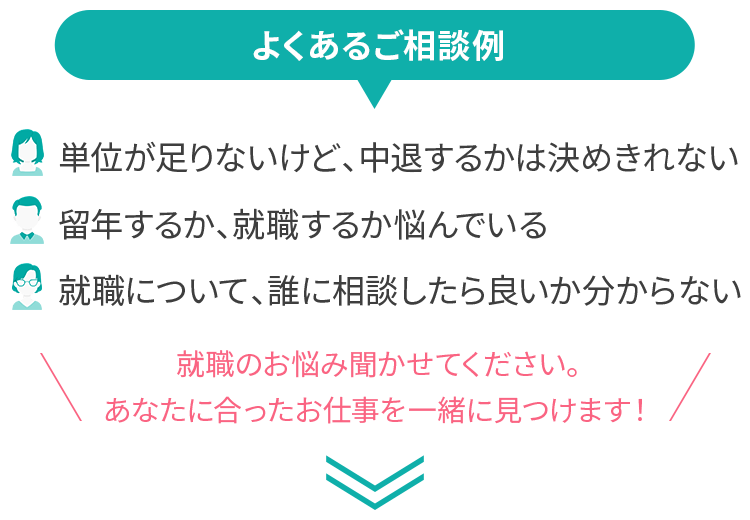
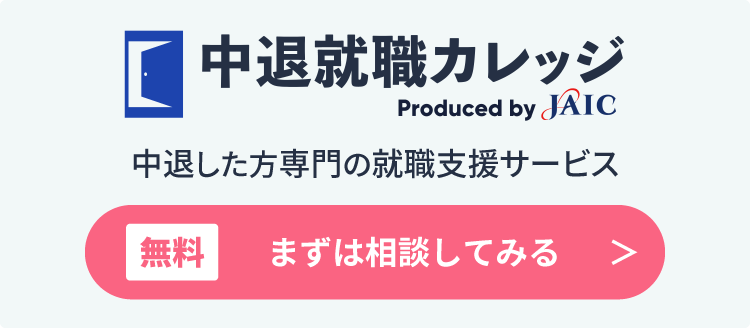
大学中退者が公務員になるメリット4つ
大学中退者が公務員になるメリットについて解説をしていきます。以下が、公務員の一般的なメリットになります。
- 福利厚生が充実している
- 社会的な信頼度が高い
- 倒産のリスクがない
- 地域に貢献できる
それぞれについて解説をしていきます。
1. 福利厚生が充実している
公務員は、民間企業の正社員と同様に、有給休暇や各種手当が充実しています。病気休暇はもちろんですが、夏休みなどに利用できる特別休暇や介護休暇などが幾つか用意されていることが多いようです。
また、女性の育児休業実績も多く、出産や育児をしながら働き続けられる点もメリットになるでしょう。
加えて、公務員は、独自の共済組合などに加入しているケースが多く、退職後は共済年金が支給される場合があります。組合員向けの貸付制度や積立制度もあり、ライフステージを支えるサポートが豊富です。
2. 社会的な信頼度が高い
公務員という職業は社会的な信頼を得やすく、安定的に仕事できることが多いでしょう。安定した職種を求めている人、将来的に転職せず腰を据えて働きたい人にはおすすめです。
3. 倒産のリスクがない
公務員は、雇用が安定していることから、住宅ローンなどの金融機関による審査でも概して有利になります。民間企業のように倒産のリスクがなく、国家公務員・地方公務員を問わず経営不振によるリストラの心配もほとんどありません。
民間企業の場合、業績などによるリストラの可能性もあります。加えて、自分はどれだけ頑張って働いても、会社全体の業績によってボーナスの支給額が変動することもあるので、公務員の方が収入が安定しているといえるでしょう。
4. 地域に貢献できる
職種によっては、地域に密着した仕事ができるところもメリットです。実際、都道府県や市町村などに就職した地方公務員は、地域の行政に関する仕事に携わります。
地域に貢献をしたい人にとっては、やりがいのある仕事ができるのが地方公務員の魅力になります。地域密着で転勤がない方がいいという人にもおすすめです。
大学中退者が公務員になるデメリット5つ
次に公務員になるデメリットについて解説をしていきます。例えば以下のような点は、公務員になる際のデメリットになるでしょう。
- 会社員と比べて、実績に伴う昇給の機会が少ない
- 基本的に試験の難易度が高く、人によっては合格までに時間がかかる
- 規模が小さい職場の場合、閉鎖的な環境・人間関係をつらく感じることがある
- 職種によっては、転勤が必要となる場合もある
それぞれについて解説をしていきます。
1. 会社員と比べて、実績に伴う昇給の機会が少ない
公務員は、一般的に勤務している期間が長いほど給与が上がるシステムになっています。年功序列を守り続けていることが多く、勤続年数が長くなるにつれて昇給があります。
公務員の場合、民間企業の正社員のように実績が給与の額にダイレクトに結びつくといったことはほとんどありません。
したがって、仕事で何らかの実績を上げても、昇給のペースは同時期に就職した同僚とほぼ同じです。自分が頑張っただけの報酬を得たい方にとっては、このような点がデメリットになるかもしれません。
2. 基本的に試験の難易度が高く、人によっては合格までに時間がかかる
公務員試験は、人によっては合格するまでにある程度の時間がかかります。
難関と言われている試験の場合は、数年程度の勉強をしなければならない場合もあるでしょう。試験範囲はかなり広いため、短期間で合格するには専門学校に通って勉強する、などの対処が求められます。
受験資格に年齢制限が設けられている場合、試験を受けられる回数も限られるため、効率良く勉強する必要があります。
公務員を目指す場合は、あらかじめ自分なりの期限を決めましょう。例えば、2年以内に合格できなかったら他の仕事を目指すなど、途中で方向転換をする勇気も必要です。
可能であれば、公務員試験と並行して、興味がある業界の民間企業への就職も検討してみるといいでしょう。
3. 規模が小さい職場の場合、閉鎖的な環境・人間関係をつらく感じることがある
公務員であっても、出先機関などに配属されると少人数の職場で働くこともあります。こうした職場では閉鎖的な雰囲気になりやすい傾向もあり、人間関係における風通しの悪さをつらく感じる人もいるようです。
社会や地域に積極的に貢献したいと考えている人にとっては、個々の意見が通りづらく、仕事に対してのやりがいを感じられなくなることもあり得ます。
職種や職場によって差がありますが、配属される職場によってはこうした可能性もあることを理解しておきましょう。
4. 職種によっては、転勤が必要となる場合もある
職種によっては、民間企業の正社員のように、転勤を求められることもあります。
都道府県や市町村に就職した地方公務員の場合は転勤先のエリアが比較的に限られますが、国家公務員として就職した場合は遠隔地に転勤となるケースもあることを知っておきましょう。
5. 大卒に比べると年収が下がる
人事院の「平成30年国家公務員給与等実態調査」によると、行政職の場合、公務員の高卒と大卒の基本給(俸給)は、それぞれ以下の通りです。
以下が、もっとも等級や経験年数が高い行政職の基本給(俸給)です。
- 高校卒(1級/経験年数1年未満):14万9731円
- 大学卒(1級/経験年数1年未満):18万4403円
そして以下が、もっとも等級や経験年数が高い行政職の基本給(俸給)です。
- 高校卒(10級/経験年数35年以上):52万4200円
- 大学卒(10級/経験年数35年以上):54万2900円
引用:人事院「平成30年国家公務員給与等実態調査」
上記のデータから、高卒と大卒では新人時代の一か月あたりの給料は約3万5000円程度、ベテランになっても約2万円弱の差があることがわかります。多くの民間企業のように、大卒のほうが高卒よりも給料が高く設定されているのは、公務員も同じです。
そのため、いまの時点で大学に通っていて将来は公務員になりたいのであれば、よほどの事情がない限りは大学を卒業したほうが経済面で有利といえます。
ただし、高卒と大卒で基本給の金額に極端な差があるわけではないため「大学中退で公務員になったから、金銭的に大幅に損をしてしまう」ということでもなさそうです。すでに大学を中退をした人も、公務員を目指す価値はあるといえるでしょう。
大学中退者が目指せる国家公務員の職種5選
安定した職や社会貢献を目指す人にとって、学歴不問で挑戦できる国家公務員は魅力的な選択肢です。
ここでは、大学中退者が目指せる国家公務員の職種について、厳選して5つ紹介します。ぜひ、自分に合った職種を見つけてください。
官公庁の事務[大学中退者が目指せる国家公務員の職種 1/5]
官公庁の事務とは、国の行政機関で働く事務職のことです。
一般的に、書類作成、窓口対応、庶務業務などが中心となりますが、配属先や担当業務によって内容は多岐にわたります。
一般職試験(高卒者試験・大卒程度試験)であれば、大卒中退者でも受験可能です。
総合職試験と比べると難易度は低めであるため、対策をしっかり行えば合格の可能性を高められるでしょう。
大学中退者の中には「一つの業務だけをずっと続けるのは向いていない」と感じる人もいるかもしれません。しかし、官公庁の事務職は数年ごとに異動があるのが一般的で、幅広い経験を積みながら成長できる環境があります。
| 平均年収 | 478.3万円 |
| 必要なスキル | ・PCスキル ・コミュニケーション能力 ・正確性と注意力 |
| 向いている人 | ・人のサポートをするのが好きな人 ・地道な作業が苦にならない人 ・臨機応変な対応力がある人 |
| 仕事に就くためには? | ・国家公務員採用試験に合格 ・公務員試験対策の専門学校を活用 |
刑務官[大学中退者が目指せる国家公務員の職種 2/5]
刑務官は、刑務所や拘置所で受刑者の生活を管理し、社会復帰を支援する仕事です。
受刑者の監視や指導、安全管理を行いながら、規律を守らせる役割を担います。具体的には、施設内の巡回、食事や運動の管理、作業の監督、受刑者との面談などがあります。また、受刑者とのコミュニケーションを通じて、彼らの更生を促すことも大切な仕事の一つです。
刑務官採用試験に合格すれば、高卒でも受験可能のため、大学中退者でも挑戦できます。
筆記試験の他に体力試験もあるため、学力面の不安がある人でも対策がしやすいでしょう。
刑務官は体力が求められる場面もありますが、その分、公務員としての安定性が保証されている職業です。
| 平均年収 | 600~700万円 |
| 必要なスキル | ・コミュニケーション能力 ・冷静な判断力 ・体力 ・精神力 |
| 向いている人 | ・社会貢献したいと考えている人 ・冷静に対応できる人 ・体力に自信がある人 |
| 仕事に就くためには? | ・刑務官採用試験に合格 ・公務員試験対策の専門学校を活用 |
検察事務官[大学中退者が目指せる国家公務員の職種 3/5]
検察事務官は、検察庁で検察官(検事)の業務をサポートする公務員です。
主な仕事は、捜査・裁判の補助、証拠書類の整理、事務処理などで、検察官と協力しながら刑事事件の処理や法廷での手続きを円滑に進める役割を担います。
検察事務官になるには、国家公務員採用一般職試験(大卒程度・高卒者試験)に合格する必要があります。学歴不問のため、大卒中退者も受験可能です。試験合格後、各地方検察庁の面接を経て採用されます。
なお、実務経験を重ねることで、各部門の管理職などより高度な職種へ昇進するチャンスがあります。一定の受験資格を満たした後に試験に合格すれば、副検事や検事としてのキャリアを目指すことも可能です。
| 平均年収 | 1121.7万円 |
| 必要なスキル | ・事務処理能力 ・冷静な判断力 ・守秘義務を守る意識 |
| 向いている人 | ・法律や捜査に興味がある人 ・責任感があり、ルールをしっかり守れる人 ・冷静に物事を処理できる人 |
| 仕事に就くためには? | ・国家公務員採用一般職試験に合格 ・公務員試験対策の専門学校を活用 |
入国審査官[大学中退者が目指せる国家公務員の職種 4/5]
入国審査官は、空港や港で外国人の入国・出国を審査し、日本の安全を守る国家公務員です。
外国人の在留資格の審査、違法入国の取り締まりなども行います。
入国審査官になるには、国家公務員採用一般職試験(大卒程度または高卒者試験)に合格する必要があり、学歴要件がないため、大学中退者でも受験可能です。
試験に合格した後、各地方の出入国在留管理局での面接を経て採用されます。
外国人と接する機会が多く、英語やその他の外国語を活かせる職場です。
語学は独学や実践を通じて習得できるため、大学に通わなくても努力次第でスキルを伸ばし強みとして活かせるでしょう。
| 平均年収 | 478.3万円 |
| 必要なスキル | ・語学力 ・コミュニケーション能力 ・冷静な判断力 |
| 向いている人 | ・国際的な仕事に興味がある人 ・状況に応じて柔軟に対応できる人 ・英語など外国語が得意な人 |
| 仕事に就くためには? | ・国家公務員採用一般職試験に合格 ・公務員試験対策の専門学校を活用 |
税務事務官[大学中退者が目指せる国家公務員の職種 5/5]
税務事務官は、国税庁や税務署に勤務し、税金の適正な徴収と管理を行う国家公務員です。
納税者からの税務相談に対応し、申告内容の確認や誤りの修正をサポートするほか、未納税の督促や税務調査の補助などを担当。また、税務関連の書類作成やデータ入力といった事務作業も行い、税務行政が円滑に進むように支える役割を担います。
税に関する幅広い業務を通じて、適正な課税や公正な税制運用を実現することが求められる仕事です。
税務事務官になるには、高校卒業者向けの「税務職員採用試験」と、大学卒業者向けの「国税専門官採用試験」の2種類の試験があります。
大卒中退者は、高校卒業者向けの税務職員採用試験を受験することが可能です。
| 平均年収 | 484.6万円 |
| 必要なスキル | ・法律や税務に関する基礎知識 ・事務処理能力 ・分析力 ・計算力 |
| 向いている人 | ・法律や税務に興味がある人 ・コツコツと正確に作業できる人 ・人と接するのが苦ではない人 |
| 仕事に就くためには? | ・国家公務員採用一般職試験に合格 ・公務員試験対策の専門学校を活用 |
大学中退者が目指せる地方公務員の職種5選
地域に密着した仕事が多い地方公務員は、住民の生活を支えるやりがいのある職種です。
ここでは、大学中退者が目指せる地方公務員の職種を5つ紹介します。ぜひキャリア選択の参考にしてください。
地方自治体の事務[大学中退者が目指せる地方公務員の職種 1/5]
地方自治体の事務職は、市役所や県庁などで、住民サービスや行政の運営を支える仕事です。
具体的には、窓口業務を通じた住民対応や、税務・福祉・教育などの各種行政サービスの手続き、予算管理、庶務業務などが主な業務です。また、地域の課題解決や政策の企画・運営に関わることもあり、地域社会を支える重要な役割を担います。
地方公務員の試験は自治体ごとに名称や選考内容が異なりますが、一般的に「1種(大卒程度)」「2種(短大卒程度)」「3種(高卒程度)」に分かれています。
自分の学力に合った区分の試験を受験できるため、大学を卒業していなくても問題なく挑戦できます。
| 平均年収 | 478.3万円 |
| 必要なスキル | ・事務処理能力 ・コミュニケーション能力 ・法律や制度の理解力 |
| 向いている人 | ・地域の役に立ちたい人 ・人と接するのが苦ではない人 ・コツコツと正確に作業できる人 |
| 仕事に就くためには? | ・各自治体の地方公務員試験に合格 ・公務員試験対策の専門学校を活用 |
公立学校の事務[大学中退者が目指せる地方公務員の職種 2/5]
公立学校の事務職は、小学校・中学校・高校などの学校運営を支える地方公務員です。
主な業務は、予算管理、物品購入、生徒や保護者の対応など多岐にわたります。
事務作業を中心にしながらも、教育現場を支える役割を持つことが特徴です。
公立学校の事務職は、地方自治体が実施する地方公務員試験(学校事務)に合格すれば、大卒中退者でも応募可能です。
学歴ではなく公平な試験で評価されるため、大学卒業が必須ではありません。
学校の事務室でのデスクワークがメインのため、身体的な負担が少なく、落ち着いた環境で働けます。
先生や生徒を支える仕事なので、教育に関心がある人にはやりがいを感じやすいでしょう。
| 平均年収 | 478.3万円 |
| 必要なスキル | ・事務処理能力 ・コミュニケーション能力 ・柔軟な対応力 |
| 向いている人 | ・コツコツと正確に作業できる人 ・人をサポートするのが好きな人 ・教育に興味がある人 |
| 仕事に就くためには? | ・各自治体の地方公務員試験に合格 ・公務員試験対策の専門学校を活用 |
警察官[大学中退者が目指せる地方公務員の職種 3/5]
警察官は、地域の安全を守るために犯罪の防止・捜査、交通取り締まり、住民対応などを行う地方公務員です。
交番勤務やパトロール、事件・事故の対応、取り調べなどの業務があり、配属先によって仕事内容は異なります。また、警察内部で事務を担当する部署もあり、幅広い業務を通じて地域社会を支える役割を担います。
警察官として地方公務員になるには、都道府県警察官採用試験(大卒程度・大卒程度以外)に合格する必要があります。
学歴は問われず、試験の成績や適性によって判断されるため、大卒中退者でも受験可能です。
体力や適性、努力が評価される仕事のため、大学中退者でも実力次第でキャリアを築けます。
| 平均年収 | 700~720万円 |
| 必要なスキル | ・基本的な法律知識 ・体力と精神力 ・判断力と冷静な対応力 |
| 向いている人 | ・体を動かす仕事が好きな人 ・社会に貢献したいと考えている人 ・責任感が強く、冷静な判断ができる人 |
| 仕事に就くためには? | ・都道府県ごとの警察官採用試験に合格 ・採用後に警察学校で訓練を実施 |
消防官[大学中退者が目指せる地方公務員の職種 4/5]
消防官は、火災や災害現場での人命救助、消火活動、救急対応などを行う地方公務員です。
主な業務には、火災時の消火活動、交通事故や自然災害での救助、119番通報に対応する救急業務などがあります。
常に地域の安全を守るため、体力と迅速な判断力が求められる仕事です。
消防官になるには、各自治体の公務員試験(消防職員採用試験)に合格し、採用後に都道府県などの消防学校で研修を受ける必要があります。
研修で知識や技術が学べるため、大学中退者でも安心してスタートできます。
消防士として経験を積めば、消防士長や消防司令へとステップアップできるため、学歴に関係なくキャリアを築ける職業です。
| 平均年収 | 350.2万円 |
| 必要なスキル | ・基本的な応急処置の知識 ・体力と持久力 ・冷静な判断力 |
| 向いている人 | ・体を動かす仕事が好きな人 ・人の命を守ることにやりがいを感じる人 ・冷静に行動し、リーダーシップを発揮できる人 |
| 仕事に就くためには? | ・各自治体の消防職員採用試験に合格 ・消防学校での研修が必須 |
ごみ収集作業員[大学中退者が目指せる地方公務員の職種 5/5]
ごみ収集作業員は、自治体の清掃部門に所属し、住民の家庭ごみや事業所ごみを収集・運搬する地方公務員です。
決められたルートでごみ収集車に乗り、可燃ごみ・不燃ごみ・資源ごみなどを回収し、処理施設へ運搬するのが主な仕事です。また、ごみの分別指導や、不法投棄の対応なども担当し、住民と直接関わる機会もあります。
ごみ収集作業員として地方公務員になるには、各自治体が実施する地方公務員採用試験に合格しなければなりません。多くの自治体では学歴要件を設けておらず、大卒中退者でも受験可能です。
地方公務員のため、給与や福利厚生が充実しており、安定した雇用が保証されているのが魅力です。
民間の清掃会社よりも待遇が良く、定年まで安心して働けます。
| 平均年収 | 386.4万円 |
| 必要なスキル | ・体力と持久力 ・チームワーク ・安全管理意識 |
| 向いている人 | ・体を動かす仕事が好きな人 ・ルーティンワークを苦にしない人 ・地域に貢献したい人 |
| 仕事に就くためには? | ・各自治体の地方公務員試験に合格 |
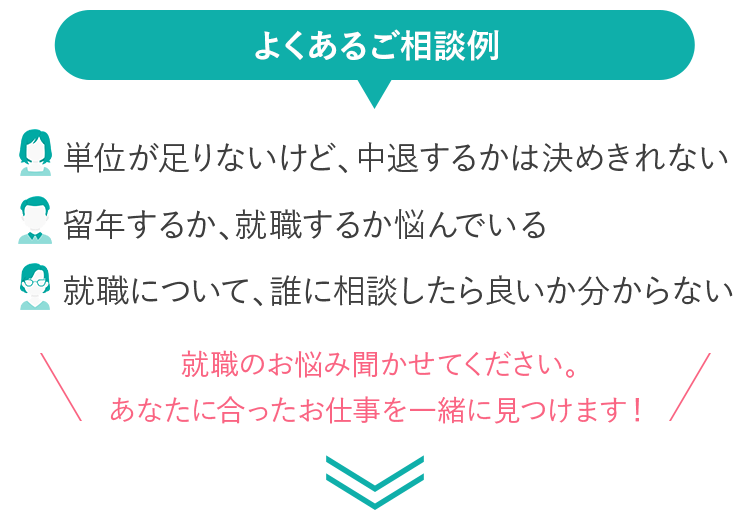

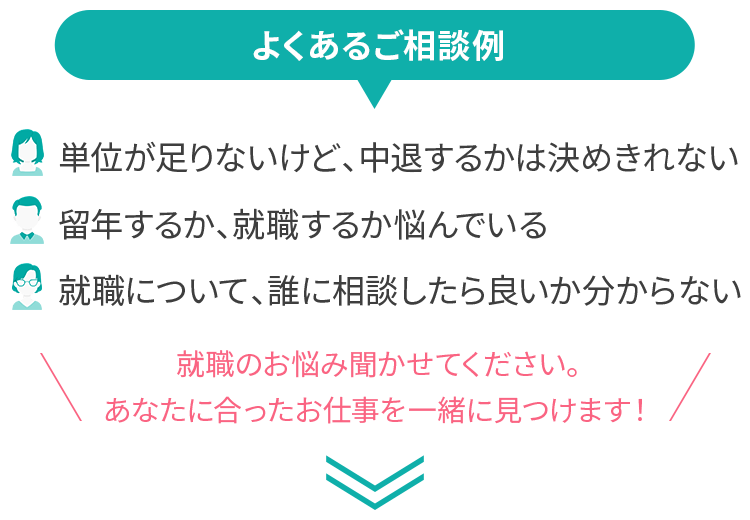
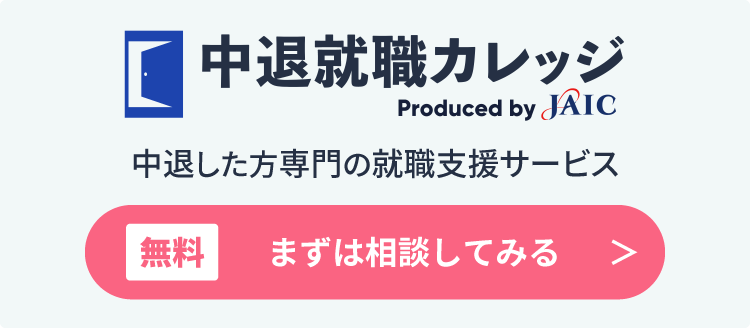
大学中退から公務員就職の成功率を上げる方法
大学中退で公務員になりたい方のための、面接や筆記試験の対策をご紹介しましょう。
面接対策
公務員試験でも、民間企業と同じく面接があります。大学中退の経歴がある場合、公務員試験の面接では100%中退理由を聞かれることになるので、対策が必要です。大学を辞めたことは事実ですが、ネガティブな中退理由だけを伝えるのはやめましょう。
「大学は中退してしまったが、その経験から〇〇を学んだ」「公務員の仕事に就くことができたら、自分の弱みである●●な部分に気をつけて働いていきたい」など、前向きに転換したり、反省している姿勢を示すことをおすすめします。
筆記試験
大学中退者が公務員試験を受ける場合、高卒者対象の試験を受験するケースが多いでしょう。「高卒者対象」であってもむずかしい試験に変わりはないため、計画的に学習をすすめる必要があります。
また、公務員試験の試験種目や試験方式は受験先によって大きく異なるため、必ず、希望する公務員試験の受験案内を確認するようにしてください。
公務員試験の専門学校に行くのも選択肢の一つ
公務員試験の受験勉強は、独学で行う以外に、公務員試験対策をしている専門学校に通う選択肢もあります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、自分に合った方法を選択しましょう。
▽独学のメリット・デメリット
参考書などを購入して独学する場合、最低限の費用に抑えられるというのが大きなメリットです。今はさまざまな出版社が公務員試験対策の教材を出しているため、いくつかの参考書を購入すれば試験対策が可能です。
しかし、試験勉強はある程度長い期間行う必要があるため、一人で勉強するモチベーションを保てない場合もあります。また、予備校のノウハウをもとに勉強する人に比べて、独学のほうが合格率が低くなりがちです。
独学を選択するのであれば、合格に対する目的意識を人一倍高く持ち、情報収集や学習計画、自己管理をしっかり行う必要があります。
▽公務員試験の専門学校のメリット・デメリット
専門学校では、公務員試験の勉強に特化したカリキュラムが構築されており、比較的に短期間で効率よく試験対策ができます。
また、専門学校では同じ目標を持った人たちと共に取り組むことができ、お互いに刺激しあうながら試験へのモチベーションを維持できるのも大きなメリットと言えるでしょう。
しかし、専門学校に通うには費用がかかり、ある程度まとまったお金が必要になります。専門学校の費用のために、アルバイトを並行して行う人もいますが、勉強と仕事の両立は体力的に難しい場合もあります。無理をして体調を崩してしまっては本末転倒なので、自分の環境を見直して現実的な方法を選ぶようにしましょう。
本当に公務員になるのがベストなのか考えることが大切
大学を中退した人にとって、本当に公務員になることがベストな選択なのかは、個々によって異なります。公務員にはメリット・デメリットの双方があり、なかには民間企業への就職の方が適しているケースも少なくありません。
大学を中退しても公務員になることは可能ですが、「何となく安定してそうだから」といった安易なイメージに捉われて公務員になると、後悔するかもしれません。
自分が本当に公務員に向いているのか、公務員という選択肢が自分にとってベストな選択肢なのかをしっかり考え、そのうえで判断することが重要です。
大学中退後、民間企業も検討しておくべき人の特徴
ここまで、大学中退者が公務員になるメリット・デメリットをご紹介しましたが、中退後の進路として民間企業への就職を目指したほうがいい場合もあります。実は、公務員になって『損する人』と『得する人』がいるのです。ご自身がどちらのタイプなのか、考えてみてください。
公務員試験までの時間やお金がない
公務員の人気が高まっている現在では、おのずと競争率も高まっています。受験を思い立ってから合格に至るまでには、どうしても一定の学習量が必要になるため、次の試験に間にあわなかったり、試験を数回受けても合格できないケースもあります。試験勉強に何年も時間を費やしてしまうと、社会人としてのスタートが遅れたり、受験の年齢制限を迎えてしまったりと、さまざまなリスクがあります。
また、試験勉強にかかる費用も見過ごせないポイントです。独学であれば参考書を数冊購入する程度で済みますが、専門学校に通って効率的に学びたい場合はまとまった費用が必要となります。
自分には学習にあてる時間的な余裕があるのか、試験勉強のために使える資力があるかを冷静に見極めましょう。
スキルアップして挑戦をしていきたい
「公務員の職種の中に明確にやりたい仕事がある人」や「仕事の内容よりも安定性を重視する人」には、公務員が向いているでしょう。
ただ、かなり専門的な技術職などでない限り、特定の分野でのスキルアップの機会は民間企業に比べて少ないかもしれません。明確に定められている業務をこなすのがメインである場合、好奇心が旺盛な人は退屈さを感じてしまうでしょう。
仕事にやりがいを求めたい
SNS投稿分析のスナップレイスが『公務員の仕事に対する満足度は、全業種の中でワースト5』という調査結果を発表しました。
引用:PRITIMES「17業種別の仕事満足度ランキング発表!ソーシャルリスニングで遂に真実が判明」
仕事満足度ランキングによると、公務員は下から4番目という結果で、残念ながら仕事への満足度は低いと言われています。
また、公務員の仕事満足度を詳細に分析したヒストグラムを見てみると、次のような特徴が見られます。
- 満足感も不満もないという人が非常に多い
- 高い満足度を持つ人はほとんどいない
- 少しの満足感や少しの不満を抱える人が多い
仕事への満足度が高い公務員は、給与の安定性以外に「仕事の面白みを感じられる職種や職場環境にいる人」だと推測できます。ただ、満足度の高い職種や職場環境にいる公務員はごくわずかであるようです。
大学中退で正社員就職を目指す方は、ぜひ以下の記事を参考にしてください。
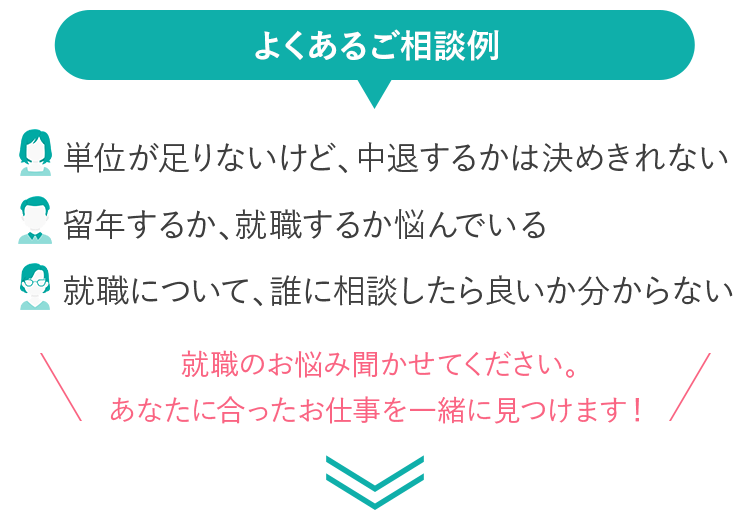

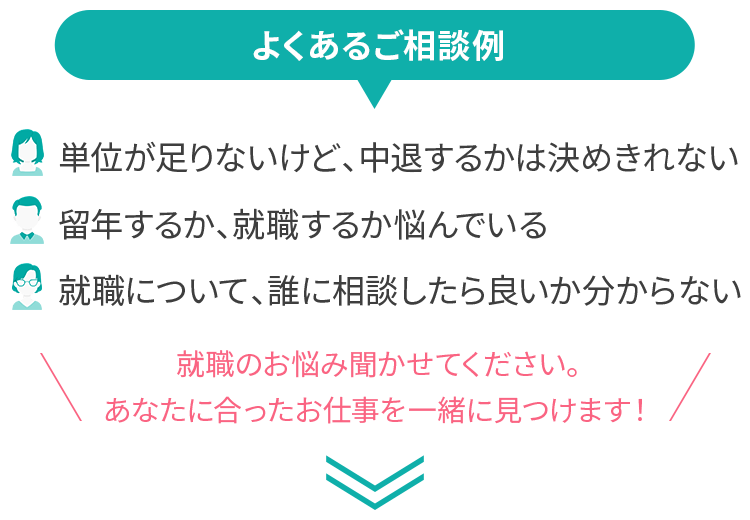
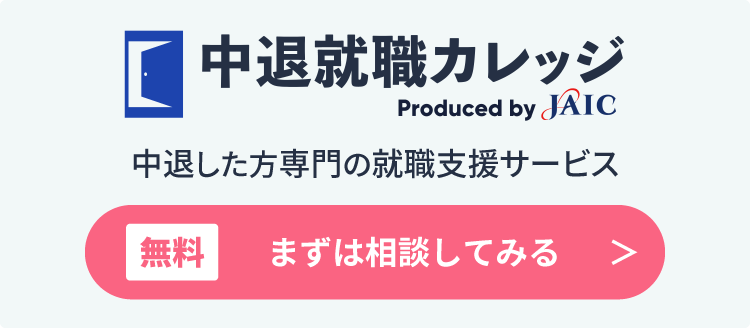
公務員よりも民間企業に就職するメリット3つ
公務員の道よりも、民間企業で働くことのメリットとは何でしょうか?具体的に3つ、ご紹介します。
1. 専門的なスキルを身に付けることができる
民間企業では業界ごと、あるいは「営業」「プログラミング」「マーケティング」などの職種ごとに、専門性のあるスキルを身に付けられる可能性があります。
2. 副業をすることが可能
公務員は副業を禁じられていますが、民間企業ならば副業OKの会社もあります。
以前は企業も副業を禁止している事が多かったので、勤め先にバレないようこっそり副業している人もいました。近年では副業を許容・推奨している企業が増加し、堂々と副業する人も増えてきました。将来不安やコロナ禍もあり、ひとつの仕事からの収入だけに頼らず、複数の収入源を持つことが理想とされつつあります。
3. 将来的に、転職や独立がしやすい
民間企業に勤める方が、将来的に転職や独立を目指しやすいという傾向があります。
民間企業で培われる専門的なスキル・知識や、多様な取引先を通じて得られる経験・人脈などを活かして、より条件のいい企業に転職したり、自分自身で事業を起こす人もいます。
大学中退者が民間企業に就職する方法
大学中退後に民間企業に就職するには、大学を卒業後に就職する場合とは異なる対策が必要になります。後悔しないために、事前にしっかりと準備して臨みましょう。
就職するための準備が必要
新卒での就職活動においても、企業の情報収集・自己分析・面接対策など、さまざまな準備を行います。
大学中退者の就職活動であれば、「卒業まで至らなかった事情」に応じて、なおさら入念な準備、さらに中退者特有の工夫が必要です。
「中退」という事実を、自分自身がネガティブにとらえてしまう傾向もあるため、ひとりで抱え込まず、就職活動に関する外部の助言・アドバイスを求めることをおすすめします。
大学の就職課に個別に相談してみる、中退者の就職活動を支援している民間サービスを利用するなど、客観的・専門的な知見を取り入れて、前向きに就職活動の準備を整えていきましょう。
大学を中退して就職できるか詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
大学中退の理由を答えられるようにする
大学中退者は「大学を中退した理由」について、面接の場で必ず質問されます。そのため、あらかじめ回答を用意しておかなければなりません。
中退理由はネガティブな回答になりやすいため、伝え方には注意が必要です。「単位が取れなかった」「学校に行くのが面倒になった」などの中退理由であれば、ポジティブに伝えるのはなかなか難しいと思います。
ポイントは、中退理由に合わせて「将来のビジョンや、仕事に対しての熱意・取り組む姿勢」を伝えることです。「大学中退という挫折を乗り越えられる人」、「過去の失敗から学び、それを今後の仕事に活かせる人」、そういう人材を企業も求めています。
「中退理由の説明」をしっかりと行うだけでなく、その経験をむしろアピールポイントとして伝えるところまで準備しておきましょう。
大学中退の理由を面接でうまくアピールする方法やコツを詳しく知りたい人は、以下の記事を参考にしてください。
就職支援サービスを利用する
前述のとおり、大学中退した場合の就職活動には、新卒時とは異なる工夫や準備が必要です。
ジェイックでは、大学中退者向けの就職支援も積極的に行っています。これまでも多くのご相談をいただいてきました。
そして、多くの方が以下の理由から「もっと早く相談すれば良かった」と言います。
- まずは無料で相談ができる
- 専任のアドバイザーから、自己分析・面接対策への助言が得られる
- 研修、複数社と面接ができる集団面接など、短期で効率的に活動できる
- 「中退であっても、良い人材ならば採用したい」と考える企業がエントリーしている
- 最短の場合、約2週間で企業から内定がもらえる
上記のようにジェイックでは、大学を中退した方への就職支援を行っているので、ぜひ気軽に相談してみてください。
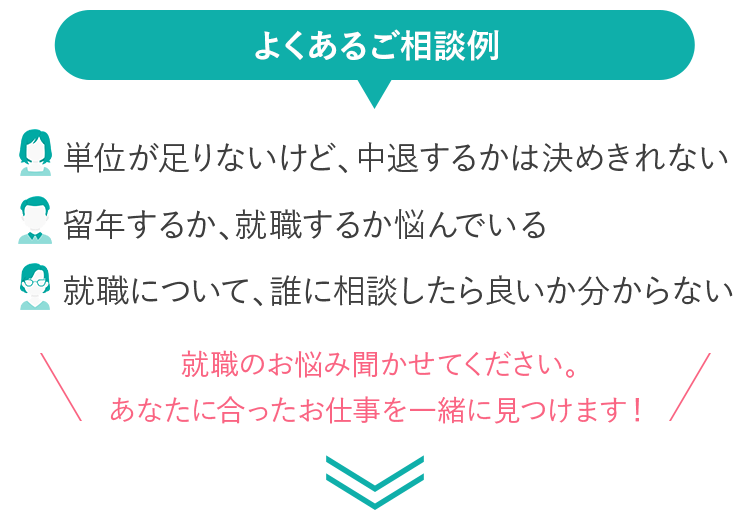

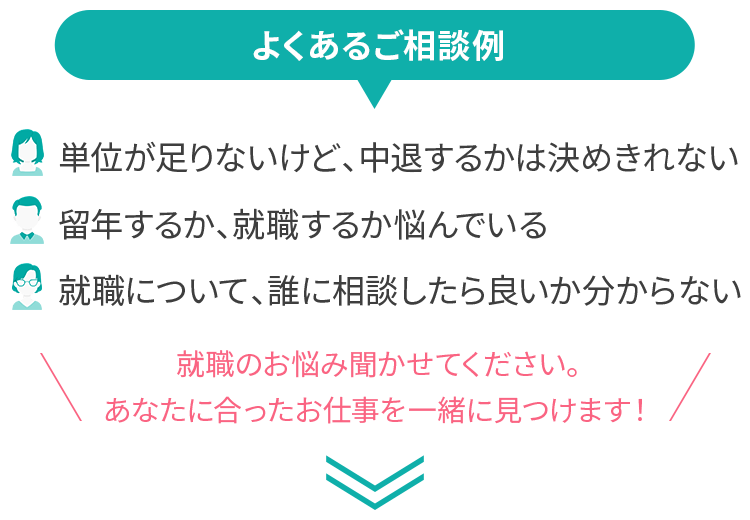
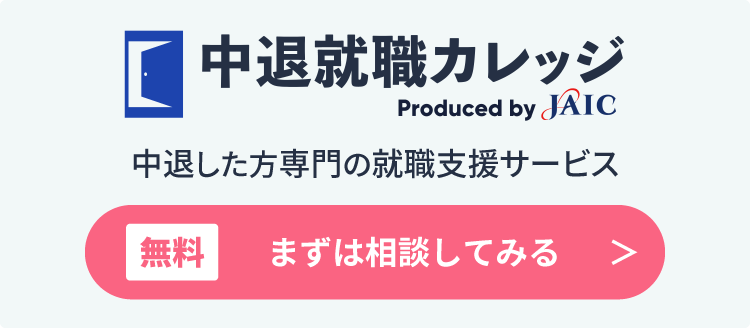
「大学中退 公務員」についてよくある質問
大学を中退して、公務員になりたいと考えている人にとって、わからないことや不安なことはたくさんあるはずです。
大学を中退した人が公務員への進路を考えるときに、よくある質問をピックアップして紹介しましょう。
大学中退でも地方上級公務員になれるのか?
大学を中退した人でも、地方上級公務員になることは不可能ではありません。
地方上級公務員とは、地方公務員試験で大学卒業程度のレベルが求められる試験区分のことです。
しかし、試験のレベルが非常に高く、倍率も高いので採用ハードルが必然的に上がります。
大学を中退した人が地方上級公務員になるのであれば、まず高校卒業程度のレベルが求められる地方公務員初級の試験に合格して、働きながら上級試験を目指すのがおすすめです。
地方上級公務員の試験は大卒程度のレベルが求められていますが、これはあくまでも目安であり、学歴を問わず受験できます。大学中退の人が地方上級公務員になりたいのであれば、しっかり対策を取り、計画的に準備することが必要です。
大学中退で公務員になることはできるの?
「大学中退で公務員になることは可能?」の章で、大学中退者が公務員になれるのかについて解説しています。また、大卒と高卒の公務員試験の採用者の割合や給料・キャリアの面で比較をしていますので、ご参照ください。
大学中退で公務員になる方法とは?
大学中退者が公務員になるために必要な対策方法や、大学中退者が目指せる公務員の種類について「大学中退で公務員になる方法とは」の章で解説しています。ぜひご覧ください。
大学中退でも公務員試験に合格できる?
大学を中退した人でも、公務員試験に合格することは可能です。
ただし、公務員試験の種類によっては大卒程度のレベルを求められるケースもあり、難易度も倍率も高いため、合格へのハードルは非常に高くなります。公務員試験には年齢制限もあるため、合格して公務員になるためには、計画的かつ入念な準備が必要といえるでしょう。
大学中退した23歳でも公務員になれる?
大学を中退した23歳でも、地方公務員なら自治体によって受験できるケースもあるので、公務員になれるチャンスはあります。
ただし、高卒程度のレベルが求められる公務員の場合、受験資格が20~21歳までに定められている自治体が多いのです。そのため、受験できるところが限られてしまうのが現実。
自分が受けたい公務員試験の受験資格や必要な学歴を、事前に調査しておくことがポイントです。
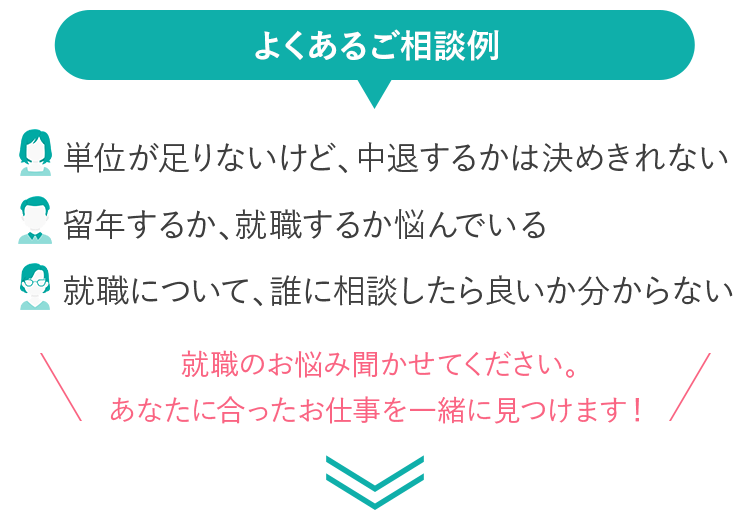

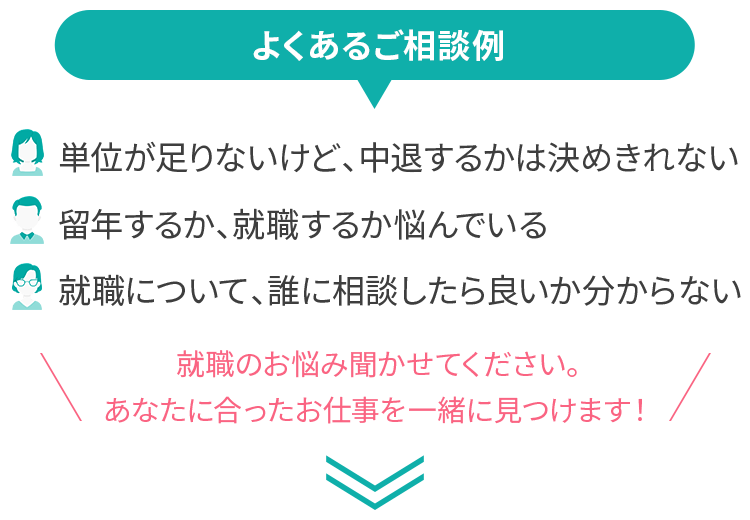
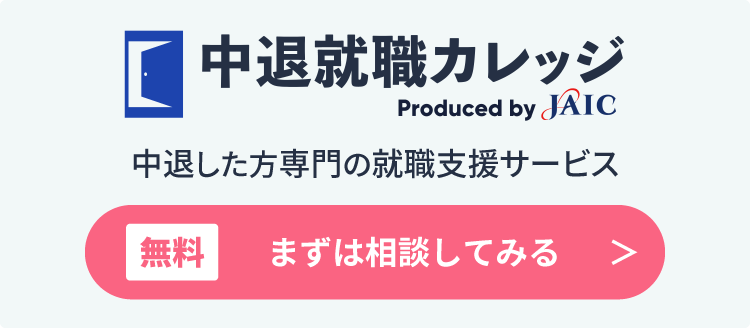
まとめ
大学を中退しても公務員になれるのか、またその方法についてご紹介してきました。
そして、民間企業への就職も選択肢の一つであること、就職活動の具体的なポイントも解説しました。
公務員と民間企業、それぞれの持つメリット・デメリットを知った上で、現在の自分の状況や、これからどう働いていきたいかを踏まえて検討してください。いずれの道を選ぶにしても、短期間で効率よく目標に向かっていくことを心がけましょう。

こんな方におすすめ!
- 学歴に自信がないから就職できるか不安
- 就職について、誰に相談したら良いか分からない
- 中退しようかどうかを迷っている
- 学歴に自信がないから就職できるか不安
- 就職について、誰に相談したら良いか分からない
- 中退しようかどうかを迷っている