
ひきこもりの年齢層は?
ひきこもりの年齢層は40代以降が特に多く、40歳~69歳のうち2.97%がひきこもり状態にあります。
一方で、15歳~39歳のひきこもりの割合は2.05%です。
| 15歳~39歳 | 40歳~69歳(参考:うち40~64歳) | |
|---|---|---|
| 広義の引きこもりの割合 | 2.05% | 2.97%(2.02%) |
出典:内閣府「こども・若者の意識と生活に関する調査(令和4年度)第3部 調査結果の概要Ⅱ 」p.163(一部加工)
なお、ここでの引きこもりとは「広義の引きこもり」を指し、内閣府の調査「こども・若者の意識と生活に関する調査 (令和年4度) 」では以下のように定義しています。
| 広義の引きこもり 「準引きこもり」と「狭義の引きこもり」の合計 ■準引きこもり普段は家にいるが、自分の趣味に関する用事のときだけ外出する ■狭義の引きこもり 以下3つに該当する人を合わせた数 ・普段は家にいるが、近所のコンビニなどには出かける ・自室からは出るが、家からは出ない ・自室からほとんど出ない |
準引きこもりの割合
内閣府の調査では「普段は家にいるが、自分の趣味に関する用事のときだけ外出する」人を“準引きこもり”と定義しています。
この定義をもとにすると、15歳~39歳は0.95%、40歳~69歳は1.23%が準引きこもりに該当します。
引きこもり(広義の引きこもり)の中での割合としては、15歳~39歳は約46%、40歳~69歳は約41%です。
| 15歳~39歳 | 40歳~69歳(参考:うち40~64歳) | |
|---|---|---|
| 準引きこもりの割合 | 0.95% | 1.23%(0.70%) |
出典:内閣府「こども・若者の意識と生活に関する調査(令和4年度)第3部 調査結果の概要Ⅱ 」p.163(一部加工)
狭義の引きこもりの割合
内閣府の調査では、以下3つのパターンを“狭義の引きこもり”と定義しています。
- 普段は家にいるが、近所のコンビニなどには出かける
- 自室からは出るが、家からは出ない
- 自室からほとんど出ない
この定義をもとにすると、15歳~39歳は1.1%、40歳~69歳は1.75%が狭義の引きこもりに該当します。
これは広義の引きこもりのうち、15歳~39歳では約53%、40歳~69歳では約60%が当てはまり、準引きこもり(普段は家にいるが、自分の趣味に関する用事のときだけ外出する)を上回っていることが特徴です。
なお、この調査によると「家から出ない」または「自室からほとんど出ない」人の割合が低く、ひきこもりに対するイメージとして持たれがちな「家や部屋から全く出ない」という人はそこまで多くないことが分かります。
| 狭義の引きこもりの割合 | 15歳~39歳 | 40歳~69歳(参考:うち40~64歳) |
|---|---|---|
| 普段は家にいるが、近所のコンビニなどには出かける | 0.74% | 1.55%(1.17%) |
| 自室からは出るが、家からは出ない | 0.30% | 0.08%(0.07%) |
| 自室からほとんど出ない | 0.06% | 0.12%(0.07%) |
出典:内閣府「こども・若者の意識と生活に関する調査(令和4年度)第3部 調査結果の概要Ⅱ 」p.163(一部加工)
【参考】江戸川区の「ひきこもり大規模調査」
東京都江戸川区では、区内のひきこもりの実態を調べるために、令和3年度に大規模な調査を実施しました。
ここでは区民から10万件以上寄せられた回答をもとに、ひきこもりのリアルな現状をデータと共にお伝えします。
※江戸川区の「ひきこもり大規模調査」では、ひきこもりの定義を「仕事や学校等に行かず、家族以外の人との交流をほとんどしない方」としています。厚生労働省の定義「仕事や学校に行かず、かつ家族以外の人とほとんど交流せずに6か月以上続けて自宅にひきこもっている状態」とは異なる点にご留意ください
ひきこもり当事者は40代が最多
江戸川区のひきこもり数は40代が最も多く、割合としては17.1%でした。
40代の次は50代(16.6%)、30代(13.9%)と続くため、働き盛りといえる30代~50代のミドル層にひきこもり当事者が多いことが分かります。
一方で、本調査において割合が最も低かった年代は60代(9.6%)で、70代(10.0%)と80代以上(10.5%)が次に続きます。
| 回答数 | 割合 | |
|---|---|---|
| 20歳未満 | 742人 | 10.60% |
| 20代 | 813人 | 11.70% |
| 30代 | 968人 | 13.90% |
| 40代 | 1,196人 | 17.10% |
| 50代 | 1,155人 | 16.60% |
| 60代 | 671人 | 9.60% |
| 70代 | 698人 | 10.00% |
| 80歳以上 | 733人 | 10.50% |
| 合計 | 6,976人 | 100.0% |
出典:江戸川区「令和3年度 江戸川区ひきこもり実態調査の結果報告書|第2節 ひきこもり当事者の概要(1 年齢)」p.11 (一部加工)
女性のひきこもりのほうが男性より多い
性別でいうと、女性のひきこもりの割合(51.4%)が男性(48.3%)を若干上回っています。
| 回答数 | 割合 | |
|---|---|---|
| 男 | 3,461人 | 48.30% |
| 女 | 3,684人 | 51.40% |
| その他 | 27人 | 0.40% |
| 合計 | 7,172人 | 100.00% |
出典:江戸川区「令和3年度 江戸川区ひきこもり実態調査の結果報告書|第2節 ひきこもり当事者の概要(2 性別 )」p.11(一部加工)
ひきこもり期間は「1年から3年未満」が最多
ひきこもり期間に関しては「1年から3年未満」と答えた人が28.7%と最多です。
一方で「10年以上」と答えた人も25.7%と2番目に高くなっています。
本調査ではこうした推計をもとに、ひきこもり期間が短い人を早急に支援しないと長期化する恐れがあることを示唆しています。
| 回答数 | 割合 | |
|---|---|---|
| 6か月未満 | 525人 | 7.50% |
| 6か月~1年未満 | 610人 | 8.70% |
| 1年~3年未満 | 2,013人 | 28.70% |
| 3年~5年未満 | 878人 | 12.50% |
| 5年~7年未満 | 591人 | 8.40% |
| 7年~10年未満 | 592人 | 8.40% |
| 10年以上 | 1,799人 | 25.70% |
| 合計 | 7,008人 | 100.00% |
出典:江戸川区「令和3年度 江戸川区ひきこもり実態調査の結果報告書|第2節 ひきこもり当事者の概要(4 ひきこもり期間 )」p.11(一部加工)
ひきこもりになった原因5つ
ひきこもりになった理由は人によってさまざまですが、特に次の5つが理由で家の中に
閉じこもってしまう人が多いようです。
- 会社を退職した
- 病気にかかった
- 人間関係が悪化した
- 職場に馴染めなかった
- コロナ禍で仕事を失った
1.会社を退職した
1つめの原因は、会社を退職したことです。
たとえば仕事で大きなミスをした責任を感じて退職した場合、「また失敗したらどうしよう…」といった気持ちから家に閉じこもりがちになってしまうこともあります。
職場の人間関係に悩んで退職した場合も、ひきこもりへとつながる可能性があるでしょう。
同僚とのトラブルや、上司からのパワハラなど、こうした辛い経験をしたことで人間関係に疲れ果て、社会との接触を避けるようになってしまう人も多いのです。
退職をきっかけに生活リズムが崩れ、昼夜逆転の生活を送るようになった結果、社会復帰への意欲が減退してしまう例も見られます。
2.病気にかかった
2つめの原因は、病気にかかったことです。
たとえばうつ病や不安障害などの精神的な病気にかかると、気分の落ち込みや焦りが強くなり、外出が難しくなります。
身体的な病気や怪我によって長期間入院したり、自宅での療養が長引いてしまったりすることもあるでしょう。
なかには、治療に専念するために仕事を辞めたり、学校を休学したりする人も少なくありません。
このように病気をきっかけとして社会とのつながりが希薄になると、自分の現状と社会との間に大きなギャップを感じてしまいます。
結果として社会復帰への不安から、ひきこもり状態に陥ってしまう人が多いのです。
3.人間関係が悪化した
3つめの原因は、人間関係の悪化です。
たとえば友人との喧嘩や、恋人との別れによって深い傷を負うと、人と距離を置くようになってしまうことがあります。
学生時代に友人関係がうまくいかずに孤立した経験から、「どうせ自分なんて…」と悲観的になり、新しい人間関係を築くことに踏み出せない人も多いものです。
社会生活を営む以上、人と関わる機会は出てきます。しかし人間関係で悩んできた人は「また傷つくかもしれない」といった気持ちから、人間関係の構築にあと一歩踏み出せません。
こうして外出を避けた結果、自分の部屋に閉じこもるようになり、そのままひきこもり状態になってしまうケースも見られます。
4.職場に馴染めなかった
4つめの原因は、職場に馴染めなかったことです。
職場の雰囲気や社風にうまく溶け込めず、孤独感や疎外感を感じてしまう人は多くいます。
「自分だけ浮いている気がする」といった気持ちから会社に行くことへの抵抗感が強くなり、休みがちになってしまう人も少なくありません。
仕事内容が自分に合わずに力不足を感じることで、強いストレスを感じる人も多いでしょう。
このように職場や仕事との相性が合わず、「自分は社会人に向いていない」と悲観的になったことで会社を退職し、そのままひきこもってしまう人もいるのです。
5.コロナ禍で仕事を失った
5つめの原因は、コロナ禍によって仕事を失ってしまったことです。
コロナ禍では多くの人が職を失い、経済的に辛い状況に追い込まれました。
本人としては働きたい気持ちが強いのに仕事がなかなか見つからず、将来的な不安から絶望感を覚え、ひきこもりがちになってしまったケースも多々見られます。
人と会う機会が大幅に減ったことで、孤立感を覚えた人も多いでしょう。
コロナ禍のような閉鎖的な状況では仕事に対する意欲や自信を失いやすいため、実際に引きこもりが増える一因となってしまったのです。
まとめ
この記事では、ひきこもりの年齢層について解説しました。
内閣府の調査によるとひきこもりは40代以降が特に多く、江戸川区が令和3年に実施した「ひきこもり大規模調査」でも40代の割合が17.1%と最多でした。
40代を超えると就職の可能性がさらに狭まってしまうため、40代以降に対する求人情報の提供といったサポートを国をあげて取り組む動きが見られます。
そしてひきこもりの長期化を防ぐために、30代以下の社会復帰を支援する重要性も叫ばれています。
たとえば「就職エージェント」や「わかものハローワーク」を中心に若手世代の支援が活発におこなわれているので、ひきこもり状態から抜け出したい方はこうしたサポートを頼ってみましょう。
参考:
内閣府「こども・若者の意識と生活に関する調査 (令和年4度)第3部 調査結果の概要Ⅱ 」
江戸川区「令和3年度 江戸川区ひきこもり実態調査の結果報告書

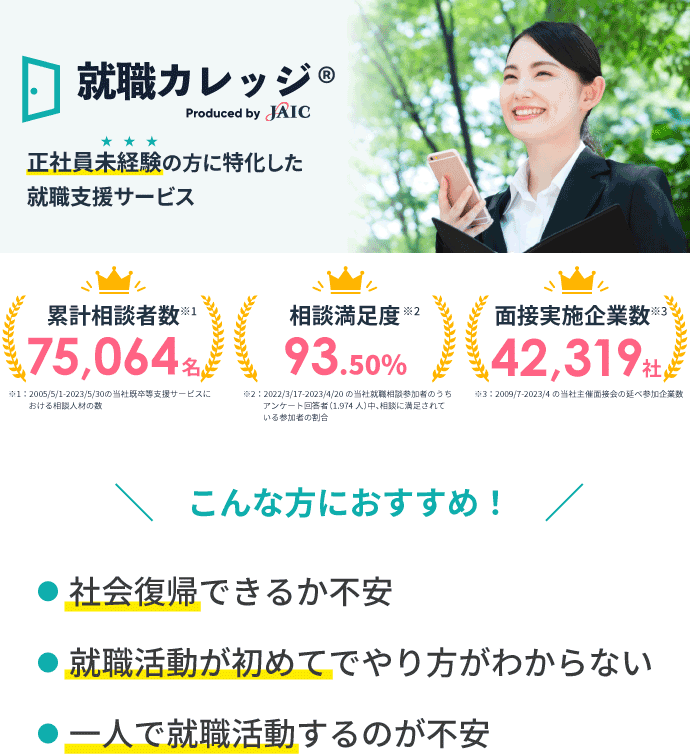

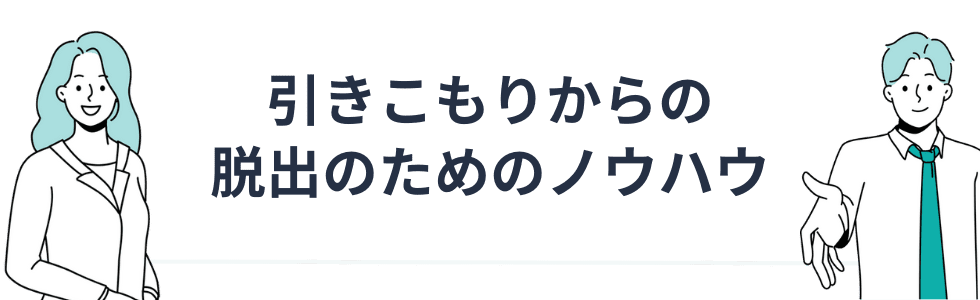
当社の就職に関するコンテンツの中から、引きこもりからの脱出や就職活動に不安を感じている方向けに、引きこもりからの脱出方法や就職活動で困りがちなことを解決するための記事をまとめました。
- 引きこもりを脱出する方法!脱出できる人とできない人の違いも紹介
- 引きこもりでもできる仕事おすすめ20選|探し方・就職支援を解説!
- 引きこもりから社会復帰するには?支援サービスやポイントを知ろう
- 引きこもりから正社員へ社会復帰する方法ーおすすめ職種/就職方法
- ニートから就職するには?就活の方法と成功させるポイントを解説
- 引きこもり・ニートの末路とは?脱するための方法も紹介!
- 無職から正社員に就職するには?賢い就活方法とポイントを解説
- ニートから社会復帰するには何からすべき?怖い原因と対処法も解説
- ニートでも安心!ニートの面接必勝法は?
- ニートの履歴書の書き方!空白期間や志望動機のポイントを例文付きで解説
- 20代の引きこもりに関する実態について!原因や脱出方法を解説
- 30代ニートの就職は難しい?ニートの割合や社会復帰の方法を紹介















































