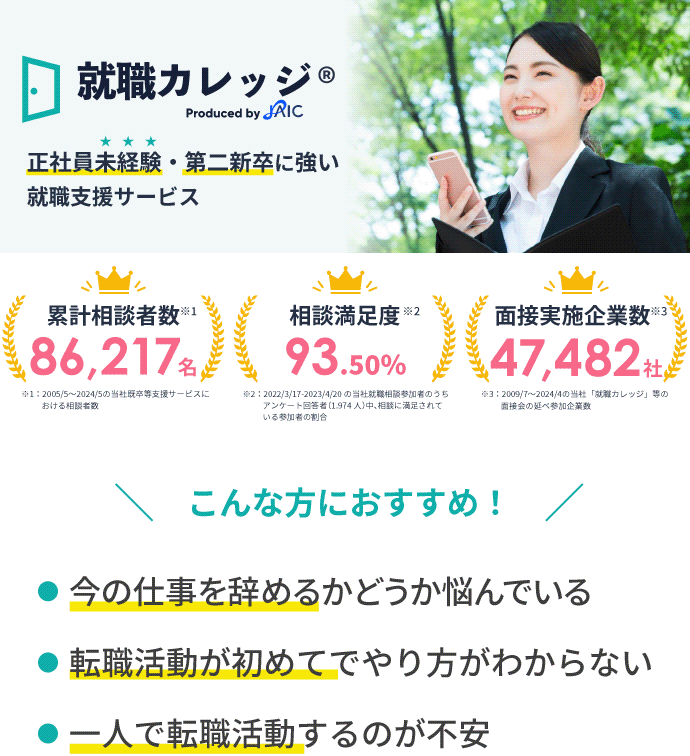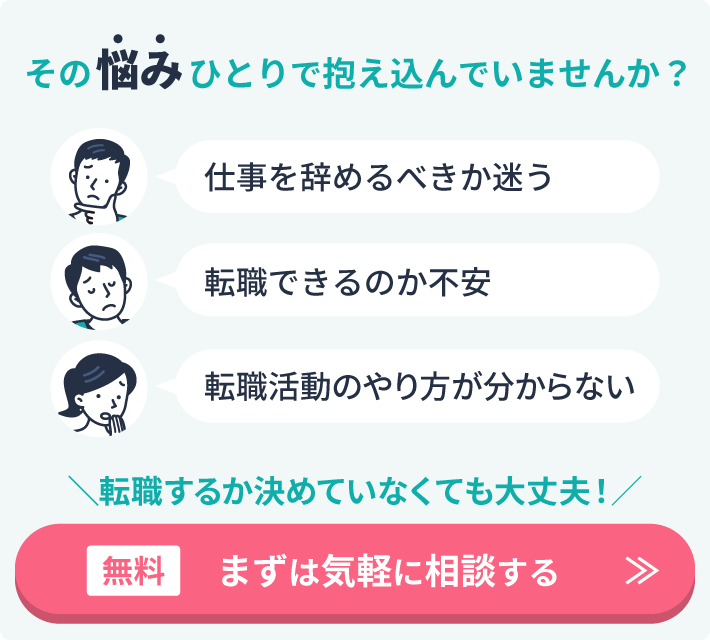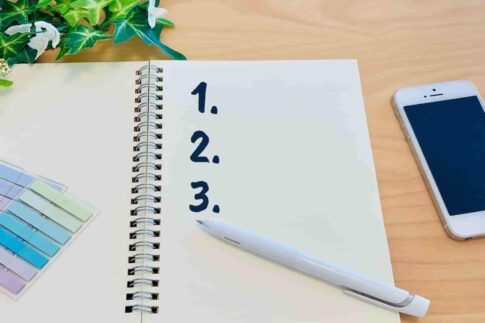「人間関係で仕事を辞めるのはもったいないでしょうか?」
そんな疑問を抱える方へ、この記事では退職の判断基準や考えるべきポイントを徹底解説します。
職場の人間関係が原因で悩むことは多くの人が経験する問題です。ですが、その「辞めたい」という気持ちが本当に退職に値するものなのか、あるいは乗り越えるべき壁なのかを見極めることが大切です。
辞めないほうが良いケースと辞めたほうが良いケースを具体例とともに解説し、適切な判断ができるようサポートします。また、退職を決意する前に考えるべき注意点や、転職面接での伝え方のコツも紹介します。
この記事を参考に、人間関係が原因で辞めるべきかどうかを冷静に判断しましょう。
この記事の目次
人間関係で辞めるのはもったいないか?甘え?
人間関係で辞めるのはもったいないのか、甘えではないのかという疑問については、状況次第で異なるため、一概に甘えと断じることはできません。
職場の人間関係が悪化し、会社に行くこと自体が精神的負担になる場合や、改善の見込みが全くない場合には、辞めることも選択肢の一つです。
辞める判断をする際、感情的な判断を避け、自分の状況を整理し現在の環境が本当に退職に値するかどうかを見極める必要があります。
また、辞めることが解決策になるのか、それとも問題解決能力を育てるチャンスを逃してしまうのかを慎重に判断しましょう。
退職理由や転職先の選択において、次のステップで同じ問題を繰り返さないための準備が重要となります。
その具体的な考え方や注意点については、後述のポイントを参考にしてください。

人間関係が理由で仕事を辞める人の割合
厚生労働省の調査によると、人間関係が理由で退職する人の割合は、女性13.3%、男性8.8%です。女性の退職理由の中では「その他の理由」を除くと、人間関係の理由が一位となっています。
この差は、女性が職場での人間関係をより重視する傾向があることや、人間関係の悩みを抱えやすいことが影響として考えられます。
一方、男性の退職理由では」賃金や仕事内容に対する不満が多くなっています。
以上のことから、人間関係が理由で辞める人は、特に女性に多いことが分かります。
厚生労働省:「転職者入職者の状況」
人間関係が理由で辞めるべきどうかの判断基準
職場の人間関係が原因で退職を考える人は少なくありませんが、感情的な判断で辞めるのは避けたいところです。辞めるべきか、それとも改善を目指すべきかを見極めるには、冷静に状況を整理し、合理的な判断基準を持つことが大切です。
そこで、人間関係が理由で会社を辞めない方がいいケースと辞めた方がいいケースについて紹介します。
辞めないほうがいいケース
以下のケースに当てはまる場合は、勢いで辞めることは避け、冷静に判断する必要があります。
- 自分にも問題があり改善が見込める
- 入社してから日が浅く仕事に慣れてない
- 社内に相談できる人がいる
- 仕事と割り切れている
- 仕事が好きでやりがいを感じている
1.自分にも問題があり改善が見込める
自分に改善の余地があると感じるなら、辞めるのはもったいないかもしれません。
以下に課題例を2つ挙げます。
1.無意識の言動が相手を不愉快にさせている場合
自分の発言や態度が無意識に相手を傷つけたり、誤解を生む原因となっていることがあるならば、相手の気持ちを考慮した言動を心掛けることが重要です。
2.職場のルールや暗黙のマナーを無視している場合
自分が知らず知らずのうちに職場の習慣やルールに反していることで、周囲から不信感を持たれているなら、適応する努力をすることが大切です。
こうした課題に向き合い、改善する努力をすることで、職場での人間関係が改善する可能性があります。辞める決断は、その後でも遅くありません。
2.入社してから日が浅く仕事に慣れてない
新しい環境では、仕事の進め方や人間関係に慣れるまで時間がかかるのは当然です。
入社して間もない時期に「合わない」と感じるのは、単なる慣れの問題である可能性が高く、この段階で辞めるのは適切ではない場合があります。
最初は周囲の雰囲気や文化に違和感を感じるかもしれませんが、時間をかけてコミュニケーションを重ねることで、信頼関係が構築され、働きやすくなることがよくあります。
よって入社後の日が浅い段階での退職は避け、まずは時間をかけて人間関係を構築し、環境に適応する努力をすることが重要です。
それでも問題が解決しない場合にのみ、退職を考えるのが良いでしょう。
3.社内に相談できる人がいる
社内に相談できる先輩や上司、人事担当者がいる場合、退職を急ぐ必要はありません。
人間関係の悩みは、自分一人で解決するのが難しいことが多いため、信頼できる人に状況を共有することが効果的です。
特に大手企業や上場企業では、トラブル専用の相談室や専門部署が設けられている場合もあり、客観的なアドバイスを受けられる環境があります。
まずは相談できる社内のリソースを活用し、それでも解決しない場合に退職を検討するのが賢明です。相談の一歩が、状況を大きく好転させるきっかけになるかもしれません。
4.仕事と割り切れている
職場の人間関係に問題があっても、それが業務に大きな支障を与えない場合は、必要最低限のコミュニケーションを取りつつ、自分の業務に集中することで対処できます。
どの職場にも多少の課題は存在するため、過剰に気にしすぎないことが重要です。
また、合わない同僚と深く関わる必要がなく、業務上の最低限のやり取りで仕事が円滑に進むのであれば、その関係を無理に改善しようとする必要はありません。
したがって、「仕事は仕事」と割り切れる場合は、退職を考えるよりも現状を受け入れ、自分の役割に集中することで問題を乗り越えられることがあります。
どの職場にも悩みはつきものだと理解し、冷静に対処する姿勢が大切です。
5.仕事が好きでやりがいを感じている
仕事が好きと感じられるのは、非常に恵まれた状況のため辞めるのはもったいないです。
また転職には新しい環境での適応やリスクが伴うため、現在の仕事への情熱を手放すのは慎重に考えるべきです。
特に、問題が人間関係に限定されている場合、他の方法で解決できる可能性があります。
上司や人事に相談し、職場内での部署異動を提案することで、人間関係の悩みを解消できる可能性があります。
好きな仕事を続けるためには、まずは社内のリソースを活用して問題を解決する方法を試すことが大切です。
それでも解決しない場合にのみ、転職を検討しても遅くはありません。

辞めたほうがいいケース
次に辞めないほうが良いケースについて解説します。
以下のケースに当てはまる場合は退職を検討してみてください。
- パワハラやセクハラなどハラスメントが横行している
- 社内でいじめや陰湿な嫌がらせがある
- 業務上の最低限のコミュニケーションができない
- ストレスで身体を壊している
- 問題や課題を改善しようとしたが見込めない
1.パワハラやセクハラなどハラスメントが横行している
ハラスメントは心身に大きな影響を及ぼす深刻な問題であるためパワハラなどが横行している場合は辞める選択肢が賢明です。
なぜなら、ハラスメントに改善の兆しが見られない場合、現状に耐え続けることはさらなるストレスや健康被害を招く可能性があるからです。
ハラスメントを受けている際は、会社の相談窓口や人事に相談し、職場環境の改善や異動などをしてもらえないか相談してみましょう。それでも解決が難しい場合は、転職を考えるべきでしょう。
2.社内でいじめや陰湿な嫌がらせがある
職場でいじめや嫌がらせが続いている場合、業務への支障や精神的負担が大きくなり、成果を出すことが難しくなります。
このような問題は、自分で解決することが難しいため、会社に異動させてもらえないか相談し、難しければ退職を検討しましょう。
特に上司からの理不尽な叱責や同僚からの排除といったケースでは、職場に留まり続けることが心身の健康やキャリアに悪影響を及ぼします。
よって改善が見込めない状況では、早めに行動を起こし転職を検討することが重要です。
新たな環境を選ぶことで、働きやすさを取り戻しより良いキャリアを築ける可能性が広がります。
3.業務上の最低限のコミュニケーションができない
職場で挨拶や業務上の報連相すら成立しない場合、心理的安全性が欠けており、働き続けるのは難しい状況です。
このような環境ではチームワークが機能せず、業務が円滑に進まないだけでなく、精神的なストレスも増大し、個人の成長やキャリアに悪影響を及ぼします。
たとえば同僚や上司が挨拶を無視し、必要な情報共有を拒む、または報連相が無視され業務に支障が出るケースなどがあります。
心理的安全性がない職場に長く留まることは、仕事の質や心身の健康に悪影響を及ぼすため、改善が見込めない場合は早めに転職を検討しましょう。
4.ストレスで身体を壊している
ストレスで体調を崩し、会社に行くのがつらいと感じたり、何もする気力が湧かない状態になっている場合は、辞めることを検討すべきです。
ストレスを放置すると、身体的な病気やメンタルヘルスの悪化を招き、キャリアや日常生活に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
たとえば、動悸や頭痛、胃痛といった身体症状が現れたり、仕事への意欲が完全に失われたり、睡眠不足や疲労感が続く場合は特に注意が必要です。
心身が発する限界のサインを見逃さず、早めに対処することが大切です。
無理をせず、より健康的な環境で再スタートを切ることで、人生の質を向上させる選択ができるでしょう。
5.問題や課題を改善しようとしたが見込めない
職場の人間関係の問題や課題に対し、改善を試みたにもかかわらず状況が変わらない場合は、退職を検討すべきです。
改善に向けて具体的な行動を起こしているので、辞めることは合理的な選択であり、転職活動においてもマイナスに評価されることは少ないでしょう。
例として、上司に相談しても状況が放置される、改善案が無視される、または話し合いを試みても相手に解決の意思が見られない場合などは、問題解決が困難な環境と言えます。
改善がない職場で無理に働き続けることは、心身の健康や成長を損ねるリスクがあります。
努力を尽くした上での退職は、次のステップへの前向きな判断として評価される可能性があります。

人間関係が理由で会社を辞めたいときに考えるべきこと
職場の人間関係が原因で辞めたいと感じることは誰にでも起こり得るものです。
ここでは感情的に決断する前に、現状を冷静に見つめ直し、改善や次の行動に向けて考えるべきポイントを解説します。
1.逃げ癖がつく可能性がある
人間関係を理由にすぐ会社を辞めると逃げ癖がつき、将来的に転職が難しくなる可能性があります。
人間関係を理由に辞職を繰り返すと、転職履歴が多くなり、「定着しない人材」とみなされるリスクが高まります。
たとえば、ちょっとした不快な出来事で退職を繰り返すと、長期的なキャリア形成に悪影響を与え、面接で短期間の退職理由を説明するのが難しくなることもあります。
人間関係の問題は、退職を最初の選択肢とせず、割り切りながら解決策を模索することで、将来のキャリアにプラスとなる対応ができるようになるでしょう。
2.転職したからと言って全てが解決するわけではない
人間関係を理由に転職を検討する際、転職が全ての問題を解決するわけではないことを理解することが重要です。
「辞めたい」と感じると視野が狭くなりがちで、転職先でも同じ悩みを抱える可能性があります。
まず「なぜ辞めたいのか」を明確にし、人間関係以外にも不満がないかを整理することで、現在の職場で解決可能な問題が見つかることもあります。
理由が明確になることで、転職を選ぶ場合も前向きなビジョンを持って行動できるようになります。
冷静に理由を見極め、最適な選択をすることが大切です。
3.成長の機会を逃すかもしれない
辞めたいと感じるとき、ネガティブな考え方に偏りがちで視野が狭くなり、成長の機会を逃す可能性があります。
辞める前に「なぜ辞めたいのか」を明確にし、人間関係以外の改善点や自身の成長につながる要素がないかを検討することが大切です。
たとえば、難しい人間関係を乗り越えることで、コミュニケーション能力や問題解決力が向上する場合があります。また、今の職場で得られる経験が将来のキャリアに役立つことも少なくありません。
辞めたい理由を整理することで、現在の環境で成長できる要素を見つけられる可能性があります。人間関係の課題を解決し、成長する機会を逃してしまうのはもったいないことなので、まずは自分で解決に向けて取り組めることを行いましょう。
それでも解決が難しい場合、前向きな転職ビジョンを持って行動することが重要です。
4.転職直後は良くても後から状況が悪くなる可能性もある
転職直後は新しい環境に期待が高まり良く感じることが多いですが、時間が経つにつれ別の問題が発生し、状況が悪化する可能性があります。
例として、上司や同僚との関係が悪化し人間関係のトラブルが再発したり、仕事内容が当初の説明と異なり不満を感じることがあるからです。
また、職場の文化やルールに馴染めずストレスを抱える場合もあるでしょう。
これらのリスクを考慮せずに転職を決めると、「転職しなければよかった」と後悔することにも繋がりかねません。
転職のリスクを冷静に分析し、今の職場での解決策や成長の可能性も検討した上で判断することが、後悔のない選択をするポイントです。
5.今の職場より良いとは限らない
転職先で必ずしも理想的な人間関係が築けるとは限りません。
新しい職場の雰囲気や人間関係は入社してみないと分からないため、期待外れになる可能性があります。
同じ状況でも人によって受け取り方が異なるため、全員にとって理想的な環境という保証はありません。
たとえば、雰囲気が良いと思った職場で派閥争いがあったり、上司との相性が悪くコミュニケーションがうまくいかない場合もあります。
転職を考える際は、現職で改善の余地がないかを検討し、新しい環境への過度な期待は控えることが大切です。
リスクを冷静に見極め、慎重に判断することで、後悔のない選択ができるでしょう。

人間関係が理由で辞めたい気持ちが強いときの対処法
職場の人間関係に悩み、辞めたい気持ちが強くなることは誰にでも起こり得るものです。
ここでは、その具体的な方法を紹介します。
1.相手の立場になって考える
相手の立場になって考える姿勢は、誤解を減らし、対話を円滑に進めるきっかけになります。
人間関係のトラブルは、相手の気持ちや背景を理解しないことが原因で起こることが多いため、相手の行動を冷静に捉え直すことが有効です。
たとえば、冷たく感じる指示も、相手が忙しく余裕を持てない状況である可能性を思えば考え方が変わるかもしれません。
このように相手の立場を考えることで、感情的な対立を防ぎ、職場での関係性を改善する糸口を見つけることができるでしょう。
辞める前に相手の立場を考える方法を試すことで、問題を解決できる可能性が広がります。
2.苦手な人とはできる限り距離を置く
職場で苦手な人がいる場合、無理に仲良くしようとせず、できる限り距離を置くことが効果的です。
挨拶や最低限の業務上のコミュニケーションが取れ、業務が円滑に進めば十分と割り切る姿勢が重要です。
具体的には、メールやチャットを活用して直接のやり取りを減らす、リモートワークを取り入れて顔を合わせる頻度を減らすなどの工夫が挙げられます。
このように距離を置きながら対応することで、不要なストレスや衝突を防ぎ、職場での心理的負担を軽減できます。
苦手な人との関係に悩む際は、こうした方法を試すことで状況を改善し、辞めたい気持ちを抑えられる可能性があります。
3.自分の考えや意見を伝える
人間関係を改善するには、自分の気持ちや意見をはっきり伝えることが大切です。
これにより誤解や摩擦が減り、対話が円滑に進む可能性が高まります。
明確な自己主張をすることで相互理解が深まり、不要な対立を回避できるため、職場でのストレスを軽減できる可能性があります。
たとえば、会議や話し合いの場で冷静に自分の意見を述べると効果的です。
感情的にならず、相手の考えも尊重しながら発言することで、建設的な関係を築ける可能性が広がります。
辞めたい気持ちが強いときでも、自分の意見を伝える方法を試すことで状況を改善できるかもしれません。
まずは対話を通じて人間関係を見直してみることが重要です。
4.自分なりのストレス解消法を見つける
ストレスが溜まると冷静な対応が難しくなり、人間関係がさらに悪化する可能性があります。
運動や趣味でリフレッシュすることで心に余裕を持てれば、職場での人間関係を穏やかに保ちやすくなるでしょう。
心の余裕があれば冷静な対応が可能になり、問題解決の糸口を見つけやすくなります。
ストレスをコントロールする力は、職場だけでなく人生全般に役立ちます。
まずは自分に合った解消法を見つけ、心の余裕を取り戻すことで、人間関係を冷静に見つめ直すことが大切です。
5.社外や公的な相談窓口で相談する
人間関係の悩みで辞めたい気持ちが強いときは、家族や友人、公的な相談窓口で相談することが有効です。
客観的な意見やアドバイスを得ることで、悩みを整理し解決の糸口を見つけられる可能性があります。
一人で抱え込むと視野が狭くなり冷静な判断が難しくなりますが、他者に話すことで気持ちが軽くなり、新たな視点で問題に向き合うことができるでしょう。
ただし、親などに相談すると感情的な反応や辞職への反対を受ける場合があるため、労働基準監督署や労働相談センターなどの公的な窓口を利用するのも効果的です。
さらに、メンタルヘルス支援の窓口を活用し、専門的なアドバイスを得るのも良い方法です。
適切な相談先を選び、冷静に状況を整理して前向きな解決を目指しましょう。
6.休職を検討する
仕事や職場の人間関係が原因で強いストレスを感じる場合、休職を検討することは有効な選択肢です。
退職せずに心身を休める時間を確保でき、雇用を維持できるメリットがあります。
休職することで経済的な安定を保ちながら、精神的・身体的な回復に専念し、冷静に状況を見直す時間を得られます。
ただし、休職制度は労働基準法で義務付けられておらず、会社ごとに条件が異なるため、事前に就業規則を確認することが重要です。
医師の診断書を取得し手続きを進めることで、ストレスの軽減と新たなキャリア選択の準備を進められるでしょう。
人間関係が理由で仕事を辞める際の注意点
ここでは、職場の人間関係が原因で仕事を辞めると決断した際に、退職後に後悔しないよう、事前に確認しておくべき注意点を紹介します。
1.勢いで会社を辞めない
感情的になり勢いで辞めてしまうと、収入面だけでなくキャリアにも大きなリスクを伴います。
たとえば、次の仕事が見つからず無職期間が長引き生活費に困る、転職先が自分に合わず再び短期間で退職を繰り返す、といったデメリットが挙げられます。
また転職回数が増えると採用担当者に「定着しない人」と見なされる可能性もあります。
感情的に辞めて転職先が自分に合わない場合、再び同じ問題に直面するリスクが高まります。
勢いで辞める前に冷静に状況を整理し、次のキャリアプランをしっかり立てることが大切です。
計画的に行動することでリスクを最小限に抑え、スムーズに次のステップへ進む準備を整えましょう。
2.人間関係が退職理由だと言わない
退職理由に人間関係を直接挙げると、周囲からの評価が下がり、次の採用にも悪影響を及ぼす可能性があります。
反対に「これまでの経験に感謝している」といった感謝の言葉を添えることで、円満退職が可能になり、今後の人脈形成にもプラスに働くことがあります。
退職時の対応で良い印象を残せば、次の職場でも信頼関係を築きやすくなります。
ポジティブな理由と感謝を示し、未来志向の姿勢で円満な退職を目指しましょう。
3.仕事を辞めるタイミングに注意する
仕事を辞める際は、業務の引き継ぎや調整を考慮し、余裕を持ったタイミングで進めることが大切です。
法律上は2週間前の申告で退職が可能ですが、企業規定や就業規則によって1ヶ月前の申告が求められる場合もあります。
また繁忙期や大規模プロジェクトの進行中に退職すると、同僚や会社に負担をかけ、トラブルの原因となる可能性があるでしょう。
閑散期やプロジェクト終了後など、周囲への影響が少ない時期を選ぶことで、円満な退職がしやすくなります。
適切なタイミングで退職することで、同僚との関係を良好に保ち、自身もスムーズに次のステップに進む準備が整います。
そのために事前に就業規則を確認し、退職準備は計画的に進めましょう。
転職の面接で転職理由を伝える際のポイント
転職の面接で転職理由を伝える際は、前向きで建設的な表現を心がけることが重要です。
ここでは好印象を与え、次のステップに繋げるためのポイントを紹介します。
1.不平不満を言わない
転職の面接で転職理由を伝える際、人間関係に関する不平不満を口にしないことが重要です。
たとえ事実であっても、「上司のパワハラがひどかった」「同僚との折り合いが悪かった」といった直接的な不満を述べると、他責的な印象を与え、面接官にネガティブに受け取られる可能性があります。
採用側は、問題を前向きに捉え成長しようとする姿勢を求めるため、過去の不満ではなく、未来の目標に焦点を当てることが求められます。
たとえば、「上司のパワハラが原因で辞めました」という表現は避け、「スキルをさらに磨き、新しい環境で挑戦したいと考えました」と前向きに伝えるべきです。
転職理由は、今後の目標や成長意欲を中心に伝えることで、面接官に好印象を与え、採用の可能性を高めることができます。
2.ポジティブに転職理由を伝える
転職の面接では、理由をポジティブに伝えることが重要です。
ネガティブな内容を話すと、他責的な印象を与え、面接官に評価を下げられる可能性があります。
一方で、ポジティブな理由を中心に伝えることで、前向きな姿勢や成長意欲をアピールでき、好印象を残すことができます。
たとえば、「業務内容に不満があった」という伝え方は避け、「これまで培ったスキルを活かし、専門性をさらに高めたい」という表現を用いると良いでしょう。
このように話すことで、ネガティブな印象を回避しつつ、自分のキャリアプランを具体的に伝えられます。
転職理由を考える際は、過去の不満や問題に焦点を当てず、未来への期待や目標を軸に構成しましょう。
そうすることで、面接官に「一緒に働きたい」と思わせる効果的なアピールが可能になります。
人間関係の改善が見込めないなら転職を検討しよう
職場の人間関係に悩み、改善が見込めない場合は、転職を視野に入れることが一つの選択肢です。
ただし、転職先でも同じ悩みに直面する可能性があるため、まずは自分で解決できることがないか考え、努力を尽くすことが重要です。
それでも問題が解決せず、今の職場での継続が精神的に厳しい場合、新しい環境でのスタートを切ることが前向きな一歩になるでしょう。
たとえば、何度も相談や対策を試みても関係性が改善しない職場では、転職を通じて新たな環境を手に入れることが可能です。
転職を検討する際は、転職エージェントに相談することで、自分に合った職場を見つけるサポートを受けられます。
ジェイックでは、希望や課題を丁寧にヒアリングし、一人ひとりに合った求人情報を提案しています。
無理なくキャリアを進めるために、まずは相談してみてはいかがでしょうか。