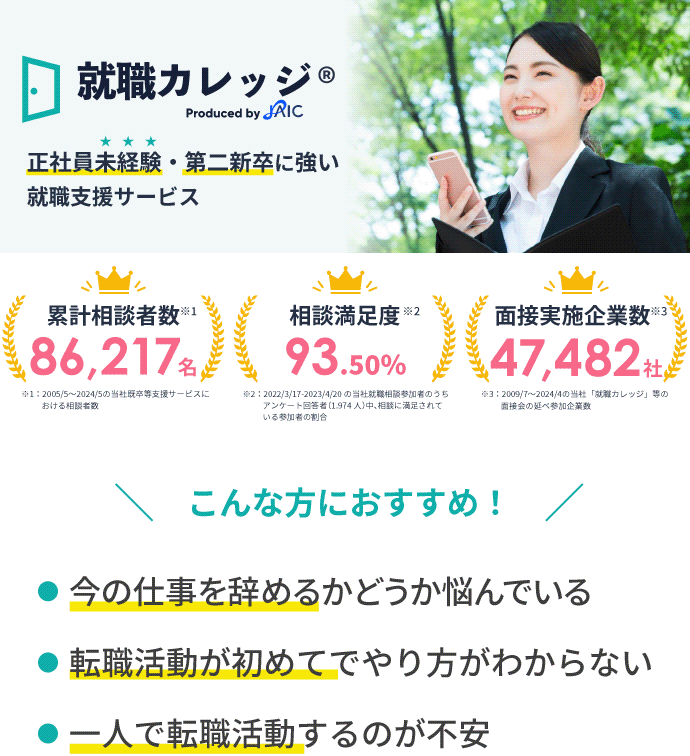面接で聞いていた仕事内容と実際の仕事内容が違うことを理由に仕事を辞めることは問題ありません。しかし、短期離職となるため転職で不利になるリスクもあります。
この記事では、仕事内容が違うときに辞めるべきかの判断基準と現状を改善する方法について解説します。
本記事を読めば、現状を改善し、自分の希望した仕事ができるようになるので参考にしてみてください。
この記事の目次
仕事内容が違うことを理由に仕事を辞めても大丈夫
仕事内容が求人内容と違っていることを理由に仕事を辞めること自体に問題はありません。
「労働基準法」第15条によって、労働条件を明示することが定められているからです。
企業は労働者に対して、実際の業務内容を記した労働条件通知書を示さなければいけません。
ただし求人情報と実際の実務内容が違うことが必ずしも違法とは限りません。求人情報は目安であり、すべての応募者に当てはまるわけではないからです。
明らかに労働条件通知書と異なる場合や面接で聞いた内容と違うことがあれば会社側と交渉したり、労働基準監督署に相談したりすることもできます。
なお、仕事内容が違うことを理由に退職することになった場合、会社都合退職になる可能性があります。
上記のことから、仕事内容が違うことを理由に辞めても問題ないでしょう。
「仕事内容が違う」が起こる原因
そもそもなぜ仕事内容が違うといった現象が起こるのか疑問を持つ人もいるでしょう。求人情報と仕事内容が違うのは以下のような原因が考えられます。
- 求人情報に誤解を生む表現があった
- 面接時の説明不足
- 採用担当と現場担当の認識違い
- 採用後に組織変更や業務内容の変更があった
1つずつ解説していくので参考にしてみてください。
求人情報に誤解を生む表現があった
求人情報は、応募者を集めるために魅力的なフレーズが使われています。うそではないものの、誇張した表現やキャッチーな言葉が使われており、誤解を生んでしまう可能性があるでしょう。
たとえば「シフト制で柔軟な働き方が可能」と求人情報で宣伝していたのに、実際はシフトは厳密に固定されていて自由に希望を伝えることは難しいといったケースがあります。
求人情報には良い情報が目立つ傾向があり、ネガティブな情報は書かれていないことも多いです。
曖昧な記載があれば、入念に調べて、実際の仕事内容を確認したほうがいいでしょう。
面接時の説明不足
面接時に企業側からの説明が不足していたことにより、応募者の認識と仕事内容が違ってしまうケースがあります。
面接ではあまり時間がないため、詳細な話ができず説明不足となってしまうからです。たとえば以下のようなケースが挙げられます。
- 面接でフレックス制の勤務形態と言われていたのに実際は固定時間の勤務だった
- 営業職として採用されたのに、最初の数年は工場勤務だった
口頭の説明だと証拠が残らないため、企業と応募者の間で認識違いが起きてしまいがちです。疑問に思ったことがあれば、面接時に質問して解消しておくのをおすすめします。
採用担当と現場担当の認識違い
採用担当と現場担当の認識に違いがあったことから仕事内容が違ってしまうケースがあります。
なぜなら、人事と現場の部署でうまくコミュニケーションがとれていない場合があるからです。
たとえば以下のようなケースが考えられます。
- 採用担当はまずは内勤で仕事を覚えてもらうと考えていた
- 現場担当は早く戦力となってもらうためにすぐに外回りに出てもらいたいと考えていた
本来は、採用担当と現場担当で共通した認識を持つ必要がありますが、うまくいかないこともあります。
このように採用担当と現場担当の間で認識違いがあると、求人情報と実際の仕事内容に違いが出てしまう可能性があるでしょう。
採用後に組織変更や業務内容の変更があった
「仕事内容が違う」が起こる原因として、採用後に組織変更や業務内容の変更があったケースが挙げられます。
組織変更や業務内容の変更は、経営陣で検討していて人事にまで情報が伝わっていないことも多いです。そのため、採用後に仕事内容が変わってしまう可能性があるでしょう。
たとえば、内定が出たのが2月頃で入社が4月からだった場合、4月から年度が変わるのに合わせて組織変更が行われるといったケースがあります。
組織変更によって配属先の部署がなくなってしまい、別の部署に配属となるケースもあるでしょう。
このように、組織変更などによって、採用時と実際の仕事内容が変わってしまうことがあります。
仕事内容が違うから辞めたい時の対処法
求人情報と実際の仕事内容が違っていれば、会社への不信感が強まり、辞めたいと感じるのも無理はありません。
自分が希望していた仕事とまったく違う仕事を任されたら悩んでしまう人も多いでしょう。
そこでここからは、仕事内容が違った時の対処法を紹介します。すぐ実践できるように、具体的な方法を解説したので、参考にしてみてください。
上司や人事に相談する
まずは、上司や人事に相談してみましょう。単純にお互いの認識が違っていたケースも考えられるからです。
労働条件通知書があれば、それを元に話し合うといいでしょう。会社の説明が不足していたり、自分が勘違いしていただけだったりする可能性もあります。
希望を伝えれば、業務内容や労働条件を変更してもらえるかもしれません。
とはいえ、どうやって上司や人事に相談したらいいかわからない人もいるでしょう。以下から
具体的な相談の仕方について紹介します。
上司や人事への相談の仕方
上司や人事へ相談する時は、以下のポイントが重要です。
- 自分の気持ちを整理して適切なタイミングで伝えること
- 具体的な例を出して説明すること
たとえば、企画職として入社したのに、その仕事はサブでメインは営業や顧客対応などの仕事だった場合を例として考えてみます。
まず、自分の認識では企画職として入社したと考えていること、実際に担当している業務は営業と顧客対応がメインとなっていることを具体的に伝えましょう。
その上で、自分の強みや興味関心は企画職にあり、経験を活かせるのも企画職であるため本来の業務に戻してもらえないかと相談してみてください。
このときに労働条件通知書を提示しながら、説明するとなお良いです。感情的にならず、冷静に状況を説明しましょう。
労働基準監督署に相談する
上司や人事に相談しても改善がみられない場合は、労働基準監督署に相談するのがおすすめです。「労働基準法」では、事業主は労働者へ労働条件を明示することが定められています。
場合によっては、違法となる可能性もあるので、専門機関に相談するのが良いでしょう。労働条件の通知内容と実際の仕事内容が違っていた場合は、契約を破棄することもできます。
違法性があったり、改善がみられなかったりする場合は、労働基準監督署に相談してみましょう。
労働基準監督署への相談の仕方
労働基準監督署へ相談する時は以下のポイントが大切です。
- 労働条件通知書を持参する
- 労働条件通知書と実際の仕事内容が違っていることを伝える
- 労働条件通知書がなければその旨も伝える
- 労働条件通知書どおりの履行を求めたが改善されなかったことを伝える
労働条件通知書がなく口頭のみの説明だったり、求人情報と明らかな違いがあったりと悪質なケースは、労働基準監督署へ相談するのがおすすめです。
労働基準法に違反している可能性がある場合は、専門家に相談することが必要になります。
実際仕事をしてみたら内容が違っていた場合には、退職を申し出ることも可能です。
とはいえ、すぐに退職するわけにはいかないので、労働基準監督署の「総合労働相談コーナー」に相談してみると良いでしょう。
転職する
上司や人事、労働基準監督署へ相談しても改善がみられない場合は、転職することも一つの手段です。
今の会社では、現状を解決することは困難であり、そのまま勤めていてもいいことはないからです。
とはいえ、入社してすぐ辞めてしまうと短期離職となり、次の転職が決まらないのではと心配な人もいるかもしれません。
その場合は、退職理由で「雇用条件の相違」があったと伝えれば問題ありません。
仕事内容が違うときは、新たな仕事を探すために、転職活動をしましょう。
仕事内容の違いを理由に辞めるべきかどうかの判断基準
求人情報と実際の仕事内容が違っていたら辞めたいと感じるのは無理もありません。しかし、本当に辞めるべきか決心がつかない人も多いでしょう。
ここでは、辞めるべきかの判断基準を紹介します。
- 上司や人事に相談し改善される可能性はあるか
- 部署異動の可能性はあるか
- 今後のキャリアに活かせるか
上記のポイントを基準に辞めるべきか判断すると良いでしょう。
上司や人事に相談し改善される可能性はあるか
1つ目の判断基準は、仕事内容が違うことについて上司や人事に相談した時に、改善される可能性があるかどうかです。
改善される可能性が低いなら、そのまま働き続けていても現状は変わらないでしょう。
実際に相談した時の上司や人事の反応を良く観察してみてください。真摯に話を聞いてくれ、具体的な改善策を考えてくれるようだったら可能性があります。
一方で、あまり話を聞いてくれない、相談しても流されてしまうといった対応だった場合は、改善される可能性は低いでしょう。
相談した時の対応によって辞めるべきか判断すると良いでしょう。
部署異動の可能性はあるか
2つ目の判断基準は、部署異動の可能性があるかです。異動によって希望する仕事ができる部署に配属されれば、問題を解決できるからです。
上司や人事に相談した時に、部署異動が可能かどうかも一緒に聞いてみるといいでしょう。違う部署で、希望に近い仕事ができるのであれば、その部署へ配属してもらえないか交渉するのがおすすめです。
企業としても、せっかく採用した人材にすぐ辞められてしまっては困るので、検討してくれるかもしれません。
仕事内容が違う時は、あきらめず部署異動の可能性があるか相談してみてください。
今後のキャリアに活かせるか
3つ目の判断基準は、今後のキャリアに活かせるかどうかです。今の仕事が希望していた内容と違っていたとしても、その仕事を経験することで今後のキャリアに活かせるのであればチャンスになるからです。
一時的に違う仕事をすることで、新しい知見を得られることもあります。特に年齢が若いうちは、さまざまな仕事を経験することで、自分の成長の幅が広がるでしょう。
とはいえ、自分の希望と違う仕事をしていると悩むことも多いかもしれません。その場合は、自分が今後どのようなキャリアを築きたいかを考えて、今の仕事がそこに活かせるかどうか考えてみるといいでしょう。
仕事内容の違いを理由に辞めてもいいケース
仕事内容が違うからという理由で辞めたいと感じるものの、本当に辞めてもいいか決心がつかない人も多いでしょう。
ここからは辞めてもいいケースを紹介します。以下を読めば、自分が辞めてもいいかわかるでしょう。
- 求人内容に明らかな虚偽記載があった
- 上司や人事に相談しても改善されない
- 仕事内容が苦痛で精神的な不調が出ている
求人内容に明らかな虚偽記載があった
求人内容に明らかな虚偽記載があった場合は、仕事を辞めてもいいでしょう。応募者を騙すような行為をする会社は信用できないからです。
もしかしたら「労働基準法」に違反している可能性があるかもしれません。
たとえば、以下のようなケースが考えられます。
- 正社員採用とあったのにパート・アルバイト採用だった
- 事務職と言われたのに営業職だった
- 基本給が残業代込みの給料であることを隠されていた
- 有給が取りやすいと記載があったが実際はほとんど取れなかった
悪質な虚偽記載があった場合は、倫理観が疑われます。明らかな嘘をつくような会社は辞めた方がいいでしょう。
上司や人事に相談しても改善されない
仕事内容が違うことを上司や人事に相談しても、改善されない場合は辞めてもいいでしょう。不誠実な対応をする会社は信用できないからです。
労働条件が違うことを相談しても、相手にされなかったり、放置されたりといったケースがあります。このような会社では、現状を解決するのは難しいでしょう。
今後何かあった場合に上司や人事に相談しても、対応してもらえない可能性が高いです。そのような職場に勤めていてもいいことはありません。
改善されるのを待つより、退職して次の職場を探す方が懸命でしょう。
仕事内容が苦痛で精神的な不調が出ている
仕事内容が苦痛で精神的な不調が出ている場合は、仕事を辞めることをおすすめします。うつ病や適応障害などの病気になって働けなくなってしまう可能性があるからです。
たとえば、事務職と思って入社したのに営業に回され、ストレスや疲労が蓄積してしまったケースなどが考えられます。
具体的には以下のような症状が出てしまうかもしれません。
- 常に憂鬱感がある
- 夜眠れない
- 朝起きれない
- 食欲がない
- 過食である
このような症状が続いている場合は、危険信号です。治療やカウンセリングが必要になる可能性もあります。
体調を崩す前に、早く辞めた方がいいでしょう。
仕事内容の違いを理由に辞めない方がいいケース
一方で、仕事内容が違っても辞めない方がいいケースもあります。退職し、新しい仕事を探すのは労力がかかるからです。
短期離職となれば、その後の転職活動にも影響があるかもしれません。
ここでは仕事内容が違ったとしても辞めない方がいいケースについて紹介します。自分の状況と照らし合わせて参考にしてみてください。
新しいスキルや自分の成長に繋がる場合
希望していた仕事内容と違ったとしても、その仕事に取り組むことで新しいスキルを得られたり、自分の成長に繋がる場合があります。
そういったケースではすぐ辞めない方がいいでしょう。今後のキャリアを築く上で役に立つ経験を積めるかもしれないからです。
たとえば、事務職を希望して入社したけれど、営業職として配属された場合。営業職で、コミュニケーションスキルや、タスク管理能力を身につけられるかもしれません。
これらは事務職の業務でも役に立つスキルです。営業の経験がある事務職として、キャリアを築く上で、大きな武器となるでしょう。
仕事内容が改善される見込みがある
上司や人事に相談した結果、仕事内容が改善される見込みがある場合は辞めない方がいいでしょう。
入社当初の希望通りの仕事ができるなら問題はありません。
一度入社を決めた会社であれば、仕事内容だけでなく他にも魅力があったと考えられます。社風や福利厚生など、仕事内容以外の条件も大事なことです。
もう一度転職活動を行うのも労力がかかりますし、短期離職となれば経歴に傷がついてしまうかもしれません。
仕事内容が改善される見込みがあれば、辞めずに今の仕事を続けた方が良いでしょう。
仕事内容以外の環境が良い
仕事内容以外の環境が良い場合、すぐに辞めない方がいいでしょう。働いていく上で、労働環境は重要だからです。
たとえば、人間関係が良好だったり、給与や福利厚生が充実していたりするのであればその職場は貴重です。
働きやすい環境が整っていれば、仕事内容が違っていても続けやすいでしょう。働き続けているうちに仕事内容を好きになるかもしれません。
すぐに辞めると、短期離職となり今後の転職活動にも影響が出る可能性もあります。仕事内容以外の環境が良い場合は、すぐに辞めず働き続けてみるといいでしょう。
自分のキャリアの目標と大きくズレていない
仕事内容が違うものの、自分のキャリアの目標と大きくずれていない場合は、すぐには辞めない方がいいでしょう。
一時的に希望外の業務をこなすことで、将来のキャリアに役立つ可能性があるからです。
たとえば、企画の仕事をしたいけど営業職になった場合。現場の仕事を経験することで、斬新な企画のアイディアを得られるかもしれません。
さまざまな業務をこなすことで、新たなスキルを得たり、大きく成長したりできます。その結果、自分のキャリアの幅を広げられるかもしれません。
このように自分のキャリアの目標とずれていなければやめずに働き続けた方がいいでしょう。
仕事内容が違う仕事に就くのを防ぐポイント
これまで紹介した対処法を実践してみたけど、どうしても辞めたい人もいるでしょう。ここからは、今後新たな仕事を探す上で仕事内容が違う仕事に就くのを防ぐためのポイントを解説します。
以下のポイントを抑えれば自分が希望する仕事内容の仕事に就けるので参考にしてみてください。
自分の希望を明確にする
まずは自分の希望を明確にしましょう。希望が曖昧だと、ミスマッチが起こりやすいからです。
自分がやりたい仕事、やりたくない仕事をリストアップしておくと良いでしょう。その際は、以下のように職種と業界の両方から考えるのがおすすめです。
- 職種 営業・事務・企画・管理
- 業界 IT系・エンタメ・金融・製造
このようにできるだけ具体的にリストアップしましょう。他にも仕事内容や給与、勤務地など、何を最優先に考えるかを決めることで希望と違う仕事を選んでしまうリスクを減らせます。
たとえば、親の介護があるので勤務地は譲れないなど、それぞれの事情に合わせて優先事項を決めるといいです。
ここを明確にしないと同じ過ちを繰り返してしまいます。たっぷりと時間をとって、できるだけ詳細に考えましょう。
企業研究をする
自分の希望を明確にしたら、応募する会社の企業研究をしましょう。自分の希望が叶えられる仕事なのかを判断するためです。
これだけは大切にしたいという条件を軸に以下の要素を調べるといいでしょう。
- 経営方針
- 成長性
- 業務内容
- 育成・福利厚生
- 社風
他にも、以下のような情報を調べるとより詳しく企業を研究できます。
- 基本情報:企業理念・経営方針・会社の歴史・売上高・従業員数・提供する商品
- 顧客情報:志望する企業がどのような顧客を対象にしているか
- 競合情報:競合他社についても市場での割合や特徴を調べる、志望企業と比較する
このようにさまざまな情報を集めて企業研究をすると、希望と違う仕事に就くリスクを減らせるでしょう。
求人情報を慎重に確認する
次に求人情報を慎重に確認しましょう。記載されている条件が入社後と違うことを防ぐためです。
具体的には、以下の点を押さえておくと良いでしょう。
- 応募企業の事業内容
- 具体的な仕事内容
- 募集背景
- 教育体制
- 労働時間や勤務形態
- 福利厚生
特に仕事内容・労働時間、勤務形態は慎重に調べましょう。曖昧な表現がある場合は、ハローワークや転職エージェントに確認するのをおすすめします。
たとえば、企画職と書いてあっても具体的にどんな業務があるのかを確認すべきです。顧客対応はあるのか、社内のみで完結する仕事なのかなど、自分の希望と合うか照らし合わせながら調べましょう。
また、基本的に求人情報の表現は誇張されていることを意識しておいてください。
会社の評判や口コミサイトを調べる
次に、会社の評判や口コミサイトを調べましょう。求人情報には載っていない会社の実態を知るためです。
求人情報は応募者を集めるために、脚色されている可能性があるので、記載されているすべてを鵜呑みにしてはいけません。
会社の評判を調べるには以下のような情報源があります。
- 転職サイト
- 転職エージェント
- 口コミサイト
- 企業のホームページ
- SNS
- 会社四季報
近年では、企業の採用担当者がSNSを利用して発信していることも多いです。SNSからは社内の雰囲気や実際の仕事現場がわかりやすいので参考になるでしょう。
また、ネットだけでなくリアルで社員や関係者に直接話を聞くことも重要です。ネットには誇張した情報も多く、特に口コミサイトはネガティブな意見が集まりやすい傾向にあります。
実際に社員や関係者に会うことで、よりリアルな話を聞けるでしょう。
面接で仕事内容を詳しく聞く
面接で仕事内容について詳しく聞くのも1つの手段です。面接は社員に直接話を聞ける貴重な場だからです。
面接の段階で、残業時間や休日、転勤など雇用条件の確認が行われる場合もあります。その時に疑問点があれば、質問しておくと良いでしょう。
とはいえ、残業があるか休日はどれくらいかなどを聞くと、面接官から悪いイメージを持たれるのではと心配かもしれません。
その場合は、この会社で長く働いていきたいと考えており、そのために労働条件をしっかりと確認しておきたいというように前向きな理由を伝えれば問題ないでしょう。
積極的な姿勢を伝えることで、入社意思の強さをアピールできます。
ミスマッチをなくすためにも、面接で仕事内容を詳しく聞いておきましょう。
労働条件通知書を入念に確認
内定の連絡後、企業から労働条件通知書が送られてくるので、面接時と条件が変わっていないか入念に確認しましょう。
労働条件通知書に記載された内容が実際の仕事内容となるからです。
具体的には以下のポイントを確認しておくといいでしょう。
- 労働契約の期間
- 勤務場所・仕事内容
- 労働時間・休憩時間
- 所定時間外労働の有無
- 休日・休暇
- 賃金について
- 退職や解雇の条件
特に仕事内容や労働時間、賃金について念入りに確認しましょう。入社後に条件が違うと気づいても、契約を交わしたあとでは手遅れになってしまう可能性もあります。
もし、納得がいかなければ、内定後の面談で労働条件を交渉することも可能です。入社後のミスマッチを防ぐために、労働条件について入念に確認しましょう。
転職エージェントを利用する
仕事内容が違う仕事に就くのを防ぐために、転職エージェントを利用しましょう。転職エージェントは企業の内情や具体的な仕事内容に詳しいからです。
自分の希望を伝えておけば、条件に合致した企業を紹介してくれます。
やりたい仕事ややりたくない仕事、給与や勤務地など自分がゆずれない条件をエージェントに伝えておきましょう。
具体的に伝えることで、エージェントから紹介される求人の精度があがります。また、自分の希望が現実的でない場合は、エージェントが指摘してくれます。
その場合、どこが譲れない条件なのか、現実的な落とし所はどこなのか一緒に考えてもらいましょう。
このように転職エージェントを利用することで、仕事内容が違う仕事に就くリスクを減らせます。
まとめ
この記事では仕事内容が違うので辞めたい時の対処法について解説しました。
- 仕事内容が違うことを理由に退職しても良い
- 仕事内容が違う原因は求人情報の誤解を生む表現やお互いの認識違いなどがある
- 仕事内容が違う時はまずは上司や人事に相談する
- 違法性があるときは労働基準監督署へ相談する
- 辞めるべきかどうかの判断基準は違法性があるか、今後のキャリアにプラスがあるか
- 自分の希望を明確にし下調べを入念に行うことが重要
上記を参考にすれば、自分の希望した仕事ができるでしょう。