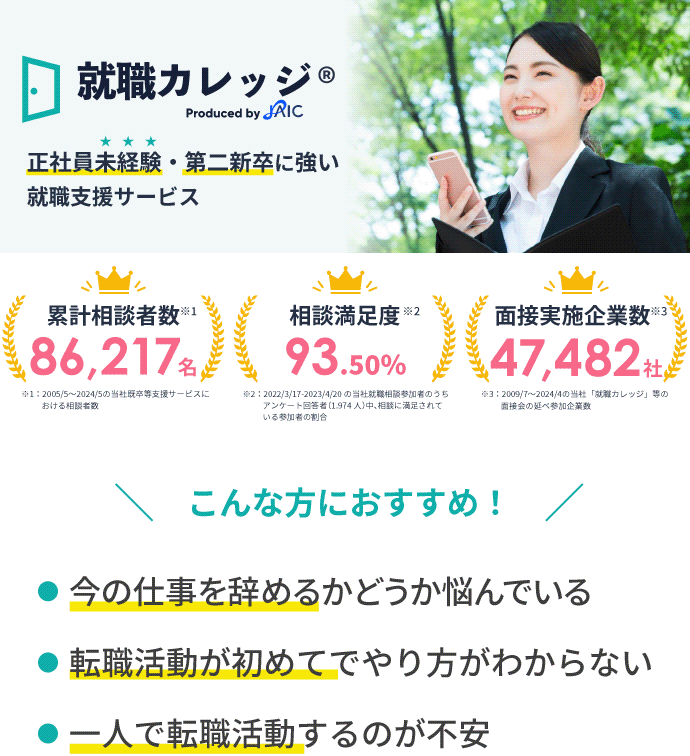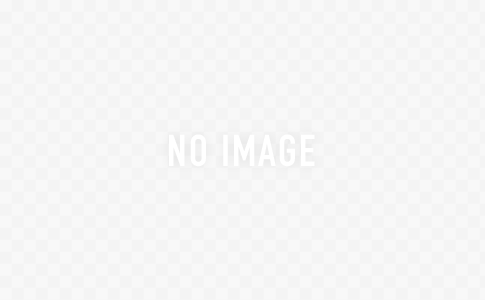「転職して間もないけれど、職場や仕事が自分に合わず退職したい」と悩んでいませんか。
「2ヶ月で辞めても大丈夫なのか」「2ヶ月で退職した理由を面接で聞かれたら、なんて答えればよいのか分からない」と悩む人も多いでしょう。
本記事では、2ヶ月でも退職できる理由や今後のキャリアに与える影響、2ヶ月で退職するメリットと退職を迷ったときの判断基準などについて解説します。
併せて、次の転職活動を成功させる方法や面接での答え方も具体的に説明しています。
この記事を読むと迷いや不安が軽減でき、自信を持って次の一歩を踏み出せるでしょう。
ぜひ最後までご覧ください。
この記事の目次
2ヶ月でも退職はできる!
今の職場が自分に合わないと感じた場合、2ヶ月で退職できます。
本章では民法を踏まえながら、以下のポイントについて解説します。
それぞれ見ていきましょう。
- 退職の意思を伝えてから2週間経つと雇用契約を解除できる
- 2ヶ月で退職する人は実際にいる
退職意思を伝えてから2週間で雇用契約を解除できる
正社員の場合、民法第627条では「退職の意思を伝えた日から2週間経過すると退職できる」と定められています。
「退職の際は1ヶ月前の予告が必要」と企業の就業規則に定められているケースがあるかもしれません。
その際も法律が優先されるため問題ありません。
アルバイトや派遣社員など、雇用期間の定めがある場合は民法第628条に記載されており、「やむを得ない場合は、直ちに契約が解除できる」ことになっています。
いずれの場合も在籍期間に関係なく、正社員の場合は2週間、有期雇用の場合はすぐに退職できるのです。
2ヶ月で退職する人は実際にいる
「2ヶ月で辞めるのは自分だけなのではないか」と不安になっていませんか。
実は、短期間で退職する人は実際にいるのです。
リクルートワークス研究所の調査の調査によると、3年以内に離職する「早期離職者」のうち、10人に1人が1ヶ月から3ヶ月未満で退職しているのです。
意外に多いと感じたのではないでしょうか。
2ヶ月で退職するのはネガティブな決断ではなく、自分に合ったキャリアを探すためのチャンスです。
この経験を活かして、次の一歩を踏み出すとよいでしょう。
2ヶ月で退職すると転職は難しい?
2ヶ月で退職した場合「次の転職が難しくなるのでは」と心配になる人も多いでしょう。
早期退職が転職活動でデメリットになる理由は以下のとおりです。
それぞれ解説します。
- 「またすぐに辞めるのでは」と思われる
- スキルが身についていないと判断される可能性がある
「またすぐに辞めるのでは」と思われる
2ヶ月で退職すると「次もまた短期間で辞めるのでは」と採用担当者に思われ、転職先が決まらないという恐れがあります。
なぜなら、企業は採用活動や教育に多くの時間とコストをかけているため、短期間で辞める可能性がある人の採用を避ける傾向があるからです。
また「仕事に対する忍耐力や責任感が不足している人材」と思われるリスクもあるため、書類選考や面接で不利になりやすいと言われています。
2ヶ月で退職した場合は「前職の経験を通じて、自分の強みと課題を把握しました。
今後も業務に必要なスキルを身につけ、チームの一員として価値を生み出していきたいと思います。」
のように、その経験から学んだことや今後の働き方に対する前向きな姿勢を明確に伝えるとよいでしょう。
スキルが身についていないと判断される可能性がある
2ヶ月で退職した場合、スキルや実績が不足している人材だと見なされる場合があります。
そのため「即戦力としての期待が難しい」と採用担当者が感じ、選考で不利になる可能性があります。
この場合は、短期間でも具体的に取り組んだ内容や学びをアピールしましょう。
「短期間でしたが、環境に適応しつつ、効率的に業務を進めました。」「チームで協力しながら、短期間で成果を出せました。」など、努力や結果を具体的に伝えると、採用担当者の印象を大きく変えられます。
2ヶ月で退職するメリット
2ヶ月で退職するのはリスクもありますが、メリットも多く存在します。
ここでは、2ヶ月で退職するメリットについて、以下の3点を挙げていきます。
- 早めにストレスを取り除くことができる
- 転職先でより長くキャリアを積める
- 転職先選びに活かすことができる
1. 早めにストレスを取り除くことができる
2ヶ月で退職するメリットの一つ目は、早めにストレスを取り除くことができることです。
「新しい職場は自分に合わない」「毎日のように長時間残業が続いて辛い」と思いながら、無理をして働き続けると、ストレスが積み重なって体調を崩したり、精神的に疲弊したりする恐れがあります。
この場合は退職を早く決断すると、ストレスの元を断ち切れるため、精神的な負担を最小限に抑えられます。
心身の負担が大きくなる前に行動を起こし、気持ちを切り替えて次のステップへ進むとよいでしょう。
2. 転職先でより長くキャリアを積める
転職先でより長くキャリアを積めることも2ヶ月で退職するメリットの一つです。自分に合う職場を見つけられると、やりがいを持ちながら働き続けられるだけでなく、キャリアアップも期待できます。
「この職場では自分の成長が見込めない」「毎日同じことの繰り返しでつまらない」と感じる場合、早く見切りをつけて自分に合った環境に飛び込むと、仕事のパフォーマンスが向上し、あなたの価値がさらに高まるのです。
環境を変える勇気を持つと、安定したキャリアと成長を同時に手に入れられます。あなたの未来を大きく前進させる一歩となるでしょう。
3. 転職先選びに活かすことができる
短期間での退職経験は、次の職場選びで非常に役立ちます。
なぜなら、自分に合う環境や避けたい条件が明確になるため、次の転職先で失敗するリスクを減らせるからです。
例えば「在宅勤務の多い職場が自分に合う」「自分のアイデアを活かせる仕事がしたい」など、自身に合う職場や仕事が見えてくるのではないでしょうか。
このように退職経験を活かすと、次は理想的なキャリアが築けるでしょう。
2ヶ月で退職するべきか?迷ったときの判断基準
「入社して2ヶ月しか経っていないけど、退職したい」と感じる人は多くいます。
しかし、迷ったときは冷静に状況を見極めたうえで、退職するか判断しましょう。
退職した方がよいケースと、慎重に判断した方がよいケースについて、それぞれ具体的に紹介します。
退職した方がよいケース
「2ヶ月で退職すると、自分のキャリアに影響するから我慢しよう」と思っていませんか。
場合によっては退職の決断が最善の行動になるケースもあるのです。
特に以下の状況では、退職を前向きに考えるとよいでしょう。以下の内容についてそれぞれ解説します。
- 心身の健康状態が悪い
- 求人票と実際の待遇が大きく異なる
- 労働環境が悪い
- 給与や残業代が支払われない
心身の健康状態が悪い
心身に負担を感じる場合、できるだけ早く退職を検討しましょう。
特に、「仕事に行くこと自体が苦痛でたまらない」「今の職場に変わってから眠れなくなった」などの症状がある場合は要注意です。
このような状況を放置すると、慢性的な疲労やうつ病などの深刻な問題に発展する恐れがあります。自身の健康を守るため、体調が悪化する前に行動を起こすことが大切です。
思い切って環境を変える決断をすると、次のステップに進む道が開けるでしょう。
求人票と実際の待遇が大きく異なる
当初に求人票や労働条件通知書で提示された条件と現実が大きく異なる場合は「労働条件の明示義務違反」に該当する可能性があります。
例えば「残業はほとんどない」と聞いていたのに、実際は毎月50時間以上の残業がある、基本給が求人票と異なるといったケースです。
このような場合は上司や人事部門に相談し、条件の確認や改善を求めましょう。
口頭ではなく、書面やメールでやり取りを残しておくと、後々の証拠として役立ちます。
しかし、改善が見込めない場合は違反が常態化している可能性があるため、その企業で長く働き続けるのは難しいかもしれません。
そのため、できるだけ早く退職を検討するとよいでしょう。
労働環境が悪い
職場の労働環境が悪い場合は、我慢して働き続けるとストレスが積み重なり、心身の不調が現れる可能性があります。
自身の健康と未来を守るためにも、早めに行動することが大切です。
「上司や同僚からのパワハラやセクハラがある」「厳しいノルマに追われてプレッシャーを感じている」という場合は、まずは信頼できる人に相談して、自分の悩みを共有してみましょう。
また、会社の人事部門に相談すると改善できるかもしれません。
しかし、それでも状況が変わらない場合は、退職を検討するのも1つの方法です。
給与や残業代が支払われない
給与や残業代が支払われないのは、明らかな法律違反です。
この状況を放置すると、経済的かつ精神的に大きな負担となるでしょう。
この場合、まずは人事部門に確認します。それでも解決しない場合は、労働基準監督署に相談しましょう。
労働基準監督署は企業の法律違反を指導する専門機関です。
相談は無料で、匿名でも対応しているため、安心して利用できます。
このような企業に長く在籍するとリスクが高いため、早急に退職を決断した方がよいでしょう。
残業代がもらえない場合は、一定時間分の残業代が給与に含まれている「みなし残業代」の場合もあります。
その場合は、求人情報や就業規則を再度確認しましょう。
退職を慎重に判断した方がよいケース
2ヶ月での退職は、場合によっては慎重に考える必要があります。
今の職場が合わないと感じる理由が、一時的なものである可能性があるからです。
退職を慎重に判断した方がよいケース3点について、以下のとおり解説します。
- 仕事が合っていない
- 業務が分からず不安に感じている
- 職場環境になじめない
仕事が合っていない
「今の仕事が合っていないから、早く退職したい」「仕事がうまく進まず、ストレスを感じている」と思う場合でも、しばらくは様子を見る方がよいケースもあります。
新しい業務を担当して間もないタイミングや未経験の分野に挑戦した場合、最初は負担に感じても、徐々に理解が深まってやりがいを感じられるかもしれません。
新しい業務の場合、慣れるまでに数ヶ月かかるのが一般的です。
その期間を目安にして、自分の気持ちや状況を振り返るとよいでしょう。
どうしても合わないと感じる場合は、上司に相談するのも1つの方法です。
業務が分からず不安に感じている
「初めての業務で、何をどう進めればよいのか分からない」「周りのペースについていけず情けない」など、業務が分からず不安に感じている場合は、慎重に退職を検討した方が良いでしょう。
なぜなら、このような不安は時間とともに解消される場合も多いからです。
「最初は分からなくて当然」と思い、上司や同僚へ積極的に質問しましょう。
慣れると不安がなくなり、次第に業務を楽しめるようになるかもしれません。
それでも不安が解消されない場合は退職を考えても遅くありません。
新しい環境に慣れるため、まずはできることから少しずつ始めてみましょう。
職場環境になじめない
職場の雰囲気や人間関係になじめない場合も、慎重な判断が求められます。
初めての環境では周囲との距離を感じたり、企業独自のルールに戸惑ったりした経験が誰にでもあるのではないでしょうか。
その場合は、コミュニケーションの取り方を工夫してみましょう。
積極的に挨拶したり、業務の質問をきっかけに話しかけるなど、小さな一歩を積み重ねるのが大切です。
「新しい職場環境に慣れるには、誰でも時間が必要だ」と思い、焦らずに少しずつ関係を築いていきましょう。
2ヶ月で円満退職するための伝え方のポイント
2ヶ月で円満に退職するためには、退職の意向を伝える際の言葉選びや態度が非常に重要です。
以下の3つのポイントを押さえると、円満に退職できるでしょう。
それぞれの注意点について詳しく解説します。
- 上司へ退職の意向を丁寧に伝える
- 退職理由について必要以上の説明は控える
- 職場の批判を避ける
1. 上司へ退職の意向を丁寧に伝える
上司へ退職の意向を伝える際は、就業規則で定められている期日を確認しましょう。
「退職希望日の2週間前」が一般的ですが、会社によっては1ヶ月前の場合もあります。
できれば直接、難しい場合はなるべく電話で上司に退職の意思を伝えます。
「お忙しいところ恐れ入りますが、お話したいことがあります。
お時間をいただけますでしょうか。」と事前にアポイントを取るとスムーズです。
「〇月〇日付で退職を考えております。今までご指導をいただき、ありがとうございました。」「責任を持って引継ぎを行いますので、どうぞよろしくお願いいたします。」と誠実な言葉を添えると配慮の気持ちが伝わり、円満に退職できるでしょう。
2. 退職理由について必要以上の説明は控える
退職理由を聞かれた際、詳細を話す必要はありません。
詳しく話すと深く質問されたり、引き止められたりする可能性があります。
また、話の内容が矛盾した場合、信頼を失う恐れもあるのです。説明が難しい場合は「一身上の都合」や「家庭の事情」程度にとどめます。
キャリアアップを目指した退職の場合は「新しい業界で経験を積みたいと思いました。」「専門分野に特化した業務にチャレンジしたいと思っています。」など、前向きな言葉で伝えるとよいでしょう。
3. 職場の批判を避ける
職場の不満を退職理由にするのは避けましょう。
批判的な言葉を口にすると、上司や同僚との関係が悪化して、円満退職が難しくなる可能性があります。
また、職場でのやり取りや引継ぎがしづらくなるかもしれません。
その代わりに「これまでたくさん学ばせていただきました。」「この経験を活かして、次のステージでも頑張ります。」などと感謝の気持ちを伝えるのがポイントです。
丁寧かつポジティブなコミュニケーションを心がけると、退職後も良い関係を維持できるでしょう。
2ヶ月で退職しても次の転職活動を成功させる方法
2ヶ月で退職しても、次の転職活動を成功させることは可能です。
ここでは、転職活動で重視すべきポイント4点について具体的に解説します。
- 自身の学びや気づきを説明する
- 次のステップに向けた準備や行動を具体的に示す
- 短期間でも得られた経験を強調する
- 前職に対してネガティブな意見を避ける
1. 自身の学びや気づきを説明する
転職の面接では「なぜ短期間で辞めたのか」と質問されるかもしれません。
この場合、短期間で得られた学びや気づきを具体的に説明すると、採用担当者へ良い印象を与えられます。
例えば「短い間でしたが、〇〇スキルが強みとして活かせると気づき、新たな業界でさらに深めたいと思いました。」「前職で得た〇〇のスキルを貴社の業務で活かしたいと考えています。」と説明すると、次のキャリアを前向きに考えていると判断されます。
短期間の退職はネガティブな要素ではありません。
誠実かつポジティブな姿勢で臨むと、好印象を残せるでしょう。
2. 次のステップに向けた準備や行動を具体的に示す
短期間で退職した場合「次もすぐに辞めるのではないか」と採用担当者が懸念する可能性があります。
そのため、次のステップに向けた準備や行動を具体的に伝えると効果的です。
「〇〇の資格を取得するために勉強しており、来月に試験を受ける予定です。」「これまでの経験を活かして、貴社では〇〇の分野で貢献したいと考えています。」と話すと、意欲的な印象を与えられます。
あなたのスキルが転職先でどのように活かせるかを明確に伝えると、採用担当者からの評価が上がり、内定に結びつくでしょう。
3. 短期間でも得られた経験を強調する
前職の2ヶ月で取り組んだ業務や実績がある場合は、しっかりとアピールしましょう。
具体的なエピソードを交えて説明すると、即戦力として働ける人材だと印象付けられます。
例えば「接客を通じてお客様満足度の向上に努め、アンケートで高評価をいただきました。」「社内ツールの効率化に取り組み、作業時間を〇時間短縮できました。」などのように具体的に伝えると「スピーディーに結果を出せる優秀な人材」と認識されます。
前職の経験を次の職場でも活かしたいという前向きな姿勢を示すと、転職活動の成功に結びつくでしょう。
4. 前職に対してネガティブな意見を避ける
退職理由を話す際に前職の悪い点を指摘すると、採用担当者にネガティブな印象を与える可能性があります。
「上司がひどかった」「職場環境が最悪だった」などと批判的な発言をすると「当社に入社しても同じように文句を言って、すぐに辞めるのでは」と思われ、次の職場が決まりにくくなるかもしれません。
そのため、退職理由をポジティブに言い換えると効果的です。
例えば「新しい挑戦をするために決断しました。」「スキルアップを目指して、新しい業界でチャレンジしたいと考えました。」と伝えると、採用担当者から信頼を得られるでしょう。
2ヶ月で退職した理由の面接での答え方のポイント
2ヶ月で退職した理由を面接で伝える際は、前向きな表現を心がけると次のキャリアへの意欲が伝わります。
以下の事実をポジティブに伝える具体例を5つ紹介します。
- 求人情報と現実のギャップがあるから
- 職場環境が合わないから
- ハラスメントがあるから
- 過度な残業や休日出勤が常態化しているから
- ストレスや長時間労働で体調不良になったから
1. 求人情報と現実のギャップがあるから
求人票に記載されていた内容と、実際の待遇や業務内容が異なっていた事実を面接で伝えると「求人票をきちんと確認していなかったのでは」と思われる可能性があります。
そのため、前職での経験を活かしつつ、次のステップでどのように貢献できるかを伝えます。
「前職では幅広い業務を担当しましたが、自分の強みや〇〇の経験を活かし、チームの一員として力を発揮したいと思いました。」と自身の気持ちを意欲的に伝えるとよいでしょう。
2. 職場環境が合わないから
「職場環境が合わなかった」という理由をそのまま伝えると「環境に適応できないのではないか」と思われる可能性があります。
しかし、伝え方次第でポジティブな印象に変えられるのです。
「自分のスキルをより活かせる環境で、新しい挑戦をしたいと思いました。」「これまでの経験で身につけた〇〇のスキルを活かしながら、業務改善に取り組みたいと思いました。」
などの表現に変えると、あなたの意気込みをアピールできるでしょう。
環境が合わないというネガティブな理由ではなく、これから自分がどのように成長し、貢献していきたいのかを伝えるのがポイントです。
3. ハラスメントがあるから
ハラスメントが原因で短期間で退職した場合も、面接で詳細を話す必要はありません。
「前職で多くの経験を積めましたが、今後はより良好なチームワークの中で、社内のサポートに取り組んでいきたいと思いました。」
「短期間でしたが、前職ではプロジェクトリーダーのスキルを身につけました。今後は自分の経験を活かしつつ、貴社の目標達成に向けて全力で取り組みたいと思っています。」などと伝えます。
退職理由がハラスメントの場合も、前向きな視点を持ち、これまでの経験やスキルを活かしながら積極的に取り組む姿勢を示すと、採用担当者に良い印象を持たれるでしょう。
4. 過度な残業や休日出勤が常態化しているから
過度な残業や休日出勤が続いた場合、その影響で転職を考える人は多くいます。
しかし、この場合も詳細は話さず、自身のキャリアを考える転換点とするのがよいでしょう。
「前職では〇〇プロジェクトに注力し、多忙な中でも業務の優先順位を考えながら効率的に進めてきました。
今後はワークライフバランスを重視しつつ、より良い成果を追求したいと考えております。」
「前職で経験した業務の効率化や改善提案の経験を活かし、貴社のチームで貢献したいと考えています。」と説明します。
新しい職場でどのようにチャレンジするのか、目標や意欲を具体的に伝えると、実行力のある人材だと評価されるでしょう。
5. ストレスや長時間労働で体調不良になったから
ストレスや長時間労働で体調を崩した場合でも、そのままの理由を伝えるのではなく、キャリアを見直す転機として前向きに説明します。
「これまでの働き方を見直し、健康を大切にしながら長期的に働ける環境でキャリアを積みたいと思いました。事務処理能力とコミュニケーション力を活かして多くの仕事に挑戦し、結果を出したいと考えています。」
「効率的な時間管理と正確な業務遂行に取り組みつつ、〇〇の経験を活かしながら新しいプロジェクトで成果を上げたいと考えています。」
前職で得た経験を活かし、心身の健康を大切にしながら最大限の成果を出す意欲を伝えると、信頼感のあるアピールができるでしょう。
2ヶ月で退職するときのよくある質問
2ヶ月で退職する際は、手続きなどが気になるのではないでしょうか。
よくある質問とその回答を以下のとおり解説します。
- 有給休暇は使用できますか
- 退職金や賞与はもらえますか
- 在職証明書は発行してもらえますか
- 2ヶ月で退職する場合も履歴書に記載する必要はありますか
- 健康保険や年金の手続きはどうなりますか
- 失業保険はもらえますか
有給休暇は使用できますか
有給休暇が使用できるかは企業の就業規則によります。
労働基準法では以下の条件で有休休暇が付与されるため、2ヶ月で退職する場合は有給休暇が使用できないかもしれません。
- 雇い入れ日から6か月続けて勤務していること
- 全労働日の8割以上出勤していること
しかし、企業によっては採用後すぐに有給休暇が付与されるケースがあるため、就業規則を確認しましょう。
有給休暇を使用する際は、上司との調整が必要です。
円満退職を目指すためにも、業務や引継ぎの日程などを考慮しながら希望日を伝えましょう。
退職金や賞与はもらえますか
退職金や賞与が支給されるかは、会社の就業規則や契約内容によります。
労働基準法では義務付けられておらず、支給の基準は会社ごとに異なるためです。
一般的に、退職金は一定の勤続年数が必要なため、2ヶ月の在籍では支給の対象外となるケースがほとんどです。
また、賞与は半期または1年の業績評価期間に基づいて計算される場合が多く、支給基準日までに在籍していない場合は対象外となる可能性が高いと言われています。
詳細は就業規則を確認するか、人事部門に問い合わせるのが確実です。
在職証明書は発行してもらえますか
在職証明書は2ヶ月で退職した場合も発行してもらえます。
これは労働基準法第22条で定められており、従業員や元従業員の求めに応じて会社が発行する義務があるからです。
在職証明書はその会社で勤務していた事実を証明する書類で、名前や生年月日の他に在職期間や雇用形態、職務内容などが記載されるのが一般的です。
退職後に在職証明書が必要になった場合は、前職の人事部門に依頼しましょう。
発行には数日かかるため、早めに依頼するのをおすすめします。
2ヶ月で退職する場合も履歴書に記載する必要はありますか
2ヶ月で退職した場合も、履歴書には正直に記載しましょう。
事実と異なる記載は、虚偽申告となる恐れがあります。空白期間について応募先企業から説明を求められるかもしれません。
また、社会保険の加入履歴と一致しない事実が分かった場合は、経歴に疑問を持たれる可能性もあります。
派遣社員の期間があった場合は、派遣元企業と派遣先企業の両方が分かるように記載します。
派遣元が正式な雇用主であり、雇用契約を締結しているからです。
健康保険や年金の手続きはどうなりますか
退職後、すぐに他の会社へ転職する場合と、しない場合で手続きが異なります。
【すぐに他の会社へ転職する場合】
健康保険と年金は新しい職場で手続きしてもらえます。
年金は次の職場が厚生年金へ加入する手続きを行うため、国民年金への切り替えは不要です。
【すぐに転職しない場合】
失業期間がある場合の健康保険には、選択肢が3つあります。
- 任意継続被保険者制度
- 国民健康保険
- 家族の扶養
| 任意継続被保険者制度 | 任意継続被保険者制度 | 任意継続被保険者制度 | |
|---|---|---|---|
| 概要 | 前職の健康保険を最大2年間利用できる制度 | 都道府県や市町村が保険者となる制度 | 家族の扶養に入る制度 |
| 条件 | 退職時に被保険者期間が連続して2か月以上ある場合 | 他の医療保険制度に加盟していない人が対象 | 年収130万円未満など諸条件あり |
| 保険料 | 全額自己負担 | 世帯の前年所得に応じて計算 | なし |
| メリット | ・退職後も同じ健康保険を使える ・扶養家族も継続して加入できる | ・所得が低い場合は保険料が安くなる可能性がある ・収入がなくても加入できる・軽減制度が充実している | ・被扶養者は健康保険を払う必要なし |
| 注意点 | ・国民健康保険と比較して保険料が高額な場合がある ・期限までに保険料を支払わないと資格を喪失する | 前年の所得が高いと保険料が高額になる | 被扶養者の収入を抑える必要がある |
参照:全国健康保険協会「退職後の健康保険について | よくあるご質問」
失業期間がある場合の年金には、選択肢が3つあります。
- 国民年金への切り替え
- 家族の扶養
- 免除や猶予の申請
| 国民年金への切り替え | 家族の扶養 | 免除や猶予の申請 | |
|---|---|---|---|
| 概要 | 厚生年金から国民年金に切り替える(第1号被保険者) | 厚生年金に加入している家族の扶養に入る(第3号被保険者) | 経済的に困難な場合、国民年金保険料の免除や猶予を申請できる制度 |
| 保険料 | 年度によって異なる | なし | 収入による |
| 条件 | – | 年収130万円未満 | 世帯収入に応じて全額または一部免除 |
参照:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
失業保険はもらえますか
失業保険がもらえる主な条件は以下のとおりです。詳細はハローワークに確認しましょう。
【もらえる場合】
- 退職日までの過去2年間で12か月以上雇用保険に加入している
- 会社都合退職の場合は、過去1年間に6か月以上加入しているともらえる
- 上記2点のうち働く意思と能力があり、ハローワークで求職活動を行っている
2か月で退職した場合、その期間だけでは条件を満たしませんが、過去に雇用保険に加入していた期間がある場合は、合算される可能性があります。
【もらえない場合】
- 過去2年間の雇用保険加入期間が12か月未満の場合(会社都合退職の場合は6か月未満)
- 自分で起業する場合
- 週20時間以上の仕事に就いている場合
- 病気やケガで働けない場合
まとめ
2ヶ月で退職するのは決して珍しいことではありません。
職場環境が合わない、体調不良になってしまった、ハラスメントが辛いなど、これ以上続けるのが難しいと思う場合は早めの決断が必要です。
転職活動を成功させるためには、短期間の退職を前向きに捉えつつ、過去の実績と今後の意欲を積極的に採用担当者へ伝えることが大切です。
面接であなたの前向きな思いを伝えると、即戦力のある優秀な人材だと認めてもらえるでしょう。
退職は新しい挑戦への始まりです。
この記事を参考にして迷いや不安を解消し、自分の身体やキャリアを大切にしながら、一歩ずつ前に進んでいきましょう。