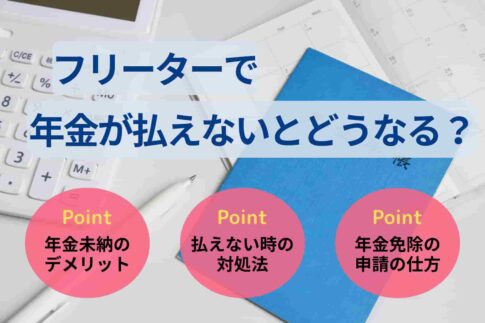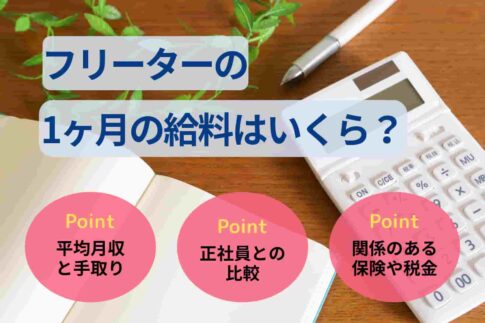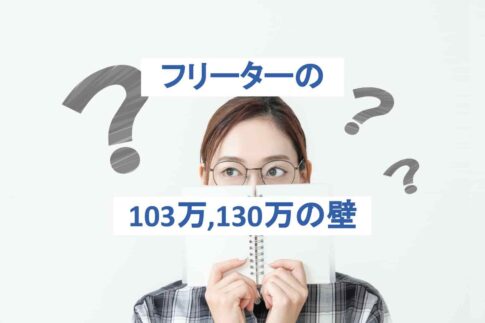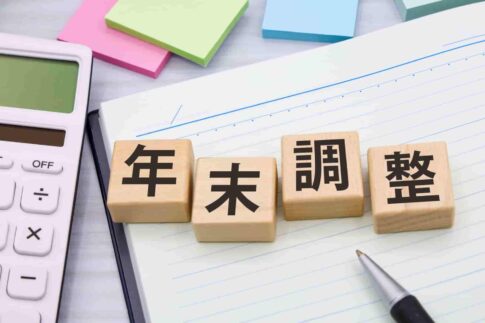フリーターとして働いていると「社会保険に入らなくても問題ないのでは?」と考えることはありませんか。しかし、社会保険に加入しないと、将来的に大きなデメリットが発生するかもしれません。
本記事では、フリーターが社会保険に加入しない場合のデメリット、加入することで得られるメリットや条件などについて解説します。社会保険の重要性を理解し、将来の安心につなげるためにも、ぜひ最後までご覧ください。
この記事の目次
社会保険とは?
社会保険とは、病気やケガ、失業、労働災害など、生活に影響を及ぼすリスクに備えるための公的な保険制度です。国民全員が一定の条件を満たす場合に加入することが義務付けられており、生活の安心と安定を目的としています。
社会保険は以下の5つの保険で構成されています。
- 健康保険:病気やケガ、出産時の医療費を一部の負担で受けられる保険
- 厚生年金保険:老後の生活を支える年金制度
- 介護保険:介護が必要になった際に介護サービスを受けられる保険(40歳以上が対象)
- 雇用保険:失業時や育児・介護休業時に給付を受けられる保険
- 労災保険:就業中や通勤中の事故や病気に対する保険
フリーターが社会保険に入らないとどうなる?
フリーターが社会保険に入らないと、医療費が全額負担になる、年金額が少なくなる、失業手当がもらえないといったデメリットがあります。以下の5つのデメリットについて解説します。
- 医療費が全額負担になる
- 年金額が少なくなる
- 失業手当がもらえなくなる
- 将来の生活設計が不安定になる
- 過去の未加入分を請求されるリスクがある
医療費が全額負担になる
フリーターが社会保険に入らない場合は、親の扶養に入るか、国民健康保険に加入する必要があります。社会保険や親の健康保険、国民健康保険のいずれにもに加入していない状態で医療機関を受診すると、医療費が全額負担になります。健康保険に加入している場合では、医療費の自己負担は3割で済みますが、未加入の場合は補助が受けられず、治療費の負担が大幅に増えてしまいます。
特に、入院や手術が必要なケースでは、数十万円から数百万円の高額な医療費が発生する可能性があるため、経済的なリスクが非常に大きくなるのです。
健康なうちは問題ないと感じるかもしれませんが、万が一の際に支払いが困難になり、治療を諦めなくてはいけない状況になるかもしれません。社会保険に入らないリスクを理解し、早めに対策を講じることが大切です。
年金額が少なくなる
厚生年金に加入しないと、将来受け取れる年金額が大幅に減少します。会社員の場合は国民年金に加えて厚生年金にも加入するため、老後の年金額が多くなります。しかし、国民年金のみの場合は受け取れる年金が少なくなるため、老後の生活が厳しくなるかもしれません。
厚生年金に加入している場合と、国民年金のみとで比較すると、老後に受け取れる年金額に約2倍以上の差が生じるケースもあります。
厚生労働省の「令和4年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、令和4年時点での厚生年金と国民年金の平均受給額は以下の通りです。
- 厚生年金:月額144,982円
- 国民年金:月額56,428円
社会保険に加入し、厚生年金の保険料をきちんと支払うことで、将来的に月額15万円程度の年金を受け取れる可能性があります。
一方、社会保険に加入しない場合、将来受け取れる年金は国民年金のみとなり、月額5.6万円にとどまります。
若いうちは実感が湧かないかもしれませんが、将来の生活を考えると、社会保険に加入できる働き方を検討することが大切です。
失業手当がもらえない
雇用保険に加入していない場合、失業した際に受け取れる「失業手当」を受給できません。失業手当は、仕事を失った際の生活を支える重要な制度であり、安定した収入を一定期間確保できる仕組みです。しかし、雇用保険に加入していないと、この支援を受けられず、無収入の状態に陥るリスクが高まります。
特にフリーターの場合、シフトの減少や契約の打ち切りによって突然仕事を失う可能性があるため、失業時のリスクがより大きくなります。再就職までの間に貯金が尽きてしまう可能性も考えられるため、雇用保険の重要性を理解し、社会保険に加入できる働き方を考えた方がよいでしょう。
将来の生活設計が不安定になる
社会保険は、病気やケガ、老後、失業といった人生のリスクに備えるための重要な制度です。しかし、未加入のままでいると、これらのリスクに対する保障を受けられず、将来の生活設計が不安定になるかもしれません。
特に、老後に受け取れる年金額が大幅に減少したり、病気やケガで医療費の自己負担が増えたりすると、家計への負担が大きくなります。また、失業時に雇用保険の給付を受けられないため、収入が途絶えたときの経済的なリスクがさらに高まるでしょう。
社会保険は現在の生活だけでなく、将来の安心を守るためにも欠かせない制度です。そのため、未加入のリスクを正しく理解することが大切です。
過去の未加入分を請求されるリスクがある
フリーターでも以下の条件を満たす場合は社会保険の加入義務が発生します。
会社の社会保険に加入する条件(いずれかを満たす場合)
- 1週間の勤務時間が20時間以上
- 月額賃金が88,000円以上
- 2カ月を超えて雇用される見込みがある
- 従業員が51人以上の企業
参考:厚生労働省「従業員のみなさま | 社会保険の加入条件やメリットについて」
社会保険の加入対象となっているにもかかわらず、社会保険の未加入が発覚した場合、法律に基づき、過去2年間に遡って未納分の保険料を請求される可能性があります。これは、健康保険法や厚生年金保険法に基づく措置であり、本来支払うべきだった保険料を徴収する仕組みです。
遡及期間と未加入分の支払方法は次のとおりです。
遡及期間:過去2年間に遡って徴収されます。
支払い方法:遡及分の保険料は、事業所(雇用主)と従業員が折半して支払うのが一般的です。ただし、従業員がすでに退職している場合や連絡が取れない場合、企業が全額を負担するケースもあります。
延滞金や法的罰則が課される可能性もあるため、社会保険の適応条件を満たしているにも関わらず、アルバイト先が社会保険の加入手続きを行ってくれない場合は、未加入状態を放置せず、早めに対応することが大切です。
フリーターが社会保険に入りたくない理由
社会保険には多くのメリットがありますが、社会保険に入りたくないと思うフリーターもいます。主な理由を4つ説明します。
- 手取り額が減るのが嫌だから
- 自由な働き方が制限されるから
- 社会保険の重要性がよく分からないから
- 年金が将来もらえるか不安だから
手取り額が減るのが嫌だから
社会保険に加入すると、健康保険料や厚生年金保険料などが給与から天引きされるため、手取り額が減少します。このため、できるだけ多くの収入を確保したいと考える人は、社会保険の加入を避けたいと感じるでしょう。
2024年度の国民年金保険料は月額16,980円ですが、厚生年金の場合は給与に応じて変動するため、国民年金よりも厚生年金に加入する方が負担が大きくなることがあります。
特に、フリーターの場合、収入が安定しないケースがあるため、手取り額を減らしたくないと思うのではないでしょうか。しかし、医療費の負担軽減や年金額の増加などの長期的なメリットがあるため、どちらがよいかを比較して判断することが重要です。
自由な働き方が制限されるから
社会保険に加入すると、同じ職場で長時間働く必要があるため、短期間で複数の仕事をしたい人や、柔軟な働き方を求める人にとってはデメリットと感じることがあります。
また、掛け持ちや副業が制限される場合もあるため「好きなときに働きたい」「労働時間を自由に調整したい」と考えている人にとっては不都合に感じ、社会保険に入りたくないと思うでしょう。
しかし、社会保険の加入によって得られる医療保障や年金のメリットも大きいため、自分に合った働き方を見極めることが大切です。自由度を優先するか、将来の安心を優先するか、長期的な視点で検討するとよいでしょう。
社会保険の重要性がよく分からないから
社会保険の仕組みを十分に理解していないため、加入するメリットを実感できず、必要性を感じられない人もいます。特に、若いうちは病気やケガのリスクを実感しづらく「健康保険に入らなくても問題ないのでは?」などと考えることもあるでしょう。
しかし、社会保険に入ると、医療費の軽減や、老後の安定した収入、失業時の生活保障など、多くのメリットが得られます。長期的な生活の安定を考え、社会保険の意義を理解することが大切です。
年金が将来もらえるか不安だから
フリーターの中には、本当に年金を受け取れるのか不安を感じている人も多くいます。そのため、社会保険の加入を避けるケースがあります。
「少子高齢化が進む中で、自分が年金を受け取る頃には制度が崩壊しているのでは?」と考え「どうせもらえないなら払いたくない」と感じる人も少なくありません。また、毎月の社会保険料が高いと感じることも、加入を避ける理由の1つです。
しかし、厚生年金に加入すると、国民年金よりも多くの年金を受け取れるだけでなく、障害年金や遺族年金といった保障も手厚くなるため、将来的なリスクに備えられます。短期的な負担と長期的なメリットを比較し、将来の安心のためにどうするべきかを考えましょう。
フリーターが社会保険に入りたくない時の対処法
社会保険に入りたくない場合、以下のように働き方を調整すると加入の対象外になるかもしれません。主な方法をそれぞれ解説します。
- 1つの勤務先で月収を8.8万円未満に抑える
- 1つの勤務先で週の労働時間を20時間未満に抑える
- 短期間の仕事を選ぶ
- 従業員が50人未満の企業で働く
- 業務委託契約を選ぶ
1つの勤務先で月収を8.8万円未満に抑える
月収を8.8万円未満に抑えると、勤務先で社会保険に加入する必要がなくなります。そのため、労働時間を調整したり、複数の仕事で収入を分散させたりして、1つの勤務先での月収を8.8万円未満に抑える方法が有効です。
しかし、社会保険に加入しない場合は、将来の年金受給額が減るだけでなく、病気やケガの際の保障が限定的になるデメリットがあります。長期的な生活設計も考慮したうえで、自分に合った働き方を選ぶことが重要です。
1つの勤務先で週の労働時間を20時間未満に抑える
1つの勤務先で労働時間を週20時間未満に抑えると、社会保険の対象から外れます。そのため、1日の労働時間を短くしたり、勤務日数を減らしたりして調整しつつ、できるだけ残業を避けることが大切です。
契約上の所定労働時間が20時間未満でも、実際の労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上になった場合、社会保険の加入対象となる可能性があります。そのため、業務量やスケジュールを確認し、必要に応じて上司に相談しましょう。
短期間の仕事を選ぶ
雇用期間が2カ月以内で、契約延長の見込みがない場合は、社会保険の加入義務はありません。そのため、短期のアルバイトや期間限定の仕事を選ぶと、社会保険の加入を避けられます。
例えば、季節的なイベント業務や臨時スタッフの場合は社会保険の対象外となるため、社会保険料の負担を避けつつ働けます。ただし、契約更新により、雇用期間が2ヶ月を超える場合は、社会保険への加入が義務付けられる可能性があるため、会社に確認しましょう。
従業員が50人未満の企業で働く
従業員が50人未満の企業で働くと、社会保険の対象外となる可能性があります。2024年10月より、従業員51人以上の企業では「月収8.8万円以上・週20時間以上」の労働で社会保険の加入が義務化されるルールに変わったためです。(2024年9月以前は101人以上の企業が対象)
ただし、50人未満の企業であっても、正社員と同等の労働時間(週30時間以上)で働く場合は、社会保険の対象となるケースがあるため、注意が必要です。また、企業が独自の判断で社会保険に加入させるケースもあるため、勤務先のルールを事前に確認しましょう。
業務委託契約を選ぶ
アルバイトやパートではなく、業務委託契約で働くと、会社が社会保険を適用する義務がなくなるため、加入せずに済みます。
業務委託契約は、企業と雇用契約を結ぶのではなく、フリーランスとして個人で仕事を請け負う働き方です。そのため、雇用保険や厚生年金の対象外となり、勤務時間や働く場所の自由度が高いというメリットがあります。また、成果報酬型の契約が多く、自分のスキルや経験次第で高収入を得ることも可能です。
社会保険に加入しない場合のリスク回避策
社会保険に加入しない場合、医療費負担の増加や将来の年金額の減少など、さまざまなリスクが発生します。しかし、適切な対策を講じると、一定の保障を確保できます。以下の方法を活用し、社会保険に加入しない場合のリスクを回避しましょう。
- 家族の扶養に入る
- 国民健康保険や国民年金に加入する
家族の扶養に入る
家族が社会保険に加入している場合、その扶養に入ると、自分で保険料を払わずに社会保険の保障を受けられるという大きなメリットがあります。
扶養に入るための条件は「年間の収入が130万円未満(従業員規模が51人以上の企業では106万円未満)」であることが求められます。そのため、労働時間や給与を調整し、この基準を超えないようにすることが大切です。
アルバイトやパートで働く場合、ボーナスや交通費なども収入としてカウントされるケースがあるため、注意しましょう。
国民健康保険や国民年金に加入する
社会保険に加入しない場合は、自身で国民健康保険や国民年金に加入しましょう。
社会保険に未加入で以下の条件を満たす人は、国民健康保険や国民年金への加入が義務付けられています。
- 自営業者、フリーランス、無職の人
- 退職後に社会保険を喪失した人
- 家族の扶養に入らない人
- 厚生年金に加入していない人(自営業者、フリーランス、無職の人)
- 退職後に厚生年金を喪失した人
- 家族の扶養に入らない人
未加入の場合は、医療費の全額負担や、年金受給資格の喪失などのデメリットがあります。そのため、社会保険を喪失した際は、速やかに最寄りの役所で手続きしましょう。
フリーターが社会保険に加入するメリット
フリーターが社会保険に加入すると、多くのメリットがあります。以下の内容について、それぞれ見ていきましょう。
- 医療費の自己負担が抑えられる
- 老後に年金がもらえる
- 失業したときの生活支援が期待できる
- 業務中のケガや病気の補償がある
医療費の自己負担が抑えられる
社会保険に加入していると、健康保険が適用されるため、医療費の自己負担は原則3割に抑えられます。これにより、突然の病気やケガの際も、安心して治療ができるでしょう。
さらに「高額療養費制度」を利用すると、手術や入院などで発生する高額な医療費も、一定額を超えた分が払い戻されます。そのため、医療費による経済的な負担を大幅に軽減でき、将来的なリスクも抑えられるのです。
社会保険に加入することで、医療費の負担を減らし、安定した生活を維持しやすくなる点は大きなメリットと言えるでしょう。
老後に年金がもらえる
厚生年金に加入すると、国民年金に加えて厚生年金の給付も受けられるため、将来の年金額が増えて、より安定した老後を迎えやすくなります。
また、厚生年金には遺族年金や障害年金といった保障も含まれているため、万が一の際には家族の生活を支える役割も果たします。
これらの保障があると将来的な収入の不安を軽減できるため、安心して老後を迎えられるでしょう。若いうちから年金制度を意識し、将来の生活を見据えた選択をすることが大切です。
失業したときの生活支援が期待できる
雇用保険に加入すると、失業時に「失業手当」を受け取れるため、収入が途絶えた際の生活費を一定期間カバーできます。そのため、仕事を失った後も当面は経済的に困ることなく、安心して次の仕事を探せます。
また、雇用保険には「再就職手当」や「職業訓練給付金」などの制度もあり、スキルアップをしながら新しい仕事に備える支援も受けられるのです。万が一の場合に備えて、雇用保険に加入できる働き方を選ぶと、将来的な安心につながるでしょう。
業務中のケガや病気の補償がある
労災保険に加入した場合、就業中や通勤途中に発生した事故やケガなどに対して、治療費や休業補償を受けられます。労災保険を適用する場合は自己負担がゼロになるため、経済的な負担を大幅に軽減できるのがメリットです。
また、休業が必要になった場合は「休業補償給付」が支給されます。そのため、一定の収入を確保しつつ、安心して治療に専念できます。労災保険は、万が一の事故や病気に備え、安全に働くための重要な保障制度といえるでしょう。
フリーターが社会保険に加入できる条件
一定の条件を満たすと、フリーターも社会保険に加入できます。フリーターが社会保険に加入できる条件について、以下の内容を解説します。
- 月収8.8万円以上の収入がある
- 週に20時間以上働く
- 2ヶ月以上雇用される見込みがある
- 従業員数が51名以上の事業所で働く
参考:厚生労働省「従業員のみなさま | 社会保険の加入条件やメリットについて」
月収8.8万円以上の収入がある
月収が8.8万円(年収:約106万円)以上になると、一定の条件を満たす勤務先で働く場合、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する義務があります。「月収8.8万円以上」の場合、保険料を負担する能力があるとみなされるため、社会保険の対象となるのです。
社会保険に加入すると、医療費の自己負担額が抑えられるだけでなく、将来受け取れる厚生年金の支給額が増えるため、老後の生活も安定しやすくなります。さらに、傷病手当金や出産手当金といった給付を受けられるため、病気や出産で働けなくなった場合の経済的なリスクにも備えられるのです。
週に20時間以上働く
週に20時間以上働くと、社会保険の対象になる場合があります。この基準は、フルタイム労働者の労働時間(40時間/週)の半分に相当し、フリーターにも一定の社会保障を提供するために設けられているものです。
また、雇用契約上の所定労働時間が20時間未満の場合でも、実際の労働時間が2ヶ月連続で20時間以上となり、その後も継続する見込みがある場合は、3か月目から社会保険の対象となる可能性があります。
2ヶ月以上雇用される見込みがある
2ヶ月以上雇用される見込みがある場合、一定の条件を満たすと社会保険(健康保険および厚生年金保険)に加入できます。「2ヶ月を超える雇用の見込みがある」とは、以下の状況を指しています。
- 雇用契約期間が2ヶ月を超えている場合
- 雇用契約期間が2ヶ月以内であっても、契約更新の可能性がある場合(就業規則や雇用契約書に更新の旨が記載されている場合など)
- 同様の雇用契約で他の従業員が2ヶ月を超えて雇用された実績がある場合
フリーターと会社の双方が「2ヶ月以内で雇用を終了する」と明確に合意している場合は、社会保険の対象外となる場合があります。
従業員数が51名以上の事業所で働く
2024年10月から社会保険の適用範囲が変わり、従業員数が51名以上の事業所も対象になりました。それ以前は、従業員数が101名以上の事業所が対象でしたが、今回の改正により、より多くの中小企業が社会保険の対象に含まれています。
一方で、従業員数が50名以下の事業所でも、フリーターと会社の合意がある場合、任意特定適用事業所として、社会保険の適用を受けることが可能です。
まとめ
フリーターが社会保険に加入しない場合、医療費の自己負担が増えたり、老後の年金額が減ったりするなど、将来的なリスクが大きくなります。収入の減少を避けるために未加入を選ぶ人もいますが、長期的に見ると社会保険に加入した方が安心といえるでしょう。
社会保険に加入すると、医療費の一部負担や厚生年金の増額、失業時の支援を受けられるなど、多くのメリットがあります。一方で、未加入を選択する場合は、家族の扶養に入る、国民健康保険や国民年金に自分で加入するなどのリスク回避策を検討することが大切です。
将来の生活設計や働き方を踏まえ、保障のバランスを考えながら、自分に合った選択をしましょう。

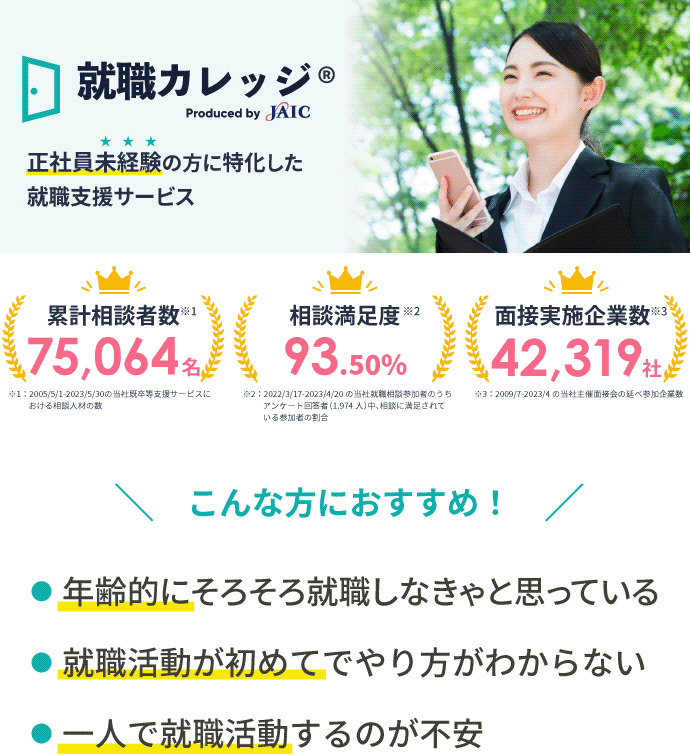

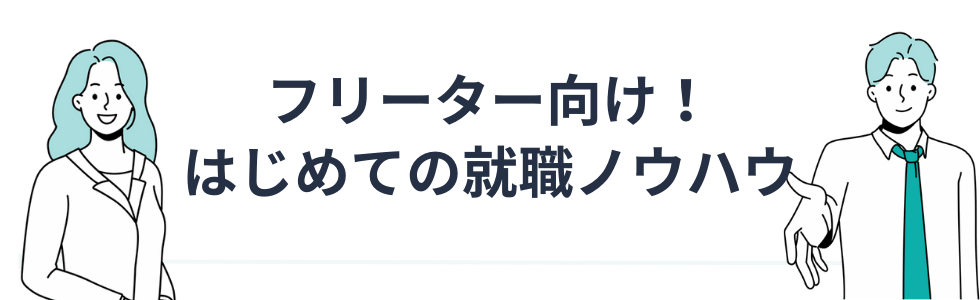
当社の就職に関するコンテンツの中から、フリーターから正社員への就職活動に不安を感じている方向けに、就活で困りがちなことを解決するための記事をまとめました。