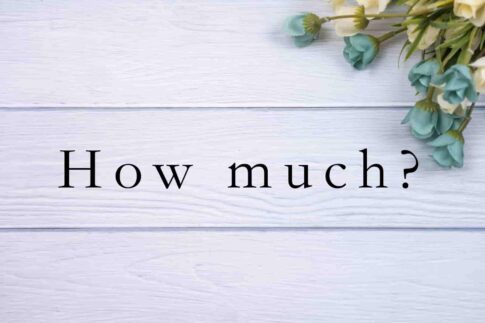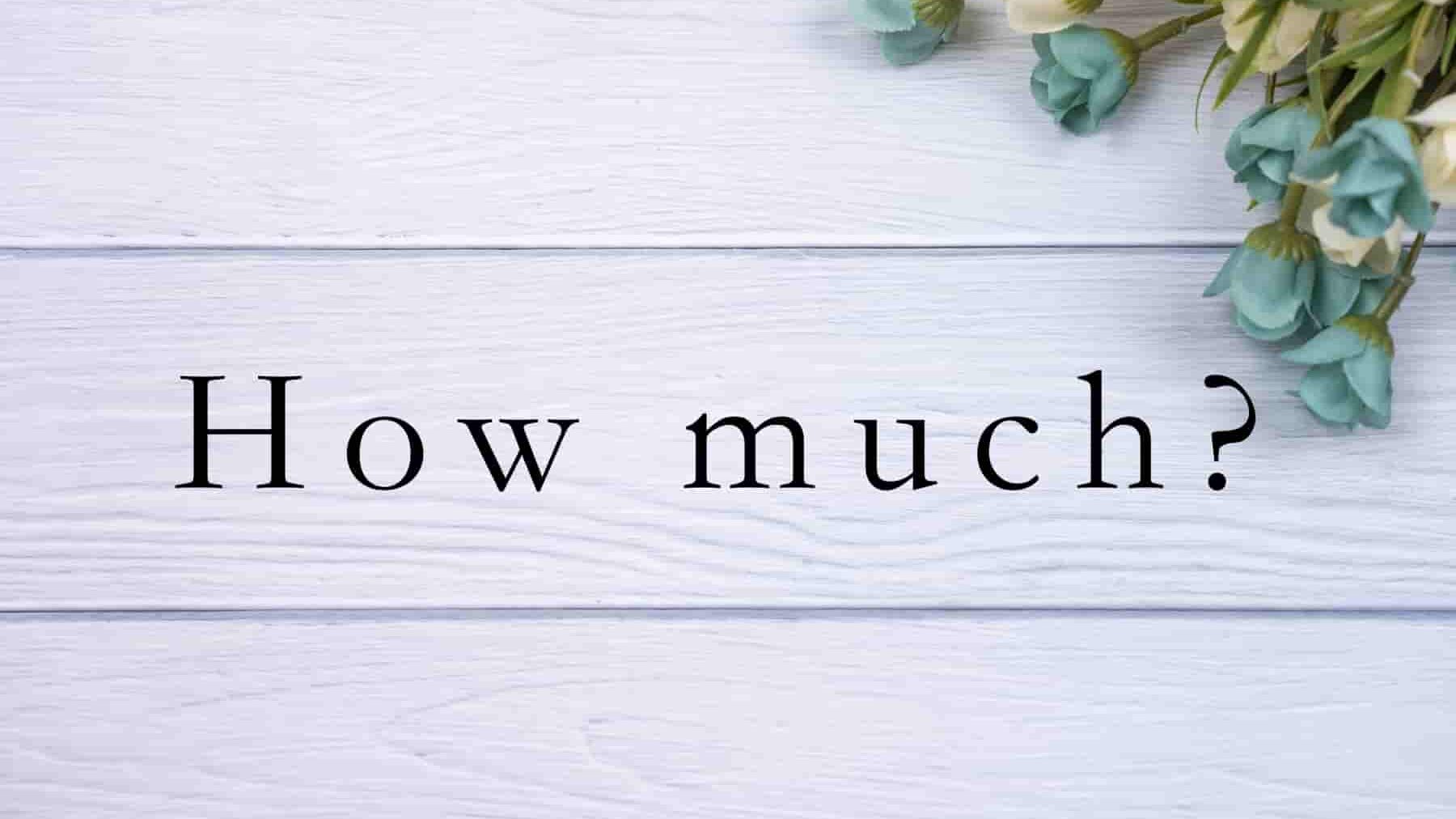
フリーターとしてある程度の年収を稼ぐと、住民税の支払いが必要になってきます。
フリーターとして生活している人の中には、自分が住民税をいくら払うことになるのか気になっている人も多いのではないでしょうか。
この記事では、フリーターだといくらの住民税を支払わなければならないのかについて、具体的なシミュレーションをもとに解説します。また、住民税の支払い方や、住民税の支払いをしなかったときの末路についても解説します。
住民税について分からないことや不安を感じているようなフリーターは、記事の内容を参考にしてみてください。
この記事の目次
住民税とは?
そもそも住民税とは何かについて理解を深めておきましょう。
日本国民に課せられる税金は、国に払う国税と、自分が住んでいる都道府県に支払う地方税に分けられます。このうち住民税は地方税に分類され、納税したお金は各都道府県が運営する公共サービスを運営するために役立てられます。
住民税を支払うことで、教育や福祉、消防や救急を始めとしたサービスが成り立っているため、我々の生活にとっても身近な税金だと言えます。
住民税は一定の条件を満たした場合、正社員だけでなくフリーターとして働く人も納税義務が発生します。また、住民税を納税する自治体は、1月1日時点で住民票がある地域と定められています。
フリーターが住民税を支払うことになる条件
フリーターであっても、一定の年収を超えていれば住民税を支払うことになります。まずは住民税を支払うことになる条件について、しっかりと理解を深めておきましょう。
基本的に前年の収入が100万円を超えたら払う
住民税は、前年の収入を参考にして納税金額が計算されます。
基本的には前年の収入が100万円を超えると住民税の納税義務が発生してきますので、フリーターの人も認識しておいてください。
なお、ここでいう年収とは、1月1日から12月31日までの1年間における額面上の収入のことを指します。
額面上の収入とは、税金が天引きされる前のお金のことであり、フリーターであれば時給× 1年間で働いた累計時間で計算することができます。
実際に自分の口座に振り込まれる手取りと額面上の年収は異なりますので注意が必要です。
もし住民税を支払いたくないのであれば、年収を100万円以下に抑える必要があるため合わせて認識しておくと良いでしょう。
自治体によって住民税がかかる収入が異なる
住民税は地方税の1つとなるため、納税する地域によって住民税がかかる収入が異なるといった特徴があります。
一般的には100万円以上の年収を超えたら住民税が発生するケースがほとんどですが、自治体によっては90万円以上の年収となった時点で住民税が発生することもあるため、自分が1月1日時点で住民票を置いている地域の情報を収集しておくと良いでしょう。
また、自治体が変わることで住民税がかかる収入だけでなく、住民税の金額そのものが変わってくる点も特徴です。
自治体によって公共サービスにかける予算や居住人数が異なってくるだけですので、住民税の高低で損得が決まるわけではないことも合わせて認識しておいてください。
フリーターが覚えておくべき年収の壁
住民税がかかるようになる年収はおおよそ100万円ということを解説しましたが、住民税だけでなく、一定の年収を超えると様々な税金や社会保障料の負担が発生します。
これは一般的に年収の壁と言われており、フリーターとして働くのであれば年収の壁の理解をしておくことが大切です。
年収の壁を簡単にまとめると以下の通りとなります。
- 100万円の壁:住民税の支払いが発生する(自治体によって金額の基準は異なる)
- 103万円の壁:所得税の支払いが発生する
- 130万円の壁:社会保険の加入義務が発生する
- 150万円の壁:配偶者特別控除の控除額が減額される
税金負担を考え、年収103万円の壁や年収130万円の壁を超えないように収入を調整するフリーターが多い傾向にあります。
特に年収130万円を超えると発生する社会保険の加入義務によって、手取り額が大きく減少してしまいます。
もし年収130万円を少し超えそうであれば、シフトを調整して年収を130万円以下に抑えると、最終的に手元に残るお金としては得をすることになります。
フリーターの住民税がいくらか計算する方法
フリーターが条件を満たしたときには住民税の支払いが発生しますが、住民税の計算方法はあらかじめ定められています。
ここでは総務省の個人住民税のページを参考にして計算方法をご紹介します。
具体的な住民税の金額についても、年収ごとにいくつかシミュレーション例をご紹介しますので、住民税の支払い金額が気になっているフリーターの人は参考にしてみてください。
均等割
均等割額と所得割額を足し合わせたものが、実際に支払う住民税の金額となります。
均等割額とは、どれだけ年収を稼いでいるかにかかわらず、住民税の納税対象全員に均一に支払いが義務付けられている金額のことを言います。
住んでいる地域によって金額が変わってきますが、一般的には都道府県県民税で1,000円、市町村民税で3,000円の計4,000円となるケースがほとんどです。
所得割
所得割額とは、実際の所得に応じて課せられる住民税であり、以下のように計算することができます。
所得金額−所得控除額=課税所得金額
課税所得金額×税率(10%)−税額控除額=所得割額
所得金額というのは、年収から社会保険料や経費などを差し引いた純粋な手取り金額となります。また、所得控除額というのは、全国民に適用される基礎控除や配偶者がいる場合の配偶者特別控除等が挙げられます。
所得金額から所得控除額を差し引くことで、住民税の計算をするための課税所得金額が求められます。基本的にはこの課税所得金額に10%を掛け合わせると、所得割の金額が算出できます。
なお、この10%の内訳としては都道府県県民税が4%、市町村民税が6%となっており、若干自分が住んでいる市町村に住民税が多く渡るように設計されています。
均等割と異なり、所得割は稼ぐお金が増えれば増えるほど高くなっていく計算になるため、高い収入を稼いでいるフリーターや正社員の場合は、その分住民税が高くなることを覚えておきましょう。
具体的な住民税のシミュレーション
住民税は均等割額+所得割額で求められることを解説しましたが、具体的なシミュレーションとして年収別に上げてみると、以下の通りとなります。
| 年収 | 想定住民税 |
|---|---|
| 100万円 | 0円 |
| 103万円 | 5,000円 |
| 130万円 | 17,500円 |
| 150万円 | 34,700円 |
| 201万円 | 64,500円 |
このように、年収130万円を超えてくると住民税の支払い金額が大きく増えていくことになります。どうしても住民税を支払いたくない場合は、年収130万円を超えないようにうまくシフトを調整すると良いでしょう。
なお、詳細なシミュレーションとしては、各地方自治体がホームページで提供しているような住民税シミュレーターを使うことをおすすめします。
フリーターの住民税の支払いかた
これまで住民税を支払ったことがない人からすると、どのように住民税を支払えば良いのか不安を感じてしまうこともあるでしょう。
ここからは、フリーターが住民税を支払う場合どのような方法があるのかについて詳しく解説します。なお、住民税の支払い方法によって納税額が減額されたり、受けられる公共サービスの種類が変わることはないことを認識しておいてください。
それぞれの方法について詳しく解説します。
給料からの天引き
フリーターの住民税の支払い方法は大きく2つあります。
その中でも給料の支払いがされるような働き方をしている人は、給料から住民税額が天引きされるような支払い方法で納税を行っていきます。
この徴収方法は、フリーターとして前年中に給与支払いを受けていて、当年度の4月1日時点でも給与支払いを受けている人が対象となります。
分かりやすくいうのであれば、フリーターとして働く期間が2年目以降になると、基本的には住民税が給与から天引きされるようになるとイメージしておくと良いでしょう。
住民税を12ヶ月で支払っていくような分割払いの方法となるため、毎月の納税負担が低くなるといった特徴があります。また、自分で住民税を支払う手続きをする必要がないため、納税忘れがなくなる点も特徴と言えます。
自分で納税する
バイト先の従業員数が2名以下であったり、フリーランスのように働くような人の場合は自分で住民税を納める必要があります。
給料から直接住民税の天引きがされないため、期日までに納付書を用いて住民税を納税しなければなりません。
この徴収方法の場合は、1年分の住民税を一括で支払う方法か、3ヶ月ごとに計4回支払う方法を自由に選ぶことができます。
給料からの天引きに比べて1回あたりの支払負担が大きくなってしまうため、お金のやりくりに注意する必要があります。
自分で住民税を納税する場合は、住民票の住所に住民税の納付書が送られてきます。
納付書を金融機関やコンビニエンスストアに持っていき支払う方法や、自治体によってはQRコード決済が可能なところもあります。
住民税の支払い時期
住民税は、収入を稼いだ年の翌年6月から翌々年の5月までが支払い時期となります。
支払い期限は自治体によって変わるものではなく、日本全国民が同じ条件となっていますので、支払い時期に遅れないように納税することが大切です。
なお、住民税の特徴として、収入を得た年の翌年に住民税の支払い義務が発生するというものがあります。
つまり、去年はフリーターとして働いていたものの、今年は仕事をしていないということになれば、去年分の住民税を今年支払わなければならなくなるため、収入がない中で納税をしなければならない状態にもなりかねません。
住民税の支払い時期については納付書にも記載されていますので、忘れずにチェックしておいてください。
フリーターが住民税を滞納した時の末路
フリーターで納税義務が発生する人の場合、基本的には給料からの天引きで住民税を支払うことができます。そのため、給料天引きの場合は住民税の支払い忘れがなくなります。
ただし、バイト先によっては住民税を自分で支払わなければならないことがあります。もし住民税を滞納した場合は、以下のような末路を迎える可能性が考えられます。
- 督促状が届く
- 給料の差し押さえがされることも
- ローンやカードが利用できなくなる
いずれも悲惨な末路を迎えることになりかねませんので、しっかりと理解して住民税の支払いに備えられるよう意識をしていきましょう。
督促状が届く
住民税の支払い義務があるにもかかわらず支払い期限を超えて納税をしていない場合、まずは地方税法第329条により、住んでいる地域の市町村役場から納付期限から2週間以内に督促状が届きます。納付期限から2週間以内に督促状が送られます。となる1ヵ月以内に督促通知がポストに投函されます。
督促状には住民税の支払いが遅れていることの事実だけでなく、今後取らなければならない対応について記載されていますので、必ず確認をして対応することをおすすめします。
なお、住民票が置かれている住所に督促状が届くことになるため、同居している家族がいる場合は、家族が住民税の滞納に気づいてしまうことがあります。
家族の関係性を悪化させることにも繋がりかねませんので、住民税に限らず税金の滞納はしないよう注意してください。
給料の差し押さえがされることも
督促状は納税期限が過ぎた後に送られてきますが、督促状が贈られてから10日を経過すると、市町村役場の担当者が直接家を訪問してくることがあります。
その訪問も無視をして住民税の支払いをしないでいると、差し押さえによる強制執行を受ける可能性があります。
差し押さえによって、財産や不動産が自分のものでなくなってしまうこともありますし、給料が差し押さえられ、これから手元に入るはずであった収入を全額住民税の支払いに当てることになるような可能性もあります。
なお、支払い期限を超えると、本来支払うべきであった住民税に加えて、滞納分の税金に対して延滞金が発生します。延滞金は日割課税となっているため、滞納期間が長引けば長引くほど延滞金も高くなっていきます。
差し押さえによって今までの生活が一変してしまうこともあるため、フリーターだからといって住民税を支払わないといった判断は絶対に避けましょう。
延滞金が発生する
税金の支払いを怠ると、延滞金が発生します。豊島区の例で言うと、納付期限経過後1ヶ月で2.4%、それ以降は8.7%が加算されます。
支払いの金額が高くなってしまいますので、住民税を支払わないことにはデメリットしかないと言えるでしょう。
住民税が払えないフリーターの対処法
住民税が払えないと悩んでしまったフリーターには以下のような対処法が考えられます。
- 役所に相談する
- 利用できる手当や給付金がないか確認する
- 正社員に就職する
それぞれの方法について詳しく解説します。
役所に相談する
住民税が支払えない場合は、納税期限を迎える前に、自分が住んでいる地域の役所に相談することをおすすめします。相談をすることで、住民税をさらに分割支払いする措置をしてもらえるなど、実質的な猶予措置を検討してもらえる可能性があります。
また、住民税が支払えない状況によっては、住民税そのものの支払いを免除してもらえるようなこともありますし、他に利用できる公的な制度を紹介してもらうこともできるでしょう。
何も相談せずに住民税を滞納してしまうと、個人の信用情報が悪化したり財産の差し押さえを受けるなど、様々なデメリットに繋がってしまうので、まずは役所に相談する意識を持っておくようにしてください。
利用できる手当や給付金がないか確認する
住民税が支払えないのは、手元にお金がないからというのが原因のケースがほとんどです。
特にこれまでフリーターとして働いていたものの、いきなり仕事がなくなってしまったようなケースであれば、手当や給付金が利用できることがあります。
代表的な例で言えば失業保険が挙げられます。
自分が働く意思があったにもかかわらず、バイト先の判断でいきなり雇用契約を解除されるようなことがあれば、失業保険をもらえる可能性があります。
失業保険だけでなく、各地方自治体にはお金に困っている人のために設けられている手当や給付金の制度がありますので、自分の状況で利用できる制度がないか調べてみることもおすすめです。
正社員に就職する
どうしても住民税が支払えないほどお金に困窮している場合は、正社員として就職することもおすすめです。フリーターの経験しかない人であっても、しっかりと自己分析や面接対策を行えば未経験から正社員就職する事は可能です。
最近では多くの企業で人手不足となっているため、未経験者を募集している求人が増えている傾向にあります。もし自分1人で就職活動を進めきる自信がないのであれば、フリーターの正社員就職支援に強い就職エージェントへの相談も検討してみてください。
住民税がいくらか怯えるフリーターに正社員就職がおすすめできる理由
住民税がいくらか不安を感じてしまうようなフリーターは、日々の家計がギリギリであることが考えられます。
収入と支出のバランスが悪く、毎月自転車創業のように生活しているフリーターには、以下の理由から正社員就職がおすすめできます。
- 安定した収入が稼げる
- 仕事を通じてスキルや収入を増やせる
- 住民税の支払い忘れがなくなる
特にお金に不安を感じているフリーターは、これらの理由も理解した上で正社員を目指すことも検討してみてください。
安定した収入が稼げる
正社員になると。フリーターと異なり安定した収入が稼げるようになります。
毎月の収入が一定以上の水準に保たれるようになるため、住民税の支払いだけでなく、生活費をやりくりしやすくなるといったメリットが挙げられます。
フリーターという働き方だと、どうしてもシフトに入った時間に応じて収入が増減してしまうため、計画的にお金をやりくりすることが難しいのが実態です。
お金の面で不安を感じたくないフリーターの人は、今すぐにでも正社員としての就職をおすすめします。
仕事を通じてスキルや収入を増やせる
フリーターの場合、どれだけ真面目に働いていたとしても、時給が数十円上がる程度に過ぎません。一方、正社員の場合は仕事を通じてスキルアップを実現できれば、毎月の給料を数万円単位で増やせるようになります。
それだけでなく、スキルアップを目的とした転職に成功すれば、年収を数十万円以上引き上げることも不可能ではありませんので、フリーターとして生活していた時よりもお金に大きな余裕を持つことができます。
仕事でのスキルアップや収入のアップを実現したいフリーターにとっても、正社員になるメリットは大きいと言えます。
住民税の支払い忘れがなくなる
正社員になると、住民税が天引きで支払われるようになります。
これによって、住民税を支払い忘れるということそのものから解放されるため、計画的に貯金をすることが苦手なフリーターにとっても安心できるといったメリットが挙げられます。
加えて、正社員は住民税を12回に分けて毎月分割して納税することができるため、1度の納税金額を実質的に抑えられるといったメリットもあります。
住民税の支払いなど煩わしいことをなるべく避けたいという人にとっても正社員になるメリットが大きいと言えるでしょう。
住民税に関するフリーターのよくある質問
最後に、住民税に関するフリーターのよくある質問を2つ取り上げて解説します。
住民税が低い自治体の方が得?
自治体によって住民税の金額が変わってくることがありますが、住民税が低い自治体だからといって得というわけではありません。
そもそも住民税は、各自治体が公共サービスにどれだけお金をかけるかなどによって金額の増減が変わってきます。
したがって、住民税が低い自治体だと、住民税が高い自治体よりも公共サービスが行き届いていない可能性も考えられます。
もちろん、住民税が低くても充分な公共サービスが提供できている自治体もありますので一概には言えませんが、住民税が低いからといって得をしているというわけでは無いことを認識しておいてください。
フリーターが支払わなければならない税金は?
フリーターが支払わなければならない税金としては、以下のようなものが挙げられます。
- 所得税:年収103万円を超えたときに発生する税金。収入に応じて税額が上がっていく
- 住民税:年収がおよそ100万円を超えたときに発生する税金。自分が住んでいる自治体に納税する
- 健康保険料:年収130万円を超えたときに発生する税金。社会保険料とも呼ばれる
- 年金:基本的に全国民が支払う。一定条件を満たすと納付が免除されることもある
- 消費税:全国民が支払う。2025年現在で商品の10%が納税額となる
フリーターであっても様々な税金を支払わなければなりません。
特に「年収の壁」と呼ばれる一定の年収額を超えると、所得税や健康保険料等の支払いが必要になってくることになりますので、シフトに入る時間を調整するなども検討する必要があります。
まとめ
フリーターが支払わなければならない住民税がいくらになるのかについて解説しました。
フリーターであっても前年の収入が100万円を超えてくると住民税を支払う義務が発生してきますので、フリーターだからといって住民税を払わなくて良いとは限らないことを認識しておいてください。
住民税の支払い義務がある状態で納税をしないでいると、様々なデメリットに繋がってしまいますので、家計をやりくりすることも大切です。
住民税の支払いに怯えるような生活から解放されたい場合は、正社員への就職も検討してみると良いでしょう。

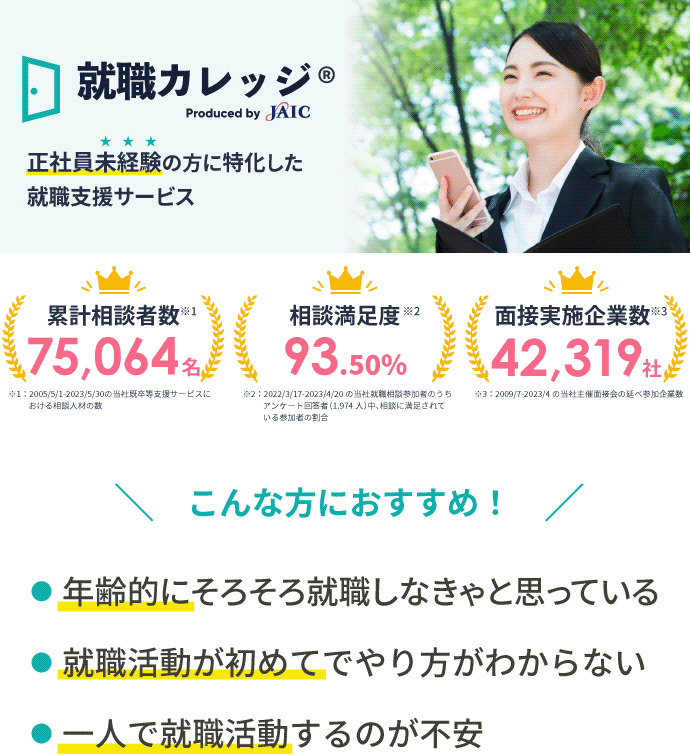

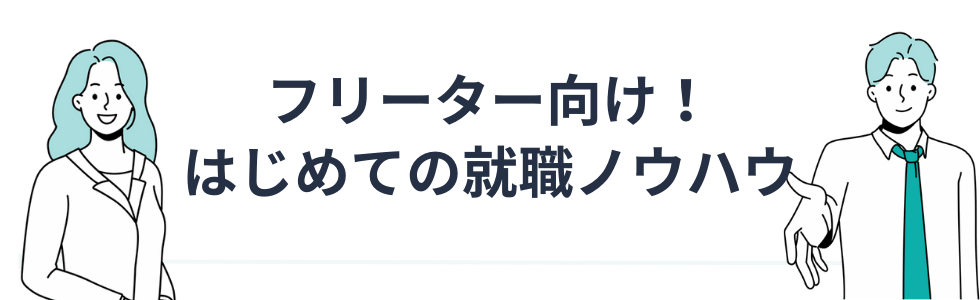
当社の就職に関するコンテンツの中から、フリーターから正社員への就職活動に不安を感じている方向けに、就活で困りがちなことを解決するための記事をまとめました。