
残業代は残業すればする程支払われると思っていませんか?実は労働時間で割増にならずに、会社によって異なる場合があります。この記事では、どのような場合に残業となり手当が発生するのかや、残業代の計算方法について解説します。休日出勤している場合や労働時間が変形の方は一読しておきましょう。
残業とはどのような場合に発生するのか?

残業とはそもそも、いつから残業時間と定められているのかご存知でしょうか。実は、残業時間は会社によって異なる場合があります。
ここでは、会社によっても異なりますが、基本的な残業時間について解説していきます。
残業代を請求できるのはどのような場合?
残業代を受け取ることができるのは元々定められている労働時間を超えて働いた場合です。元々労働基準法で定められている労働時間のことを「法定労働時間」と言い、労働基準法においては法定労働時間を超えて残業した場合に残業代の支払いを義務付けています。しかし、労働時間に関しては法定労働時間と所定労働時間の2種類の考え方が存在しており、これらの考え方を理解していないと自分は残業したつもりでも実際は残業と判断されないということがあり得ます。法定労働時間と所定労働時間はそれぞれどのようなものなのかということを次の段落以降で説明します。
残業の種類1:法定労働時間を超える残業
先ほど解説した通り、法定労働時間は労働基準法で定められた労働時間のことを言います。原則1日8時間、週40時間という取り決めがされており、会社によって変動することは基本的に無く、正社員はもちろん、アルバイトやパートなどすべての労働者に適用されます。この法定労働時間に関する取り決めは不当な長時間労働を防ぐための手段として定められており、万が一法定労働時間を過ぎて残業代が発生しているのにもかかわらず残業代が支払われなければ、法定労働時間を基準にして残業代を計算して会社に請求することも可能です。
残業の種類2:所定労働時間を超える残業
もう一つの所定労働時間とは会社が独自に定めている労働時間のことを指します。企業によっては1日の労働時間が8時間ではなく7時間や7.5時間というところもあるでしょう。このように法定労働時間の範囲内であれば企業で自由に労働時間を決めることができます。所定労働時間については雇用契約書や就業規則で定められているので、雇用契約を結ぶ際にしっかり確認しておきましょう。ただし、所定労働時間を超えて働いた場合でも法定労働時間内であれば「法内残業」といって残業代の支払い義務は発生しません。企業によっては法内残業でも残業代を払ってくれるところもありますが、それは当たり前ではないことを理解しておきましょう。
会社が残業を指示するために必要な条件
会社が残業を指示するには条件をクリアする必要があります。それでは残業をするにあたって必要な条件を見ていきましょう。労働基準法においては法定労働時間内(1日8時間、週40時間)で働くことを原則としています。そこで会社で働く労働者に残業を指示するためには会社の労働組合と「36協定」と呼ばれる取り決めを結ばなければいけません。この36協定の名前は、労働基準法36条において時間外労働や休日出勤に関する取り決めが行われていることに由来しています。そして36協定によって残業をした場合は残業時間に応じて法定労働時間内に働いた際に発生する1時間あたりの賃金に割増しした賃金を支払う必要があります。
ただし、36協定があったとしても会社が労働者を無制限に残業させることは認められていません。2010年代に入ってから残業続きによる過労が原因の過労死やうつなどといった労働災害が多数発生しており、2019年4月に「働き方改革」が提唱され、残業時間の上限に関する規制が厳しくなりました。しかも改正前は残業時間の目安が提示されてはいたものの、これはあくまで厚生労働省が提示する目安であり、法的な拘束力はありませんでした。それに対して改正後の時間外労働に関する制限は法律によって定められているので、これに違反した場合企業に対して罰金などが科されるようになりました。この改正によって労働者が健康に企業で働けるようになることが期待されています。
残業は何時間までできるの?

2019年4月の労働基準法改正により、36協定を結んだ場合の上限は原則として月45時間、年360時間と定められています。この取り決めは大企業だと2019年4月から、中小企業だと2020年4月から適用されることとなっています。これ以外にも1週間で15時間、2週間で27時間そして、年間で360時間などといった上限が設定されており、今まで以上に勤務時間の管理をしっかり行うことが求められるようになりました。
以前は特別条項を付けることにより、1年のうち6ヶ月の間無制限で残業をすることができましたが、改正によって特別条項付きでも年間720時間、休日労働を含め複数月の平均時間80時間以内、単月100時間未満に残業時間を納めなければいけないこととなりました。ちなみに特別条項が無い場合の残業時間は通常1ヶ月45時間、年間360時間で1年変形の場合は1ヶ月42時間、年間360時間となっており、この点においては改正前と同じです。ただし、改正前は法的強制力がなかったのに対して改正後は法律によって上限が設けられたのでこれに違反した場合企業に罰金が科されます。
ちなみに厚生労働省が提唱している残業の過労死ラインは80時間とされています。実際に労災が認められる健康障害を発症している人は発症するまでの2ヶ月~半年の間で平均80時間以上の残業をしていると言われています。ちなみに月80時間以上の残業が発生する場合、1ヶ月の出社日数を20日として1日4時間の残業時間が生じていると考えられます。そうすると1日の稼働時間が12時間を超えてしまうので労働者の休息時間を確保することができません。労働者が健康に会社で働くためにも、80時間はあくまで上限であり、少しでも残業を減らす企業努力が必要と言えます。
基本的な残業代の計算方法

先ほど解説した通り、企業が労働者に対して残業代を支払う義務があるのは法定時間外労働が発生した場合のみであり、法内残業の場合は支払うかどうかは企業で判断して問題ありません。そして、法定時間外労働が発生した場合は基本の1時間あたりの賃金の25%増しの残業代を支払う必要があると定められています。したがって法定時間外労働の残業代は「時間外労働の時間×1時間あたりの賃金×1.25」となります。1時間あたりの賃金に関しては「(基本給+精勤手当)÷1ヶ月の出勤日数÷8」で求めることができます。
法内残業で残業代が支払われるケースの場合、残業代の求め方は法定時間外労働の際の残業代の計算方法と同じ方法で求められることも多いです。ただし、企業によっては「法内残業の時間数×雇用契約書や就業規則で定める1時間あたりの単価」という計算式で求めることもあります。法内残業で残業代が支払われるかどうかに関しては雇用契約書や就業規則に記載されているだけでなく、入社前の企業説明会や面接などで説明されることも多いのでしっかり確認しておきましょう。
また残業時間が多く、例えば所定労働時間が6時間なのに対して毎日3時間の残業が発生した場合、2時間は法内残業、1時間は法定時間外労働と判断されます。万が一このケースで法内残業の際の残業代と法定時間外労働の際の残業代を求める計算方法が異なる場合は自分で残業代を計算してみると実際の支給額とズレが生じる可能性があるので注意しましょう。また、企業によっては残業代を計算するにあたって精勤手当などを基本給に加算したうえで計算することがあります。この際に加算される手当も企業によって異なるので気を付けましょう。
状況によって違う残業代の割増率
法定時間外労働の割増賃金は原則25%です。しかし、場合によっては割増率がさらに高くなるケースが存在します。まず、午後10時から午前5時までの深夜帯の場合、さらに25%上乗せされ、残業代は基本の賃金の50%増しで支払われます。また、1ヶ月で残業時間が60時間を超えた場合も同じく50%上乗せとなります。それに加え、休日出勤だと、基本的には賃金の35%増し、そして休日出勤で深夜帯に働く必要があったなら休日出勤分の35%と深夜分の割増分25%を合わせた60%増しの残業代が支払われます。
ただし、休日に関しても残業と同じように企業が定めた休日である所定休日と法律で定められた休日である法定休日という2種類があります。基本的に休日出勤が認められるのは法定休日ですが、企業によっては所定休日でも残業代を支払うケースもあるのでこの点に関しても雇用契約書や就業規則などを確認しておきましょう。
残業代は会社によって異なる場合がある

残業代には扱い方が厚生労働省は発表した『働き方改革』により大きく変化しつつあります。ここでは、会社によって異なる場合がありますが、大きく分けて3つの残業代の扱いが変わりつつあることを紹介します。
あなたの会社がどの残業代に扱いになっているのかチェックしてみましょう。
働き方による残業代の扱いの違い1:変形労働時間制
変形労働時間制とは所定労働時間を時期によって変え、それぞれを合計した時に法定労働時間内に収めるようにする制度を指します。この働き方はホテル業界やデパート業界など時期によって忙しさが変わる業界で多く導入されています。法定労働時間は1日8時間であり、通常なら1日の労働時間が8時間を超えれば残業代が支払われるでしょう。それに対して変形労働時間制においては1週間の労働時間を40時間と定め、例えば月曜日と金曜日は10時間働いたけれども火曜日~木曜日は6時間しか働いていない場合、1週間の労働時間は合計して38時間となります。その場合、1週間の労働時間が40時間を超えていないために残業代が支払われません。
ただし、変形労働時間制でも1週間の労働時間が法定労働時間である40時間を超えていれば残業代を受け取ることができます。しかし、労働時間が時期によって変動することから残業代が発生していることに気づかないケースも少なくありません。したがって、変形労働時間制を導入している企業で働いている場合は日単位・週単位・期間全体に分けて労働時間の計算を行い、法定労働時間と比べて何時間多く働いているか確認する必要があるでしょう。万が一自分で労働時間を確認してみて残業が発生している場合は企業にそれを請求することができます。また所定労働時間が8時間未満かつ変形労働時間制を導入している職場でも法内残業で残業代が支払われることがあるので、この点は給与規則などを確認しましょう。
働き方による残業代の扱いの違い2:みなし労働時間制
みなし労働時間制は裁量労働制とも言われ、一定の業務をこなしていることが明確な場合に「何時間働いた」とみなして給料を支払います。例えば30時間までの残業代は賃金に含むというみなし労働時間制を導入している企業で働いた場合、30時間までの残業は既に賃金に含まれているので残業代が支払われません。ただし、残業を一切しなかった場合でも30時間までの残業代は支払われます。このようなシステムは直行直帰が多い営業職など、従業員の業務時間を把握しにくい場合に良く導入されています。
また、みなし労働時間制の働き方には大きく分けると2種類が存在します。1つ目が専門業務型裁量労働制です。これは弁護士や建築士、情報処理システムの設計などといった上司の指示を受けずに働く一部の専門職に対して適用されます。次に企画業務型裁量労働制は一部のホワイトカラーの労働者に対して適用されており、業務の方法や時間配分を労働者に任せ、成果重視とすることで業務の効率アップなどを図る制度を指します。ただし、みなし労働時間制を導入している企業であっても、法定労働時間や所定労働時間を超えて働いていると判断されれば残業代が支払われます。また、もちろん休日や深夜に業務を行った場合は休日手当や深夜手当も支払われます。
働き方による残業代の扱いの違い3:フレックスタイム制
フレックスタイム制は労働者が自分自身で出勤・退勤の時間を決めて働く働き方のことを言います。フレックスタイム制においてはコアタイムと言って「この時間だけは出社していないといけない」と決められている時間があり、この時間内に社内にいれば出社時間・退社時間は自由です。このフレックスタイム制は子育てや介護と両立しやすい働き方を実現するために働き方改革によって推進されており、今後フレックスタイム制を導入する企業は増加することが期待されています。
フレックスタイム制においては一定期間の間に何時間働く必要があると決められています。大体は法定労働時間に基づき1ヶ月160時間前後であることが多いです。この労働時間を超えて働く場合はもちろん残業扱いとなることから残業代を受け取れます。基本の労働時間については就業規則などに記載されているので入社時に確認しておきましょう。
残業代の扱いをきちんと把握しておこう
法定労働時間を超えて残業をすれば基本的に残業代が支払われます。また法内残業であっても残業代が支給されることもあります。特に変動的な働き方をしている場合、残業代が発生していることに気づかないことが多いです。就職して企業で働くのであれば、自分が損をしないためにも残業代の扱いをしっかり把握しておきましょう。
















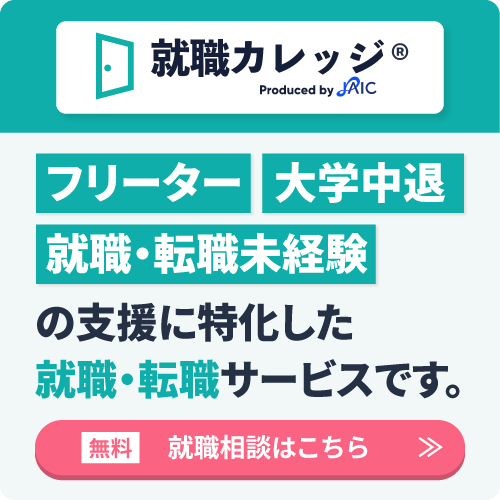
































こんな人におすすめ!