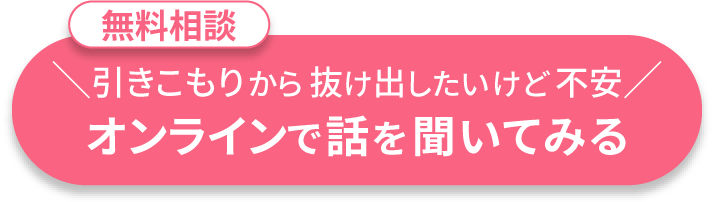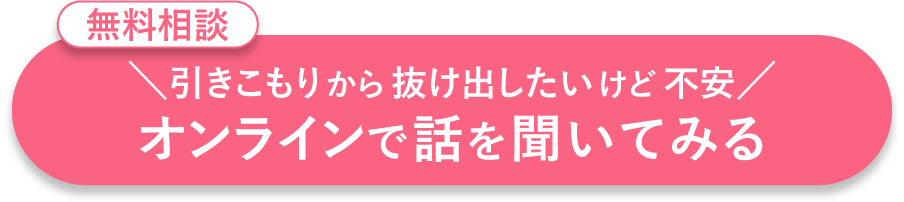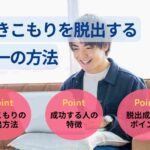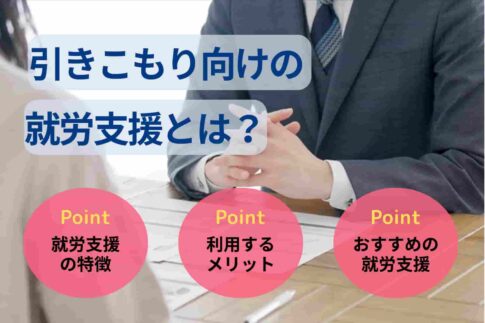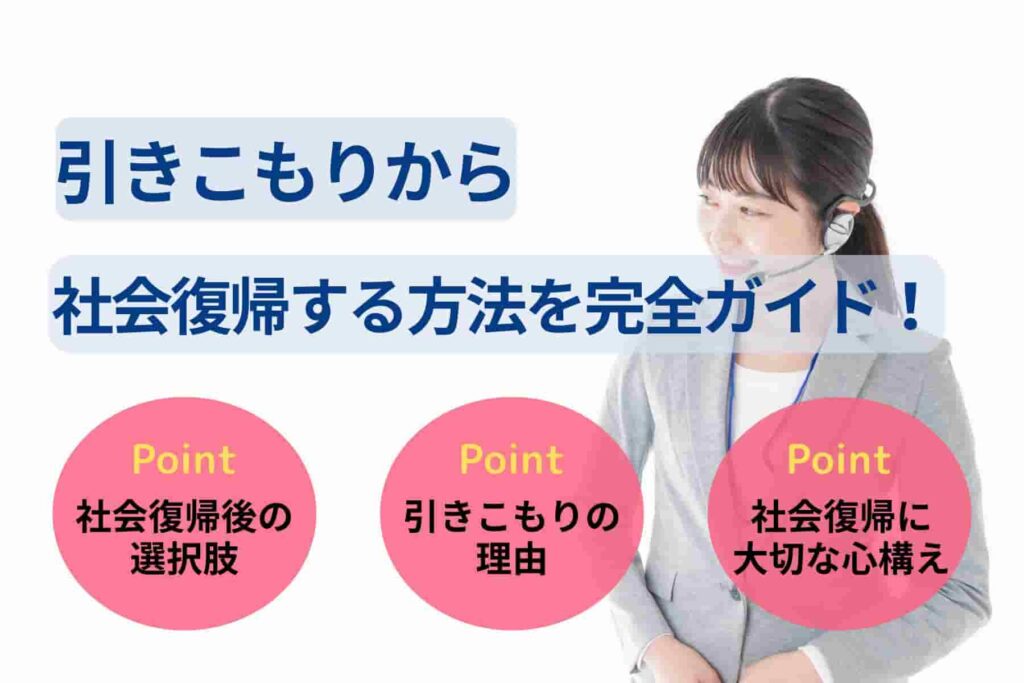
引きこもりから社会復帰するには、生活リズムを整えたり、周囲の人とコミュニケーションを取るなど日常生活から改善していき、社会復帰を支援するサービスを活用しながら少しずつ社会復帰に向けた準備をしていきます。
この記事では、引きこもりから社会復帰する方法について解説します。また、社会復帰支援サービスも紹介するので、ぜひ活用してみてください。
- 引きこもりの期間が長くなるにつれて社会復帰の難易度は上がってしまう
- 引きこもりから社会復帰を目指すなら、ハローワーク、ひきこもり地域支援センターのほか、ジェイックの就職カレッジ®なども活用しよう!
- 引きこもりから社会復帰するコツは、無理せず自分のペースで、自分に適した働き方を見つけること
- 生活リズムを整える
日中に活動するために早寝早起きをする - 周囲とコミュニケーションを取る
人と話すことに慣れる - 自分に合った無理のない働き方を考える
無理なく働ける雇用形態や仕事内容を考える - 就活の準備をする
履歴書の作成や面接対策を行う - 未経験でも挑戦しやすい求人に応募する
求人サイトや就職エージェントを活用し、求人を探す

大学卒業後、大手広告代理店にて広告営業職として従事。その後、一貫して8年間にわたり人材業界に身を置き、累計3,000回を超えるキャリア面談実績を積む。特に、フリーター・ニート・既卒といった若年層の就職支援に深く従事。
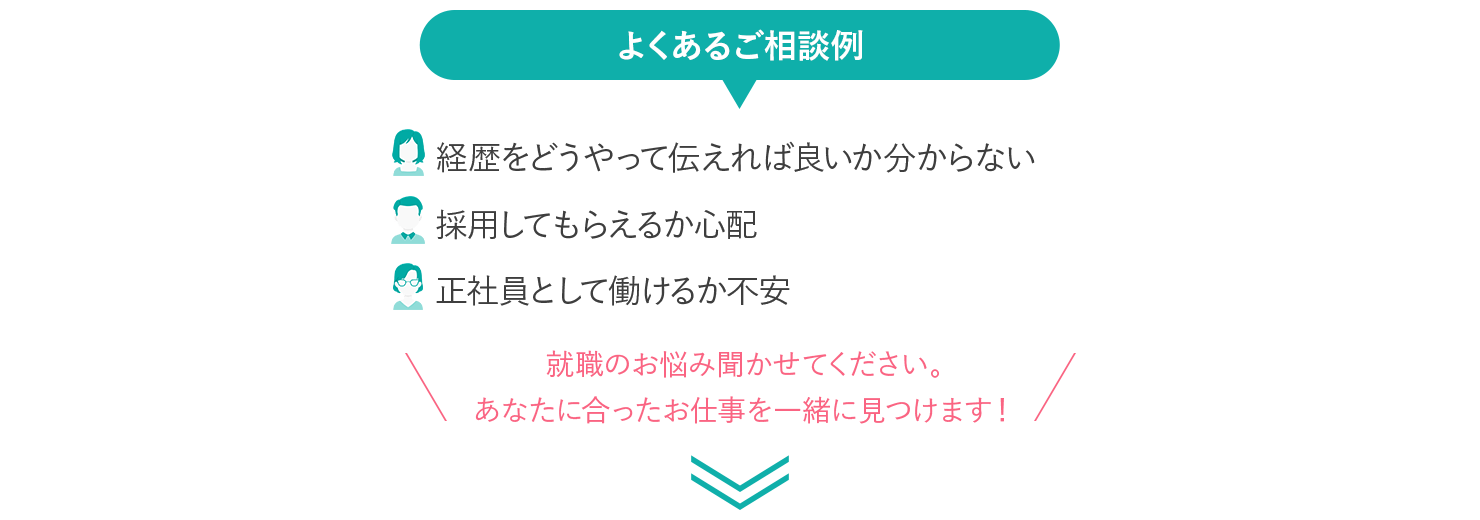



この記事の目次
引きこもりからの社会復帰とは?
引きこもりからの社会復帰とは、長期間にわたり社会との関わりを断っていた人が、少しずつ外の世界とつながりを取り戻し、生活のリズムを改善し、最終的には仕事や社会活動に参加できるようになることを指します。
社会復帰とは単に「仕事に就く」ことだけではなく、社会とのつながりを持ち、安定した生活を送れる状態を指します。
社会復帰の形は人それぞれ異なり、必ずしもフルタイムの仕事に就くことがゴールではありません。
例えば、社会復帰ができたと考えられる状態には、以下のようなものがあります。
- 生活のリズムが安定している
(昼夜逆転がなく、規則正しい生活ができる。食事や睡眠が適切にとれる。) - 社会とのつながりが持てている
(家族や友人と適度な会話ができる。近所やコミュニティと関わる機会がある。) - 外に出ることに抵抗がなくなっている
(近所の散歩やカフェに行くことができる。人混みの中でも不安を感じすぎない) - 何らかの活動に参加できる
(家事や手伝いをこなせる。趣味や学習に取り組める。ボランティア活動やアルバイトなどを始められる。) - 経済的に自立に向かっている
(正社員、パート、在宅ワークなどで働いて収入を得る。 家庭の手伝いや自立の準備ができる。)
引きこもりとは?
引きこもりは、日本の厚生労働省によると「様々な要因により、就学・就労・交遊などの社会的活動に参加せず、原則的に6ヵ月以上にわたり概ね家庭にとどまっている状態」とされています。
参考:厚生労働省「引きこもりの評価・支援に関するガイドライン」
引きこもりから社会復帰した後の選択肢
引きこもりから社会復帰した後の選択肢は、正社員としての就職以外にもフリーターやフリーランス、通信制の学校に通う、大学に行くなどがあります。
- 正社員として就職する
- フリーターになる
- 在宅ワークやフリーランスになる
- 就労支援を活用する
- 通信制・夜間の学校に通う(高校、大学、専門学校)
- 大学に通う
- 職業訓練校を受ける
引きこもりから社会復帰後については、「引きこもりから社会復帰した後の選択肢」で後ほど解説します。
ニート向けの就職支援を活用するのがおすすめ!
引きこもりからの社会復帰を目指すなら、ニートの就職支援に強いサービスを利用するのがおすすめです。
弊社ジェイックの就職支援サービスは、ニートの就職支援歴が豊富にあり、ブランクあり・未経験でも応募可能な企業とのマッチングや選考対策に強みを持っています。
就職に対する不安の相談や就活の進め方についてアドバイスを行っているので、ぜひ相談してみてください。
引きこもりになってしまう理由
厚生労働省の「引きこもり状態になった主な理由」によると、特に以下の5つが引きこもりになってしまう主要因として挙げられています。
- 会社を退職したから
- 人間関係がうまくいかなかったから
- 学生時代に不登校になったから
- 特に理由はない
- 職場に馴染めなかったから
引きこもりになる理由を知っておくことで、自分がどういった思いから現状に至っているのかを客観的に理解できるようになります。
まずはそれぞれ引きこもりになってしまう理由を詳しく解説しますので、引きこもりから社会復帰を目指す際の足がかりにしてみましょう。
1. 会社を退職したから
会社を辞めたことをきっかけに引きこもりになる人は多く、特に退職理由が人間関係の悪化や過度なストレス、過労などの場合、心身のバランスを長期的に崩して社会との関わりを避けるようになりがちです。
中でも真面目で責任感の強い人ほど、「次の仕事をすぐに探さなければならない」と焦ってしまい、結果的に自分を追い込んで引きこもりに繋がるケースもあります。
きっかけは会社の退職であっても、休息期間が長引くうちに外出が難しくなり、引きこもり状態に陥ることも少なくありません。
ネガティブな理由で会社を退職した場合、まずは休む事は悪いことではないと認識することで、精神的なプレッシャーを軽減すると良いでしょう。
2. 人間関係がうまくいかなかったから
職場や学校で孤立したり、いじめやパワハラを受けたりするなど人間関係がうまくいかない過去があった場合、自信を失って人と関わることが怖くなってしまいます。その結果、誰とも関わらないために引きこもりになることも少なくありません。
また、直接的な人間関係でなくても、SNSの影響で他人と自分を比較しやすくなってしまったが故に、「自分だけがうまくいっていない」と感じることも増えています。
人間関係でつまずいた経験は深い心のトラウマになりやすいものの、すべての人間関係でトラブルが生じるわけではありません。
信頼できる人や専門家に少しずつ相談していくことで、引きこもり状態から社会復帰を目指す1歩に繋がります。
学生時代に不登校になったから
学生時代に何らかのきっかけがあって不登校になった場合、自然と引きこもりの期間が長くなるとともに、同年代との交流機会が減り、社会との距離感を感じやすくなります。
加えて、進学や就職のタイミングで不登校の過去を恥ずかしく感じて自信を失うなど、負のループに陥ることも少なくありません。
確かに学生時代に不登校の過去がコンプレックスに繋がる事は珍しくはありませんが、社会復帰を目指す上では未来を考えることが重要です。
例えばオンライン学習や在宅ワークなど、新しい形で社会と関わりやすい時代になっていますので、自分のペースで社会との接点を再構築する意識を持つと良いでしょう。
学生時代に不登校になったから
引きこもっている理由に明確な原因がなくても、長期間のストレスや環境の変化、メンタルの悪化などが重なり、気づけば外に出られなくなっていたというケースもあります。
特に家にいながらして楽しめる娯楽が増えている現代においては、無意識のうちに社会との距離が広がりやすいと言えます。
明確な理由がなく引きこもりになった人が社会復帰を目指したい場合、引きこもりになった原因を無理に探すことなく現状を受け入れて、小さな行動を積み重ねると良いでしょう。必要以上に自己否定することなく、今できる小さなことからアクションする姿勢が社会復帰に繋がります。
職場に馴染めなかったから
満を持して就職したものの、新しい職場にうまく馴染めずに居場所を失ったことがきっかけで引きこもるケースも少なくありません。
仕事の進め方や人間関係の波長が合わないと、孤立感や疎外感が強まり、自分の価値を見失ってしまいがちです。
特に転職直後や新卒入社のタイミングでは、慣れない環境に適応しようと無理をしてしまい、結果的に家から出られず引きこもりに繋がりやすいため注意が必要です。
この場合、あくまでも「自分にとって合わなかった職場があった」という捉え方をすると気が楽になります。自分を責めすぎることなく、職場に馴染めなかった経験を活かして次の就職先を検討する意識を持っておくと良いでしょう。
引きこもりからの社会復帰率
日本の引きこもりの社会復帰率は、低い状態にあるといえます。
引きこもり状態の人の就業経験は15歳~39歳で62.5%、40歳~69歳で90.3%です。
今の自分を変えたいと思う人は75.7%いますが、努力しても希望の職種に就けないとあきらめている人も61.1%います。
内閣府が行った調査では、引きこもりの数は生産年齢人口(15歳~64歳)において全国で推定146万人いると報告されています。50人に1人が引きこもりであるという結果でした。
仕事で外出する必要がなく、私用でもほとんど外出しない「広義のひきこもり」は、15歳から39歳で2.05%、40歳~64歳で2.02%の割合です。
このことから、社会復帰したいと思いつつも、社会復帰への不安を抱えてなかなか動き出せない人が多いことが分かります。
参照:内閣府「こども・若者の意識と生活に関する調査 (令和4年度)」
15歳~36歳対象調査データ
40歳~69歳対象調査データ
引きこもりからの社会復帰が難しい理由
引きこもりから社会復帰するのは無理ではありませんが、社会復帰するのが怖いと感じてしまうことから難しいと言われています。
しかし、生活リズムを整える、周囲の人とコミュニケーションを取るなど、日常生活から改善していき、就職に向けて少しずつ準備していくことで社会復帰できるようになります。
ここでは学術論文や実際の調査データの声から、社会復帰が難しい理由を大きく6つに大別しました。
KHJ 全国ひきこもり家族会連合会のオンラインを活用した ひきこもり支援の在り方に関する 調査報告書から実際の調査の中の声を引用しながら、社会復帰を難しくさせている理由を解説していきます。
- 自信を失ってしまっているから
「働ける自信がない」「社会に必要とされていない」と感じ、行動を起こせない - 人と関わるのが怖いから
長期間人と接していないため、人との会話やコミュニケーションに強い不安を感じる - 過度なストレスを経験したため
過去のトラウマからまた傷つくことを恐れる - 生活リズムが乱れてしまうため
昼夜逆転の生活に慣れてしまい、動く気力が沸かない - 個人の力ではどうしようもないことが起きたから
会社の倒産や病気による退職で自分の力ではどうしようもないと感じてしまう - 社会的空白の期間について話をするのが苦痛である
面接で空白期間について聞かれたときにうまく答えられない
1. 自信を失ってしまっているから
引きこもりの社会復帰が難しい理由として、自信を失ってしまっていることが挙げられます。
引きこもりが長引くと、自信を喪失し、「自分なんて社会で通用しない」といった自己否定感に陥りやすくなります。
学校や職場での失敗体験や人間関係のトラブルがきっかけで引きこもった場合、その経験が心の傷として残り、「また同じことが起きるのでは」と恐れてしまいます。
また、外に出て活躍している同年代と自分を比べて劣等感を抱き、「何もできない自分」に価値を感じられなくなることも多いです。
こうした状態では、新しいことに挑戦する意欲も失われてしまいます。
社会に出たいという気持ちがあっても、強い自己否定感がそれを押しとどめ、「どうせ無理だ」と最初の一歩を踏み出せなくなるのです。
社会復帰には、まず小さな成功体験を積み重ね、少しずつ自己肯定感を取り戻すことが大切です。
2. 人と関わるのが怖いから
人と関わることを恐れるあまり、社会復帰が遠のいている可能性があります。
社会の中ではコミュニケーションは必要不可欠ですが、対人関係が苦手な人もいます。
実際に引きこもりなってしまった人は、コミュニケーションに対するハードルの高さを感じていました。
年齢相応の社会経験を積めていない上に、子供の頃から集団に適応できてこなかったため、一般就労時のコミュニケーションのハードルが非常に高い。いつも周囲に気を遣い、緊張しながら過ごしているが、それでもコミュニケーションでのミスは発生した。ミスの度合いが大きいと、集団内での立場が取り返しのつかないレベルで悪くなった。
引用:特定非営利活動法人 KHJ 全国ひきこもり家族会連合会「オンラインを活用した ひきこもり支援の在り方に関する 調査報告書」
仕事などで怒られることが続き、自信をなくして引きこもりになった人は多くいます。
散々怒られた過去の経験が頭をよぎり、人と関わるのが怖いと感じてしまうのも無理はありません。
多くの引きこもりが、家族以外の人と関わらない生活を送っています。
社会復帰したくても、コミュニケーションの壁が大きな問題となって立ちはだかっているのです。
3. 過度なストレスを経験したため
過度なストレスがきっかけで引きこもりになると、精神的ダメージから立ち直れず、社会復帰が難しくなります。
社会や法律がパワハラをどれだけ規制しても、暴言やいじめの被害者は増え続けています。
人の名前が覚えられずかなりおこられた。ば声をあびせられた。仕事が覚えられず、つかえない人間だと言われた。
引用:特定非営利活動法人 KHJ 全国ひきこもり家族会連合会「オンラインを活用した ひきこもり支援の在り方に関する 調査報告書」
自分を否定されるストレスに耐え続けた結果、心には大きな傷ができてしまうのです。
過去のトラウマから失敗するのを恐れてしまい、ストレスから逃げるため、引きこもりの期間が長くなってしまいます。
集団生活から離れている期間が長引くと、社会復帰したくても仕事に戻る意欲は失われていく一方です。
引きこもりが習慣化してしまうと、他人とのコミュニケーションが大幅に減り、他人に会うことだけでもストレスを感じ始めます。
自己肯定感が下がり自分を否定し始め、すべてに対して前向きな行動ができません。
過度なストレスが原因で不安感を抱えたまま、引きこもり生活を続けている人がいます。
4. 生活リズムが乱れてしまうため
生活リズムの乱れが、社会復帰のハードルを上げている場合があります。
昼夜逆転の生活は、社会のストレスから解放される反面、世間から取り残されてしまうからです。
朝から昼間にかけて太陽の光を浴びないと、体のリズムが崩れやすくなります。
また、もともと人の体内時計は25時間程度の周期と言われており、時間を気にしない生活を続けていると昼夜逆転の生活になりやすいものです。
昼間は、世間にどんどん取り残されてしまうような不安、焦りにさいなまれ、辛くなることがあります。一方、みんなが寝ている夜は、周囲を意識せず、楽に過ごせることがあるようです。生活リズムだけ整えようとしても、本質的な解決には結びつきません。人との会話や日中の活動が増えていけば、生活リズムも自然に改善していきます。
引用:愛知県「ひきこもりにみられる症状と対応」
社会の生活から切り離された引きこもりの人は、体内時間の周期が影響し生活リズムが崩れてしまいがちです。夜は何も気にしないで行動できるため、一度乱れてしまった生活リズムを整えることは簡単ではありません。
日中の行動時間が減り日光を浴びる機会が少なくなることで、うつ病などの健康上のリスクもあります。日光を浴びると、安心感を促すホルモンのセロトニンが分泌されますが、夜型の生活リズムではセロトニンを生み出せません。
生活リズムが乱れた引きこもりの人は、不安な気持ちから逃げるために、さらに外出を避けるようになるのです。
5. 個人の力ではどうしようもないことが起きたから
予想もしなかった事態によって、引きこもりになってしまうケースがあります。
会社の倒産や病気による退職など、個人の力ではどうしようもありません。
実際に仕事が続けられなくなり、引きこもりになった人の声を紹介します。
一方的に事業主の都合で打ち切られた。そのため収入がなくなり生活が大変になった。文句を述べたらお礼として商品券が送られてきてそれでごまかされてしまった。
引用:特定非営利活動法人 KHJ 全国ひきこもり家族会連合会「オンラインを活用した ひきこもり支援の在り方に関する 調査報告書」
長時間労働の中で精神しっかんを発症して何も出来なくなった。働きたいと思っても、年れいのことや、最ていフルタイムから、もしくはフルタイムを目ざすことが社会ふっきの目安となっていて、出来る気がしない。
引用:特定非営利活動法人 KHJ 全国ひきこもり家族会連合会「オンラインを活用した ひきこもり支援の在り方に関する 調査報告書」
突然の解雇や労働環境が原因で精神疾患の発症してしまうことは個人の力ではどうにもならないことと言えるでしょう。
雇い止めの対応には、厚生労働省の「労働条件相談「ほっとライン」(Working Hotline)|厚生労働省」が相談に乗ってくれるでしょう。
病気で仕事の継続が難しい場合、「傷病手当金」のような制度を利用できるケースもあります。
会社の倒産や病気による失業は、誰かが悪いというものではありません。
適切な支援制度を状況に合わせて利用し、社会復帰を目指すことが先決です。
6. 社会的空白の期間について話をするのが苦痛である
引きこもりの人の社会復帰が難しいのは、面接で空白期間(ブランク)について話すのが苦痛に感じてしまうことも考えられます。
引きこもりが社会復帰するには、面接で引きこもり期間の質問をされる覚悟が必要です。
履歴書にひきこもり期間があると、面接での誤魔化し方を考える必要がある等の負担がある。履歴書を書くだけでも傷つく。数回面接に落ちた後、ひきこもり歴を隠すようになった。ひきこもり経験のある人間は、社会から必要とされていないのだと感じた。
引用:特定非営利活動法人 KHJ 全国ひきこもり家族会連合会「オンラインを活用した ひきこもり支援の在り方に関する 調査報告書」
採用担当者にどう思われているのかを考え始めると、ネガティブなことばかりが気になってしまいます。履歴書を書くことにも苦痛を感じてしまい、前向きな気持ちを持ち続けることは楽ではありません。
面接では、採用担当者が無職の期間について質問してくるのは間違いないでしょう。しかし自分に不利だからといって、引きこもりを隠してしまうと、経歴詐称になってしまうこともあります。
採用担当者が知りたいのは、引きこもりの詳細な話ではなく、働く意欲があるかどうかです。過去を反省して、これからの自分の考えを伝えられれば、採用試験を乗り越えられるでしょう。
引きこもりからでも社会復帰できる理由
引きこもりからでも社会復帰ができるよう、公的支援サービスが充実してきています。また、引きこもりからの社会復帰率も30%と低くなく、人手不足の社会状況も相まって、行動すれば社会復帰をしやすい傾向が見られます。
ここからは、引きこもりからでも社会復帰できる理由を、具体的なデータをもとに3つの観点で解説していきます。
本当に社会復帰できるのかという不安な気持ちを払拭しましょう。
公的支援サービスが充実しているから
現在、日本では引きこもりの社会復帰を支援するための公的サービスが全国的に整備されています。
例えば自治体による「ひきこもり地域支援センター」や「就労支援センター」では、カウンセリングから職業訓練、就職支援まで一環したサポートが受けられます。
また、ハローワークの若年者向け専門相談員や、地域若者サポートステーションのような公的機関もあるため、引きこもりからでも社会との繋がりを取り戻す機会が豊富にあります。
このような支援も活用すれば、無理なく自分のペースで社会復帰を目指せるでしょう。
引きこもりでも30%は働けているから
労働政策研究・研修機構の「若年者の就業状況・キャリア・職業能力開発の現状」によれば、1年前に就職せず、家事や通学もしていない人が社会復帰できている割合として、以下のようにまとめられています。
| 正社員 | パート・アルバイト | 派遣社員 | その他雇用 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 15-34歳計 | 18.3% | 8.5% | 2.6% | 4.4% |
| 15‐19歳 | 16.1% | 13.0% | 5.2% | 0.9% | |
| 20‐24歳 | 20.6% | 11.8% | 2.8% | 3.8% | |
| 25‐29歳 | 22.0% | 8.3% | 2.4% | 4.9% | |
| 30‐34歳 | 12.5% | 5.1% | 2.4% | 5.0% | |
| 女性 | 15‐34歳計 | 17.4% | 13.6% | 4.7% | 6.5% |
| 15‐19歳 | 16.4% | 11.8% | 1.4% | 2.9% | |
| 20‐24歳 | 22.7% | 16.6% | 2.7% | 7.0% | |
| 25‐29歳 | 18.3% | 14.0% | 4.8% | 8.2% | |
| 30‐34歳 | 10.7% | 10.1% | 7.4% | 4.3% |
例えば、男性の20代前半の人は引きこもりから20.6%が正社員になれているのに加え、雇用形態に関わらなければ40%弱が社会復帰に成功している水準となります。
昨今では、在宅ワークやスポットワークなど多様な働き方が広がっているため、自宅や近所で働ける環境が整っています。
かつては引きこもりは働けないと考えられがちでしたが、現代はその常識が変わりつつあると理解しておきましょう。
人手不足で引きこもりが就職しやすい状況にあるから
帝国データバンクの調査によれば、2025年7月時点で正社員の人手不足を感じている企業の割合は50.8%と高くなっています。
中小企業のみならず、大企業でも慢性的な人手不足が続いているため、引きこもりで経験が浅い人でも就職しやすい状況にあります。
特に介護や物流、ITやサービス業などは採用ニーズが高く、引きこもり経験がある人でも挑戦しやすい企業が多く存在します。また、研修制度やメンター制度を整える企業も増えてきており、社会復帰のハードルが下がっている点も、引きこもりからでも就職できる理由と言えます。
引きこもりからの社会復帰で大切な心構え
引きこもりから社会復帰を目指す上で大切なのは、自分を責めて焦ることなく、1歩ずつ進む姿勢です。
引きこもりからの社会復帰には時間がかかる場合もありますので、1人で向き合わずに他人を頼ることも重要な心構えとなってきます。
ここからは、引きこもりからの社会復帰で大切な心構えを5つ解説します。
社会復帰をしようとして無理をしすぎてしまうと、引きこもりが長引いてしまうこともありますので、これらの心構えを意識して行動に落としてみてください。
小さな一歩でも自分を褒める
社会復帰の道のりにおいては、外に出る・朝起きる・メールを確認するなど、小さな1歩でも自分を褒めることが重要です。
完璧を求めすぎてしまうと「まだ足りない」などと自分を責めてしまい、社会復帰までのモチベーションが保ちづらくなってしまいます。
自分を肯定する力が積み重なれば、次の大きな行動に繋がりやすくなるため、「昨日よりも少しできた」と思える感覚を意識し、心のエネルギーを回復するような心構えを持っておくと、社会復帰への道が自然と開けていけるでしょう。
焦って社会復帰を目指さない
「早く働かないと」「周りに追いつかないといけない」などと考えると、焦って自分を追い詰めることに繋がります。
引きこもり状態が長い人ほど、生活リズムや社会的な感覚を取り戻すのに時間がかかってしまいますので、焦らず今できることから取り組むと良いでしょう。
例えば、「生活リズムを整える」「他人と話す練習をする」など、目標を小さく分けることで、焦らずとも達成感を得ながら前に進めます。
無理せずに続けられる自分のペースを見つけて取り組むことで、結果的に社会復帰の近道に繋がります。
一人で向き合い続ける必要はない
引きこもりからの社会復帰においては、メンタル面をケアすることも重要なため、家族や友人、専門機関に相談し、客観的な意見や具体的な支援を受けることがおすすめです。
特に地域の引きこもり支援センターでは、同じ悩みを抱える人との交流の場が提供されていますので、利用すると良いでしょう。
自分の悩みを誰かに話すことで心が軽くなり、自分を責める気持ちが和らぎます。
心が元気になると次の行動も取りやすくなるため、「誰かに頼る」といった小さな勇気を持って社会復帰に役立てていく意識を持ってみてください。
様々な働き方があることを知っておく
社会復帰といっても、必ずしもフルタイムの正社員を目指す必要はありません。
近年では在宅ワーク、副業、スポットワーク、フリーランスなど柔軟な働き方が増えています。したがって、社会復帰を目指す際も、様々な働き方の中から自分にマッチしたものを選ぶ心構えをしておきましょう。
「周りが正社員として働いているから」などと、無理に周囲と同じ働き方を選ぶ必要はありません。
選択肢の対応性を理解し、自分が安心できる形で社会復帰を踏み出すことがおすすめです。
過度に他人と比較しない
他人と自分を比較しすぎてしまうと、自分だけが遅れていると感じ、自己否定に陥ることがあります。ただ、人生のペースは人それぞれのため、他人の成功や活躍を焦りではなく「自分にでもできるかもしれない」という希望に変える意識を持ちましょう。
どうしても比較しがちな人は、比較の対象を他人から昨日の自分に変えるだけで、心の負担は大きく軽くなります。
他人と比較することなく、自分のペースで1歩ずつ行動することで、結果的に社会復帰を成功させることにも繋がります。
引きこもりから社会復帰するまでの流れ
引きこもりから社会復帰するまでの流れは以下のようになります。
社会生活に戻るには、日常生活から少しずつ直していく必要があります。
下記の順番で徐々に活動範囲を広げてください。
- 生活リズムを整える
日中に活動するために早寝早起きをする - 周囲とコミュニケーションを取る
人と話すことに慣れる - 自分に合った無理のない働き方を考える
無理なく働ける雇用形態や仕事内容を考える - 就活の準備をする
履歴書の作成や面接対策を行う - 未経験でも挑戦しやすい求人に応募する
求人サイトや就職エージェントを活用し、求人を探す
それぞれ解説していきます。
1. 生活リズムを整える
規則正しい生活を送るために、まず生活リズムを整えるところから始めてください。
生活リズムを整えるには、以下の点に注意して生活しましょう。
- 早寝早起きする
- 朝に散歩をする
- バランスの取れた食事を摂る
- 暴飲暴食をしない
日中に活動するためには、朝起きる習慣に戻す必要があります。
自分が理想とする起床時間から逆算して、最低でも7時間の睡眠時間が取れるように行動してみましょう。朝の散歩は体内時計を整えるほかに、睡眠の質を向上させるのに効果的です。
1日3食のバランスの取れた食生活は、体の調子だけでなく心のバランスも整えてくれます。
暴飲暴食を避けて、食事のリズムも一緒に整えていきましょう。
2. 周囲とコミュニケーションを取る
周囲とコミュニケーションを取って、誰かと交流するストレスに慣れていきましょう。
会社で働くうえで、必ず周りとの報連相が必要になります。就職活動でも、避けては通れない問題です。
初めは家族を相手にするところからで構いません。誰かの話を聞くだけでなく、自分の考えを伝えるようにしてください。
コミュニケーションの練習として、「自立訓練(生活訓練)事業所」や「引きこもりの当事者会」などを活用する方法もあります。
引きこもりを自分の力だけで乗り越えようとする必要はありません。コミュニケーションに壁を感じているなら、自分を理解してくれる人に協力してもらいましょう。毎日コミュニケーションを取り続けているうちに、自分の言葉で話せるようになるはずです。

山田 純輝/キャリアコンサルタント
まずは、自分の「味方」を3人見つけよう!
できる範囲でよいので、人とのコミュニケーションはとるようにしましょう。
コミュニケーションは避ければ避けるほど苦手意識が出てきますが、できる範囲で続けていると慣れてきます。
家族、友達、知人、就活アドバイザーなど周りの人と話す機会を定期的につくるとよいでしょう。
その際、上手く話せなくても大丈夫です。
人に話を聞いてもらった経験、受け止めてもらった経験を少しずつでも重ねることで、コミュニケーションに対する苦手意識が少しずつ消えていきます。
3人でいいので、自分の周りにいる味方を見つけてください。
難しいようなら、地域若者サポートステーションや当事者の会など、自立や社会復帰に向けてサポートしてくれるサービスもあるので、相談してみるとよいでしょう。
思ったよりも、手を差し伸べてくれる人は世の中に多く存在します。
3. 自分に合った無理のない働き方を考える
社会復帰して働き続けるなら、自分に合った働き方が必要です。世の中には多くの仕事があり、雇用形態も仕事によって分かれています。
正社員だけが正解ではないので、派遣・パート・アルバイトまで視野を広げて、働き方を探してみましょう。
フルタイム勤務が難しい場合、アルバイトでも社会復帰の大きな1歩です。週5日の勤務ができなくても、条件次第で働ける仕事があります。業務内容も自分の得意不得意を見直してから、考えてみましょう。
焦って働き方を決める必要はありません。無理せず働ける方法が、社会復帰を実現する企業選びの基準になります。

山田 純輝/キャリアコンサルタント
働き方はひとつじゃない!
働き方は、世の中にたくさん存在します。
まずはアルバイトやボランティアから始めることも、社会との大切な接点ですので、いきなり正社員に挑戦する必要はありません。
また、職場体験や仕事に関する情報サイトなどを上手く活用することも、自分が安心して働けるかを考える際に有効と言えます。
たとえば多くの場合、地域若者サポートステーションでは職場体験を行っています。
厚生労働省の職業情報サイトである「jobtag」なども使うことで、仕事内容や働き方への理解を深めることができるでしょう。
使えるサービスや制度はうまく活用しながら、無理のない範囲で社会との接点をつくる努力をしてみてください。
4. 就活の準備をする
引きこもりから抜け出すために、就活の準備は丁寧に進めていきましょう。
以下の準備が就職活動では必要です。
- 自己分析をする
- 業界・企業研究をする
- 書類を作成する
- 面接対策を入念に行う
順に説明していきます。
自己分析をする
求人に応募する前に、自己分析をすることで就職活動をスムーズに進められます。
自己分析には、自分の強み・弱みや価値観を客観的に判断できる効果があります。
自分に合った仕事が見つけやすくなるだけでなく、就職後のミスマッチを防げることも大きなメリットです。
面接では自分が想定していない内容を質問されることがあります。
自己分析で「働くうえで大切にしたいこと」「やりたいこと・やりたくないこと」を理由も含めて考えておけば、どんな質問にも慌てることなく回答できるはずです。
インターネットで探せば、無料で自己分析できるサービスがあります。
ハローワークや就職・転職エージェントでも自己分析のサポートを受けられます。
あなたの利用しやすい方法で、自己分析を進めていきましょう。
業界・企業研究をする
業界・企業研究は、志望動機を固めるために取り組んでいきましょう。
自己分析の結果と合わせれば、面接でどんな質問をされても困ることがなくなります。
業界・企業研究をすることで、就職後の仕事内容がわかります。興味を持った業界が自分に合っているかを事前に理解できれば、採用後に後悔することがありません。
また、企業が求める人物像やスキルを知り、企業ごとに合わせた選考対策を行えば、就業経験が少ない人でも採用される可能性が高まります。
業界・企業研究は1社1社に対して行う作業なので、時間と手間がかかります。引きこもりから社会復帰を成功させるために、粘り強く取り組んでください。
書類を作成する
企業に応募するためには、履歴書やESが必要になることがほとんどです。
中途採用の場合、社会経験を見るために職務経歴書の提出が義務付けられる場合もあります。
書類の書き方次第では良い印象を与えられずに、書類選考を通過できない可能性があります。
何度も書類選考で落ち続けてしまう人は、就職エージェントといったキャリアのプロによる添削を受けてみましょう。
面接へ進むためには、書類選考の通過が最優先です。
添削指導を申し込むことに、初めは抵抗を感じてしまうかもしれません。
しかし、引きこもりから抜け出した先でも、誰かに相談しなければ解決できない問題は発生するはずです。
1つのトレーニングだと思って、勇気を出して添削を申し込んでみてください。
面接対策を入念に行う
引きこもりの人は、面接対策に力を入れて取り組む必要があります。
面接のコミュニケーションは日常的な会話と違い、回答が難しい質問をされる場合もあります。引きこもりになった理由や、心身の健康状態などの質問に対して、好意的に受け取ってもらうために考え抜いた回答が必要です。
対人コミュニケーションに不安がある人は、自分で考えた回答に自信が持てないかもしれません。
対策として、就職エージェントやハローワークのサービスを利用して、面接対策として模擬面接を行うことも有効です。
面接では回答内容も大事ですが、面接中の態度も採用担当者の評価基準に入ることがあります。面接の回答案を含めた面接練習も進めていけば、実際の面接でも自信を持って対応できるはずです。
5. 未経験でも挑戦しやすい求人に応募する
未経験でも挑戦できる求人を探して、応募をしていきましょう。
ここまで紹介した準備が整っていれば、気になる求人へ積極的に応募して問題ありません。
社会人経験があるなら、知識を持っている業種を選んで応募してください。
就職活動中でも、必要に応じて対策を継続する方が採用される可能性が高まります。
もし、就職活動が進まなくなってしまったら、ここまでに紹介した内容を一度振り返ってみると改善点が見つかるはずです。
引きこもりから社会復帰する方法を完全ガイド【チェックリストつき】
次の3つのカテゴリに分けて、引きこもりから社会復帰する方法を“完全ガイド”として紹介します。
- 日常生活編
- 社会生活編
- 就職活動編
引きこもりから社会復帰できる状態かわかるチェックリスト
自分が社会復帰できる状態にあるか知りたい方は、次のチェックリストを参考にしてみてください。
あくまで目安ではありますが、該当する項目が5個以上あれば「社会復帰できる状態にある」と判断しても良いでしょう。
- 就寝時間と起床時間が一定である
- 規則正しい食事をとっている
- 約束の時間を守って行動できる
- その場に応じた身だしなみができる
- 健康状態が良好である
- 週5日間休まずに活動できる自信がある
- 感情をコントロールできる(イライラや落ち込みがあっても安定した気持ちに戻せる)
- 自分で目標を考えて設定できる
- その場に応じた挨拶や言葉遣いができる
- 人と会話をする機会が頻繁にある
- 人と関わるうえで不安が特にない
- 自分の意思や気持ちを周りの人に伝えられる
- 大勢の人と一緒に協力して作業に取り組める
- その場の雰囲気に合わせて自分の感情や行動をコントロールできる
- 人の話を聞くときは「聞くこと」に専念でき、 内容や気持ちも理解できる
- 自分にも何かできることがあると思う
- 自分の得意・不得意を理解し、受け入れることができる
- 働きたい気持ちがある
- 働き続ける自信がある
- 1日の業務に集中して取り組める自信がある
- 希望する仕事に就くための情報収集をしている
- 求人に応募する準備ができている
- 就職活動をしている、または就職相談をしている
- 興味・関心が高い仕事がある
- 希望する仕事で働くための知識や技能がある
出典:京都自立就労サポートセンター「就労準備支援事業評価指標の全国普及及び指標に係る調査研究事業報告書|1-2.GN-25 評価シート」p.59
※実際の評価シートの文言を一部変更しています
※「GN-25 評価シート」は本人だけでなく、支援者もチェックするシートである点に留意してください
【日常生活編】引きこもりから社会復帰を目指す方法
まずは「日常生活」で意識したいことを中心に、引きこもりから社会復帰を目指す方法を5つのパターンに分けて紹介します。
▼日常生活で自立できているか?
| 現在の状況 | 対応策 | |
|---|---|---|
| A | ・就寝・起床時間がバラバラ ・食事に気を配れていない | 夕方以降の行動に気をつける |
| B | ・約束の時間を守れない ・その場に応じた身だしなみが分からない | 動画やイラストで社会人マナーを学ぶ |
| C | ・体調不良が続いている ・プログラムに休まず参加できる自信がない ※プログラム:「ひきこもり地域支援センター」での就労支援など | スモールステップを取り入れる |
| D | 感情をうまくコントロールできず、イライラや落ち込んだりすることが頻繁に起きる | 感情が乱れた原因をメモする |
| E | 目標を考えるのが苦手 | 自立相談支援機関や就職エージェントで就労プランを一緒に考えてもらう |
A:夕方以降の行動に気をつける
就寝・起床時間がバラバラな方や、食事に気を配れていない方は、夕方以降の行動に特に気をつけましょう。睡眠の質を高められるため、心身ともに健康的な生活を送りやすくなるからです。
厚生労働省では、夕方以降の行動として次の2つをすすめています。
- 夕方から夜(就寝の3時間くらい前)に運動をする
- 就寝に近い時間の夕食や夜食は控える
引きこもりから社会復帰を目指すうえで「健康的な生活習慣」は重要なので、特に日中の活動意欲や集中力に影響するといわれる「睡眠の質」を高めることから始めてみましょう。
出典:厚生労働省「快眠と生活習慣」
B:動画やイラストで社会人マナーを学ぶ
約束の時間をなかなか守れない方や、その場に応じた身だしなみが分からない方は、動画やイラストを通して「社会人マナー」を学ぶとイメージしやすいでしょう。
たとえばYouTubeで「ビジネスマナー」と検索すると、多くの動画が見つかります。
また就活生向けの本には、面接で着ていく服装などが写真で掲載されていることも少なくありません。
動画やイラストであれば、NGな行動や、適切な服装・髪型などを理解しやすいので、ぜひ活用してみてください。
▼参考動画
C:スモールステップを取り入れる
体調不良が続いていたり、プログラムに休まず参加できる自信がなかったりする方は「スモールステップ」を意識しましょう。
スモールステップとは、「大きな目標を小さな目標に分けて一つずつ達成していく」という考え方です。
たとえば社会復帰プログラムに継続して参加できるか不安な場合は、「まずはオンラインの説明会に参加してみる」といったことでもOKです。
一気に頑張ろうとすると心身ともに疲れ、挫折する要因になるので、まずは今の自分にできる範囲の中で行動を起こしましょう。
D:感情が乱れた原因をメモする
感情をうまくコントロールできない方は、「自分の感情が乱れた原因」をその都度メモしておくのがおすすめです。
自分の気持ちが乱れるパターンを把握することで、事前に対策を考えたり、感情が落ち着く方法を見つけたりしやすくなるからです。
たとえば「相手の何気ない一言に傷ついた」ことが原因であれば、「その場を一度離れて気持ちを落ち着ける」といった対策を考えておくのも一つの手といえます。
小さな気づきを積み重ねながら、少しずつ対処法を増やしていきましょう。
E:自立相談支援機関や就職エージェントで目標を一緒に考えてもらう
目標を考えるのが苦手な方は、自立相談支援機関や就職エージェントを頼りつつ、目標を一緒に考えてもらうのがおすすめです。
自立相談支援機関では就職に向けた具体的なプランを作る手伝いをしてくれるので、「どんな目標に向けて、自分は何をすればいいんだろう…」と悩んでいる方には心強い存在といえます。
または、社会経験が少ない方に特化した就職エージェントに相談するのもおすすめです。
引きこもりの方の中には、働くイメージがわかず、社会復帰に向けて自分が何を目標にすれば良いか分からない方も多いかもしれません。
こうした方はまずは専門機関を頼りつつ、自分に合った道を見つけていきましょう。
【社会生活編】引きこもりから社会復帰を目指す方法
次は「社会生活編」と題して、引きこもりから社会復帰を目指す方法を5つのパターンに分けて解説します。
▼社会生活で自立できているか?
| 現在の状況 | 対応策 | |
|---|---|---|
| F | ・その場に応じたあいさつや言葉遣いができるか不安 ・自分の考えを周りに伝えるのが苦手 ・人と話す機会が多くない | ソーシャルスキルトレーニング(SST)に参加する |
| G | ・人と関わることが苦手 ・大勢の人と協力するのが苦手 | 1人でできる仕事や在宅仕事について調べてみる |
| G | その場の空気を読んで自分の感情や行動をコントロールするのが苦手 | 感情をコントロールする手法を試してみる |
| I | 人の話を集中して聞いたり、話の内容や相手の感情を理解したりするのが苦手 | 「大人の発達障害」かと思ったら専門相談窓口に相談する |
| J | ・「自分にできることはない」と悲観している ・自分の得意・不得意なことが何か分からない | 自分が否定されない環境に身を置く |
F:ソーシャルスキルトレーニング(SST)に参加する
他者とのコミュニケーションの面で不安が大きい方は、「ソーシャルスキルトレーニング(SST)」への参加を検討してみましょう。
SSTは、コミュニケーションに関わる基本的なスキルを学べるトレーニングです。
あいさつの仕方や言葉遣い、相手の気持ちを考えた会話の進め方などをロールプレイ形式などで学べます。
SSTは“人と話すリハビリ”としても役に立つため、家族以外とはほぼ話していない引きこもりの方や、対人不安が大きい方が社会復帰を目指す際のトレーニングとしても有効でしょう。
参考:不登校・引きこもり相談センター「ソーシャルスキルトレーニング」
G:1人でできる仕事や在宅仕事について調べてみる
人と関わることや、誰かと協力することに苦手意識がある方は「1人でできる仕事」や「在宅仕事」への就職を検討してみましょう。
たとえば、次のような仕事が挙げられます。
- 動画編集者
- Webライター
- ネットショップの運営
上記の仕事も同僚やお客様とのやり取りは発生しますが、職場(オフィス)などでのコミュニケーションに比べると会話の頻度が抑えられるのがメリットです。
詳しくは次の記事でも紹介していますので、参考にしてみてください。
H:感情をコントロールする手法を試してみる
その場の空気を読んだり、自分の感情や行動を制御したりするのが苦手な方は「感情をコントロールする手法」を試してみましょう。
具体的には、次の6つが有効とされています。
- 感情的になったときのルールを決めておく
- 場所を変える、時間を置く
- マイナスのイメージをプラスに転換する
- 体を動かす、姿勢を変える
- 相手の立場に立ってみる
- 「感謝のリスト」をつくる
たとえば些細なことでカッとなってしまう場合は、「イライラしたら深呼吸を3回する」と決めておくことで衝動的な行動を減らせる可能性があります。
社会復帰にあたって「周りの人に迷惑をかけないかな…」と不安な引きこもりの方は、上記の方法をぜひ試してみてください。
I:「大人の発達障害」かと思ったら専門相談窓口に相談する
人の話を集中して聞いたり、話の内容や相手の感情を理解したりするのが苦手な方は、専門の相談窓口に相談することも考えてみましょう。
こうした状況は、いわゆる“大人の発達障害”が原因となっていることがあり、社会で働くうえで支障をきたしてしまう場合もあるからです。
たとえば、全国の「発達障害者支援センター」はこちらのページで確認できるので、心当たりがある方は一度話を聞いてもらっても良いでしょう。
あわせて、政府が提供している「大人になって気づく発達障害 ひとりで悩まず専門相談窓口に相談を!」にも目を通しておくこともおすすめします。
J:自分が否定されない環境に身を置く
「自分にできることはない」と落ち込んでいる方や、自分の得意・不得意が分からない方は、“自分が否定されない環境”に身を置くことを意識しましょう。
否定される環境にいると「どうせ何をやってもダメだ」と自己否定が強まり、新しいことに挑戦する意欲をさらに失ってしまうからです。
“自分が否定されない環境”としては、次のような場所が挙げられます。
- 引きこもり支援団体(ひきこもり地域支援センターなど)
- 趣味に関わるオンラインコミュニティ(読書会など)
支援団体で軽作業を手伝ってみたら、意外と細かい作業が得意だと気づいたなど、自分の強みに気づけることも少なくありません。
まずは焦らず、自分にとって安心できる場所を見つけることから始めてみましょう。
【就職活動編】引きこもりから社会復帰を目指す方法
最後は「就職活動編」として、引きこもりから社会復帰を目指す方法を6つのパターンに分けて紹介します。
▼就職活動に取り組む準備ができているか?
| 現在の状況 | 対応策 | |
|---|---|---|
| K | 「働きたい」という気持ちが湧いてこない | 1人でできることから始めてみる |
| L | 働き続ける自信がない | 正社員以外の働き方を考えてみる |
| M | 就労支援プログラムなどに集中して取り組める自信がない | オンライン上で就労サポートを受ける |
| N | ・希望する仕事で働くための情報収集をしていない ・会社に応募する準備(履歴書の作成など)ができていない ・求人を探したり、誰かに就活について相談したりしていない | サポステについて調べてみる |
| O | 興味のある仕事がない | 適職診断を受けてみる |
| P | 興味がある仕事があるが、スキルがないので働けるか不安 | 無料の「リスキリングサービス」を活用する |
K:1人でできることから始めてみる
「働きたい」という気持ちが湧いてこない方は、1人でできることから始めてみるのがおすすめです。小さな行動を積み重ねることで、前向きな気持ちを取り戻せる可能性があるからです。
たとえば引きこもりから社会復帰を果たした30代の方は、まずは一人でもできることとしてプールとカラオケに行ってみたそうです。
そして、これらを無理のないペースで生活に取り入れた結果、「自分の現状を打破するにはどうすればいいだろう?」と考えるようになり、引きこもり相談センターに足を運ぶ意欲も湧いてきました。
働く意欲が出なくても焦る必要はありません。まずは、自分ができそうなことから少しずつ試していきましょう。
L:正社員以外の働き方を考えてみる
働き続ける自信がない方は、正社員以外の働き方にも目を向けてみましょう。なぜなら、負担を軽減できる可能性があるからです。
正社員以外の主な働き方は、次のとおりです。
- パート・アルバイト
- 派遣社員
- 業務委託・フリーランス
- 就労支援での仕事(主に障害がある方を対象)
いきなりフルタイムで働けるか不安な引きこもりの方は、まずは週2〜3日のアルバイトから始めてみるのも一つの方法です。
社会復帰は正社員だけが正解ではありません。 自分に合ったペースで働ける選択肢を探しつつ、無理なくステップアップしていきましょう。
M:オンライン上で就労サポートを受ける
就労支援プログラムなどに集中して取り組める自信がない方は、オンライン上で就労サポートを受けるのも手といえます。
対面のプログラムに不安がある方でも、オンラインであれば自宅から気軽に支援を受けられるからです。
たとえば「東京しごとセンター」では、就業支援アドバイザーによる個別相談や、就職セミナーなどをオンライン上で提供しています。
電話やメールで相談できる支援センターも多いので、「対面での相談はハードルが高い…」と感じている方は非対面の相談窓口を活用しましょう。
N:サポステについて調べてみる
就職意欲はあるものの、具体的な行動に起こせていない方は「サポステ(地域若者サポートステーション)」について調べてみてください。
サポステとは、引きこもりから社会復帰を目指している人を含め、“働くことに困難がある人”を対象とした就労支援機関です。
15歳~49歳の方であれば、無料で次のような就職サポートを受けられます。
- 就活セミナー(履歴書の書き方、面接のコツなど)
- 就活講座(ビジネスマナー講座など)
- 職業体験
全国に170か所以上設置されているので、就活の準備・対策をしたい方はまずは自宅近くのサポステを調べてみましょう。
O:適職診断を受けてみる
興味のある仕事がない方は、適職診断の受検がおすすめです。
たとえば厚生労働省の職業情報提供サイト「job tag」では、「職業興味検査」を無料で提供しています。
この検査では、42問の簡単な質問に答えることで「自分が何が好きか」について、そしてその興味関心に近い職種を複数知ることができます。
その職種の仕事内容や平均年収もサイト内で細かく解説されているので、興味がある仕事が見つからない方はまずは適職診断を受けてみましょう。
P:無料の「リスキリングサービス」を活用する
興味がある仕事はあるものの、スキルがないので働けるか不安に感じている方は「リスキリングサービス」の活用がおすすめです。
リスキリングサービスとは、ITスキルを中心に、仕事で役立つ様々なスキルが身につく学習サービスです。
特に以下のサービスは、多くの講座を無料で受講できます。
社会人未経験でスキルに自信がない方や、経済的な負担を減らしつつスキルアップをしたい方は、上記のリスキリングサービスをチェックしてみましょう。
引きこもりの社会復帰におすすめの仕事
引きこもりが社会復帰を目指す際は、無理なく働ける仕事を選ぶことが重要です。
特に、人とも関わりが少ない仕事や、在宅でできる仕事、自分のペースで作業できる職種であれば、就職後にも長く働き続けやすくおすすめです。
ここからは、引きこもりの社会復帰におすすめの仕事を5つ解説します。
少しでも気になる仕事を見つけたら、まずは求人を見てみるところから始めてみてください。
事務職
事務職は、パソコンのデータ入力や書類作成など静かな環境でコツコツ作業できるため、人との関わりが少なく、引きこもりでも精神的に働きやすいためおすすめです。
未経験からでも基本的なパソコンスキルがあれば就職しやすいことに加え、在宅事務の求人も増えている点が特徴です。
| 平均年収 | 529万円 |
| 向いてる人の特徴 | ・コツコツと地道な作業を続けられる人 ・正確さや丁寧さを意識できる人 ・人前に出るよりサポートに回ることが得意な人 |
| 引きこもりでも働ける理由 | ・人との関わりが比較的少なく、静かな環境で働ける ・在宅の事務サポートやデータ入力案件が増加している ・ルーティン業務が多く、徐々に社会リズムを取り戻しやすい |
| キャリアパスの例 | ・一般事務→総務 ・経理事務→事務リーダー ・派遣社員→正社員事務職→管理職(総務課長など )・事務サポート→在宅アシスタント→フリーランス事務代行 |
平均年収出典:厚生労働省「一般事務 – 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))」
Webライター
Webライターは在宅で記事を執筆する仕事で、人と直接関わらずに働ける点が引きこもりにおすすめできる理由です。
未経験からでも論理的に文章を書ければ活躍しやすく、実績を積むことで収入を増やしていける点も魅力です。加えて、引きこもり経験を活かして共感を生む記事が書けるなど、引きこもりならではの強みが発揮できる点もポイントです。
| 平均年収 | 429万円 |
| 向いてる人の特徴 | ・文章を書くことが好きで、自分の考えを整理できる人 ・一人で集中して作業することが得意な人 ・継続力があり、締切を守る責任感を持てる人 |
| 引きこもりでも働ける理由 | ・完全在宅で働けるため、外出が苦手でも安心 ・顔を合わせる機会が少なく、オンラインで完結できる ・自分の経験や知識を文章に変えることで自己肯定感を高められる |
| キャリアパスの例 | ・クラウドワークスなどで執筆→継続案件獲得→専属ライター ・ライター→編集者 ・ディレクター→コンテンツ企画職 ・個人ブログ運営→SEOライター→フリーランスとして独立 |
平均年収出典:株式会社カカクコム「ライターの仕事の年収・時給・給料(求人統計データ)」
動画編集
動画編集は、自宅でパソコンを使って映像を編集する仕事であり、スキルを磨けば安定した収入が得られます。
引きこもりの環境を変えずに仕事に向き合えるだけでなく、人との接触が少ないため、細かな作業が得意な人や集中力がある人であれば活躍していけます。
| 平均年収 | 591万円 |
| 向いてる人の特徴 | ・集中力が高く、細かい作業が苦にならない人 ・映像や音楽に興味があるクリエイティブ志向の人 ・一人で黙々と作業することが好きな人 |
| 引きこもりでも働ける理由 | ・自宅のPCで作業でき、通勤が不要 ・コミュニケーションはオンラインで完結できる ・スキルを磨けば副業 ・個人事業としても活躍できる |
| キャリアパスの例 | ・個人案件で練習→YouTube動画編集→企業案件受注 ・動画編集→映像ディレクター→動画制作会社勤務 ・クラウド案件受注→チーム化→事業立ち上げ |
平均年収出典:厚生労働省「映像編集者 – 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))」
警備職
警備職は施設や駐車場などで安全を守る仕事です。業務内容が明確で、マニュアルに従って働けるため、初めて社会復帰を目指す引きこもりにもおすすめです。
業務中は真面目に警備業務に取り組む必要がありますが、仕事柄人と話す機会が少なく、コミュニケーションに自信がない人でも安心して働けます。
| 平均年収 | 353万円 |
| 向いてる人の特徴 | ・真面目で責任感が強く、指示をしっかり守れる人 ・規則的な生活を維持できる人 ・黙々と業務をこなすことが得意な人 |
| 引きこもりでも働ける理由 | ・業務内容が明確で、マニュアル通りに動けば安心 ・初期研修があるため、未経験でも始めやすい ・夜勤や単独勤務など、人との関わりが少ない勤務形態も多い |
| キャリアパスの例 | ・施設警備員→班長→管理職 ・交通誘導警備→施設常駐警備→警備会社正社員 ・警備スタッフ→資格取得→警備指導教育責任者 |
平均年収出典:厚生労働省「施設警備員 – 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))」
プログラマー
プログラマーはシステムやアプリを開発する仕事で、黙々と作業できることに加え、リモートワークが多い点が引きこもりにおすすめできる理由です。
最近ではオンライン学習のサービスも増えてきていますので、未経験からでも基礎を身に付ければ就職は可能です。
社員とのやりとりもチャットが中心なケースが多く、人間関係に不安がある人でも安心して働けます。
| 平均年収 | 574万円 |
| 向いてる人の特徴 | ・論理的思考が得意で、問題解決が好きな人 ・一人で集中して作業できる人 ・コツコツ学び続けられる探求心のある人 |
| 引きこもりでも働ける理由 | ・在宅勤務・リモートワークが広く普及している ・実力重視のため、学歴やブランクが不利になりにくい ・独学やオンライン講座でスキルを身につけられる |
| キャリアパスの例 | ・独学で基礎学習→IT企業の未経験枠→社内SE ・プログラマー→システムエンジニア→プロジェクトリーダー ・在宅フリーランス→受託開発→自社サービス開発へ展開 |
平均年収出典:厚生労働省「プログラマー – 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))」
引きこもりから社会復帰するきっかけ
引きこもりから社会復帰するきっかけには、以下のようなものがあります。
- 成功体験を積めたとき
自己肯定感が高まり、前向きな考え方ができるようになる - 周囲の環境の変化
引きこもり続けていることに焦りや危機感を覚える - 専門家や支援機関のサポート
自分一人では気づけなかった前向きな視点が得られる
自分は社会でやっていけないと自信を失っていた状態から、成功体験を積むことで自信がついたり、家族や友人の就職や定年退職、結婚などにより自分だけ取り残されたように感じ、焦りや危機感を覚えて前に動き出したい気持ちが沸くことがあります。
また、就職支援サービスなどで専門家に相談することで、自分の過去の失敗について前向きな視点が得られたり、似たような境遇の人が社会復帰に成功した事例を聞くことで社会復帰に向けた行動を起こしやすくなることがあります。
このように、何かに挑戦したり、人との接触をするなど、小さな一歩を踏み出すことで、社会復帰するきっかけに繋がります。
引きこもりからの社会復帰支援サービス
引きこもりの方向けの社会復帰支援サービスには、公的機関が運営する「ひきこもり地域支援センター」「精神保健福祉センター」「地域若者サポートステーション」や、NPO法人の引きこもり支援、民間企業が運営する就職支援サービスなどがあります。
- ひきこもり地域支援センター
- 精神保健福祉センター
- 保健所
- 子ども・若者総合相談センター
- 地域若者サポートステーション
- 市区町村社会福祉協議会
- NPO法人のひきこもり支援機関
- ハローワーク
- 就職カレッジ®(民間運営の就職支援サービス)
ひきこもり地域支援センター
ひきこもり地域支援センターは、都道府県・指定都市に設置された、ひきこもり専門の相談窓口です。
社会福祉士や精神保健福祉士などの資格を持つひきこもり支援コーディネーターが配置されており、電話や来所による相談、訪問支援を通じて、適切な関係機関への早期連携をサポートします。
また、同じ悩みを持つ方が集まる居場所の提供や家族への相談支援も行っています。
ひきこもり地域支援センターでは、関係機関との連携体制の構築や、ひきこもりに関する普及啓発活動も行っています。
無料相談(本人・家族向け)
- 電話・対面・オンラインで相談可能
- ひきこもりの悩みや今後の支援についてアドバイス
専門機関への橋渡し
- 必要に応じて、精神保健福祉センター、ハローワーク、福祉施設、医療機関などを紹介
訪問支援(自治体による)
- 専門スタッフが自宅を訪問し、外出が難しい人をサポート
家族向け支援
- 家族が集まる交流会や勉強会を実施
- ひきこもりの対応方法や支援制度について情報提供
就労・社会復帰支援(地域による)
- サポートステーションや職業訓練と連携し、就労をサポート
- 小さな一歩から始められる活動の紹介
すべての都道府県・指定都市に設置されている(令和3年4月現在)ため、以下のページからお近くのひきこもり地域支援センターを探してみてください。
精神保健福祉センター
精神保健福祉センターは、都道府県や政令指定都市が運営する公的な機関で、引きこもりを含む、心の悩みを抱える本人やその家族を対象に、電話相談や来所相談を行っています。
また、同じ悩みを持つ人や家族のグループ活動も支援しています。
相談支援(無料)
- 本人や家族が電話・面談で相談できる
- 精神的な不安や生活の悩みに対応
医療・福祉機関との連携
- 必要に応じて精神科・心療内科の受診をサポート
- 生活困窮者支援や就労支援機関と連携
訪問支援(地域による)
- 外出が難しい人には専門スタッフが自宅訪問し、状況に応じた支援を提供
家族向け支援
- ひきこもりの家族が相談できる場を提供
- 家族向けの講習会やグループ支援を実施
以下のページから、お近くの精神保健福祉センターを探してみてください。
保健所
保健所は、地域保健法に基づき、地域住民の健康の保持、増進活動の中心となる公的機関として、都道府県、指定都市、中核市その他の政令で定める市又は特別区で設置されています。
保健所では、精神保健対策の一環として、ひきこもり相談をはじめ、心の健康、保健、医療、福祉に関する幅広い相談を受け付けています。
相談方法としては、電話相談や来所による相談があり、相談者の要望に応じて、保健師や精神保健福祉士が家庭訪問をして相談を行うことも可能です。
相談支援(無料)
- 電話・窓口相談:ひきこもりに関する悩みを相談可能
- 家族向け相談:親や家族が対応方法についてアドバイスを受けられる
医療・福祉機関との連携
- 必要に応じて、精神保健福祉センター、医療機関、福祉サービス(生活困窮者支援など)を紹介
- 発達障害や精神疾患の可能性がある場合は、専門機関への受診を案内
訪問支援(地域による)
- 保健師や相談員が自宅を訪問し、状況に応じた支援を提供
- 外出が難しい人に対し、社会との接点を持つきっかけを作る
訪問支援(地域による)
- 保健師や相談員が自宅を訪問し、状況に応じた支援を提供
- 外出が難しい人に対し、社会との接点を持つきっかけを作る
子ども・若者総合相談センター
子ども・若者総合相談センターは、内閣府の「子ども・若者育成支援推進法」に基づき、ニート、ひきこもり、不登校など社会参加や社会的自立に困難を有する子ども・若者等を対象とした総合相談窓口です。
子ども・若者総合相談センターの支援内容は、困難を抱える子どもや若者の育成支援に関する総合相談・助言、保護者のための面接相談、相談内容に応じた情報提供、専門機関との連携などです。
相談支援(無料)
- 電話・対面・オンラインで相談可能
- ひきこもり、不登校、就職・進学、対人関係などの悩みに対応
- 本人だけでなく家族も相談OK
専門機関への橋渡し
- 状況に応じて、ハローワーク、サポートステーション、精神保健福祉センター、NPO団体などを紹介
- ひきこもり支援の専門機関と連携し、適切なサポートを提供
家族向け支援
- 家族向け講習会・交流会を開催
- 他のひきこもり家族と悩みを共有し、情報交換できる場を提供
就労・社会復帰支援
- 必要に応じて、就労支援機関や職業訓練制度を紹介
- 「いきなり就職」ではなく、ボランティア活動や小規模な仕事から始められる支援も
多くの自治体では「子ども・若者総合相談センター」という名称ですが、「若者総合窓口」「若者自立相談窓口」などの名称もあります。
年々設置数が増加していますが、未設置の市町村もあります。以下のページからお近くのセンターを探してみてください。
こども家庭庁「子ども・若者総合相談センター所在地一覧(令和6年4月1日現在)」
地域若者サポートステーション
地域若者サポートステーションは、働くことに悩みを抱えている15歳~49歳の方に対し、就労に向けた支援を行う機関です。
厚生労働省がNPO法人や株式会社などに委託して運営されており、各都道府県に必ず設置されています。
地域若者サポートステーションでは、以下のような支援を提供しています。
キャリアカウンセリング(無料)
- 相談員が仕事に関する悩みや不安に対応
- 自分に合った働き方や職業の選び方をアドバイス
ミュニケーション支援
- コミュニケーション講座やグループワークを実施
- 対人関係や面接の練習ができる
職業体験・職場見学
- 実際の職場で働く体験ができるプログラムを提供
- 「いきなり正社員は不安」という人向けのステップアップ支援
就職活動サポート
- 履歴書の書き方や面接対策をサポート
- ハローワークと連携し、求人紹介も実施
家族向け支援
- ひきこもりや就労に悩む子どもを持つ家族向けの相談も実施
市区町村社会福祉協議会(社協)
市区町村社会福祉協議会(社協)は、地域の福祉向上を目的とした団体で、引きこもりや生活に困っている人向けの支援を提供しています。
各市区町村に設置されており、無料で利用可能です。
市区町村社会福祉協議会の支援内容は以下のようなものがあります。
生活相談・引きこもり支援
- ひきこもり当事者や家族が相談できる窓口を設置
- 生活上の困りごとや、社会復帰に向けたサポートを提供
生活困窮者自立支援制度
- 収入がない・生活が苦しい人向けに、就労支援や住居支援を実施
- 社会福祉協議会がハローワークや福祉事務所と連携し、支援を調整
外出支援・居場所づくり
- 地域でのボランティア活動や交流の場を提供
- 引きこもりの人が社会との接点を増やせる環境を整備
緊急小口資金・福祉資金貸付
- 生活費が厳しい人向けに無利子・低利子の貸付支援
例:「緊急小口資金」「総合支援資金」などの貸付制度
家族向け支援
- 引きこもりの家族が相談できる場を提供
- 家族向け講習会・交流会を実施
以下のページからお住まいの地域の市区町村社会福祉協議会を探してみて下さい。
地域福祉・ボランティア情報ネットワーク「全国の社会福祉協議会一覧」
NPO法人のひきこもり支援機関
NPO法人のひきこもり支援機関は、各法人によって支援内容が異なりますが、一般的に、電話相談や面接相談に加え、訪問支援、居場所づくり、家族会、当事者会、生活寮など、独自の取り組みをしています。
相談支援(無料・低料金)
- 本人や家族が電話・オンライン・対面で相談可能
- 引きこもりの状況に合わせたアドバイスを提供
居場所支援(フリースペースの提供)
- 外出が不安な人でも通える、安心できる居場所を提供
- 自由に過ごせるスペースで、他の参加者やスタッフと交流できる
訪問支援(アウトリーチ支援)
- 専門スタッフが自宅を訪問し、外出が難しい人をサポート
- 家族とも連携しながら、段階的に社会との接点を増やす
就労・職業訓練支援
- 軽作業や農業体験、ITスキル習得など、働く練習ができる
- 就職活動のサポート(履歴書添削、面接練習、職業紹介)
家族向け支援
- ひきこもりの家族が集まり、情報交換や支え合いができる場を提供
- 家族向けの講習会や勉強会を実施
イベント・交流活動
- 趣味活動(ゲーム・スポーツ・創作活動など)を通じた交流イベント
- 自信をつけるための体験型プログラムを提供
ハローワーク
ハローワークは、引きこもりや長期間無職の人向けに、就職支援や職業訓練を提供する公的機関です。全国にあり、無料で利用できます。
相談支援(ジョブカウンセリング)
- 専門の相談員が、仕事の悩みやキャリアプランをアドバイス
- 「いきなり就職は不安…」という人もOK
職業紹介・求人情報の提供
- 全国の求人情報を閲覧・応募できる
- 正社員・契約社員・パートなど、希望に合った仕事を探せる
職業訓練(ハロートレーニング)
- 無料または低料金で、資格取得やスキル習得が可能
- 例:PCスキル、介護、事務、IT、ものづくり など
- 受講中は「職業訓練受講給付金(月10万円+交通費)」を受け取れる場合も
就職準備支援(ステップアップ支援)
- コミュニケーション講座や模擬面接を実施
- 就職に向けた心構えや応募書類の作成支援
サポートコーナー(若年層・長期無職向け)
- 「わかものハローワーク」や「就職氷河期世代支援窓口」**で、個別サポートが受けられる
- 必要に応じて、地域若者サポートステーション(サポステ)と連携
トライアル雇用(お試し就職制度)
- 最大3ヶ月間、企業で試しに働ける制度(給与あり)
- 本採用につながることも多く、未経験者向けの支援が充実
ハローワークの効率的な利用方法は下記のページで詳しく紹介しています。ぜひ読んでください。
就職カレッジ®
ジェイックの「就職カレッジ®」は、正社員就職の支援サービスです。20代~30代・未経験からの正社員就職の成功実績が多数あるため、現在のご状況から正社員就職を成功させたいという方にぜひご利用いただきたいサービスです。
就職カレッジ®をおすすめする理由としては、以下があります。
- 社会人としてのマナーや就職に必要なスキルを講座で学べる
- 書類選考なしの面接会に参加可能
- 就職後も長期的な活躍のため研修を実施
就業経験がない・または少ない方を、短期間で企業で通用する人材へと育成し、内定獲得を実現します。
「就職したら終わり」ではなく、就職活動~入社後の定着まで手厚いサービスを提供します。
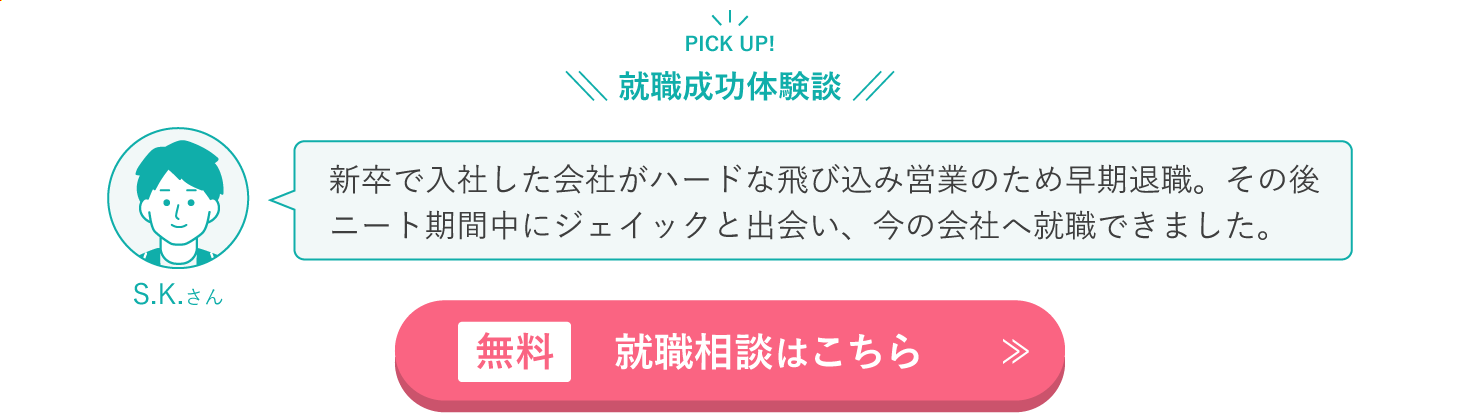
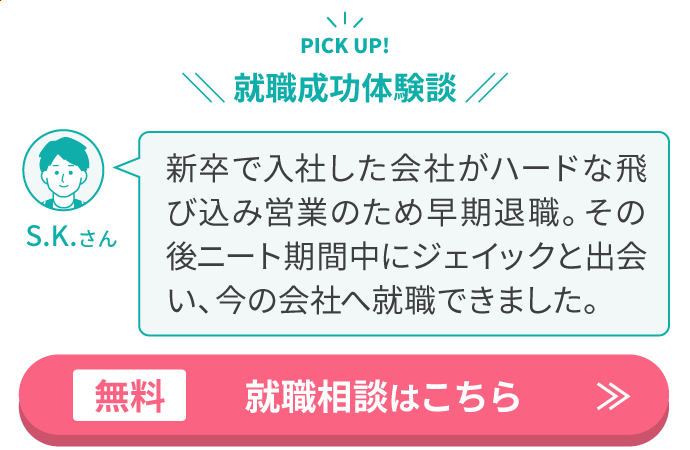
引きこもりから社会復帰した後の選択肢
引きこもりから社会復帰した後に取るべき選択肢を紹介します。
社会復帰後は企業に勤め、社会人生活を続けていくことになります。また引きこもりにならないように、会社勤めを続けられそうな選択肢を選んでください。
1. アルバイト
引きこもりから正社員の勤務が難しく感じるなら、アルバイトから始めてみましょう。
アルバイトで経験を積んでから、正社員登用を目指す方法もあります。
働くことに慣れるまでは、勤務時間や出勤日数を調整してもらえることもアルバイトの強みです。できる範囲から取り組んで、徐々に社会復帰を目指せます。
アルバイトに応募する際には、自分の適性や心身の状況に合った仕事を選びましょう。自分に合った仕事なら、仕事を覚える速度が早くなり、仕事のストレスも軽減されます。
社会復帰の1歩がなかなか踏み出せないなら、まずはアルバイトから探してみましょう。
2. 派遣社員
派遣社員もアルバイトと同様に、社会復帰の最初のステップにおすすめです。
アルバイトより給与面で優れていますが、スキルや経験もアルバイト以上に要求されます。
就業経験がある人なら、アルバイトよりも経験を活かせる仕事が見つけやすいでしょう。
実力が認められれば、正社員登用のオファーもありえます。
派遣社員のデメリットは、雇用が不安定なことです。
仕事ぶりを評価されていたとしても、仕事がなくなれば契約更新されないケースもあります。
正社員ではないので責任のある仕事は任されず、経験を積むには不向きな選択肢です。しかし、就業経験がある人なら社会復帰しやすい点でおすすめの選択肢です。
3. 正社員
正社員としての勤務経験があるなら、培ってきた経験やスキルを活かせる仕事を探してください。内定までのハードルが低く、就職後も即戦力として仕事を任せてもらいやすくなります。
経験がある業種に復帰した場合は、職場の人間関係にも馴染みやすく、社会復帰がスムーズに進むでしょう。
正社員を目指すなら、後述する就職支援サービスの利用をおすすめします。
就活の支援が行き届いており、内定までサポートを受けられます。
持っているスキルや経験を活かした仕事に就きたいなら、責任のある仕事を任せてもらえる正社員を目指して就職活動を進めていきましょう。
4. 専門学校
就職したい業界が決まっていて金銭的な余裕があるなら、専門学校に通うのも選択肢の1つです。専門的な知識やスキルを覚えつつ、生活リズムを整えていきましょう。
引きこもり期間が長いと、就職活動に悪影響が出ることがあります。
専門学校に通うことで、就職する意欲をアピールできます。
就職後も学校で学んだスキルを活かすことで、評価される仕事ができるでしょう。
専門学校に通うメリットは、スキルや経験だけではありません。学校で集団生活に戻ることで、コミュニケーション能力が鍛えられ面接で有利に働きます。
スキルが要求される業界に就職したい場合は、金銭状況と相談して専門学校を検討してみてください。
5. 大学
まだ年齢が20代前半で金銭的に余裕がある場合に限り、大学進学を検討する価値があります。
通信制や夜間学校なら、アルバイトをしながら通学も可能です。
大学卒業の資格があれば、大卒以上を求めている企業に応募できます。
デメリットは大学卒業までに4年間の時間を失うことです。
20代後半になれば、社会的に求められる人間性が変わってきます。
入社したとしても、自分の同期は年下になり、同じ年の社員は目上の存在になる点も忘れてはいけません。
何も考えずに大学生活を送って、4年間の時間を無駄に過ごしてしまわないようにしてください。
「引きこもり 社会復帰」によくある質問
引きこもりから社会復帰をしたい人がよく抱く質問・疑問にお答えします。
- 引きこもりからの社会復帰は難しいの?
- 引きこもりが利用すべき社会復帰の支援サービスは?
- 引きこもりになるきっかけは?
- 引きこもりから社会復帰できる年齢は?
- 引きこもりの精神状態は?
引きこもりからの社会復帰は難しいの?
1年前に無職状態にあった人のうち、2~4割が就職先を見つけて働いているというデータもあるため、引きこもりからの社会復帰は一概に難しいとはいえません(※)。
また、日本には引きこもりの方向けの支援サービスが多く、ブランクが長い方や、仕事経験に乏しい方を積極的に採用する企業も多数存在します。
そのため焦らずに着実に歩みを進めていけば、社会復帰を実現できる可能性は高いでしょう。
※出典:独立行政法人 労働政策研究・研修機構「若年者の就業状況・キャリア・職業能力開発の現状③-平成29年版「就業構造基本調査」より-」p.105
引きこもりが利用すべき社会復帰の支援サービスは?
社会復帰を目指す引きこもりの方は、次の就職支援サービスの利用がおすすめです。
| 就職支援サービス | 特徴 |
|---|---|
| ハローワーク | 無料で職業相談や求人紹介を受けられる |
| 相談支援ひきこもり地域支援センター | ひきこもりの方や、その家族向けに相談支援を行い、社会復帰を目指すためのプログラムを実施 |
| 就職エージェント | 民間の職業紹介サービス。キャリアアドバイザーが個別に相談にのり、求人の紹介や面接対策をしてくれる |
支援内容を具体的に知りたい方は、次の記事も参考にしてみてください。
引きこもりが利用できる就労支援とは?利用するメリットや種類を紹介
引きこもりになるきっかけは?
内閣府の調査によると、年代別の「引きこもり状態になったきっかけ」としては次の理由が挙げられています。
| 年齢 | 引きこもり状態になったきっかけ |
|---|---|
| 15~39歳 | ・退職 ・人間関係がうまくいかなかった ・新型コロナウイルス感染症の流行 ・病気 ・中学校時代の不登校 ・妊娠 |
| 40~64歳 | ・退職 ・新型コロナウイルス感染症の流行 ・病気 ・人間関係がうまくいかなかった ・介護・看護を担うことになった ・就職活動がうまくいかなかった |
出典:厚生労働省「まず知ろう!「ひきこもりNOW」!」
引きこもりから社会復帰できる年齢は?
引きこもりから社会復帰できる年齢に限界はありません。確かに年齢を重ねるほど社会復帰できる割合は減ってきているものの、40歳を超えても20%弱が社会復帰できているため、行動を起こせば再出発は可能です。
※参考:独立行政法人 労働政策研究・研修機構|JILPT 資料シリーズ No.217|若年者の就業状況・キャリア・職業能力開発の現状③― 平成 29 年版「就業構造基本調査」より ―
引きこもりを支援する公的支援サービスが充実している事はもちろん、社会人経験がない人の就職支援に強い民間の就職エージェントも多く登場していますので、うまく活用することでいつからでも社会復帰を目指せます。
ただ、年齢的に若い方が採用されやすい傾向も見られますので、社会復帰を目指したい場合は早めに行動すると良いでしょう。
引きこもりの精神状態は?
引きこもりの人は、長期間の孤立や過去のネガティブな経験により、不安や無気力、自己否定感を抱えていることが多い傾向にあります。特に「社会に出るのが怖い」「自分には価値がない」と感じる引きこもりも少なくありません。
ただ、このような精神状態は一時的なものであることが多く、適切な支援や環境の変化によって少しずつ回復できます。
引きこもりになった場合は過度に自分を責めるのではなく、今の自分自身も認めることで精神的な回復が期待できます。
引きこもりでもステップを踏めば社会復帰できる!
この記事では、引きこもりの人でも社会復帰できる方法を、実態と合わせながら紹介しました。
引きこもりの人が社会復帰しようと思っても、状況を変えられないまま引きこもり生活を続ける人が多いのが現実です。
しかしあきらめる必要はなく、できることから自分自身を変えていくことで、徐々に社会復帰に近づいていきます。
ジェイックでは、引きこもりの人が社会復帰するためのサポートを行っています。フリーター就職支援実績が19年以上のジェイックは、ミスマッチの少ない社会復帰を実現し、非常に入社後定着率を誇ります。
ぜひジェイックの就職支援を受けて、自分に合った社会復帰を目指してください。
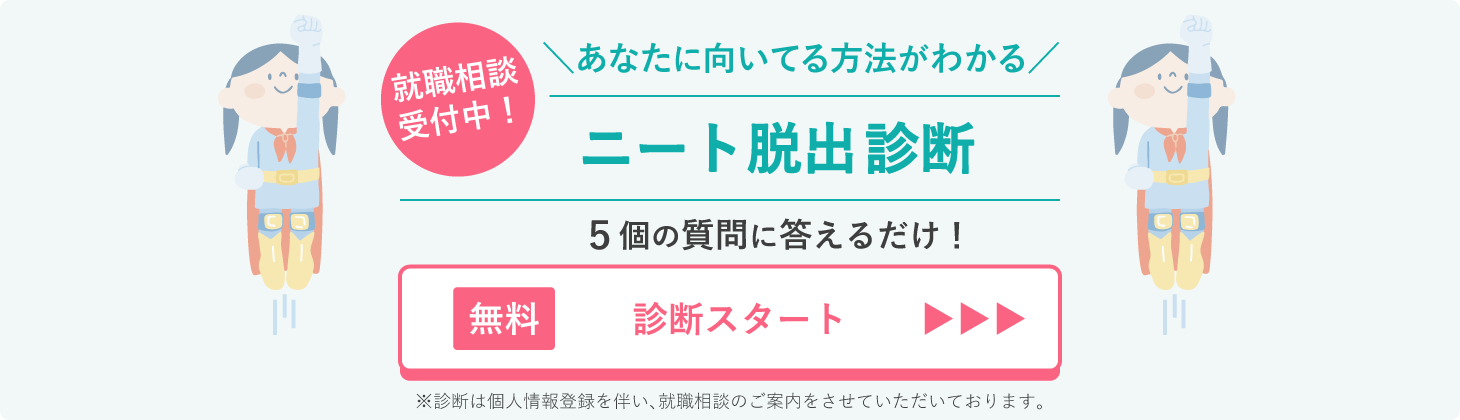
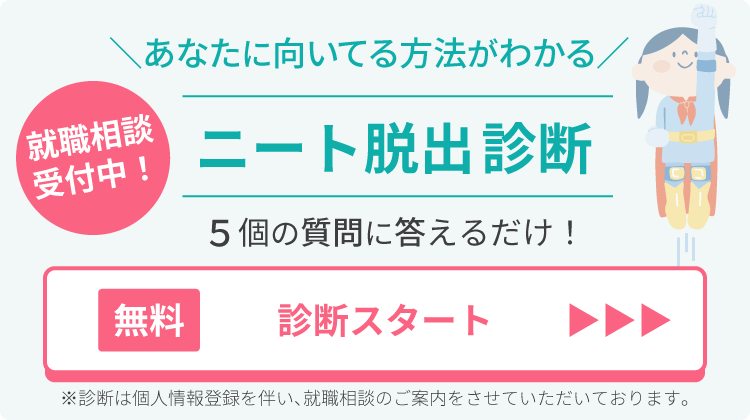
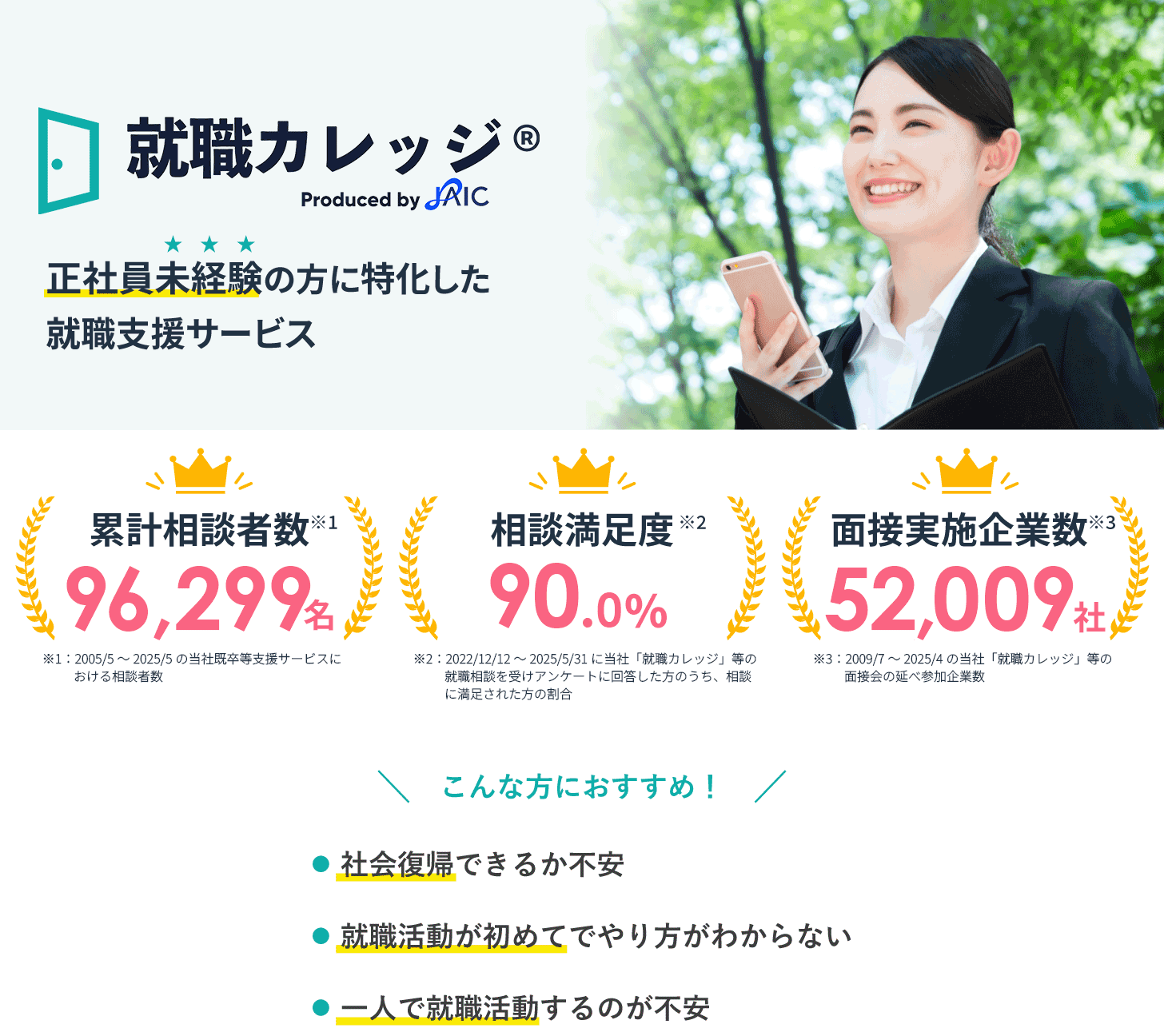
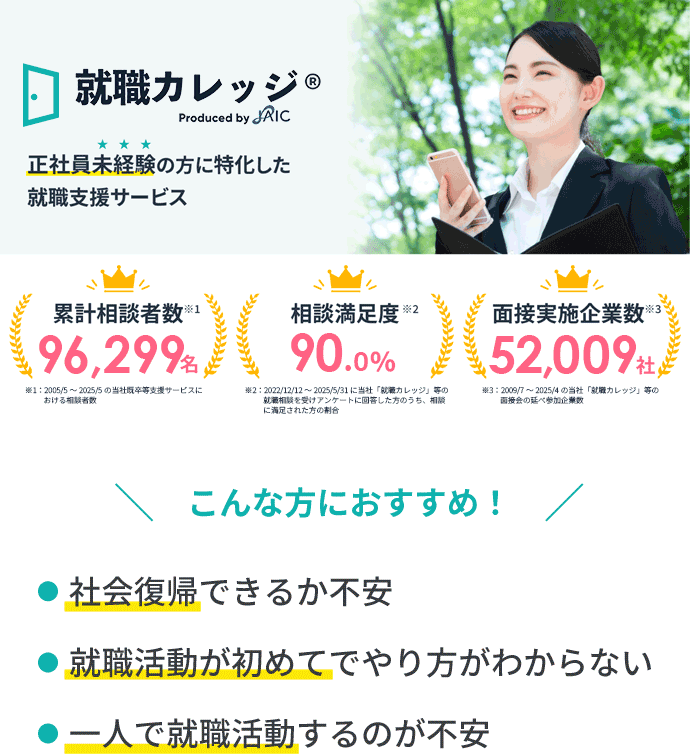

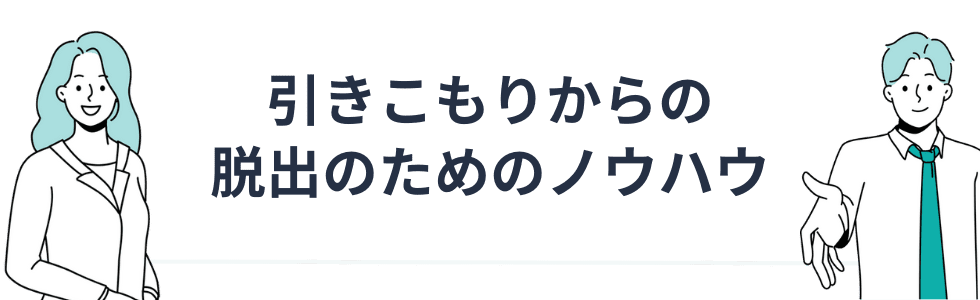
当社の就職に関するコンテンツの中から、引きこもりからの脱出や就職活動に不安を感じている方向けに、引きこもりからの脱出方法や就職活動で困りがちなことを解決するための記事をまとめました。
- 引きこもりを脱出する方法!脱出できる人とできない人の違いも紹介
- 引きこもりでもできる仕事おすすめ20選|探し方・就職支援を解説!
- 引きこもりから社会復帰するには?支援サービスやポイントを知ろう
- 引きこもりから正社員で就職する方法!おすすめ職種を解説
- ニートから就職するには?就活の方法と成功させるポイントを解説
- 引きこもり・ニートの末路とは?脱するための方法も紹介!
- 無職から正社員に就職するには?賢い就活方法とポイントを解説
- ニートから社会復帰するには何からすべき?怖い原因と対処法も解説
- ニートでも安心!ニートの面接必勝法は?
- ニートの履歴書の書き方!空白期間や志望動機のポイントを例文付きで解説
- 20代の引きこもりに関する実態について!原因や脱出方法を解説
- 30代ニートの就職は難しい?ニートの割合や社会復帰の方法を紹介