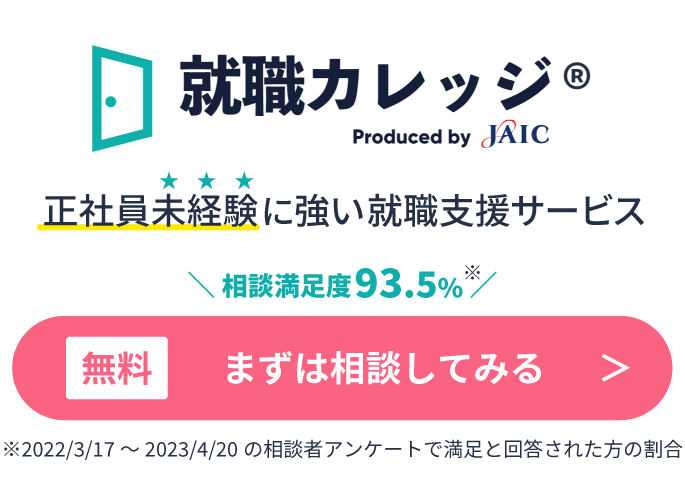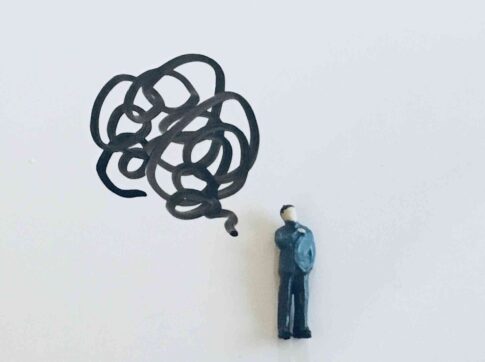ニートの方で求人の探し方が分からない、自分に合った仕事が見つかるか不安といった悩みを抱えていませんか?
この記事では、ニートが求人を探すときのポイントを解説しています。
求人の選び方だけでなく、求人を探すときの注意点や「求人票の見方」も紹介しているので、就職活動で失敗したくない人は参考にしてみてください。
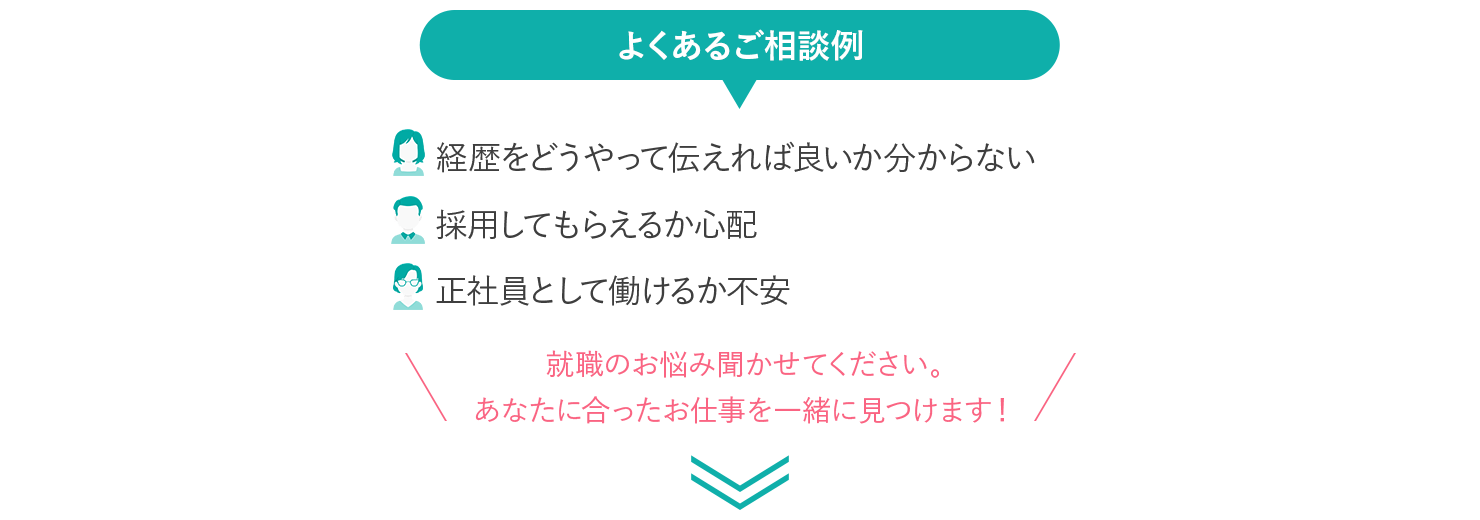



この記事の目次
ニート向けの求人を選ぶポイント
「ニートから就職したいが、どうやって求人を探したらいいのか分からない…」
そう感じている人向けに、ここでは求人を選ぶ際のポイント3点を解説します。
- 未経験者歓迎の求人を選ぶ
- 人手不足の求人を選ぶ
- 給与や待遇で判断しない
1. 未経験歓迎の求人を選ぶ
ニートから求人を探す際は、未経験歓迎の求人を選ぶことをおすすめします。なぜなら、ニートは社会人経験があまりなく、経験者優遇の求人に応募すると不利になるからです。
未経験者歓迎の求人を探すうえで知っておきたいことは、業種と職種の違いです。
- 業種:事業そのものの種類
- 職種:働く人が行う作業の種類
実際の求人情報には、以下のような記載がされています。それぞれの違いを知って、求められていない求人に応募してしまわないよう、気をつけましょう。
業種・職種未経験可:完全な未経験者を歓迎している(ただし若い人をターゲットにした求人も多い)
- 業種未経験可:扱う商材は違っても構わないが、業務自体の経験がある人を探している
- 職種未経験可:業界ならではの知識・技術・慣習が分かる人を探している
2. 未経験歓迎の求人は多い
大手求人サイトで調べてみると、未経験歓迎の求人は豊富に掲載されていることが分かります。
たとえば「マイナビ転職」は、約16,000件のうち未経験歓迎の求人が59.1%を占めるなど、実に半数以上の求人で未経験者を積極的に募集しています。
同じく大手求人サイトの「doda」は割合こそ低いものの、マイナビ転職を上回る32,000件以上の未経験求人を保有しています。
社会人経験がないニートでも応募できる求人が多いので、「未経験歓迎の求人は多い」ということを自信に変え、就職活動に前向きに取り組んでいきましょう。
| 求人サイト名 | 総求人数 | 未経験者歓迎の求人数 | 総求人数に対する 未経験者歓迎の求人数の割合 |
|---|---|---|---|
| マイナビ転職 | 28,165件 | 16,662件(※1) | 59.1% |
| doda | 255,324件 | 32,475件(※2) | 12.7% |
| 合計 | 283,489件 | 49,137件 | 17.3% |
2024年11月時点※1「職種未経験OK」「業種未経験OK」の求人を集計
※2「職種未経験歓迎」「業種未経験歓迎」の求人を集計
3. 人手不足の業界の求人を選ぶ
人手不足の業界の求人は、採用される確率が高いのでおすすめです。具体的には、以下の7業種が人手不足の業界といわれています。
- 小売業
- 建設業
- 運輸業
- サービス業
- 放送業
- 金融業
- 警備業
これら7業種は、それぞれ適性や大変さが異なります。ニートで求人情報を探している人は、自分の興味や適性から合う業界がないかを考えてみましょう。
4. 給与や待遇で判断しない
給与や待遇で判断しないことも大切です。なぜなら、求人案内に記載されているものと実態が違うことはよくあるからです。例えば、求人に記載されている給与の中には、残業代や深夜割増など各種手当が含まれていることもあります。その場合、実際にその額がもらえるわけではありません。
また、給与や待遇以外にも、以下のように仕事を選ぶポイントはたくさんあります。
- 仕事内容
- 将来性
- 人間関係
- 勤務時間
給与や待遇は他の求人情報と比較しやすいため目が行きがちですが、まずは自分にとって条件の優先順位をつけてみましょう。
ニートがチェックしたい求人票の項目
「仕事を早く探さないと…」と焦ってしまうと求人票を十分に確認せず、いわゆる“ブラック企業”のような会社に入ってしまう可能性があります。
安心して働ける会社に就職するためにも、求人票は次の3つの項目を特にチェックするようにしてください。
1. 賃金
求人票の賃金は「額面」で書かれているケースが多いことに注意しましょう。
額面とは、社会保険料などを差し引く前の金額のことです。つまり手取り(実際に受け取れる金額)は額面よりも少なくなります。
手取りは、額面の8割ほどが一般的です。たとえば求人票に「20万円」と記載されていた場合、手取りは16万円ほどと予想できます。
賃金に関しては「固定残業代」にも注意しましょう。
固定残業代とは、給与にあらかじめ含まれている残業代のことです。「残業◯時間を含む」と求人票に書かれていることが多いでしょう。
一見すると給料が高くみえるので魅力的に思えますが、単に残業代が含まれているだけです。
「◯時間の残業はほぼ発生します」という会社からのメッセージとも読み取れるので、こうした会社に入社すると仕事に追われる忙しい日々を過ごす可能性もあります。
2. 休日
求人票を見る際は「休日」も確認しておきましょう。
厚生労働省の「令和4年 就労条件総合調査 概況」(※)によると、日本の平均年間休日数は107日です。
一般的に年間休日が120日以上あればホワイト企業と言われることが多いので、休みをしっかり取りたい人は「120日以上」の会社を探してみてください。
休日に関しては、次の違いも理解しておきましょう。
| 完全週休2日制 | 毎週2日間の休日が必ずある |
| 週休2日制 | 週2日の休日が月に1回以上ある |
出典:厚生労働省「令和4年 就労条件総合調査 概況(p.5)」
3. 勤務時間
勤務時間は「始業時間」と「終業時間」が求人票に書かれていることが多いですが、なかには「フレックスタイム制」と明記されている求人もあります。
フレックスタイム制とは、従業員が自分の都合に合わせて始業時間と終業時間を決められる制度のことです。
多くの場合、フレックスタイム制には「コアタイム(必ず勤務しなければならない時間帯)」が設定されています。
たとえば10時から15時がコアタイムの会社であれば、10時から15時は出社し、それ以外の時間帯は自分の都合に合わせて勤務時間を調整できます。
なお「フルフレックス」の会社もあり、この場合はコアタイムもなく、1日の決められた勤務時間を満たせばいつ働いてもOKです。
ニートは求人サイトを利用しよう!
ニートが就職活動を進めるときは、求人サイトの利用がおすすめです。
求人サイトとは、求人が一覧で掲載されているWebサイトのことです。ほとんどの求人サイトは無料で利用できます。
就職エージェントのようにキャリアアドバイザーはつきませんが、そのぶん就活を急かされることなく、マイペースに就職活動を進められるのがメリットです。
「就活を少しずつ始めたい」「自分がどんな求人に応募できるか確認したい」という人は、まずは求人サイトに登録してみましょう。
ここでは、求人サイトを使う時の押さえておくべきコツと注意点について解説してきます。
1. 求人サイトを使う時のコツ
求人サイトのメインの機能は「求人検索」ですが、実はそれだけではありません。
求人サイトを効果的に使いたい人は、次の3つの方法も試してみましょう。
「気になる」ボタンを押す
求人サイトによっては、求人票の下あたりに「気になる」というボタンが用意されています。
気になるボタンを押すメリットは、あとから求人票をゆっくりと見返せることです。「お気に入り」と似たようなイメージを持つと良いでしょう。
また、「気になる」という気持ちが企業に伝わる仕組みになっている求人サイトも少なくありません。
企業に自分の存在を知ってもらうきっかけにもなるので、気になるボタンは積極的に押していきましょう。
スカウト機能を利用する
求人サイトの中には「スカウト機能」を無料で利用できるところもあります。
スカウトとは、企業の採用担当者からオファーが届く仕組みのことです。
求人サイトに登録した経歴を企業が見たうえで、「この人にぜひ応募してほしい」と考えたときにスカウトを送るケースが一般的です。
スカウト機能を利用するメリットは、次のとおりです。
就活のノウハウについて調べる
求人情報だけでなく、求人サイトには就活に役立つ情報も豊富に掲載されています。就活の基礎が分かる情報も多数載っているので、就活が初めてのニートや、書類選考や面接に合格できるか不安な人はぜひチェックしておきましょう。
たとえばジェイックでも、履歴書や面接対策、未経験からの就職に関して役立つ情報を発信しています。ぜひ参考にしてみてください。
就活ノウハウ
内定率を高めるためにも、こうした情報収集もぜひ積極的に行ってみてください。
2. 求人サイトを使う時の注意点
求人サイトは便利なサービスですが、いくつか注意したいポイントもあります。
条件を絞り込みすぎない
応募できる求人が減ってしまうため、求人サイトで求人を探すときは条件を絞り込みすぎないようにしましょう。
社会人経験が乏しいニートの場合、応募できる求人は経験者より多くありません。条件を細かく設定すると選択肢がさらに狭まってしまうため、はじめは条件をゆるく設定するのがおすすめです。
多くの求人を見ることで、自分が本当に働きたいと思える会社や仕事が見つかる可能性もあるでしょう。
求人サイトを利用する際は、条件を絞り込みすぎない、ということをぜひ強く意識してみてください。
スケジュール管理に気をつける
求人サイトを使うときは、スケジュール管理にも気をつけましょう。
求人サイトは一人で就活を進めるサービスのため、面接日程の調整などについて企業と直接やり取りする必要があります。
1社だけでも複数回のやり取りが必要なケースが多いですが、応募数が5社、10社と増えていくと「A社とB社の面接日が重なってしまう」といったミスが起こりがちです。
面接日をカレンダーにしっかり書き込んでおくなど、求人サイトを使う際はミスを防ぐ対策を特に意識しましょう。
ニートが求人サイトを使う流れ【5ステップ】
求人サイトを使ったことがない人に向けて、5つのステップに分けて使い方の流れを紹介します。
ステップ1:登録
まずは求人サイトの登録から始めましょう。
使いたい求人サイトの公式ホームページに行き、「会員登録」のページで以下のような情報を入力します。たとえばマイナビ転職の場合、入力する項目は4つだけです。「LINE ID」などを持っている場合には情報を連携できるので、上記の入力すら不要です。登録が終わると「会員登録を完了させてください」といった件名のメールが届き、そのメールに記載されている認証URLをクリックすることで登録が完了します。
ステップ2:求人検索
求人サイトには、事前に登録したメールアドレスとパスワードでログインできます。
無事にログインできたら、求人を早速探してみましょう。
求人検索画面では、以下のような条件を設定できます。「未経験OK」といった条件を選択できる求人サイトは多いので、仕事経験がないニートや、経験のない仕事にチャレンジしたい人は「未経験OK」の条件を設定しておきましょう。
ステップ3:応募書類の作成
気になる求人が見つかったら、応募書類を作成しましょう。
多くの求人サイトでは「Web履歴書(Web上で応募書類を作れるサービス)」を提供しています。
Web履歴書を使うと写真を簡単にアップロードできたり、選択式で学歴を入力できたりするため、紙の履歴書に手書きする必要がありません。
ちなみにWeb履歴書には「自己PR」の入力が必要な場合があり、何を書けばいいか迷ってしまう人も多いでしょう。
とはいえ、心配はいりません。「自己PRの書き方」といった情報を詳しく載せている求人サイトが多いので、書き方に悩んだらこうした内容をぜひチェックしてみてください。
ステップ4:面接
応募書類を提出後、選考結果の連絡がマイページ上の「メッセージボックス」などに届きます。
面接日程については、企業とメッセージで直接やり取りするか、希望日程をマイページ上で入力するだけでOKな場合もあります。
面接では、これまでの経験や、志望動機などについて面接官から質問されます。ニートの場合には「働いていない期間が長い理由」を聞かれる可能性もあるため、聞かれたときに慌てないように回答を準備しておきましょう。
受け答えのコツは、以下の記事で解説しています。
ステップ5:内定
面接に合格すると内定をもらえます。
内定後は「内定通知書」と「労働条件通知書」を企業から渡されるケースが一般的です。
求人票に記載されている情報と違う場合もあるため、「労働条件通知書」に記載されている勤務形態や給与、業務内容などは特にしっかりと確認しましょう。
条件に納得できれば入社の意思を企業に伝え、その後は入社日の調整を企業の人事担当者と進めていきます。
ニートは就職エージェントを使うのもおすすめ
ニートが求人を探す際は、求人サイトだけでなく就職エージェントも利用してみましょう。
就職エージェントとは、専任のキャリアアドバイザーが就職活動をマンツーマンで支援してくれるサービスです。
求人サイトと同じく無料で利用でき、以下のようなサポートを受けられます。就職エージェントと求人サイトの違いは以下の通りです。
| 就職エージェント | 求人サイト | |
| 特徴 | 専任の担当者がサポートしてくれる | 自分一人で就活を進める |
| 主なメリット | 自分に合った求人を紹介してくれる | マイペースに就活を進められる |
| 主なデメリット | 自分のペースで就活を進めにくい | 自分に合った求人を見つけるのが難しい |
就職活動を一人で進めていける自信がない人は、就職エージェントの利用がおすすめです。
では、就職エージェントの主なサポートについて具体的に紹介します。
1. 自己分析を手伝ってくれる
就職エージェントを使うと、キャリアアドバイザーが自己分析を手伝ってくれます。
これまでの経験や性格などを“就職のプロ”の目線で分析しつつ、あなたに向いている業種や企業を教えてくれるので、自分に本当に合った仕事に出会える可能性が高いでしょう。
特にニートの中には、社会で活かせる自分の強みがわからない方も多いかもしれません。自分のことは自分自身が分かっていないケースも多いので、キャリアアドバイザーの客観的な意見をぜひ取り入れてみましょう。
2. 履歴書や面接をサポートしてくれる
就職エージェントを使うと、選考対策についても具体的なアドバイスを受けられます。
たとえば履歴書の書き方や、強みをアピールする方法などを教えてくれるので、就活が初めてのニートはぜひ積極的にアドバイスを求めてみてください。
また、応募する企業ごとに評価される強みや経験を教えてくれるのも就職エージェントを使うメリットの一つです。
3. 企業との調整作業を代行してくれる
就職エージェントは求職者と企業の間に入り、様々な調整作業を代行してくれます。
企業とのやり取りは神経がすり減る場面も多いですが、就職エージェントを使うと企業との調整作業をほぼ全て代行してくれるので、大きなストレスなく就職活動を進められるでしょう。
【Q&A】ニートが抱く求人についての質問
就職活動を始めたばかりのニートが抱きやすい「求人の疑問」にお答えします。
Q. ニートをほしがる会社はある?
A. ニートを採用したい会社は多数存在します。
仕事をしていない期間が長い人からすると、「ニートをほしがる会社は存在するのかな…」と心配になるかもしれません。しかし人手不足に悩んでいる会社は日本に多いので、社会人経験を問わず、特に10代・20代の若い世代を採用したいと考えている企業はたくさんあります。
Q. ニートでもできる仕事はある?
A. 多くの職種があるので、ニートでもできる仕事はきっと見つかります。
「社会経験が少ない自分にできる仕事はあるのかな…」と不安な人も多いかと思いますが、心配はいりません。なぜなら、日本だけでも18,000種以上(※)の職種があると言われているからです。
「営業」や「販売」など、未経験者が多く活躍している仕事も多いので、ぜひ諦めずに仕事を探していきましょう。
※出典:独立行政法人 労働政策研究・研修機構「第5回改定厚生労働省編職業分類 職業名索引(2022年改定)」
Q. ニートはブラックな会社にしか採用されないのでは?
A. “ブラック”の定義は曖昧なので、「ニートはブラックな会社にしか採用されない」と一概に言うことはできません。
たとえば「残業が多い会社はブラックだ!」と考える人もいれば、「給料が高くなるのでむしろ残業をしたい」と考える人もいます。
このように“ブラック”の定義は人によって異なるので、まずは「どんな会社を避けたいか?」について具体的に考えてみましょう。
避けるべき会社が明確になることで、自分にとってのブラックな会社に入社するリスクを下げられます。
まとめ
この記事では、ニートが求人を探すときのポイントを解説しました。
就職活動を成功させたい人は、次のポイントを意識して求人を探しましょう。社会復帰には大きな不安がつきまといますが、求人サイトや就職エージェントなど、ニートの就職をサポートしてくれるサービスは多く存在します。
一人で悩んでしまうときこそ、まずは周りを頼ってみましょう。
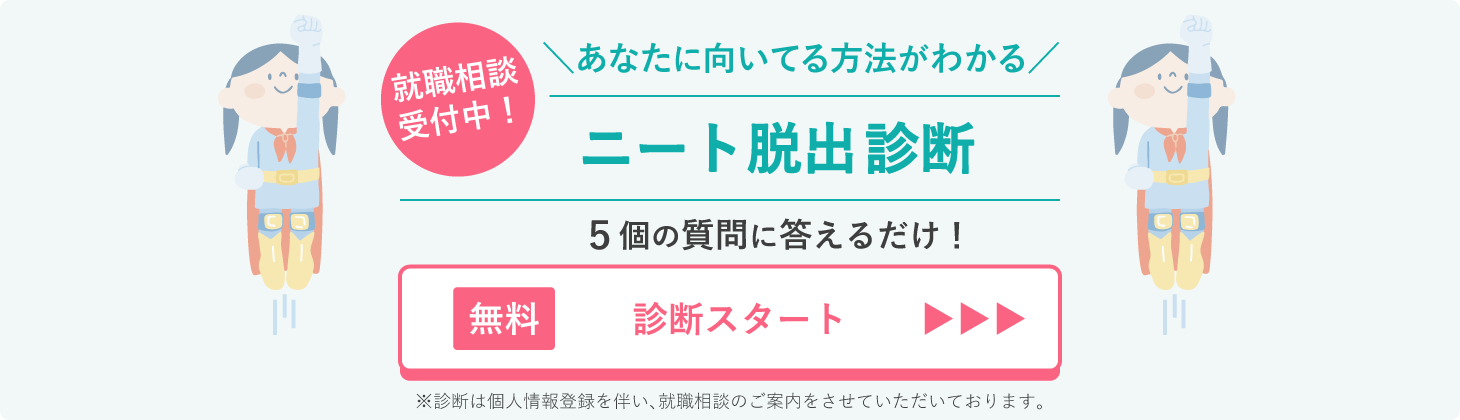
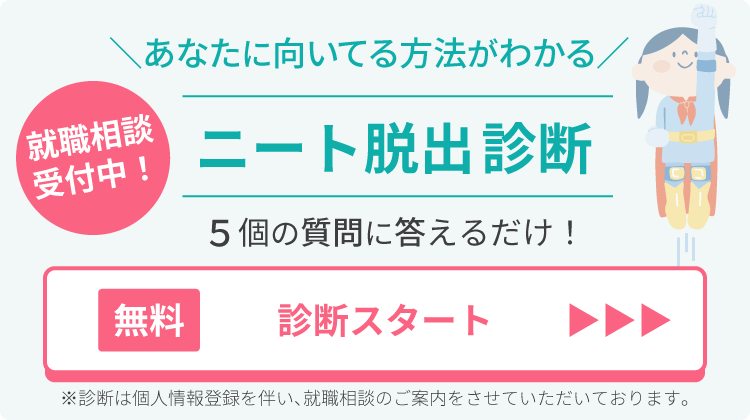

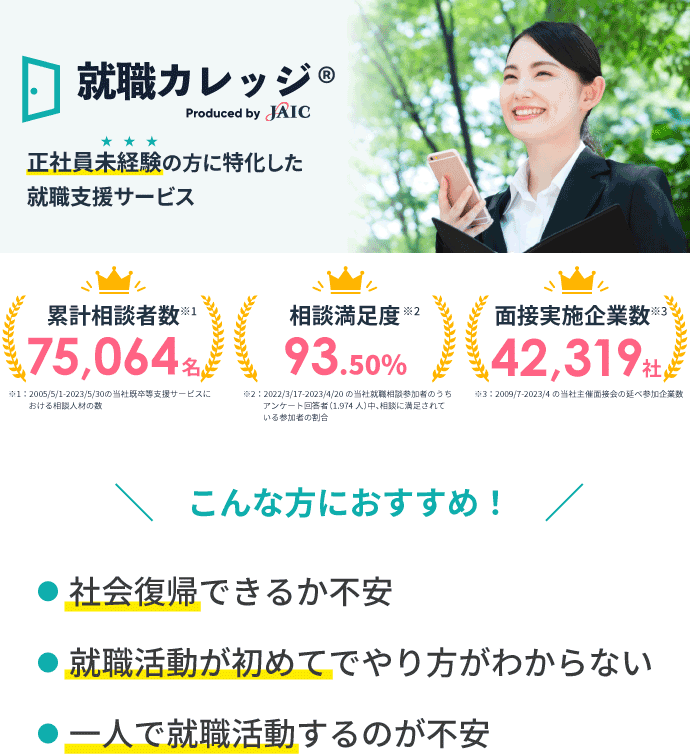

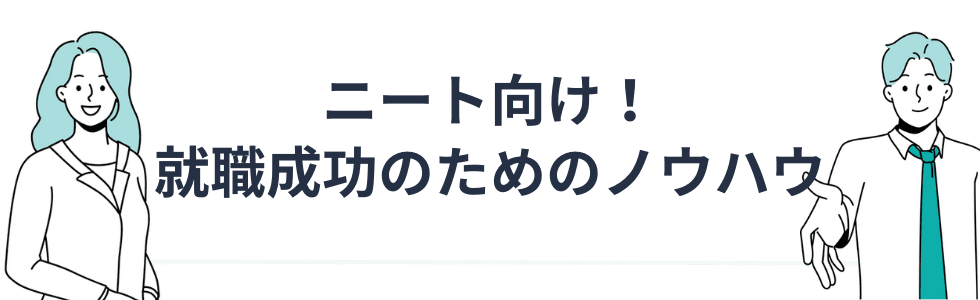
当社の就職に関するコンテンツの中から、ニートの就職活動に不安を感じている方向けに、就活で困りがちなことを解決するための記事をまとめました。
- ニートから就職するには?就活の方法と成功させるポイントを解説
- ニートの就活は何からすべき?就職活動のやり方の流れとコツを解説!
- 無職から正社員に就職するには?賢い就活方法とポイントを解説
- ニートから社会復帰するには何からすべき?怖い原因と対処法も解説
- ニートでも安心!ニートの面接必勝法は?
- ニートの履歴書の書き方!空白期間や志望動機のポイントを例文付きで解説
- ニートにおすすめの仕事25選【向いている仕事の特徴も解説】
- 高卒ニートは就職できる?職歴なしで正社員になる方法を解説!
- 大卒ニートの割合はどれくらい?末路や就職のコツを解説
- 30代ニートの就職は難しい?ニートの割合や社会復帰の方法を紹介
- ニートが就職するのにおすすめのサイトは?就職サイト7選を紹介