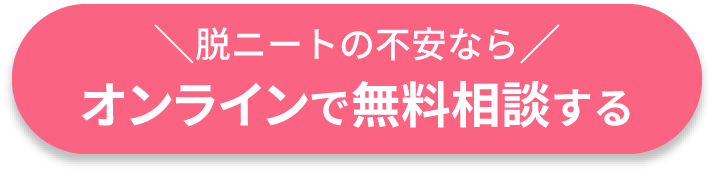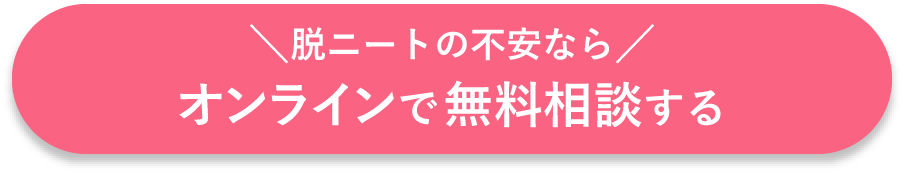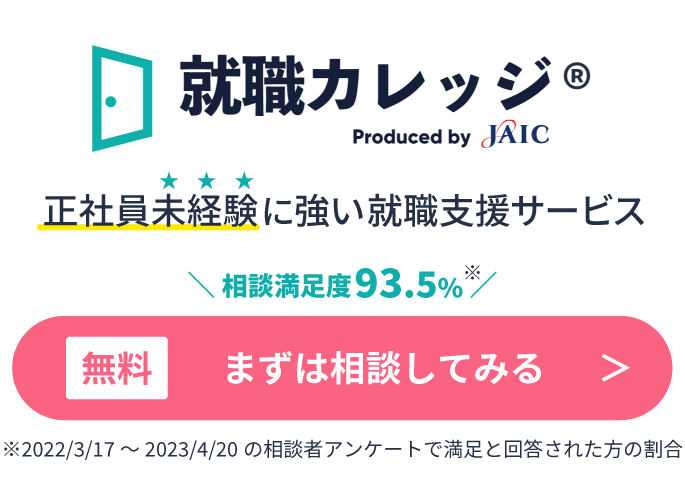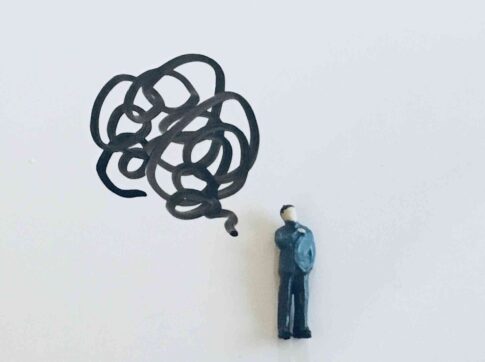ニートから公務員になることは不可能なのか、と疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?
実は、ニートから公務員になることは不可能ではありません。なぜならば、年齢制限はあるものの、公務員試験自体はだれでも平等に受けることができるからです。
こちらの記事では、ニートから公務員になれるのか?公務員より一般企業の方がいいのか?といった内容について解説しています。
最後までご覧いただくことで、ニートから公務員は目指せるのか、目指すべきなのかについて理解できるようになっています。
気になった方は是非、参考にしてみてください。
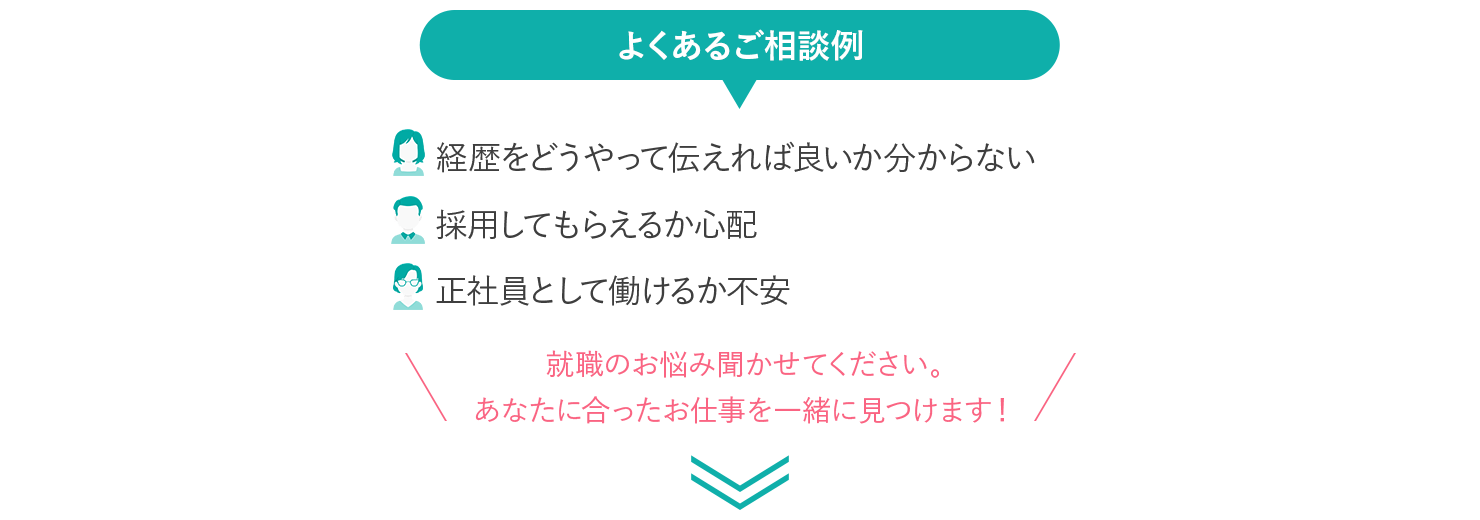



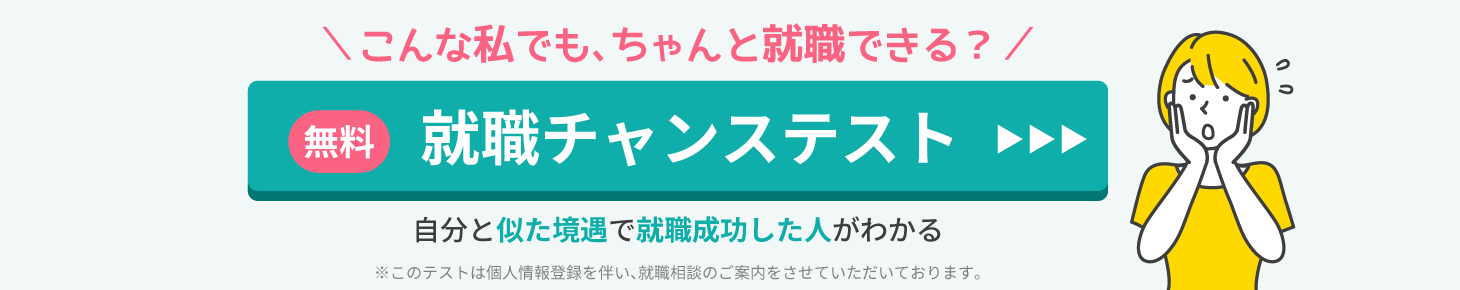
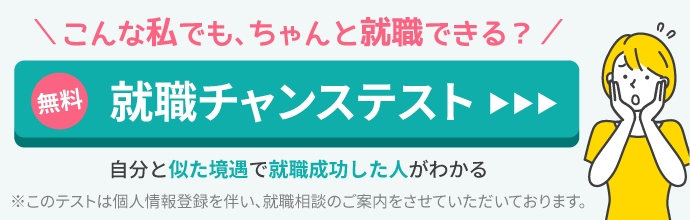
この記事の目次
ニートから公務員になることは不可能ではない
ニートから公務員になることは可能です。年齢制限はありますが、学歴が問われない公務員試験も多くあります。「高卒ニート」「大卒ニート」「大学中退ニート」から、公務員になるルートは不可能ではないことになります。
「地方公務員法 第13条第1項(平等取扱いの原則)」によれば、地方公務員は社会的身分や門地(家柄)などによって差別してはならないと法律で定められています。「ニートの経歴がある人は公務員にさせない」といったことはできず、あくまで、ニートから公務員になれるかどうかは公務員試験の結果次第と考えておいて良いでしょう。
ニートが受験できる2種類の公務員
ニートが受験できる公務員の種類は次の2つです。
- 国家公務員
- 地方公務員
一つずつ詳しくお伝えします。
1. 国家公務員
国家公務員は主に「総合職」「一般職」「専門職」の3種類があります。
総合職は政策の企画立案を担当する仕事で、キャリア官僚とも呼ばれます。
一般職は政策の実行やフォローアップなどがメインの仕事です。
総合職と一般職の違いに関しては、以下の表をご覧ください。
| 種類 | 区分 | 年齢制限(受験資格) | 仕事内容 |
|---|---|---|---|
| 総合職 | 院卒程度 | 30歳未満 | 政策の企画及び立案または調査及び研究に関する職務 |
| 総合職 | 大卒程度 | 21歳以上30歳未満 | |
| 一般職 | 大卒程度試験 | 21歳以上30歳未満 | 政策の実行やフォローアップなどに関する職務 |
参考:人事院『国家公務員試験ガイド 2025総合職』
参考:人事院『国家公務員試験ガイド2025一般職』
受験教養区分の「大卒程度」や「高卒程度」とは、あくまで試験の難易度を示すものであり、必ずしも大学や高校を卒業している必要はありません。そのため年齢条件を満たしていれば、学歴や職歴にかかわらず受験できるため、ニートの方も受験できます。
総合職は専門性が高く、将来キャリア官僚として活躍したい方に向いているでしょう。
一般職は実務中心で、文系・理系を問わず受験しやすい特徴があります。
また、専門職とは特定分野の専門知識を活かす職種です。主に次の職種があります。
- 皇宮護衛官
- 財務・国税専門官
- 労働基準監督官
- 入国警備官
- 航空保安官
- 海上保安官
- 刑務官
参考:人事院「試験情報 専門職試験」
試験内容は職種によって異なりますが、一般試験に加えて、専門分野の知識を問う試験が実施されます。
2. 地方公務員
地方公務員は、都道府県や市区町村などの地方自治体で働き、地域住民に密着した行政サービスを提供する仕事です。
地方公務員の主な職種と仕事内容に関しては、以下の表をご覧ください。
| 職種分類 | 主な仕事内容 |
|---|---|
| 行政 | 一般的な行政事務や企画立案 |
| 心理 | 心理相談や支援業務 |
| 福祉 | 福祉施設での相談や支援 |
| 技術 | 専門技術(機械や土木など)を活かした業務 |
| 公安 | 警察官など地域の安全や秩序を守る業務 |
地方公務員試験の年齢制限はおおむね35歳程度までとされることが多いですが、自治体や職種によって年齢制限が異なります。
各エリアにおける地方公務員の年齢制限の目安は、以下の表をご覧ください。
| エリア | 年齢制限 |
|---|---|
| 北海道・東北 | 29~39歳 |
| 関東・甲信越 | 29~35歳 |
| 中部・北陸 | 28~39歳 |
| 近畿 | 25~35歳 |
| 中国・四国 | 26~36歳 |
| 九州・沖縄 | 25~35歳 |
ニートの方が地方公務員を目指す場合、自分の居住地や希望職種に合わせて、幅広い自治体の採用情報を調べるのがおすすめです。また、年齢制限は毎年変更される可能性があるため、必ず最新の募集要項を確認しましょう。
ニートから公務員試験を受験する時の流れ
ニートから公務員試験を受験する時の流れをお伝えします。
- 国家公務員を受験する時の流れ
- 地方公務員を受験する時の流れ
詳しくお伝えします。
1. 国家公務員を受験する時の流れ
国家公務員総合職と一般職における受験の流れは次のとおりです。
【総合職試験流れ】
- インターネットによる受験申込
- 一次試験
- 一次試験合格発表
- 二次試験(筆記・政策課題討議・人物)
- 最終合格発表
- 官庁訪問
- 採用内定
- 採用
参考:人事院 国家公務員試験採用情報NAVI『総合職試験採用情報』
【一般職試験流れ】
- インターネットによる受験申込
- 一次試験
- 一次試験合格発表
- 官庁訪問
- 二次試験(人物)
- 最終合格発表
- 採用内定
- 内定
参考:人事院 国家公務員試験採用情報NAVI『一般職試験採用情報』
国家公務員試験の大きな特徴は「官庁訪問」があることです。
総合職では最終合格後に官庁訪問が始まりますが、一般職では一次試験合格後に官庁訪問と二次試験が並行して行われます。
また、総合職と一般職で試験内容が異なります。
総合職と一般職の試験内容に関しては、以下の表をご覧ください
| 試験区分 | 一次試験 | 二次試験 |
|---|---|---|
| 総合職試験 (大卒程度試験・教養区分以外) | ・基礎能力試験 ・専門試験 | ・専門試験 ・政策論文試験 ・人物試験 ・英語試験 |
| 一般職試験 (行政区分) | ・基礎能力試験 ・専門試験 ・一般論文試験 | ・人物試験 |
参考:人事院『国家公務員試験ガイド「総合職」』
参考:人事院『国家公務員試験ガイド「一般職」』
一般職試験の行政・教養区分以外の一次試験は、専門試験が増える傾向にあります。
専門職は、各職種によって試験日程や内容が異なるため、志望する官庁のホームページで最新情報を確認しましょう。
2. 地方公務員を受験する時の流れ
地方公務員を受験する時の流れは下記のとおりです。
- 出願
- 一次試験
- 一次試験合格発表
- 二次試験
- 最終合格発表
- 内定
一次試験は主に筆記試験が実施され、教養試験と専門試験が基本です。
自治体によっては、適性検査や論文試験が加わる場合もあるでしょう。
教養試験は社会科学や人文科学などの一般知識や、数的処理や文章理解といった一般知能などから出題される傾向があります。そして二次試験は主に人物評価がおこなわれ、個別面接や集団面接、グループディスカッションなどが実施されます。
試験のスケジュールは受験する自治体や応募する職種などにより大きく異なるため、募集要項は必ず確認しましょう。
ニートが公務員試験で合格するために行う2つのこと
ニートが公務員試験で合格するために行う2つのことは次のとおりです。
- 筆記試験を合格するために勉強する
- 面接で自信を持って回答できるよう対策する
詳しくお伝えします。
1. 筆記試験を合格するために勉強する
公務員試験に合格するには、筆記試験対策が必須です。
公務員を目指す方法は、独学か予備校に通うかの選択肢があります。
独学と予備校のメリット・デメリットに関しては、以下の表をご覧ください。
| 学習方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 独学のメリット | ・自分のペースで学習できる ・費用を抑えられる | ・効果的な学習方法を自分で見つける必要がある ・疑問点をすぐに解決しにくい |
| 予備校に通うメリット | ・専門講師の指導を受けられる ・計画的に学習できる ・同じ目標をもった人と一緒に勉強できる | ・費用がかかる ・スケジュールの制約があり ・通学の場合、通う時間や交通費がかかる |
予備校には、高額な費用がかかる場合もあります。
まずは独学で勉強してみて難しいと感じたら、自分に合った予備校を見つけるようにしましょう。
2. 面接で自信を持って回答できるよう対策する
面接でニート期間について質問された時は、正直に答えつつポジティブな側面を強調することが重要です。
公務員面接の回答例は、以下の表をご覧ください。
| 質問内容 | 回答例 |
|---|---|
| ニート期間に対する質問 | 「体調不良で一時的に就労が難しかったですが、その間に資格取得の勉強に励みました」 「家族の介護が必要な時期があり仕事を離れていましたが、その経験を通じて今は人の役に立つ仕事に就きたいと考えるようになりました」 |
| 公務員の志望理由に関する質問 | 「ニート期間中に行政の支援を受けたことで、公務員の仕事が多くの人を支えていると実感しました。今度は自分が支える側になりたいと思い、志望しました。」 「働いていない期間に自分を見つめ直し、安定した環境で人の役に立つ仕事がしたいと考えるようになりました。地域に貢献できる公務員の仕事に魅力を感じ、志望しました。」 |
面接前は想定質問に対する回答を準備し、自信を持って話せるよう練習を重ねておくと良いでしょう。
ニートが公務員になるメリット6選
ニートが公務員になるメリット6選は下記のとおりです。
- 働けなくなるリスクが低い
- 収入の見通しが立てやすい
- 福利厚生が充実している
- 社会的な信用を得られる
- 男女にかかわらず平等に評価してもらえる
- 国や地域に貢献できる喜びを感じられる
一つずつ詳しく解説します。
1. 働けなくなるリスクが低い
ニートが公務員になるメリットは、働けなくなるリスクが低いところです。
公務員は法律によって身分が保障されており、業績不振による解雇や倒産のリスクがほとんどありません。
頑張って入社した会社が倒産してしまうと、また一から転職活動をやり直さなければなりません。仕事を失ったというトラウマが残る可能性があるため、雇用が安定している公務員であれば安心して働けるでしょう。
また、体調や精神面の問題でニート状態になった方にとって、公務員の充実した休暇制度は大きな安心材料といえます。
2. 収入の見通しが立てやすい
収入の見通しが立てやすいことは、ニートの方が自立した生活を再構築する上で非常に重要です。経済面での不安が解消されることで精神的な安定も得られ、社会復帰への自信につながるでしょう。
公務員の給与体系は法律や条例、職務などに基づいて定められています。
初任給から退職金まで、おおよその収入の流れが事前に把握できるでしょう。
また、ボーナスも支給される傾向にあることから、頑張った分だけ自分にご褒美を与えられます。
住宅ローンや将来の貯蓄計画など、長期的な人生設計を立てる際の基盤となるはずです。
3. 福利厚生が充実している
公務員の福利厚生は民間企業よりも充実している傾向にあるため、ニートの方が生活を立て直せるきっかけとなるでしょう。住居手当や単身赴任手当があれば、家賃に対する不安も少なくなるはずです。
国家公務員と地方公務員の育児休業に関しては法律が設けられており、子育てしながら短時間勤務を行うことも可能です。
さらに、共済組合による低金利の貸付制度や、保養所などの福利施設も利用可能です。充実した福利厚生があれば、ニートの方も安心して働けるでしょう。
4. 社会的な信用を得られる
公務員になるとニートの時よりも社会的信用が高まり、社会的立場を確立できるメリットがあります。
社会的な信頼性の高い職業に就くことで得られるメリットは、主に次のとおりです。
- ローンやクレジットカードの審査が通りやすい
- 賃貸物件を借りやすくなる
ニートから公務員になると、世間からの信頼性だけでなく「社会とのつながり」を回復できる可能性が高くなるでしょう。
5. 男女にかかわらず平等に評価してもらえる
公務員は性別に関係なく、公平に評価されるシステムが確立されているのもニートから公務員になるメリットです。
民間企業では、性別によって昇進や給与に差が生じるケースもありますが、公務員制度では法律に基づいた平等な評価基準が適用されます。
試験による採用や昇進の仕組みは、学歴や職歴、性別ではなく現在の能力や実績を重視しているためです。
特に女性のニートの方は、結婚や出産後も働き続けられる環境が整っている点も、公務員になる大きな魅力の一つといえるでしょう。
6. 国や地域に貢献できる喜びを感じられる
ニートから公務員になることは、国や地域に直接貢献できる喜びを実感できるメリットがあります。
公務員は市民サービスの提供や地域の課題解決など、目に見える形で社会に貢献できるためです。
たとえば、窓口業務を通じて市民の悩みを解決したり、公共施設の管理を通じて地域の安全を守ったりする経験は「社会の役に立っている」という実感につながります。
ニートから公務員へと転身することで、自分の居場所と社会的役割を見つけられる可能性は広がるでしょう。
ニートが公務員になるデメリット6選
ニートが公務員になるデメリット6選は、下記のとおりです。
- 部署によって仕事の忙しさが異なる
- 同じ部署で働き続けるのが難しい
- 試験を乗り越えたからこそ仕事を辞めづらくなる
- 評価や業績を上げてもすぐ給料が上がらない
- 古い慣習やルールが残っている場合がある
- 副業が禁止されている
一つずつ詳しく解説します。
1. 部署によって仕事の忙しさが異なる
公務員の仕事量や忙しさは部署によって大きく異なるのがデメリットです。
社会での就労経験が少ないニートの方にとって、急な業務量の変化への対応は身体的・精神的な負担となり得るでしょう。
特に長期間働いていない状態から、突然忙しい部署に配属されると、仕事のペースやストレス管理に苦労する可能性があります。
また、忙しさの予測が難しい環境は、仕事に慣れるまでの時間が必要なニートの方にとって、就労継続の障壁になることがあります。
職場に適応できず、再びニート状態に戻ってしまうリスクを避けるためにも、配属先の特性を事前に理解しておくことが重要です。
2. 同じ部署で働き続けるのが難しい
公務員は定期的な人事異動があり、ニートから社会復帰した方にとって環境変化への適応が大きな負担となる場合もあるでしょう。
一般的に公務員の部署移動は2〜4年ごとに実施されます。異動が多い理由は、特定の個人や団体との癒着防止、ジョブローテーションなどの観点からです。
やっと仕事に慣れ、人間関係を構築できた頃に異動があると、また一から人間関係を作り直す必要があり、精神的な負担に感じる人もいるでしょう。
3. 試験を乗り越えたからこそ仕事を辞めづらくなる
公務員試験は難易度が高く、合格するまでに多くの時間と労力を費やすからこそ、仕事が合わないと感じても辞めづらくなるデメリットがあります。
ニートから抜け出すために懸命に勉強し、試験に合格した達成感は大きいものです。しかし、実際の業務が自分の想像と異なったり、職場に馴染めなかったりしても「せっかく合格したのだから」と不満を抱えたまま働き続けてしまうケースがあります。
また、公務員は「安定した良い職業」というイメージから周囲の期待も大きく、辞めることへの心理的ハードルが高くなるでしょう。
自分に合わない仕事を続けることで新たなストレスに直面する可能性があります。
自分の適性と向き合いながら職業を選択していくのが重要です。
4. 評価や業績を上げてもすぐ給料が上がらない
ニートが公務員になるデメリットは、評価や業績を上げてもすぐ給料が上がらないところです。公務員の給与体系は年功序列的な要素が強く、個人の成果や努力が収入に反映されにくい傾向があります。
ニート期間を経て働き始めた場合、早く経済的な基盤を築きたい思いが強い人もいるでしょう。しかし公務員は、どれだけ頑張っても、基本的に勤続年数に応じた昇給が中心です。民間企業のように業績に応じて大幅な昇給や特別ボーナスを期待しても難しいでしょう。
能力を発揮してもすぐに処遇に反映されないことで、モチベーションを維持しづらくなる可能性があります。経済的な遅れを取り戻したいニートの方にとって、努力と報酬の関係が見えづらい環境は、焦りや不満につながるかもしれません。
5. 古い慣習やルールが残っている場合がある
ニートが公務員になるデメリットは、古い慣習やルールが残ってる場合でも適切に対応しなければいけないところです。
公務員の職場には形式的な慣習や複雑な決裁手続きなど、古いルールが残っている場合があります。効率の悪さに疑問を感じても改善提案がしにくい環境のため、働きづらさを感じるケースもあるでしょう。
また、飲み会の参加といった暗黙のルールが多い職場は、ニートの方にとってストレスを感じる場合があります。
約3年で異動できるからと自分に言い聞かせて働くのも一つの手段ですが、無理が続く場合は周りに相談してみてもよいでしょう。
6. 副業が禁止されている
公務員の副業禁止はニートの方にとってデメリットの一つです。
公務員は国民・市民のために働くのが職務だからこそ、他の企業に勤めてお金を稼ぐのは望ましくないとされているためです。
近年、一般企業では副業OKな企業が増えています。会社からもらえる給料以外に、副業で得た事業所得で総収入を増やすことができたり、将来的な仕事の選択肢を増やせたりするメリットがあります。
良くも悪くも、会社だけに頼る働き方が必ずしも正解とはいえない時代になってきました。副業の内容によってはもちろんリスクもありますが、無理のない範囲からスタートして収入の柱をいくつか持っておくことは決して損にはならず、デメリットは少ないといえます。
一方で、公務員になると原則として副業ができません。実際に、読売新聞オンライン「消防士ユーチューバー、ゲーム実況で収入115万円…副業禁止で懲戒「認識甘かった」」によると、消防士がYouTuberとして副業収入を得ていたことが判明し、懲戒処分を受けたニュースもあります。
せっかく副業で稼げる力を持っていても、副業禁止の規程があるために能力を発揮できない事実が、公務員にはあるのです。
ニートから公務員を目指すべき人の特徴3選
「明確な目的があって公務員の仕事に就きたい(公務員としてやりたい仕事が決まっているなど)」いう人以外で、民間企業よりも公務員のほうが向いているニートの特徴を3つ、ご紹介します。以下を大きなメリットだと感じる方は、公務員試験を検討してみても良いでしょう。
特徴1:生活を安定させることが最重要だと思う人
前述の通り、公務員の安定感は抜群です。日本トップクラスの大手企業ですら、早期退職の勧奨や人員削減などのリスクはゼロにはなりませんが、公務員はその心配がありません。
たとえば、親や親戚から「公務員になれ」と言われた経験がある人もいるかもしれません。それだけ「安定している」ことはひとつの強みである、とも言い換えられます。収入や仕事が必ず保障されている職業は公務員くらいだからです。生活に不安を感じたくない人にとっては、公務員の満足度は高いでしょう。
特徴2:人の役に立てる仕事がしたいと思う人
人の役に立つ仕事に就きたいと考えるニートの方は、公務員に向いています。
公務員の仕事は、市民サービスの提供や人々の生活を支援する業務が中心です。
自分の行った仕事が役に立ったと喜んでもらえると、やりがいを感じることでしょう。
同じように孤立感を感じている方に対して、寄り添いながらサポートすることも可能です。
「人の役に立ちたい」とポジティブなエネルギーに変えられるニートの方にとって、公務員は理想的な職業といえます。
特徴3:定年まで公務員が良いと思っている人
転職もごく普通の選択になりつつある一方で、最後までひとつの職場で勤め上げたいという人も一定数います。そして、どちらの考え方も間違いではありません。
公務員としてずっと働けば、慣れた職場や仕事を長年続けることができます。環境の変化が苦手な人、慎重な人も公務員向きといえそうです。
公務員の場合、定年まで勤めればもらえる退職金も高額になります。定年までは公務員として勤め、定年退職してからまた第二の人生をスタートする、という人生設計もひとつのありかたではあります。
ニートで公務員を目指すべきではない人の特徴5選
ニートから公務員にならないほうが良い人、向いてない人の特徴を3つ、ご紹介します。民間企業ならではのメリットや良さもあり、人によっては公務員よりも民間企業のほうが生き生きと働けることもあります。迷っている方は、慎重に検討しましょう。
特徴1:将来的に独立/起業を考えている
いずれは起業したい、フリーランスで働きたいなどと考えている人の場合、民間企業で経験を積んだほうが圧倒的に近道です。なぜならば、公務員は「ビジネスをして稼ぐ」仕事ではないからです。仮に公務員経験のみでいきなり起業や独立をした場合、かなりのギャップがあるでしょう。
また、前述の通り、公務員は副業が禁止されています。民間企業であれば、副業で稼ぐ方法を増やしたり起業の準備をしたりもできます。一方で公務員は、公務員でいる限り、公務員以外の仕事を経験できないという縛りがネックになってしまいます。
特徴2:成功してお金を稼ぎたいと考えている人
公務員の場合、安定した収入は確約されているものの、もらえる額に上限はあります。公務員の仕事には「成果を上げたから収入が増える・儲かる」という基準はありません。
バイタリティがあってどんどん稼ぎたい人、積極的に上を目指したい人にとっては、公務員の環境は物足りない可能性が高いでしょう。危機感を持ったり、ぬるま湯のように感じたりするかもしれません。
特徴3:時間や場所に縛られたくない人
公務員の場合、決まった時間に勤務するのが基本だったり、出勤しないと仕事ができない職種だったりすることもあります。フレックスタイム制やリモートワークなども導入されてきてはいるものの、まだ民間企業ほどではないといえそうです。
民間企業の場合、フルリモート・フルフレックスの仕事もあります。また、起業したりフリーランスとして働いたりする場合も比較的自由に仕事ができます。公務員の場合、時間や場所といった働き方の自由度が低いところはどうしてもあるでしょう。
特徴4:公務員試験を頑張ろうと思えない人
公務員試験に合格する意欲のないニートの方は、公務員を目指すべきではないでしょう。
公務員試験に合格するには、数ヶ月から1年以上の計画的な勉強が必要です。
長期間のモチベーション維持が難しい方にとって、大きな挫折を招く可能性があります。
特に、1日を好きなように過ごしていたニートの方は、まず勉強を習慣化する必要があります。勉強が続かないと自己否定感が強まり、精神的な負担となることもあるでしょう。
試験勉強へのやる気が持続しない場合は、公務員にこだわる必要はありません。
資格不要の求人に応募したり、職業訓練を受けたりするなど、別のアプローチから就職を目指しましょう。
特徴5:早く就職しなければいけない事情がある人
経済的理由や家庭の事情で早急に就職する必要があるニートの方は、公務員を目指すべきではないでしょう。
公務員試験は年に数回しか実施されず、試験から採用までの期間が長いためです。
早期の就職が必要な場合は、アルバイトや派遣会社の登録など、より早く働ける方法を選びましょう。
まずは収入を確保し、余裕ができてから公務員を目指すことも可能です。
ニートから公務員になるよりも一般企業の方が将来性が高い2つの理由
ニートから公務員になるよりも一般企業の方が将来性が高い2つの理由は、下記のとおりです。
- 公務員だとビジネススキルがつかない場合がある
- 職歴なしの状態が続くと就活が難しくなる
詳しくお伝えします。
1. 公務員だとビジネススキルがつかない場合がある
公務員の場合、職種にもよりますが、公務員特有の仕事のやり方に慣れてしまい、それが当たり前だと思ってしまう可能性はあります。民間企業であれば普通に身に付くようなスキルがなかなか身に付きづらい、その機会が少ないとはいえそうです。
公務員は営利目的ではないため、いわゆる一般的なビジネススキルがなくてもやっていける業務も一定数あります。世の中との「仕事への認識」がズレたまま年齢を重ねて、そのことに気づかないままという人もいそうです。
そもそもの業務の目的が異なるため仕方がない部分はありますが、仕事の進め方や目標設定、評価、業務効率への意識などが、公務員と民間企業では大きく異なることはやはりあるでしょう。
2. 職歴なしの状態が続くと就活が難しくなる
ニートの方は職歴なしの状態が続くと、就活が難しくなる場合があります。
公務員試験の勉強に長期間費やすより、早めに一般企業への就職を検討した方が将来的なキャリア形成において有利な場合もあります。
実際にニートだった方の1年後の雇用形態を見ると、年齢を重ねれば重ねるほど正社員になる割合が下がっているとわかりました。
具体的な数値は以下の表をご覧ください。
| 年齢層 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 20-24歳 | 20.6% | 22.7% |
| 25-29歳 | 22% | 18.3% |
| 30-34歳 | 12.5% | 10.7% |
引用:独立行政法人労働政策研究・研修機構『若年者の就業状況・キャリア・ 職業能力開発の現状 ③』
ニートの状態から公務員試験に挑戦すると、職歴がない状態が続きます。
企業は働いていない期間が長い方に対して以下のような印象を持つ傾向にあるため、就職難易度が上がりやすくなるでしょう。
- 基本的な社会人スキルが身についていない
- コミュニケーション能力に不安がある
- 1日8時間働き続ける体力や精神力があるか不安になる
公務員試験を受ける場合は、覚悟を持って挑戦するのをおすすめします。
ニートから公務員以外の就職をする方法3選
これまでご紹介してきたように、ニートから公務員になることはできるものの、公務員の仕事が向いているとは限りません。ニートから民間企業への就職を考えた際におすすめの方法を3つ、ご紹介します。すべて無料で利用できるため、積極的に活用していきましょう。
方法1:ハローワークを利用する
ハローワークは公共職業安定所のことで、厚生労働省が管轄しています。仕事を探している人であれば誰でも、登録をすればすぐに利用できます。
求人検索や応募、就職相談、セミナーやイベントの参加などが可能です。若者向けに、ニートや既卒、フリーターなどの層を支援するサービスもあります。ニートの場合は職業訓練を受講し、就職に有利なスキルを身につけたり資格取得を目指したりするのもひとつの選択肢です。
また、ニートから就職を目指すなら「ハロートレーニング」を受講するのが効果的です。ハロートレーニングとは、ハローワークが実施する就職に必要な知識やスキルを学べる公的職業訓練制度です。
ハロートレーニングを受講する際は、基本的にテキスト代しかかかりません。
ニートの方にとってハロートレーニングを受けるメリットは、下記3つのとおりです。
- 就業に必要なスキルや技術を習得できる
- 業界や職種に特化したスキルを身につけられる
- 日中の訓練が多いため生活リズムが整いやすくなる
訓練期間は通常2〜6ヶ月で、事務やIT、介護など多様なコースがあります。
就職活動時にアピールできる経歴や資格を得られることは、ニートからの脱出に大きな助けとなるでしょう。
参考:厚生労働省『ハロートレーニング』
方法2:就職サイトの利用する
就職サイトは求人検索・応募ができるサイトで、民間企業が運営しています。
複数のサイトに登録して使い分けたり、情報収集をしたりすることもできます。
フリーター歓迎の求人や、未経験者や転職者の比率が高い企業などを検索して見つけることもできます。
スマートフォンなどでスキマ時間などに情報収集ができるため、就職・転職経験がある人、自分で調べたい人にはおすすめです。
方法3:就職エージェントを利用する
就職エージェントは就職のサポートを受けられる、民間企業が運営するサービスです。ハローワークや就職サイトとの違いは「細やかな支援が受けられる」「一人ひとりに合った就職を目指せる」点です。
プロのキャリアアドバイザーが在籍しているため、第三者から見た客観的なアドバイスをもらえたり、新たな強みを見出してもらえたり、自分では考えていなかった職種や企業を紹介してもらえたりします。
弊社ジェイックも就職エージェントとして、数多くのニートの方の正社員就職を実現してきました。本気で就職したい方向けに、短期間スクール型の就職支援講座や、書類選考免除の合同面接会などのサービスを提供しています。就職後も一年超に渡り、研修などを通じて定着を支援しています。
「ニートから公務員になるべきか、就職すべきか」といった悩みがある方、ニートから抜け出して社会人として活躍したいと考えている方は、ぜひご相談ください。
まとめ
ニートから公務員になることはできますし、公務員の仕事にも意義ややりがいはたくさんあります。ただし、公務員試験のための勉強期間が必要だったり、仮に合格できても公務員としての仕事に適性がない人もいたりするため、「安定しているから」という理由だけでおすすめできる選択ではありません。
ニートから公務員になるべきか考えている方は、そもそもの理由や動機を考え直してみましょう。
どうしても挑戦したければ目指すべきですし、本音としてそこまでではないのであれば、早めに民間企業への就職に動いたほうが有利です。
以下よりご登録いただければ、プロのキャリアアドバイザーがアドバイスさせていただきますので、お気軽にご登録ください。
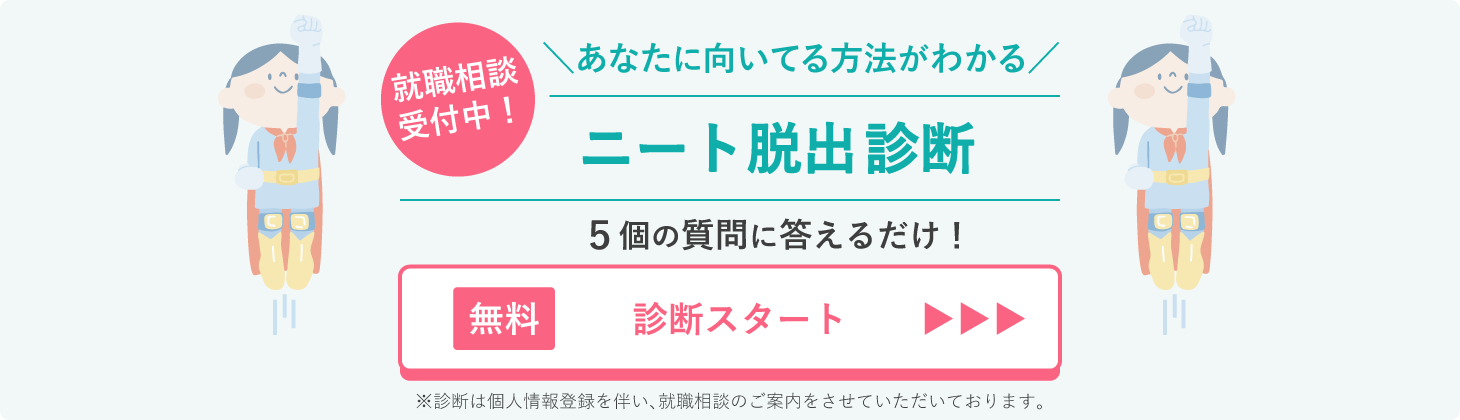
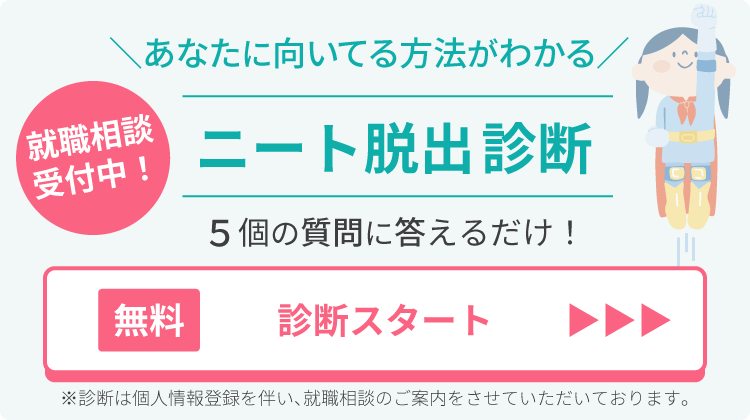

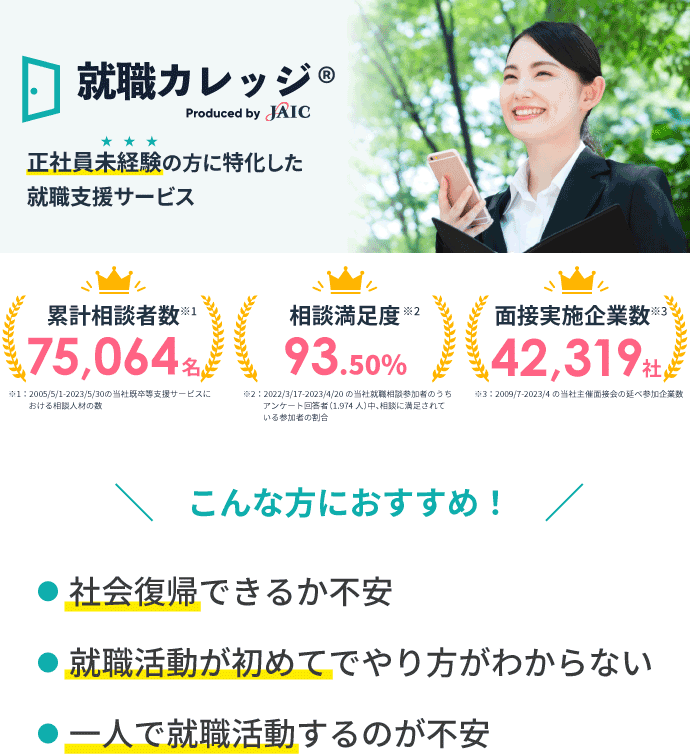

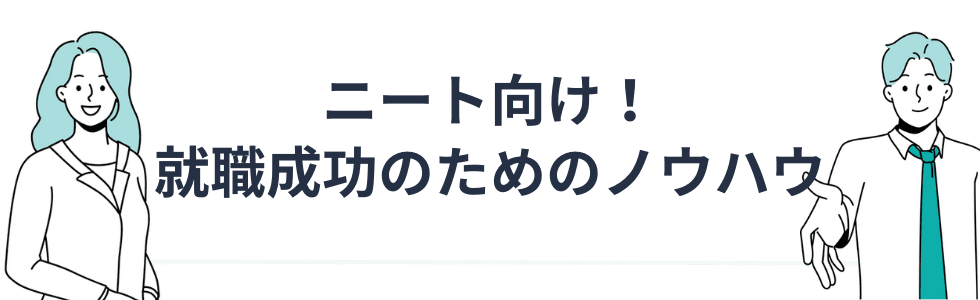
当社の就職に関するコンテンツの中から、ニートの就職活動に不安を感じている方向けに、就活で困りがちなことを解決するための記事をまとめました。
- ニートから就職するには?就活の方法と成功させるポイントを解説
- ニートの就活は何からすべき?就職活動のやり方の流れとコツを解説!
- 無職から正社員に就職するには?賢い就活方法とポイントを解説
- ニートから社会復帰するには何からすべき?怖い原因と対処法も解説
- ニートでも安心!ニートの面接必勝法は?
- ニートの履歴書の書き方!空白期間や志望動機のポイントを例文付きで解説
- ニートにおすすめの仕事25選【向いている仕事の特徴も解説】
- 高卒ニートは就職できる?職歴なしで正社員になる方法を解説!
- 大卒ニートの割合はどれくらい?末路や就職のコツを解説
- 30代ニートの就職は難しい?ニートの割合や社会復帰の方法を紹介
- ニートが就職するのにおすすめのサイトは?就職サイト7選を紹介