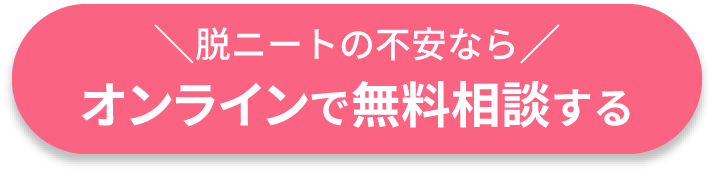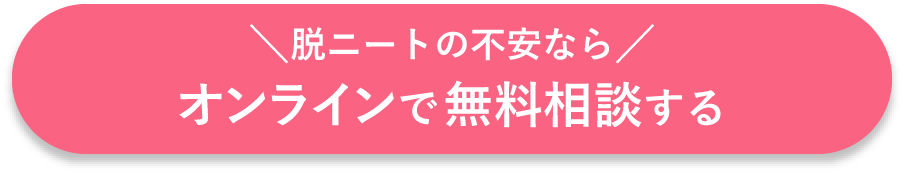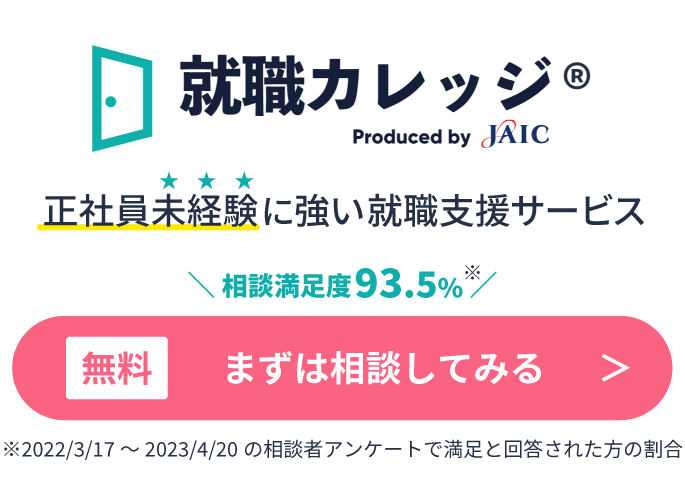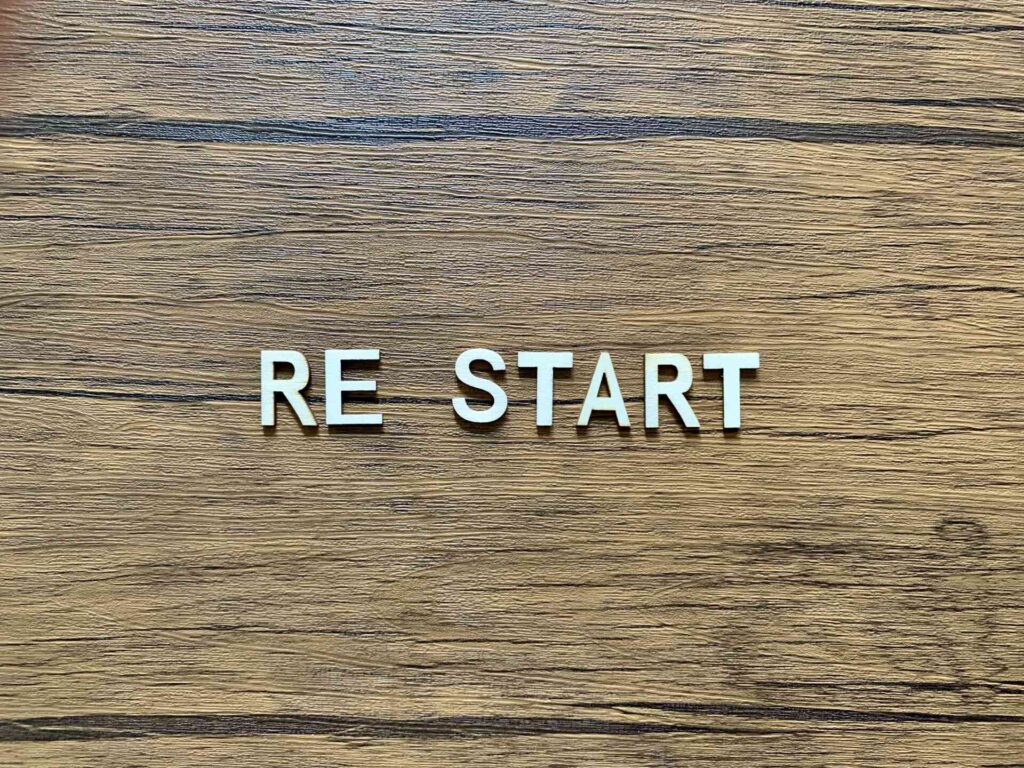
ニートから再就職するには、まずは自己分析やキャリアの棚卸をし、面接で聞かれやすい退職理由や空白期間の取り組みについて説明できるように準備しましょう。
この記事では、ニートから再就職は無理なのか、再就職する方法、おすすめの仕事について解説します。ニートからの再就職は何からすればいいのか不安な方はぜひ読んでみてください。
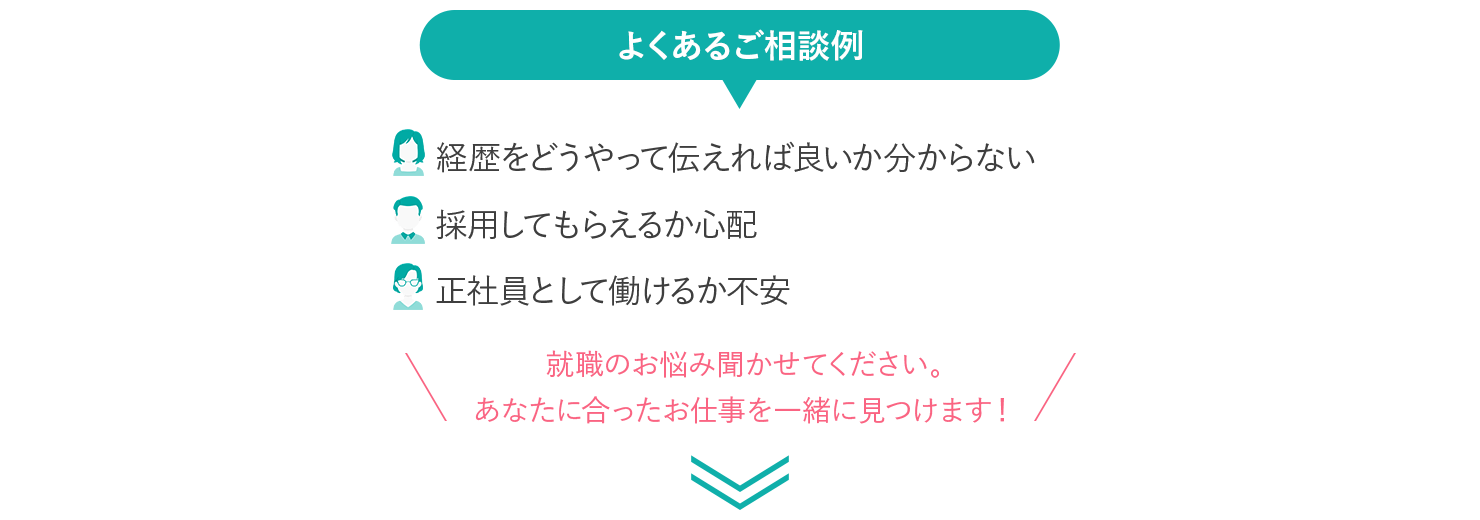



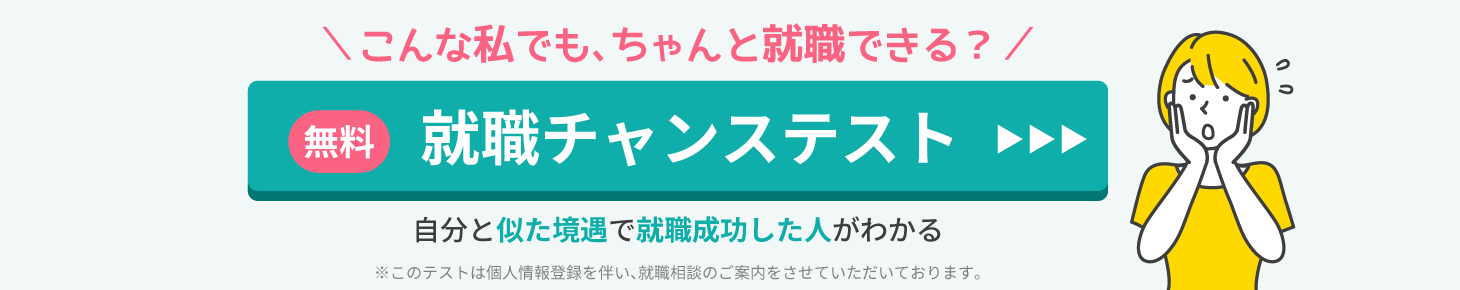
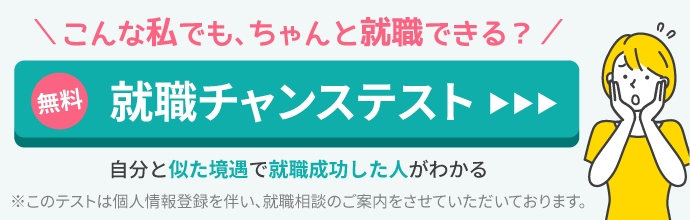
この記事の目次
ニートから再就職は無理?
ニートからの再就職は無理ではありません。なぜならニートのうち、約3割が再就職を果たしている可能性があるからです。
労働政策研究・研修機構の調査によると、「ニートの社会復帰率(1年前にニート状態にあった15歳~34歳男女が1年後に社会復帰している割合)」は39.4%です(※)。
ここでの社会復帰率にはアルバイトや派遣なども含まれますが、15歳~34歳の場合、およそ3人に1人以上の割合でニート状態から定職に就けていることが分かります。
別の調査によると、ニート状態にある若者のうち「連続で1ヶ月以上就労した経験」がある者は79.0%というデータもあります。
これらのデータを加味すると、概算で30.4%のニートが再就職を果たしているといえるため、ニートからの再就職は決して不可能ではないのです。
出典:独立行政法人労働政策研究・研修機構「若年者の就業状況・キャリア・職業能力開発の現状③-平成29年版「就業構造基本調査」より-」p.105
出典:厚生労働省「ニートの状態にある若年者の実態および支援策に関する調査研究報告書(概要)」
ポテンシャルに期待して採用されることもある
ニートは、いわゆる「ポテンシャル採用」のチャンスが比較的あります。ポテンシャル採用とは「応募者のスキルやキャリアではなく、潜在能力や将来性を期待した採用」のことです。そのため、ニートの方でも十分に採用の可能性があります。
ポテンシャル採用のメリットには、以下があります。
- 職歴なしでも働ける
- 入社してから仕事を覚えていけばよい
- 適性があれば活躍できる
ポテンシャル採用の最大のメリットは、就業経験や正社員経験がゼロでも採用の可能性があることです。また、入社時点ではスキルを求められていないため、実務をやりながら業務を覚えていくことができます。未経験からでも、その仕事に向いていれば能力を発揮でき、しっかりとしたキャリア形成も可能です。
諦めずにチャレンジしよう
ニートからでも、再就職はできます。道のりはスムーズにいかないことも多いかもしれませんが、「どうせ無理」とあきらめる必要はありません。実際に、ニートから再就職に成功している人もたくさんいます。
就職活動自体は大変なこともありますが、内定をもらえれば、その職場でコツコツと努力を重ねることで、社会人として通用する人材になっていくことは誰でも可能です。就職→入社というスタートラインにさえ立てれば良いわけですから、「ニートだから再就職できない」と極端に思い込まず、落ち着いて就職活動をしていきましょう。
ニートが再就職するコツ
ニートの方が再就職するには、まずは早めに就活を始めることが大切です。
就業経験を振り返る「キャリアの棚卸し」や、ニート期間中の気づきや反省を志望理由に盛り込むことも効果的でしょう。
ニートが再就職するには、以下のコツがあります。
- 早めに就活を始める
- キャリアの棚卸しをする
- 退職理由には反省を含める
- 空白期間をポジティブに伝える
- 職業訓練や資格取得でスキルを高める
- 人手不足の業界を検討する
ここでは、ニートの方が再就職を成功させるためのコツを6つ紹介します。「ブランクがある」という事実を乗り越え、再び働き始めたい方は参考にしてください。
1. 早めに就活を始める
ニートの方が再就職を目指す際は、できるだけ早めに就活を始めましょう。無職の期間が長引くほど、再就職が不利になってしまうからです。
離職からのブランク期間が再就職率に与える影響を調べた調査によると、ブランクがない人に比べ、たとえ3ヶ月の空白期間でも再就職率は15%ほど下がります。さらに、6ヶ月を超えると約20%も下がってしまうのです。
ブランクが長くなると再就職が不利になるのは、「働く意欲が低いのでは?」「職場に馴染めないのでは?」といった懸念を抱かれやすくなることが理由です。
求人情報をチェックしたり、職務経歴書の準備を進めたりするなど、ブランクをこれ以上伸ばさないためにも早めに行動を始めましょう。
出典:リクルートワークス研究所「なぜ転職したいのに転職しないのか―転職の“都市伝説”を検証する―」P.13
2. キャリアの棚卸しをする
再就職を目指す時は「キャリアの棚卸し」にも取り組みましょう。自分の強みを明確にすることで、面接などで自信を持ってアピールできるからです。
キャリアの棚卸しとは、仕事経験を振り返り、自分が身につけたことを整理する作業のことです。
たとえば「クレーム対応を通して問題解決力を身につけた」「プレゼン資料の作成を通して伝える力が身についた」といったことも立派な強みといえるでしょう。
自分の強みがはっきりすると何をアピールすれば良いか明確になり、自信を持って経験や強みを伝えられるので、キャリアの棚卸しにもぜひ取り組んでみてください。
3. 退職理由には反省を含める
前職の退職理由を説明する時は、反省の気持ちを素直に伝えることがポイントです。企業は過去の経歴よりも、「そこから何を学び、どう変わろうとしているか」を重視する傾向があるからです。
たとえば「上司との相性が悪かった」「残業が多すぎた」など、環境への不満をそのまま伝えたくなることもあるかもしれません。しかし他責的な印象を与えてしまうと、マイナス評価につながる恐れがあります。
そのため退職理由を伝える時は、次の3点を意識しましょう。
- 前職を退職した経緯
- 反省・学び
- 就職意欲
前職では人間関係に悩み、退職しました。
自分から働きかける姿勢が足りなかったと反省し、現在は職場のコミュニケーションに関する書籍を読むなど、改善に取り組んでいます。
今後は学びを活かし、職場で良い関係を築けるよう努めていきたいと考えています。
上記のポイントを参考に、面接官に前向きな印象を持ってもらえるように準備しておきましょう。
4. 空白期間をポジティブに伝える
面接で空白期間を聞かれた時は、「その期間に何をしていたか」「そこから何を学んだか」を前向きに伝えることが大切です。
「ニート状態にあった」という、一見するとネガティブに見える経歴も、自分の成長や意欲を伝える材料に変えられるからです。
空白期間を説明する際は、次の3点を意識しましょう。
- 再就職を目指す理由
- 空白期間に取り組んでいたこと
- 就職意欲
体調を崩し、しばらく社会と距離を置いていましたが、その間に自分と向き合い、再び働きたいという気持ちが強くなりました。
現在は就職後に備えて生活リズムを整えており、毎日決まった時間に起き、食事を取るように心がけています。
今後は自己管理力をさらに高め、御社に長く貢献できるように努力を重ねていきたいと考えております。
空白期間があっても、伝え方を工夫すれば前向きな印象につながります。
上記のポイントや例文を参考に、空白期間をポジティブに伝える準備もしておきましょう。
5. 職業訓練や資格取得でスキルを高める
再就職を有利に進めるには、職業訓練や資格取得でスキルを高めておくのも効果的です。具体的なスキルがあると、採用担当者に即戦力と評価されやすくなるからです。
職業訓練とは、ハローワークを通じて受けられる公的な職業教育のことで、雇用保険を受給している方は「公共職業訓練」を利用できます。ITスキルや介護、事務などの講座があり、ほとんど無料で受講可能です。
また「エンジニア経験を補うために、基本情報技術者の資格を取得しました」といったエピソードもアピールになるでしょう。
スキルに不安がある方は、職業訓練や資格取得にも目を向けてみてください。
6. 人手不足の業界を検討する
再就職を目指すニートの方は、人手不足が深刻な業界に目を向けてみるのもおすすめです。こうした業界は社員を確保するため、ブランクが長い人も歓迎するケースが多く、他の業界よりも採用のハードルが低めだからです。
特に、介護・福祉、建設、IT、小売り業界は人手不足が深刻です。これらの業界の中には、意欲や人柄を重視する会社も多く、ブランクが長い未経験者の採用に前向きな会社も少なくありません。
人手不足の業界は、裏を返せば「今後も需要が見込める業界」ともいえます。長く安定して働ける可能性もあるため、再就職先の候補として検討してみましょう。
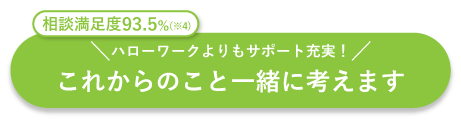
※4. 2022/3~2023/3の当社相談参加者へのアンケートで『満足』『どちらかといえば満足』を選んだ方の割合
ニートで再就職が失敗する人の特徴
ニートからの再就職がなかなかうまくいかない人によくある特徴と、対策についてご紹介します。
就職活動の方法がわかっていない
一度も就職したことがないニートの方に多い特徴です。たとえば、敬語をはじめとした基本のマナーが身についていない、面接に適した服装を理解できていない、正しい求人の探し方がわかっていない、などです。
就職活動の基本が理解できていないと、よくわからないまま自己流で進めることになってしまうため、がんばって行動しても落とされることが続く…ということがあり得ます。
インターネットの記事や動画、書籍などにも、就職活動に関する情報は掲載されています。さほど難しいものではありませんので、最低限、必要なことは自分で調べておきましょう。
履歴書や面接の対策ができていない
企業の求人に応募する際、書類選考免除の採用も一部あるものの、基本的には必ずといってよいほど書類選考と面接があります。いずれも、自分はどのような人材で、どんな強みがあるのかを適切にアピールする機会でもあります。
ニートの場合、履歴書の書き方が間違っていたり、面接官からの質問にうまく答えられなかったりして、適切にアピールできずなかなか選考を突破できないことがあります。こちらも、インターネットや書籍で調べる、面接の練習をしておくなど事前準備を万全にし、自信を持って臨める状態にしておくことが就職への近道です。
書類や面接対策を適切に進める際には、自己分析がきちんとできていることも大切です。
こちらの記事も、ぜひ参考にしてみてください。
1回の失敗で行動できなくなる
ニートから就職活動をした人のなかには、一社に応募して落とされただけであきらめたり、就職活動をしなくなってしまったりする人もいます。面接で厳しいことを言われたり否定されたりして自信をなくし「やっぱり再就職は無理なんだ」と、すぐに断念してしまうケースも見られます。
ニートに限らず、通常の就職・転職活動でも一社で内定が決まることは稀です。また、一般的な就職・転職と比較すれば厳しいことに変わりないので、選考で落とされても過度に気にせず、気持ちを切り替えてどんどん挑戦していくことが再就職への近道です。
ポテンシャル採用の求人を中心に応募する、弊社ジェイックの「就職カレッジ®」などの就職支援サービスを活用するといった工夫で、ニートの方の採用の可能性はアップします。
ニートで再就職を成功させる人の特徴
ニートからの再就職を成功させる人の特徴と、そのコツについてお伝えします。
失敗したら振り返りをする
就職活動で失敗した(例:面接でうまく話せなかった、受かると思っていた企業に落ちてしまった、など)ときは、具体的に振り返りを実施し、次につなげましょう。
振り返りをする際の注意点として、「感情的にならないこと」が挙げられます。「あのとき、なんでうまく答えられなかったんだろう…」など、細かいことを気にして落ち込みすぎると冷静さを欠き、できているところまで「全然だめだった」と否定することにもなりかねません。紙に書き出すなどして客観視し、できたことはきちんと認め、反省すべき点のみを改善することをおすすめします。
未経験歓迎などの求人を探す
未経験歓迎の求人をニートの方におすすめする理由は、以下の通りです。
- 採用のチャンスが多い
- 社内にも未経験者が多いため安心
- 選考に自信を持って挑むことができる
未経験歓迎の求人は、そうでない求人よりも多くの人にチャンスがあります。研修などが手厚い職場やマニュアル完備の職場を選べば、より安心して社会人生活をスタートできます。上司や先輩も未経験者や中途採用者が多い可能性も高く、職場にもなじみやすいでしょう。
また、経験を問わない求人ならば気後れせず応募できます。「スキル・実務経験がなくてもOK」となっているわけですから、書類・面接で堂々と自分の良さをアピールして問題ありません。
注意点としては、未経験歓迎であっても、まったく興味を持てない求人には応募しないほうが良いという点です。入社のハードルは低いかもしれませんが、やる気が出ず早期離職になっては意味がありません。少しでも「やってみたい」「自分に向いていそう」と思える求人をメインに応募しましょう。
また「未経験歓迎」と書かれていなくても、どうしてもチャレンジしたい求人には応募したほうが良いでしょう。「やっぱり応募すればよかった」という悔いがなくなりますし、採用の可能性はゼロとは限らないからです。
ニートに特化した就職支援サービスを利用する
ニートの方に特化した就職支援サービスの利用は、スムーズに再就職をする方法としておすすめです。おすすめする主な理由は、以下の通りです。
- ニートの就職実績・ノウハウが豊富にある
- 職歴なしでもOKの求人を紹介してもらえる
- 就職活動に集中できる
まず、ニートに特化しているということは、ニートの方を正社員就職へと導くための方法を熟知したスタッフからのアドバイス・指導を受けられるということです。自己流で就職活動をする場合と比べて、はるかに効率的といえます。
求人を出している企業も、応募者がニートなど社会人経験が少ない方であることを理解しています。「なんでうちに応募したの?」などと聞かれることもなく、自信を持って応募できます。また、企業への応募や面接の日程調整、入社時の交渉などはスタッフが担当するため、就職活動のみに専念できる点もメリットです。
ニート向けの就職支援サービスを利用する際には、サービスの内容をよく確認することをおすすめします。就職実績や受けられるサポートなどもチェックしたうえで、自分に合いそうなエージェントを選びましょう。
ニートから再就職する際におすすめの仕事
ニートからの再就職におすすめの仕事を3つ、仕事内容・向いている人の特徴・注意点の観点からご紹介します。
営業職
顧客に商品・サービスを提案する仕事で、既存顧客メインのルート営業、自身でお客さんを見つけていく新規開拓営業の2種類があります。
営業職に向いてる人は、人と接することが好き・得意な人、臨機応変な対応ができる人です。営業職だからといって必ずしもおしゃべりが上手である必要はなく、物静かでも受注に成功している営業職の人もいます。ただし、「人」が苦手な人には不向きであることは間違いありません。
注意点としては、ノルマが厳しすぎる職場もなかにはある点です。休日も仕事をしないと終わらなかったり、遅くまでアポイントを取ることが恒常化しているなどの状況から定着率が悪い職場もあるため、労働環境は確認しておきましょう。
介護職
日常生活のサポートが必要な高齢者を実際にケアしたり、適切な支援につなげたりする仕事です。職種の例としては、介護スタッフ、ケアマネージャー、生活相談員などがあります。
介護職に向いてる人は、必要とされることに意義を感じる人、誰かの役に立ちたい気持ちが強い人です。介護職に就く人のなかには「天職」と考え、忙しいながらも長年働き続けている人も少なくありません。
注意点としては、ある程度の忍耐力が求められる仕事である点です。特に現場で働く介護スタッフはやりがいがある一方でストレスも大きく、未経験からでも始められる反面、誰にでも務まる仕事ではないため、適性を見極める必要はあるでしょう。
事務職
社内にまつわる業務を担当し、来客対応や書類作成、備品管理、社内行事の運営、従業員の管理・連絡など、幅広い仕事を担当します。企業によっては、経理や人事などの役割も兼ねているケースがあります。
事務職に向いている人は、コツコツとした作業が得意な人、人をサポートすることが好きな人です。デスクワークや静かな環境で働きたいという人にも向いています。
注意点としては、いわゆる「飽きっぽい人」には向かない点です。基本的にはオフィスでの勤務が中心で、社外の人と関わる機会も比較的少ないため、変化や新たな刺激を求める気質の人にはあまり適性がないでしょう。
ニートが再就職したら必要な手続き
再就職が決まったニートの方は、いくつかの手続きが必要になる場合があります。
たとえば、ハローワークでの失業保険の受給停止手続きや、国民健康保険から会社の健康保険への切り替えなどが挙げられます。
スムーズに社会復帰するためにも、次に紹介する内容を参考に、再就職後の手続きについてはしっかりと確認しておきましょう。
ハローワークでの手続き
再就職先が決まったニートの方は、必要に応じてハローワークで次の手続きを行いましょう。
- 失業保険の受給停止
- 再就職手当の申請
- 就業促進定着手当の申請
再就職手当や就業促進定着手当は、ニート期間の生活費や就職後の収入を補う制度です。受け取り忘れを防ぐためにも、自分が対象かどうかハローワークで確認しておきましょう。
では、それぞれの手続きについて解説します。
失業保険の受給停止
失業保険(失業手当)を受給している場合、再就職が決まったら速やかに受給停止の手続きを行いましょう。
失業保険は「働いていない期間」を支援する制度のため、就職が決まった(失業状態ではなくなった)時点で受給を止める必要があるからです。
手続きの流れは、以下の通りです。
- 就業開始日を確認する
- ハローワークに連絡し、受給停止手続きを依頼する(再就職先の会社名や就業開始日などを伝える)
- 必要書類をハローワークに提出する(採用証明書、雇用保険受給資格者証、失業認定申告書)
手続きをせずに給付を受け続けると、不正受給とみなされる恐れがあります。そのため再就職が決まったら、忘れずにハローワークで停止手続きを済ませましょう。
再就職手当の申請
再就職手当とは、失業手当の受給資格を満たしている人が、就職先を早く見つけた場合に受け取れる手当です。
申請の流れは、以下の通りです。
- 再就職先に「採用証明書」の記載を依頼する
- 必要書類をハローワークに提出する(採用証明書、雇用保険受給資格者証、失業認定申告書)
- ハローワークから「再就職手当支給申請書」を受け取り、再就職先に記入を依頼する
- 「再就職手当支給申請書」と「雇用保険受給資格証」をハローワークに提出する
再就職手当を受給するには、「失業手当の支給残日数が3分の1以上残っている」など、複数の条件を満たす必要があります。
詳しい受給条件はこちらのリーフレットで確認できるので、申請前に確認しておきましょう。
就業促進定着手当の申請
就業促進定着手当とは、再就職先の賃金が前職より低い場合に支給される手当です。
基本的には、再就職手当を受給した人が再就職先で6か月間働いた場合に対象となり、前職との賃金差額の一部が支給されます。なお、再就職手当を受けていない人は対象外のため注意が必要です。
申請の流れは、以下の通りです。
- ハローワークから届く「支給証明書」を記入する
- 再就職後、6か月が経過した翌日から2か月以内の間にハローワークに必要書類を提出する(支給証明書、雇用保険受給資格証など)
詳しい支給条件や金額は、厚生労働省のリーフレットで確認できます。
再就職後の収入減をカバーできる制度のため、条件に該当するニートの方は忘れずに申請しましょう。
国民健康保険の手続き
国民健康保険に加入していた方で、再就職後に会社の健康保険に加入する場合は、国民健康保険の脱退手続きを行う必要があります。
国民健康保険とは、会社に勤めていない人(自営業者やニートなど)が加入する公的な医療保険です。
脱退の一般的な流れは、次の通りです。
- 再就職先から健康保険証を受け取る(または資格取得証明書を準備する)
- 必要書類を用意する(国民健康保険証、本人確認書類など)
- 住んでいる市区町村の役所で申請をする(郵送やオンライン申請が可能な場合もあり)
脱退の届け出をしないと、保険料の二重払いになる恐れもあります。
手続きは自分で行う必要があるので、失業保険の受給停止などと共に、国民健康保険の脱退手続きも忘れずに行いましょう。
ニートから再就職をする際におすすめの就職方法
最後に、ニートからの再就職を目指す方におすすめの、弊社ジェイックの「就職カレッジ®」の特徴について、ご紹介いたします。
未経験の人に特化した就職サービス
就職カレッジ®は、社会人経験がない・少ない方に特化した就職支援サービスです。一度も就職したことがない方、はじめて就職活動をする方、前職を短期間で辞めたという方も、安心してご利用いただけます。
同じような境遇の方も数多く参加していますので「ニートなんだけど大丈夫かな…」と気にする必要はありません。プロの専任スタッフが、しっかりとサポートします。
面接や履歴書対策で内定率アップ
就職カレッジ®では、無料の就職講座を実施しています。自己分析、ビジネスマナー、企業研究などのほか、書類・面接対策も実施しています。就職活動の基本を短期集中で学ぶことができるため、効率的です。
就職講座の受講後は、書類選考免除の合同面接会に参加可能です。一度に複数の企業担当者と会うことができ、自身をアピールするチャンスです。場合によっては短期間で内定獲得も可能ですので、なるべく早く就職先を決めたい方にもおすすめです。
就職後の定着もサポート
通常の就職支援サービスでは、「就職するまで」のサポートがメインとなっています。一方で弊社ジェイックでは、「就職後、定着するまで」のサポートを実施している数少ないエージェントです。入社後に悩みや不安が出てきた際は、専任スタッフに相談可能です。また、研修などを通じて長期的な活躍を支援しています。
ニートからの再就職を最後まで手厚くバックアップしますので、ぜひ参加をご検討ください。
まとめ
ニートの再就職は簡単とはいえませんが、可能です。ニート期間があっても自分に合った企業を見つけ、社会人として自分らしく働いていくことはできます。ただし、行動しなければ何も始まりません。就職活動において多少大変なことがあってもめげず、ニートである現状を気にしすぎずに、これからのことを前向きに考えて行動していきましょう。
「ニートからの再就職を目指したいが、自信がない」「どのように就活を進めればよいかわからない」という方は、お気軽に弊社ジェイックへご相談ください。
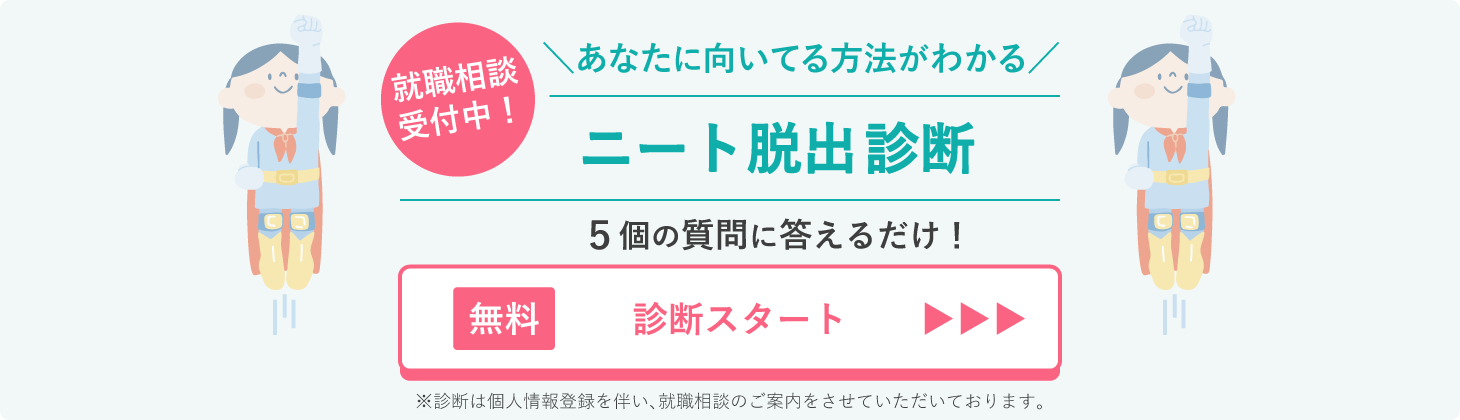
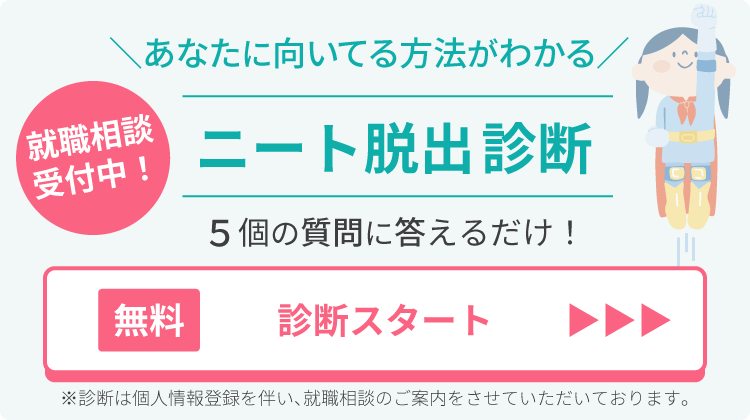

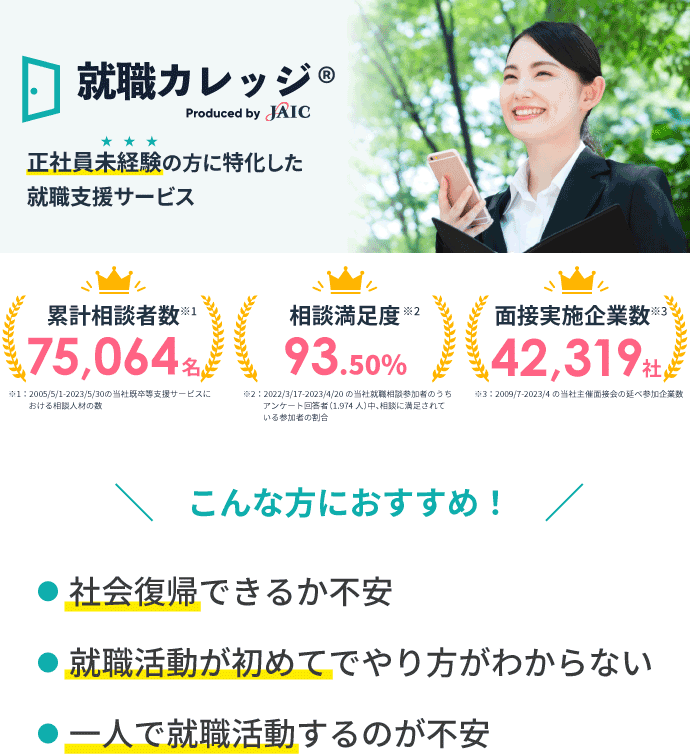

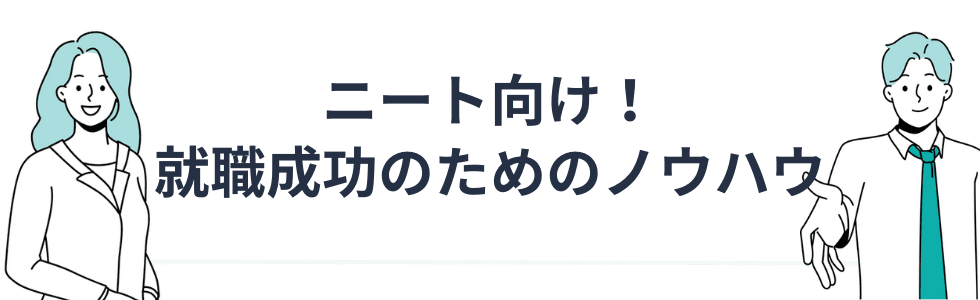
当社の就職に関するコンテンツの中から、ニートの就職活動に不安を感じている方向けに、就活で困りがちなことを解決するための記事をまとめました。
- ニートから就職するには?就活の方法と成功させるポイントを解説
- ニートの就活は何からすべき?就職活動のやり方の流れとコツを解説!
- 無職から正社員に就職するには?賢い就活方法とポイントを解説
- ニートから社会復帰するには何からすべき?怖い原因と対処法も解説
- ニートでも安心!ニートの面接必勝法は?
- ニートの履歴書の書き方!空白期間や志望動機のポイントを例文付きで解説
- ニートにおすすめの仕事25選【向いている仕事の特徴も解説】
- 高卒ニートは就職できる?職歴なしで正社員になる方法を解説!
- 大卒ニートの割合はどれくらい?末路や就職のコツを解説
- 30代ニートの就職は難しい?ニートの割合や社会復帰の方法を紹介
- ニートが就職するのにおすすめのサイトは?就職サイト7選を紹介