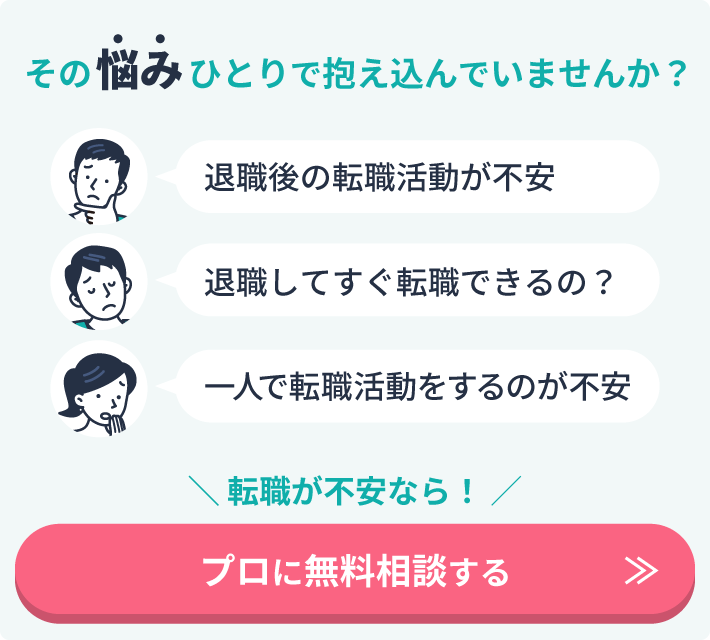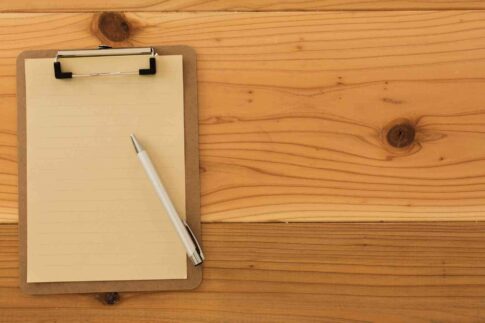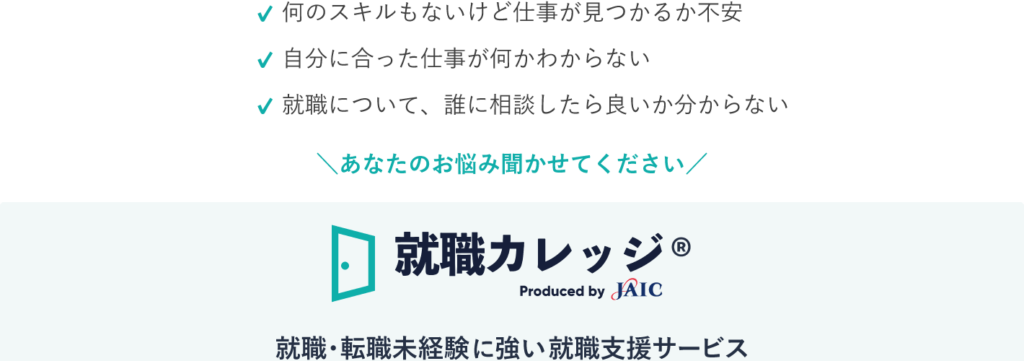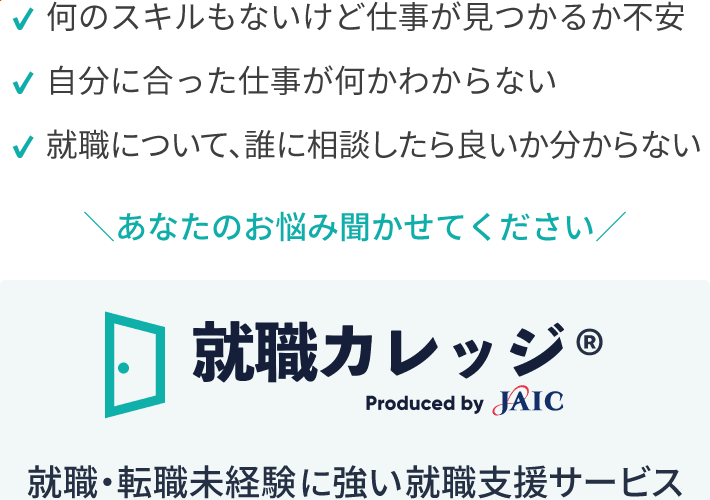仕事を辞めたらすることは何かについて、仕事を辞める前に知っておきたいという人も多いのではないでしょうか?退職自体は会社に申し出ればすぐにできるものの、実は退職後にやるべきことはたくさんあります。
そこでこの記事では、仕事を辞めたらすることを7つに分けてご紹介します。中には対応が漏れてしまうことで金銭的に損する可能性もありますので、近々仕事を辞めたいと思っている人は特に参考にしてみてください。
この記事の目次
仕事を辞めたらすること5選
仕事を辞めるには、退職の申し出や退職書類の提出、引き継ぎから挨拶と手順的な意味で簡単なステップしか存在しませんが、いざ仕事を辞めた後は以下のようなことをしなければなりません。
- 健康保険の手続き
- 年金の変更手続き
- 失業保険の手続き
- 住民税の支払い
- 確定申告
主に社会保険に関係する手続きと、自分の今後の生活に関わるアクションの2種類に対して向き合っていく必要がありますが、基本的に自分で調べて行動することが求められます。
ここからは実際に、仕事を辞めたらすることをそれぞれ詳しく解説していきます。対応期限が決められているものもありますので、仕事を辞めた後に焦ってしまうことを避けるためにもしっかり覚えておきましょう。

仕事を辞めたらすること①健康保険の手続き
まずやるべきことは、健康保険の手続きです。
健康保険とは、病気や怪我、出産などの医療サービスを受けることに備える公的な医療保険制度のことで、日本国民である限り何らかの形で加入が必須となっています。
基本的に会社に就職すれば健康保険証が発行されますが、発行された健康保険証は仕事を辞めたら返却する必要があります。
仕事を辞めた後、次の職場に転職するまで1日も間が空かない場合は健康保険の手続きは不要ですが、もし離職期間が1日でも生じる場合は、以下の選択肢から選んで手続きを進めていく必要があります。
- 選択肢1.任意継続で健康保険に加入し続ける
- 選択肢2.国民健康保険に切り替える
- 選択肢3.家族の扶養に入る
いずれも手続きする先やメリットとデメリットが異なるものの、「医療サービスを受ける時は基本的に自己負担は3割」という健康保険そのものの仕様は変わりません。そのため、以下の解説を踏まえて、自分で自由に選択しましょう。
選択肢1.任意継続で健康保険に加入し続ける
| 手続きの期間 | 退職の翌日から20日以内 |
| 手続きする場所 | 前職で加入していた健康保険組合か、住んでいる地域の社会保険事務所 |
| 必要なもの | ・健康保険任意継続被保険者資格首都申請書 ・1ヶ月分の保険料 |
| 保険料 | 今まで給料天引きで負担していた分の倍額程度が目安 |
| メリット | ・前職と同じ健康保険を利用できる ・要件をクリアすれば家族を扶養に入れられる |
| デメリット | ・最長で2年までしか利用できない ・支払う保険料が倍近くになる |
任意継続被保険者制度というものを使えば、退職した会社の健康保険を最長2年まで継続して利用することができます。原則、今までと全く変わらない健康保険の内容となりますので、病院によくかかるような人であればこの選択肢が良いかもしれません。
ただ、支払う保険料が倍近くになるというデメリットは抑えておいてください。これは、就業中は勤務先の会社が自分の健康保険料を半分負担する義務があったものの、仕事を辞めることで、会社が自分の健康保険料を負担する義務がなくなるからです。
なお、手続きの期間である「退職の翌日から20日以内」を過ぎてしまうと、原則申し出は不可になる点に注意してください。
選択肢2.国民健康保険に切り替える
| 手続きの期間 | 退職の翌日から14日以内 |
| 手続きする場所 | 住んでいる地域の市区町村役所の国民健康保険担当窓口 |
| 必要なもの | 健康保険の資格が無くなったことが分かる以下のいずれかの証明書 ・健康保険被保険者喪失証明書 ・退職証明書 ・離職票 各市町村で定められている届出書 印鑑 |
| 保険料 | 市区町村によって異なる |
| メリット | ・自宅から近い役所で手続きや相談ができる ・人によっては選択肢1の任意継続より保険料が安くなる |
| デメリット | ・傷病手当や出産手当が無かったり少ない場合がある ・家族を扶養に入れられない |
勤めている時は会社が保険者となっていましたが、保険者が市区町村になるのが国民健康保険です。扶養に入っていない自営業者やフリーランスなどは、通常国民健康保険に加入しています。
国民健康保険の保険料の算定方法は市区町村によって異なりますので、この方法で手続きをしたいのであれば、まずは最寄りの市区町村役所に足を運ぶのがおすすめです。直接窓口で相談できるのは嬉しいポイントと言えるでしょう。
ただし、家族を扶養に入れられないため、例えば今まで家族のうち一人だけが働き、それ以外の家族が扶養に入っていた場合は、家族全員が国民健康保険に加入する必要が出てくる点には注意が必要です。
なお、手続きが遅れたとしても後から手続きすること自体は可能です。ただし、退職日の翌日以降から加入までの期間の分の保険料は遡って支払う必要がある点には注意してください。
選択肢3.家族の扶養に入る
| 手続きの期間 | 退職が決まったと同時に、健康保険に加入している家族に相談するのが望ましい |
| 手続きする場所 | 家族が加入している健康保険組合 |
| 必要なもの | 健康保険組合によって異なる |
| 保険料 | ゼロ |
| メリット | ・保険料の負担が全くなくなる ・所得税を負担する必要がなくなる |
| デメリット | ・給料を一定以下の水準に抑えなければならない ・年金として将来もらえる金額が減る |
パートナーが会社の健康保険に加入(≒サラリーマンとして働いている状態)していて、自分の年間の収入が130万円未満の見込みの場合は、パートナーの扶養に入るという選択肢も取れます。
この場合、自分の健康保険料の負担は一切なくなりますので、金銭的に最もメリットのある選択肢と言えるでしょう。もちろん、扶養に入ったからといってパートナーの支払う健康保険料が上がることはありません。
ただ、パートナーの扶養に入ることで年収に制限が出ます。月10万円以上稼いでしまうと扶養から外れるリスクが出てきますので、一年内に再就職する予定がある人は国民健康保険に加入する方が望ましいと考えられます。

仕事を辞めたらすること②年金の変更手続き
成人している全ての人には、年金制度に加入し続ける義務があります。
収入や生活状況によって支払いの免除や減額などはできるものの、仕事を辞めて離職期間が1日以上あるなら必ず変更手続きが必要です。
ここでは具体的な手続きを3つご紹介します。
国民年金の種類と変更期限
まず始めに、国民年金保険には以下の3種類があることを理解しましょう。
- 第1号被保険者:農業者、自営業者、学生、無職の人など
- 第2号被保険者:会社員・公務員など
- 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されていて、年収130万円未満の20歳以上60歳未満の配偶者
会社員として働いていた人がすぐに転職しない、もしくは個人事業主やフリーランスになるという場合は、第2号被保険者から第1号被保険者に切り替える手続きが必要になります。
手続きをする場所としては最寄りの市区町村役所の国民年金窓口で、必要書類を提出することで完了します。
また、手続きをする期限としては、退職日の翌日から14日以内となっていますので、健康保険の切り替え手続きと同時に行うのが望ましいでしょう。
資格喪失証明書を手にいれる必要がある
年金の変更手続きをするためには、資格喪失証明書の提出が役所から求められることがあります。この証明書は基本的に会社を辞める際に会社からもらえるため、退職時に受け取った書類は必ず保管しておくようにしてください。
ただし、資格証明書の発行は会社の義務ではないため、退職時にもらえていないこともあります。その場合は、最寄りの年金事務所で「健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失等の確認請求書」を提出する必要があります。
窓口だけでなく郵送でも手続きできますので、気になる人は日本年金機構のWebサイトをチェックしてみてください。
すぐに転職する場合は手続き不要
健康保険と同じく、年金の変個手続きについても退職日と新しい職場の入社日が連続している場合は手続きが不要になります。
ただ、1日でもどの会社にも属していないような離職期間がある場合は、それぞれの変更手続きが必要になりますので注意しましょう。

仕事を辞めたらすること③失業保険の手続き
仕事を辞めると、当然ですが収入がなくなります。転職活動は短ければ1ヶ月で終わることもできますが、中には数ヶ月かかってしまうケースの人もいますので、無職の期間の生活が家計的に厳しくなる人もいるでしょう。
そういった人のために用意されている国の制度として、失業保険があります。ここからは、仕事を辞めたらすることの一つである失業保険の手続きについて解説します。
失業保険とは仕事を辞めたらもらえるお金のこと
失業保険とは、仕事を辞めてから再就職までの期間において、収入面で安定した生活を送りながら就職活動を進めることを目的として国が用意している支援制度のことを言います。
「保険」という単語が入っていますが、特に失業保険に対する保険料を直接支払っているわけではありませんので、条件を満たした人であればどのような人でも受給することができます。
勤務期間によっては失業保険をもらえない
失業保険は会社を辞めた人を対象にしている制度ですが、退職理由によって受給対象となる勤務期間が異なってきます。
まず、失業保険について理解するためにも、失業保険の受給資格対象者として区分されている3つの退職の種類について理解しておきましょう。
- 自己都合退職(一般):いわゆる一身上の都合による退職のこと。職場に不満を持った、転職をしたい、独立しようとしているなど、会社と自分との間のウマが合わずに退職するケース
- 自己都合退職(特定理由):自分の意思と反する正当な理由がある退職のこと。家族の介護が必要になった、希望退職制度で退職した、転勤などを命じられたが別居生活を続けることが困難と判断したなどの理由がある
- 会社都合退職:会社の倒産や、解雇命令を受けたことによる退職
それぞれ自分の意思だけで退職したかそうでないかがポイントとなり、失業保険をもらうための勤務期間も変わってきます。
- 自己都合退職(一般)の場合:離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上あること
- それ以外の場合:離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算6ヶ月以上あること
つまり、一身上の都合による退職の場合であれば、直近2年間で1年以上働いていなければ失業保険を受給できないということです。
そのため、入社と退職を繰り返して失業保険だけをもらい続けるということはできませんので、あらかじめ認識しておいてください。
年齢によってもらえる総額が変わる
失業保険はそれまでの勤務期間や年齢によって90日〜330日もらい続けることが可能ですが、実際にどれくらいの給付金額がもらえるかについては、年齢によって変わってきます。
まず、失業保険の受給金額は「給付日数×基本手当日額」によって決められますが、基本手当日額は以下の計算式で計算されます。
基本手当日額=賃金日額(退職前6ヶ月の賃金合計÷180)×給付率(50%〜80%)
また、賃金日額と基本手当日額については年齢によって上限下限金額が以下のように定められています。
| 離職時の年齢 | 賃金日額の上限額 | 賃金日額の下限額 | 基本手当日額の 上限額 | 基本手当日額の 下限額 |
|---|---|---|---|---|
| 29歳以下 | 13,670円 | 2,657円 | 6,835円 | 2,125円 |
| 30〜44歳 | 15,190円 | 2,657円 | 7,595円 | 2,125円 |
| 45〜59歳 | 16,710円 | 2,657円 | 8,355円 | 2,125円 |
| 60〜64歳 | 15,950円 | 2,657円 | 7,177円 | 2,125円 |
また、給付率については年齢と賃金日額によって変わってきますが、非常に細かく定められていますので、ざっくりと「退職した会社の給与が少なければ高い給付率になる」と認識しておけば良いでしょう。
失業保険についてはハローワークで手続きを行いますので、どれくらいもらえるのか気になるのであれば、ハローワークで聞いてみましょう。
失業保険の具体的な手続きの流れ
失業保険を受給するための具体的な手続きの流れは以下の通りです。
1.必要書類を準備する:雇用保険被保険者離職票やマイナンバーカードなど
2.ハローワークに行って手続きを行う:書類の提出と同時に求職申し込みを行う
3.雇用保険説明会に参加する:ハローワーク職員に指示された日時で参加
4.失業認定日にハローワークに行く:失業の認定をしてもらうことで失業保険が受給できる状態になる
5.失業保険の受給開始:指定した講座に定期的に振り込まれる
基本的にハローワークに行けばそこからの手続きは全て完結できますので、失業保険を受給したいならハローワークに行くということだけを覚えておけば良いでしょう。
ただ、失業保険をもらい続けるためには、失業期間でしっかり就職活動を行っている証明が必要になります。1ヶ月に一回はハローワークで失業状態を認定してもらう必要がある点は認識しておいてください。
ハローワークでの失業保険の手続きについては、詳しく以下の記事でも解説していますので合わせて参考にしてみてください。

仕事を辞めたらすること④住民税の支払い
日本国民として生活している以上、自分が住んでいる地域に住民税を支払う義務があります。会社員として働いていれば、住民税は給料から天引きされる形で納税することになりますので、自分が手続きをする事は特にありません。
しかし、仕事を辞めたら会社から支払われる給料がなくなりますので、当然ながら天引きで住民税が納税できなくなります。したがって、仕事を辞めたら住民税の支払い手続きを自分で進める必要があります。
住民税は退職日によって手続きの流れが異なりますので、退職日に応じてやるべきことを解説します。
退職日が1月1日~5月31日の場合
退職日が1月1日から5月31日までの期間に当てはまる場合は、仕事を辞めてもその年の住民税の支払い手続きとしてやるべき事はありません。
住民税は、1年間の所得に対する税金を6月1日から5月31日までの1年間で収めるような仕組みになっています。もし1月1日から5月31日までに退職をしたのであれば、未納分である住民税が退職時に一括で徴収されるようになっています。
したがって、退職日が1月1日から5月31日までに該当する場合は、既に住民税の手続きを会社が代わりにやってくれているため、自分がやるべきことがないということになります。
ただし、会社の手続きタイミングや次の職場に転職する時期によっては、それ以降の住民税の支払い手続きを自分で行う必要があります。
住民税の支払い手続きを自分で行う必要がある場合は、自治体から納付用紙が送られてきますので、その用紙の指示に従って納税していきます。
退職日が6月1日~12月31日の場合
退職日が6月1日から12月31日に属する場合は、会社による住民税の一括徴収が行われませんので、自分で手続きをする必要があります。
自治体から住民税の納付用紙が送られてきますので、その用紙を使って住民税の支払いを行います。支払いはコンビニや銀行など様々な場所で行うことができ、納付用紙とお金だけあれば手続きが済みますので難しい事はありません。
ただし、納税期限までに納税しないと延滞税が発生してしまうため、自分で期限の管理を徹底することを意識してください。
仕事を辞めたらすること⑤確定申告
会社員として働いている期間は、所得税や社会保険料等の各種税金の計算や支払いを全て会社が行ってくれますが、会社を辞めて次の職場に就職するまでのタイミングによっては、それらの計算をすべて自分が行うために確定申告をしなければならない場合があります。
具体的には、会社を辞めてその年の年末までに転職をした場合、確定申告は原則不要となります。転職先の会社で、前職の源泉徴収票をもとに所得税や社会保険料等の計算を行ってくれます。
もし会社を辞めたその年の年末までに転職しなかったり、自営業やフリーランスになった場合は確定申告が必要です。
確定申告には提出期限が定められています。
原則2月16日から3月15日までの間に昨年1年間の確定申告を行い、税務署に提出する義務が発生します。
確定申告に必要な書類は確定申告書と本人確認書類に加え、前職を退職する際に受け取った源泉徴収票の3種類となります。
そもそも確定申告のやり方がわからない場合は、確定申告の時期になると税務署で無料のセミナーが行われるため参加をしてみると良いでしょう。
確定申告の大まかな流れ
確定申告の大まかな流れは以下の通りです。
1年間の収支について帳簿作成→帳簿を元に確定申告書類を作成→税務署に提出→計算結果によって納税か還付を受ける
基本的に自分で事業をしていたり副業をしていない場合であれば、源泉徴収票を元に簡単に書類をまとめるだけで確定申告が可能です。
ただ、間違えると様々なトラブルに発展するリスクがありますので、迷ったら最寄りの税務署に聞くことをおすすめします。
仕事を辞めた後に確認すべきこと
未払いの給料や残業代の確認
特にブラック企業の場合は、本来社員に支払わなければならない手当を支払っていないケースがあります。働いているうちは怖くてなかなか訴えることができなかったと思いますが、退職するタイミングで未払いのチェックをすると良いでしょう。
会社が未払いの状態というケースが多いものとしては、残業代が挙げられます。当然ですが残業代の発生しない「サービス残業」は法的に認められていません。残業した分は1分単位で給料を支払う義務が会社にはあります。
ただ、残業代を遡って請求するためには証拠を提出する必要があります。大抵の場合、サービス残業が横行している職場ではタイムカードを定時に切らせて証拠隠滅を図ろうとしているでしょう。
しかし、以下のようなものであれば、「実態として残業をしていた」という対外的な証拠とすることが可能です。
- メールの送受信履歴
- タクシーの領収書
- チャットツールなどでの業務連絡のスクショ
- 会社で撮影した、会社に置かれている時計の写真
- 時刻の写っている業務用パソコンのスクリーンショットやログインログアウト履歴
ただ、これらの証拠はほとんど退職前でないと集めることが難しいのも現実です。少なくともこれから仕事を辞めたいと思っていて、かつ残業代が支払われていないのであれば、上記の証拠をできる限り集めておくようにしてください。
もし退職後の人であれば、通勤に使っている交通系ICカードの入退場履歴も証拠になり得ますので、交通機関に問い合わせることも検討しましょう。
退職金がもらえるか確認
会社を辞める時にもらえるお金として「退職金」をイメージする人もいると思いますが、実は退職金は会社ごとによって制度が大きく変わってきます。
そのため、会社によっては退職金の制度がそもそも存在しないというケースもあるので注意しましょう。
自分の会社で退職金制度があるか分からない場合は、会社に対して質問をしてみてください。もし退職金制度があるにも関わらず、退職金が振り込まれていないようであれば催促するのがおすすめです。
ただ、退職金は長期間勤めればその分増えていくような設計がほとんどですので、勤務期間が短い人の退職金はそこまで期待できないということも合わせて認識しておいてください。
会社都合の退職なら他にももらえるお金がある
イレギュラーなケースではありますが、会社から解雇された場合は「解雇予告手当」がもらえることがあります。
労働基準法では、労働者が会社から解雇される場合、会社から30日前に解雇を予告されていない場合、解雇予告手当を請求できることが定められています。
つまり、「お前はクビだ!」と言われて即日解雇されるものなら、その分の手当がもらえるというイメージです。
ただ、経歴詐称や法律違反、バックれるような退職など自分に100%非があるような場合は請求できないので覚えておくと良いでしょう。

退職したらやることを順番で解説
退職したらやることを時系列順にまとめると以下の通りになります。
| 順番 | やること | 期限 |
|---|---|---|
| 1 | 住民税の支払い | 退職前後 |
| 2 | 失業保険の申請 | 退職後すぐに行う |
| 3 | 年金の切り替え手続き | 退職してから14日以内 |
| 4 | 健康保険の切り替え手続き | 退職してから14日以内か20日以内 |
| 5 | 確定申告 | 年末までに転職しなかった場合、翌年の3月16日まで |
特に年金の切り替え手続きや健康保険の切り替え手続きについては、退職してから2週間から3週間程度しか期限がありません。
それぞれ対応期限を超えてしまうと、自分だけでなく家族に金銭的な迷惑をかけることにもなりますので、どうしても手続きの方法がわからない場合は、最寄りの役所に早めに行って相談することをおすすめします。
また、いずれの手続きにおいても、前職を退職する際に受け取った源泉徴収票を始めとする各種書類が必要になるケースが大半です。
したがって、前職を退職する際に受け取った書類一式は、いつでも取り出せるよう管理しておくように心がけましょう。

仕事を辞めたらすること【市役所での手続き】
仕事を辞めたら健康保険や年金の切り替え手続きも必要になってきます。
具体的には役所で手続きをすることになりますので、わからなければ役所の担当者に質問をすることをおすすめします。
ここではそれぞれの切り替え手続きについて解説します。
健康保険の手続きをする
会社員として働いていると、会社が加入している健康保険組合に自動的に加入することになりますが、会社を辞めた場合は、これからどの健康保険組合に加入するのかを選んで手続きする必要があります。
健康保険の手続き方法についてはこの記事の序盤で解説しましたが、いずれにせよ手続きは退職日から14日以内に行う必要があります。
健康保険の任意継続制度を利用する場合は退職日から20日以内が期限となりますが、家族の扶養に入る場合は退職日から5日以内に手続きをする必要があります。
いずれにせよ退職日から期限がありませんので、早めに行動しましょう。
国民年金への加入手続きをする
年金についても自分で手続きをする必要が出てきます。
役所の年金窓口に行くことで手続きを進められますので、退職したら以下の持ち物を持って役所に足を運びましょう。
- 年金手帳
- 退職証明書や資格喪失証明書等の退職日を証明できる書類
- 本人確認書類
- 印鑑
なお、仕事を辞めた後に配偶者の扶養に入る場合は、配偶者の勤務先に連絡をして年金の手続きをする必要が出てきます。
もし仕事を辞めて配偶者の扶養に入るのであれば、早急に配偶者に手続きを進めてもらうよう相談してみてください。
仕事を辞めたらすること【ハローワークでの手続きに行く】
仕事を辞め、次の職場に就職するまでにある程度期間がかかる場合は、失業保険の手続きを行います。
失業保険はハローワークで以下の流れで進めていくことになります。
- 1.ハローワークに求職票と離職票を提出
- 2.7日間の待機期間を過ごす
- 3.雇用保険受給説明会に参加する
- 4.失業認定を受ける
- 5.失業保険が支給される
それぞれの流れについて解説します。
1.ハローワークに求職票と離職票を提出
まずは最寄りのハローワークに行った後、求職票と離職票を提出する必要があります。
求職票とはハローワークでの就職活動を始めるのに必要になる書類で、ハローワークで受け取ることが可能です。
また、離職票については前職を退職する際に受け取る書類になりますので、忘れずに持っていきましょう。
2.7日間の待機期間を過ごす
ハローワークに求職票と離職票を提出することで、失業保険の受給資格があることを承認してもらいます。
ただ、失業保険の受給資格が証明されたからといって、すぐに失業保険を受け取れるわけではありません。
失業保険の受給資格が決まった日を起算日として、7日間は待機期間となります。この待機期間は失業保険の受給期間としてカウントされず、失業保険が振り込まれることもありません。
なお、自己都合で退職した場合は、ここからさらに2ヶ月間の待機期間が発生しますので、注意してください。
3.雇用保険受給説明会に参加する
待機期間が終了した後は、雇用保険受給説明会に参加します。
これは失業保険を受給するにあたって、知っておかなければならない情報や就職活動のスタンスなどについての説明会であり、この説明会に参加しないと失業保険を受給することはできません。
説明会の日程はハローワークに求職票と離職票を提出したタイミングで教えてもらうことができますので、忘れずに予定を管理しておきましょう。
説明会に参加することで、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を受け取ることができます。これらの書類は失業認定を受ける上で必須の書類となりますので、なくさないように注意してください。
4.失業認定を受ける
説明会終了時に受け取った失業認定申告書に記載されている失業認定日にハローワークに足を運びます。この際、ハローワークの職員と面談をすることになりますが、この面談で失業保険を受給できるかどうかが判断されます。
なお、失業保険を受給できるかどうかは、失業認定日までに原則2回以上の休職活動実績が必要となります。
言い換えると、次の職場を見つけるために具体的な行動をしていないと失業保険が受給できないということになりますので、認識しておきましょう。
5.失業保険が支給される
面談を経て無事に失業認定されれば、失業保険が支給されるようになります。
失業保険は失業認定が承認された後、およそ1週間程度で自分が指定した口座に振り込まれます。
失業保険として受け取れる金額は、前職の給料や年齢、勤務期間など、様々な計算方法によって決定されます。失業保険の支給日にきちんと失業保険が振り込まれているかどうか確実にチェックしておくことをおすすめします。
仕事を辞めたらもらえるお金
仕事を辞めたらもらえるお金として、以下のようなものが挙げられます。
- 失業保険
- 求職者支援制度
- 求職者支援融資制度
- 広域求職活動費
- 就職促進給付金
- 未払賃金立替払制度
- 傷病手当金
- 特例一時金
それぞれ簡単に解説しますので、自分はどういったお金がもらえる可能性があるのかを知っておきましょう。
失業保険
仕事を辞めたらもらえるお金として代表的なものが失業保険です。
この記事でも既に解説しましたが、所定条件を満たした上でハローワークで手続きをすることにより、毎月前職の給料の50%から80%程度のお金を受け取ることができます。
ただし、失業保険を受け取り続けるためには、次の就職先を見つけるための就職活動を行い続ける必要があります。
また、失業保険にはあらかじめもらえる期限が決まっていますので、基本的には失業保険の受給期間中に次の職場に就職することが望ましいと言われています。
求職者支援制度
ハローワークでは職業訓練が受講できますが、所定の条件を満たすことで毎月10万円をもらいながら職業訓練を受講することが可能になります。これを求職者支援制度といいます。
求職者支援制度を利用するためには、ハローワークで申請する必要があります。
受け取るためには複数の条件を満たしている必要があり、自治体によって条件が異なる場合もありますので、最寄りのハローワークで相談してみることをおすすめします。
求職者支援融資制度
求職者支援融資制度は、厳密にいうとお金をもらえるのではなく、お金を貸し付けてもらえる制度です。対象としては、先ほど解説した求職者支援制度を受けていて、かつハローワークの審査に通過した人となります。
単身世帯であれば1ヵ月あたり最大50,000円、配偶者や子供がいる場合は1ヵ月あたり最大100,000円を、最長12ヶ月間借りることができます。
どうしても生活が困窮している場合は求職者支援融資制度という制度もありますので、むやみに消費者金融にお金を借りる必要がないことを認識しておきましょう。
広域求職活動費
ハローワーク経由で応募した求人の企業に面接をする際、遠方に足を運ぶ必要がある場合に限って交通費を支給してくれます。この交通費を広域求職活動費と呼びます。
広域求職活動費は、2011年の3月に発生した東日本大震災の被害を受けた人のために始まった支援です。基本的にハローワークには地元密着型の求人が多いため、遠方の会社に面接に行くような事は少ないと考えられます。
就職促進給付金
仕事を辞めてすぐに再就職を実現できれば、就職促進給付金が受け取れます。
就職促進給付金には「再就職手当」「就業促進定着手当」「就業手当」「常用就職支度手当」の4種類に分かれますが、それぞれ条件が異なりますのでハローワークで話を聞いてみると良いでしょう。
就職促進給付金もあるため、場合によっては失業保険を満期間もらうのではなく、早めに就職を決めて就職促進給付金を受け取った方が総合的にプラスになることがあります。
未払賃金立替払制度
勤めていた会社が倒産したことで給料がもらえなくなった際は、未払賃金立替払制度を活用してお金をもらうことが可能です。
会社が倒産したという条件がありますので使う機会はあまりありませんが、覚えておくと良いでしょう。
傷病手当金
仕事中に怪我や病気で働けなくなった際、傷病手当金が支給されます。具体的には、15日以上継続して働けなくなった場合にお金がもらえる制度です。
なお、失業保険と傷病手当は両方同時に受け取ることができません。
傷病手当を申請するためには、まず医療機関で受診する必要があります。
医師に傷病手当を申請したい旨を伝え、診断書を受け取らないと手続きが進められませんので注意が必要です。
申請する先としては、会社が所属している健康保険組合や社会保険事務所となります。必要書類や医師の診断書を提出し、審査に通過すれば、傷病手当が振り込まれるようになります。
特例一時金
夏の海の家や冬のスキー場など、天候に左右されるような季節に限定して行っている仕事に従事していた場合、その仕事で失業した人は特例一時金を受け取ることが可能です。
1週間の所定労働時間が30時間未満で、11日以上働いた月が通算して6回以上ある場合に申請できるようになっており、申請先はハローワークとなるので覚えておくと良いでしょう。
もし自分が季節に左右されるような仕事に就いていた場合は、特例一時金についてハローワークの職員に相談してみてください。
仕事を辞めた後の就職活動のやり方
仕事を辞めたらすぐに再就職のための行動を取りましょう。離職期間が長くなればなるほど、次の再就職の難易度が上がりますし、家計も厳しくなってきます。
ここでは再就職のための行動として意識しておきたいポイントを5つご紹介します。
自己分析をしてやりたい仕事を見つける
自分のやりたい仕事に再就職できた方が、精神的にも収入的にも安定します。そのためにも、まずは自己分析をしてやりたい仕事を見つけましょう。
自己分析とは、自分の今までの経験を棚卸しして長所と短所を言語化し、自分自身のことをより深く知るために行う行為です。
自己分析の方法やメリットについて、詳しくは以下の記事で解説していますので合わせて参考にしてみてください。
企業研究をして自分に合った企業を見極める
ストレスフリーに働くためには、自分の性格やスキルに合った企業に就職することが大切です。そのためには企業研究が重要になります。
企業研究とは、応募する企業の求人票や企業ホームページ、転職口コミサイトなどを見て就職後のイメージを具体的にする調査のことを言います。
企業研究の方法については以下の記事で詳しく解説していますので、先ほどの自己分析の記事と合わせて理解を深めておきましょう。
就職エージェントに登録してサポートを受ける
再就職を最も効率的に進めたいのであれば、就職エージェントの利用がおすすめです。就職エージェントを利用することで、自分の経験や希望に合った求人を紹介してくれるだけでなく、自己分析や企業研究までサポートしてくれます。
それだけでなく、模擬面接の実施や企業との面接日時の調整代行などもカバーしてくれるため、今まで真面目に就職活動をしたことがない人でも安心して再就職先を見つけることが可能です。
就職エージェントの利用にお金はかかりませんので、気になるサービスを見つけたらまずは登録からしてみましょう。
いい求人を見つけたら積極的に応募する
新卒採用とは異なり、中途採用においては求人の掲載期間が定められていたり、募集枠が数名と少なかったりなど、とにかくスピードが重要となっています。
いい求人はその分たくさんの応募が集まりやすく、内定者も早々に出てしまうことが考えられますので、なるべく積極的に応募していくのがポイントです。
転職・再就職における平均応募社数は20社超というデータもあるため、どんどん併願していくことも意識してみてください。
離職中の人の面接ではひと工夫が必要
離職中の人が面接をすると、面接官から高い確率で「なぜ前職を辞めたのか?」「どうしてすぐに就職しなかったのか?」といった質問が飛んできます。
この際ネガティブに回答すると面接官の印象が悪くなってしまいますので、あらかじめ以下のような返答を準備しておくことがおすすめです。
- 自身の長所を改めて考え直した結果、御社のような仕事で働きたいと考えた
- 家族の介護に集中していたため離職期間が発生しました。
特に20代の第二新卒の場合について、以下の記事で好ましい面接の例文をご紹介していますので合わせて参考にしてみてください。

仕事を辞めたらすること【生活面】
離職期間がある場合は、生活の見直しも同時に行う必要があります。ここでは3つの観点で意識しておいてほしいポイントをご紹介します。
基本的に毎月の収入は減る
仕事を辞めて働かない期間ができれば、仮に失業保険をもらうにしろ、再就職活動をするにしろ、基本的に毎月の収入は大きく下がることになります。
今までと同じような生活水準で生活することは困難になるということをまずしっかり理解することが大切です。
ちなみに、仕事を辞めたら安易に生活保護を受給すればいいと考えている人がいますが、生活保護をもらうためには非常に高いハードルがありますので基本的に難しいと思っておいてください。
まずは月々の固定費を見直す
収入が減るのであれば、当然目をつけるべきは支出の見直しです。生活に不要な衣類の購入や飲食代などの削減をしていくことが求められますが、まず最初は月々の固定費を見直しましょう。
具体的には、以下のような固定費であれば見直せる余力があるケースが多いため、検討してみてください。
- スマホの通信費
- 家賃
- サブスクサービス
- 電気代
特にスマホの通信費は各通信会社が様々な格安プランを出していますので、削減しやすいポイントです。中には毎月5千円程度固定費を削減できたという人もいるため、仕事を辞めるのであれば生活水準を変えることも意識する必要があります。
貯金次第では実家に相談することも検討
固定費を見直し、食費や娯楽費を切り詰めてもなお貯金が足りないというケースも考えられます。貯金残高に焦って就職活動をすると、よくない企業であっても入社してしまい後悔することもあり得ますので、実家に相談することも検討してみてください。
今はオンラインでも面接ができる時代ですので、無理して首都圏に住む必要はありません。少し離れた実家からであっても問題なく就職活動は進められるはずです。
家族に頼ってゆっくりと就職活動をした方が返って効率よく内定を獲得できる可能性がありますので検討してみてください。

仕事を辞める時の注意点
最後に、仕事を辞める時の注意点を簡単に3つご紹介します。
健康保険や納税手続きは絶対に行う
健康保険や年金、住民税などやるべき手続きが多く面倒だと感じるかもしれませんが、いずれも必ず行いましょう。
もし行わないと追徴課税といって余計な納税が必要になったり、最悪の場合財産差し押さえになることもあります。
手続きが分からない場合は、所管の市役所や税務署などに行って全て聞いてしまうのもおすすめです。
バックれるような退職は自分も迷惑する
どれだけ会社が嫌だからといって、バックれるように退職してしまうと退職に必要な書類がもらえなかったり、手続きができなかったりと自分が困ることになります。
後々面倒になることを避けたい人こそ、しっかりと会社に退職の意思を自分で示し、正式な手続きを持って退職することを心がけましょう。
退職時にもらう書類は絶対に無くさない
退職時にはいくつかの書類をもらうことになりますが、いずれも再発行が難しく大切なものになりますので絶対に無くさないでください。
もし無くすと、仕事を辞めた後にする手続きが上手く進められなくなるので注意しましょう。

まとめ
仕事を辞めたらすることはこの記事でも大きく7つあることを解説しました。やることが多く面倒に感じるかもしれませんが、いずれも大切なことですので確実に実行しましょう。
また、退職と同時に転職ができればやることを大きく減らすことが可能です。本来の目的とは異なりますが、手続きをなるべく少なくしたいのであれば、在職中に転職活動をして内定を獲得しておくというのも検討してみてもいいかもしれません。